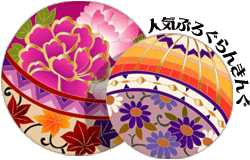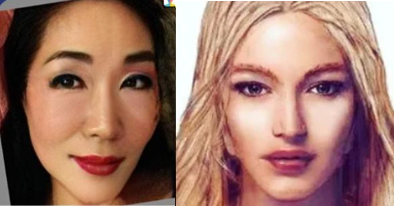1952年カラス29歳の全盛期のライヴ録音
ドニゼッティ作曲「ランメルモールのルチア」
これを聴けば、如何にマリアカラスのテクニックが凄かったか、声が凄かったのかが分かります。
2オクターブ半を全て美しく鳴らして、自由自在に歌っているだけでなく、表現力も凄いです。
これが本物のルチアです。
今では、高音しか出ない細い声のソプラノばかりが歌っていますが、本来この役は、ドラマチックソプラノで、高音が出せ、且つ、コロラトゥーラが出来る人の為に作曲された役です。
私は17歳で声楽を始めた当初から、カラスのレコードばかりを聴いて育ってきたので、カラスの歌っている役を、現在のソプラノが歌っているのを聴くと、みんな下手にしか聴こえませんでした。
今でもそうです。
デルモナコのオテロや道化師を聴いて育ったので、他の誰を聴いても、みんなへたくそに聴こえました。
今も勿論、一人も聴きたい歌手は居ません。
本気でオペラ歌手を目指すのなら、本当の本物を聴いて勉強するべきです。
本物の世界一をお手本に必死で勉強すれば、相当に上手く成れる可能性はあります。
目標の程度が低いと、決して本物には成れません。
カラスやデルモナコには成れなくとも、少しは近い所まで登れるかも知れません。
日本の声楽の先生は、理論は何も分かってないせいか、やたらと
「何とかみたいに、かんとかみたいに・・・・・」
と言うのが多くてうんざりした。
デルモナコのマスタークラスの後、ブルガリア国立ソフィア音楽院で
オーディションの結果、一番の先生につく事に成った。
ブルガリア出身には、ボリス・フリストフ(世界一のバス歌手と言われ、カラスのノルマで、父親役オロヴェーゾ役をやっていた。)
その後輩で、ニコライ・ギャウロフの様な偉大なオペラ歌手を輩出している。
ロシアやブルガリアのオペラ歌手にはベルカント唱法は出来ない。
東欧風のベルカントで、本物のイタリア式ベルカントとは違っている。
何が違うかと言うと、イタリア式では声帯を酷使しないが、東欧式ではかなり、声帯に負担をかけている。
でも、国際歌手に成ったブルガリアの歌手は、ミラノスカラ座で勉強してプロに成っているので、本物のベルカント唱法を身に着けているし、教える力も有る。
私が習ったのは、ミラノスカラ座で勉強して、国際的に活躍しているプリマドンナだったので、ベルカント唱法の理論を、人間の顔を描いて説明してくれた。
1、先ずは、声の通る道が目の下約1cmの所に有って、声は、その位置より下には落としてはいけない事。
歌う時には常に口角を上げて、ほほ笑んだままで歌う事=大口を開けて、百面相をしてはいけない。
2、a e i o u どの母音でも、同じ質の響きで歌う事。
これを実行するには、舌は柔軟にして力が入っていては出来ない。
これは上記の「ほほ笑んだまま」と繋がる。舌は柔軟に、口の中で平にしたり、すぼめたりする事で、正確な発音が出来る。腹話術に通じるものが有る。
3、喉声に成らない事=喉を傷めるからやってはいけない。
4、肩に力を入れてはいけない。=肩に力が入ると、喉にも力が入る。
高音を出そうとして、力んでしまい、肩が上がる人が多い。
肩に力が入るほどに、喉は締まるので、高音は出なくなる。
これを回避させるには、「膝を屈伸して!」と言えば、肩の力はストンと落ち、高音が嘘の様に簡単に、スポーンと出る。
5、声帯を意識してはいけない=声を出そうと意識するのではなく、息が声帯を通る時に、声帯はたまたま振動するだけで、その時に音声が出るだけの事である。
6、顎に力を入れてはいけない、にっこりしたまま、口角を上げ、顎には一切力は入れずに、自然体にする事。(顎はぶらーっとしたイメージ)
7、喉の奥を高く開けること=大口を開ければ、喉の奥は締まる。喉を開ける事と口を開ける事は全く別の事である。
意識としては、口の中に、まるごとの茹でたてじゃが芋が入っていると想像する。
するとどうなるか?! 熱いから、喉の奥が天井に向かって大きく開く。
8、練習はピアノで練習する、フォルテで、大声でしてはいけない。
ピアノで出せない音は、フォルテにも出来ない。
どんな高音であっても、怒鳴って出してはいけない。ピアノからフォルテにもっていけないとダメ。
9.息は鼻から一瞬で吸い上げて、口からゆっくりと吐く。この時、息漏れが無い様に、息=響きに変える。
これの訓練には、ローソクを使うと分かりやすい。息の全てが響きに変わっていれば、ローソクの炎は揺れない。たとえフォルテッシモに成っていても炎は消えない。
10、声は目の高さで1m位先にフォーカスする。(声は視える)
正しくフォーカスされた声は、ピアニッシモでも、ホールの天井を鳴らして、お客様の耳に届く。
その他、まだまだ沢山重要なテクニックが有って、それが全部出来る様になれば、感情を込めて、自由自在に3オクターブ近い声域を歌える様になる。
(これを読んでも理解できる人は、殆ど居ないと思いますが、オペラをやっている人には分かるかも?)
カラスは「トリル、トリル、トリル、よ!」とインタビューで言っているのだけど、トリルが出来る様に成れば、ビブラートのコントロールも出来る様に成り、表現力が倍増するから、トリルが出来るか出来ないかで、歌手の力量は変わってくる事を言っている。
私はトリルが出来る様になるまで、毎日練習して三か月が掛かった。
でも、生徒にやらせてみたら、早い人は、一週間で出来る様に成ったし、普通でも一か月くらいで出来る様になる事が分かった。
私の生徒は全員、トリルが出来る様に成りましたよ。
出来ない人は、「出来るまでやらない人」に他なりません。
実は、巻き舌も全然出来なくて、これが出来るのにも三か月かかりました。
高い e の音を伸ばせる様に成るには、三年掛かりました。
声域を1オクターブ伸ばすには、1年半くらい掛かってます。
出来ない事を出来る様にするには、只管、練習、練習に明け暮れるのみ、です。
トリルが多用されているドニゼッティのアンナ・ボレーナ狂乱の場です。
49歳の時の録音で、2オクターブを歌っています。↓