汚染水の問題、土壌からのセシウム検出、首都圏にも現れるホットスポットなど、不安材料は今だ増え続けている。昨日の東京新聞こちら特報部の見出しには、「口先の安全、不信増幅」の見出し。原発事故から3ヶ月近く。いつまでたっても国民と政府のこうした関係は解消されない。そして、マスメディアも少しずつ、大丈夫一辺倒の報道から変化を見せているものの、まだまだ国民の不安は消えない。
今国民の最大関心事となっている、放射能汚染への不安の解消。
先日ツイッター上で、批評家の東浩紀氏が朝日新聞に抗議するという一件があった。それがまさに、「放射能汚染への不安とマスメディア」について考えさせられるやりとりだったのでとりあげてみたい。
発端は、ツイッター上で朝日の原発問題担当記者が、3月15日の時点で東氏が伊豆に避難したことについてつぶやいたこんなツイート。
「うーむ、まあ妻子つれて伊豆に逃げてたくらいなのだから、いまもまだ錯乱状態が続いているのだと思うことにしよう。」(削除されたようなので、東氏側のRTでしか確認出来ず)。
東氏の抗議はこの発言に対するものだが、記者がそのツイートに至ったそもそもの発端は、この記者が5月30日付けの夕刊に書いた以下の記事に東氏がコメントしたことだ。→http://goo.gl/Fm3NU
5月30日朝日新聞より一部引用>>>
東京電力は30日、東電福島第一原子力発電所で作業していた男性社員2人が数百ミリシーベルトの放射線を浴びていた恐れがあると発表した。今回の作業で認められている被曝(ひばく)線量の上限250ミリシーベルトを超えた例はこれまでなかったが、この値を超えれば今後の作業はできなくなる。ただ急性症状が出る1千ミリシーベルトの被曝までには至らなそうだという。(後略)
引用ここまで>>>
これに対し、東氏が次のようにツイートした。
「「ただ急性症状が出る1千ミリシーベルトの被曝までには至らなそうだという。」という表現に我が国の麻痺を感じるな…… asahi.com(朝日新聞社):東電の2社員、多量の内部被曝 数百ミリシーベルトか - 社会 http://goo.gl/Fm3NU」。
そして、このつぶやきに対して、朝日の記者氏は「麻痺とかじゃなく、正しい記述なんですけど。」というリプライを飛ばした。これによって、東氏に火がついた。
東氏の5月30日ツイートより引用>>>
posted at 14:56:08
(その後のやりとりは、Twilogでこの日の東氏@hazumaの発言とこの記者 氏@ryomakom(現在非公開)の発言を見て下さい。http://twilog.org/hazuma/date-110530)
いくつかのやり取りの後、朝日の記者氏は「錯乱状態」発言に至った。
この記者は、東京の安全性を確信しているらしく、世論に影響を与える立場にありながらこうした行動に出た東氏の行動は、無用な不安を与えるリテラシーがないものだと判断した。
私は、この記者のほうが間違っていると思う。
「東京は危険だ」と言ってるわけではない(もちろんホットスポットの話がでてきてる今、完全に安全だとも言えない)。
将来、やっぱりあの時避難しとけばよかったと後悔することになる可能性がないと、100%の自信をもっては誰も言えない。だからこそ、その対応には個人の意志を最大限尊重せねばならないはずだ。そういうことをこの記者は意識しているのだろうか。
彼のツイートは現在非公開になっていて確認出来ないが、東氏のツイートで記者氏の発言がRTされている。
東浩紀氏のツイッターTLより引用>>>
このひとまだ言ってるんだ。RT @ryomakom: 「錯乱」と書いたのは礼を失していた。重ねて謝罪します。一方、東さんが伊豆に避難した判断は、東京の現在の放射能レベルをみても、間違っていました。しかも当時、避難の必要がないということは、マスメディアで広く報道されていました。
posted at 20:56:57
この嫌みの連投は、つまり喧嘩する気なんでしょうねえ……RT @ryomakom: 国民は正しい情報にもとづき、安心できました。知識人に求められるのは、こういった行動じゃないでしょうか。お二人は、「学者のノブレスオブリージだ」と言っておられました。東さんとは結果として対照的だった。
posted at 20:58:15
そういう話ではありません。あなたの見識が問われています。RT @ryomakom: いいえ、喧嘩する気はございません!平に平にご容赦を。@hazuma
posted at 21:14:55
TL引用ここまで>>>
記者氏は 謝ってはいるけれど、基本的に当時東京が安全であったという立場に変わりはなく、東氏が間違ったことをしたという認識もそのままのようだ。
当時、東京は安全であったという認識に記者氏が立つのは、自らの取材の上での判断なのだろうからまだ認めるにしても、それを強要してはいかんと思うのよ。それが影響力のある知識人であったとしても同じ。「東浩紀が東京から避難しない」というのも、ひとつのメッセージではあるからね。
新聞という公器に、記者が記事を書くとき、彼が取材によって得た情報は、それが全てではないかもしれないという謙虚さを持って書くべきだ。
なのにマスメディアは、国民に不安を感じさせてはいけないという強迫観念にも似た方針からか、違う価値観を持つ人を容認しない(このところ変化も見られるが)。しかし、その「国民に不安を感じさせてはいけない」という政府やメディアの行動基準こそが、現在もっとも国民を不安に陥れる原因となっているように感じる。
インターネット全盛で、様々な情報を人々が手に入れられる時代。ウィキリークスなどに、日本の外務官僚がアメリカ様に自国政府の御し方を御注進申し上げていることまでも白日の下に晒される時代である。原発情報に関しても、一般の人でも様々な情報が手に入る。もはや何を信じていいかわからない。情報を廻って不安になることはデフォルトな時代なのである。それを自覚している人々は、もはや最終的には自分が判断するしかないと腹を括っていると思う。国民がそこまで真剣になっている状況で、いくら「安全です」「こっちの情報のほうが正しい」とバカの一つ覚えのように訴えたところで、国民から「バカにすんな」と言われるのがオチだ。
記者氏のいう「学者のノブレスオブリージュ」は、そういう現代の情報のあり方を理解しないで、専門性を持つ自分たちだけが世の中に正しいことを伝えられるという、時代遅れな奢りになってしまってはいないだろうか。
そもそもこの記者が特別扱いする、知識人の行動とか、専門性ということも、今回の原発事故によって、その学者の立場がデータの読み方や説明の力点を変えてしまうことがあからさまになった。そういう、目の前で起こっている事実を直視せずして、知識人のあり方や専門性を語るのは本末転倒だろう。
政府やマスメディアが掲げる2大錦の御旗。
1)「国民を不安に陥れ、パニックを起こさせてはいけない」
2)「俗説を排せ、専門性を重視せよ」
一見、正しそうに見えるこの命題であるが、これが、今回、政治やメディアの行動が、国民の多くから反発を買っている大きな原因だ。
1)は、先程も述べたように、国民の知性を信用せず、大衆は無知蒙昧であるという前提に立った、石器時代の命題である。しかし、さすがに国民はそんなに無知蒙昧ではない。政治家や官僚やメディアは、いわゆる「B層」を想定して、いまだに自分たちが大衆を先導している、灯台の明かりであると思っているのだろうが、今回の震災や原発事故で、自ら考え始めようとしている国民は多いはずだ。自分たちの方が最後尾を走っていることに早く気づいた方がいい。
2) の俗説と専門性についても同様にこれまでの考えは通用しない。何が俗説で何が定説であるか、様々な研究が成されている現代では、意見が対立していることは珍しくない。どっちの立場にたつかで、データの読み方も微妙に変わってくる。そういう意味で、メディアは「ただ専門家に話を聞く」だけではダメなことは自明だ。専門家にもいろいろいるのだから、どの立場で語っている専門家なのかを明示し、一方の立場の学者しか呼ばないならば、自分たちはそちら側の立場でものを言っていることになるということを自覚すべきだ。
そして、「お上の言う事は正しい」を基本とする記者クラブメディアの発表報道もここらで見直さねばならないのだろう。後から後から訂正が繰り返される保安院からの原発情報や冤罪事件を見ても明らかだ。
あらためて、この記者の書いた件の記事を見てみると、まさに発表報道の典型のような記事だ。発表をそのまま報じているから「ただ、急性症状が出る1000ミリシーベルトの被爆には至らないという」なんて間抜けな一文を入れてしまうのだろう。もちろん、全てのマスメディアの記者がそうだというのではない。特にこの記事が間抜けだったのだと思う。優秀な記者も一緒にしては申し訳ない。
それに、よく見れば、その前の文章「この値を超えれば今後の作業はできなくなる」もやばい感じ。「困ったなあ、じゃあ上限もっと引きあげないとだめじゃんか」という声が聞こえてきそうだ。いや、記者自身がそう思っているということではない。そう思っているようにも読める文章なのだ。自分がどう思っていようが、記者ならばそう読まれることも想像できねばならない。
東電側が会見で「でも、急性症状の出る1000ミリは超えてませんから(大丈夫)」とか言ったのかなあ?それをそのまま書いちゃったのかなあ、とか想像する。基準がもとは100ミリシーベルトだったことも、字数の関係上、既知の事実だと判断して入れなかったのだろうか。
もちろん1000ミリ浴びてないというのは事実だろう(その後あびてないことが確認)。1000ミリまでは緊急症状が出ないというのも「正しい記述」なんだろう。では逆に、緊急ではなく、数年後にどうなるか、晩発性障害についての「正しい記述」ができるのだろうか。晩発性障害については、被爆線量が低くても出るという話もある。
もしや、こっちがわからないから、はっきりわかっている「緊急症状は出ない」という情報だけを出したわけじゃあるまいな?まあこれは勘ぐり過ぎですか・・・。
緊急症状がでないのは事実だろうけど、それを書くことにどういう意味があるか考えてる?と聞きかえしたい。あなたはこの一文を入れることで何が伝えたかったの?「そのまんまですけど、なにか?」って言う?言える?
それとも、さっきも指摘した、国民を不安に陥れてはいけないというマスメディアの使命により、「大量被爆した職員は、被爆はしましたが大丈夫です!」ってことを強調したかったのでしょうか。
東氏のツイッターを見ると、朝日新聞とは和解したようだから、この記者氏が未熟でしたという辺りで収まったのか。
この記事と記者のツイートの問題点は、東浩紀氏がツイートの中で指摘されている。http://twilog.org/hazuma/date-110530)。
上記のツイートを見れば、十分という気もするが、その後私も、一般人の情報収集とか専門性の問題とか、不安の問題とかいろいろ考えたので、この項目もう少し続けたい。
次回に続く>>>












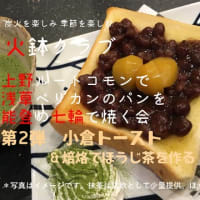



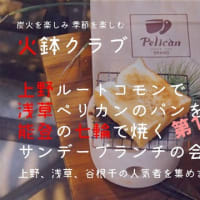



まああなたが言うとおり、人の受け止めは自由ですからね。危険と思うなら、さっさと東京から離れてください
このひと、3/11のあと伊豆に逃げたら3/15の地震に遭遇しちゃったって。
そしてニューヨークタイムズに寄稿したら、師匠に「脳天気すぎる」と
指摘されちゃって、それ以降評論家って名乗ってないらしいよ・・・。
ところで奥様(ほしおさなえ氏)は作家さんなんですね。
↓のサイトに行き着いて、東氏との関係を知りました。
http://www.birthday-energy.co.jp/ido_syukusaijitu.htm
私生活の苦悩を、仕事である文筆業に生かす事で、仕事が発展
していくみたいです。
来年あたり、もめちゃったりして・・・。