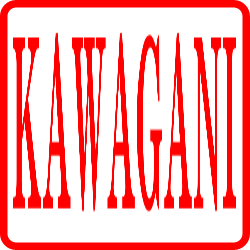初回
DQX毛皮を着たヴィーナス
前回
『DQX毛皮を着たヴィーナス』ゼフェリン
<告白>
ロシアの小説家ゴーゴリは、どこかで述べている。
「真の喜劇は、笑いの仮面の下で涙を流しているのじゃ!」


この告白を書こうとして、ぼくはいま実に妙な気持ちになっている。刺激の強い花の匂いに満ちあふれた雰囲気に圧倒されて、頭痛がする。暖炉の煙はただよい集まって凝り固まり、

白いひげの小妖精になってぼくをあざ笑っている。

下ぶくれの頬っぺたをしたキュービッドはぼくの膝のうえや、椅子の腕のうえに乗っている。

ぼくはいま、恋の冒険書を書きながら、ひとりでほほえんだり、声をたてて笑ってたりしている。しかしこのインキは、ぼくの心臓からほとばしり出たまっ赤な血汐だ。心臓の傷口は鼓動するたびに、ぼくの苦痛をあたえている。紙の上に、ときどき涙の粒が落ちる・・・・・
「みんなあたいのことを木だと思い込んで、これであたいも完璧な森ガールだわ。」

「うまいことをいったものだ。」
「ある官能のすぐれた男の告白だっち」

「官能?」
「官能だっち」


さてこのカーぺイシアン山脈の保養地では、毎日がのろのろと過ぎている。ぼく以外にだれもいない。自然の風景、田園の情景なんか書くのは退屈だ。できるなら、十分の暇を得て画廊いっぱいの大きな絵を描いたり、1シーズンの間劇場をにぎわす新作ドラマを書いたり、十数人の音楽家を養成して世間へ送り出したいものだ。しかしいまのぼくは、せいぜい画布をひろげ、楽弓をみがき、楽譜の線をひく程度だ。要するにぼくは、人生芸術のデレッタント(お道楽者)にすぎない。

ぼくはいま、窓際で横になってくつろいでる。この小さな町はぼくをひどく失望させているが、詩にあふれた町のように見える。高い山脈の青い壁面には太陽の金色の光が織り込まれていて、素晴らしい景観だ。ぼくがいま泊まっている家は公園の一隅にあるとも見えるし、森林のなかに建っているとも見える。見る人の気持ちしだいだ。

ここに住んでるのは、レンベルグ市から来た未亡人と

宿の女主人タルタコフスカ夫人とぼくだけだ。
宿の女主人は年寄りで、日が経つにつれだんだん小さくなっていく。

未亡人はなかなかの美人だ。まだ二十四、五にはなっていまい。ぼくの部屋のまえで、いつも黒のブラインドがおろしてあり、黒のつる紐のからまったバルコニーがある。

階下のぼくの領分には、気持ちいい忍冬亭がある。ぼくはここで本を読み、原稿を書き、鉛筆をもてあそび、小鳥のように歌ったりする。

そして二階のバルコニーを仰ぐと、黒の紐の網目から白い上衣がチラチラ見える。
この未亡人は、しかし、ぼくの心をそれほど強くはひきつけない。というのは、ぼくにはほかの恋人がいるからだ。

それは、実は大理石のヴィーナスなのだ。その点、ぼくはこのうえなく不幸だ。このヴィーナス像は、大きな屋敷内の美しい牧場の中にある。今までみたことのない美しい女像である。

この女像は美しいといえば、もうそれで十分だ。それ以上いうことはない。ぼくは病的なはげしさで情熱的に彼女を恋している。

永遠にかかわらず、静かで、石の無言の微笑みのほかはなにひとつぼくの恋に答えてくれない。ぼくにできるのは、この女像に恋をするだけだ。そんな狂おしさでぼくは彼女をあがめ、その前にひざますいている。
次回