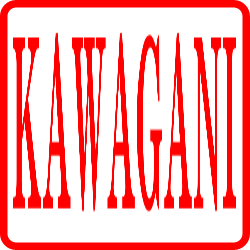初回
DQX毛皮を着たヴィーナス
前回
『毛皮を着たヴィーナス』告白
<ヴァンダ>

太陽が森の上から光をそそぐとき、ぼくはモミの木の葉の下から横たわって本を読む。

夜中に出かけていって、この冷酷で残酷な愛人を訪れる。そして彼女の足元の台座に顔を押しあてて折れると、ぼくの気持ちは彼女の足から腹、そして胸へのぼっていく。

そういうときに月がのぼってくると、いうにいわれのない感動をおぼえる。月光の木々の間でためらいながら、牧場ぜんたいを銀の光の中に溺れさせてしまう。すると、たちまち女神はやわらかい月光のなかで沐浴してるように見えてくる。

ある夜、ぼくが恋の祈願をこめてから散歩道をたどってもどってくると、月光の下の一列の木々のむこう側に、大理石のように白い女性がちらりと目にうつった。大理石の彼女がぼくに同情して、生きた姿なって来てくれたと思ったからだ。

が、ぼくは名状しがたい恐怖にとられて、

心臓ははげしい鼓動で張り裂けんばかりだった。

ぼくは恐怖のあまり、ものすごい早さで逃げ出してしまった。

「バカな奴め!」
ぼくは自分で罵倒した。すると、この言葉が不思議な魔力でぼくのなにものかから解放してくれた。ぼくは平静にもどった。

「彼女の名はヴァンダ・フォン・ジュナウ。だっち」

「偶然にもあるユダヤ人の美術商からティチアーノの「鏡のヴィーナス」の複製画を入手しただっち。」

彼女が美しい裸体を毛皮でつつんでいる図だ。ぼくはそれに魅せられて空想にふけった。

「バカ者め!」
ぼくはもう一度繰り返した。いっさいのものがはっきりとぼくの目にうつってきた。泉、ツケの森のなかの小道、ぼくの宿、忍冬亭。またもさきほどの白衣の女性が迫ってきた。ぼくはいよいよおそれて家の中へ飛び込んでしまった。

こうしてぼくと彼女のつきあいははじまったのである。
「あなた、何であんな仕草を考えついたのですか?」
「あなたのご本のひとつに、小さい絵がはいっていましたからよ」
「ぼくはすっかり忘れていました」
「あの絵のうらに妙なことが書いてありましたわね」
「妙って?」
「わたし、いつも本当の夢想家というものにあってみたいと思っていましたのよ。ちょっと気まぐれにね。そうしたら、あなたが目についたのよ」
「・・・・・」
ぼくはすっかり口ごもって、顔を真っ赤にしないではいられなかった。

「昨夜は、あなたひどくわたしをこわがりましたわね」
「そうです。まア、どうぞ、おかけになって」

彼女は腰をおろして、ぼくの当然ぶりをおもしろがった。ぼくはいま、真昼の光に満ちあふれたなかにおりながら、昨夜よりいっそうおもしろく感じた。彼女はそれを見て、唇のあたりに喜ばしげな軽蔑の色をはっきり浮かべて、
「あなたは恋愛や女性について、ほかの男とは全く違った、敵対的なものをお考えになっているらしいですわね。あなたには、恋愛や女性はたのしい苦痛、刺激の強い残酷、そんな気持ちを抱かせるもの、そんなふうに考えていらっしゃるのね。それが近代的とでもいうのでしょうが・・・・・」
「あなたはそう思わないのですか?」
「そうよ」

彼女は決然とした態度で首を横にふった。そして髪の毛を真っ赤な焔のように逆立てて、

「わたしの理想は、むかしのギリシャ人のような静かで感覚的な考え方、苦痛のない快楽よ。」

「キリスト教が唱道する恋愛なんか、わたし信じていないわよ。わたしは邪教の信者よ、わたしには、
神々と女神たちが恋をした
という詩の一節にあるように、古代の英雄時代の恋があるだけよ。そのころには、
ひと目見たあと、すぐに身体を求め
求めたあとに、たのしみがあった
のよ。それ以外のことは、みんな不自然な作りもので、ウソよ。理性と感覚の戦い、それが近代人の奉じている信条ね。でも、わたしはちがうわ」

「あなたには、ギリシャのオリンボスの山がいちばん適しているでしょう。ボクたち近代人には、恋愛の場合には、そんな古代の静寂なんか支持できません。ほかの男といっしょに女を共有するなんて、たとえそれが有名な遊女であっても、ボクたちにはたえられません。思うだけで胸が悪くなります。ボクたちは古代の神さまたちと同じように嫉妬します。ヴィーナスがどんなにこうごうしくても、今日はアンキセスを愛し、あすはアドニースを愛すというのだったら、ボクはそれを悪魔的な残酷だと見なします」

「あなたもやっぱり女性観については、気狂いじみた近代的な考えをなさるおひとりね。」
「しかし、あなたは・・・・・」
「まア、終わりまで聞いてちょうだい。女性をたいせつな宝のようにするのはいいけど、自分の懐中にしまおうなんてのは、男性のエゴイストよ。」

「バカ者め!」
「!!」

「恋愛に永続性を見いだそうといくら努力したって、そりゃ無理よ。この変わりやすい人生で、恋愛くらい変わりやすいものないですから、法律上の義務づけや宣言などはなんの効き目もありませんわ」
「しかし・・・・」

「あなたは、こうおしゃりたいのでしょうー正義人道に反する人は、社会から追放され、こらしめられるとね。」
「わたしの主義は異端よ。自分でたのしい生活だと思ったら、そういう生活を送るつもりよ」

「わたしを愛してくれれば、だれでもわたし幸福をさしあげあげるわよ。それが醜いことかしら?そうじゃないと思うわ。相手の人がわたしの美しさに刺激されて苦しんでいるのを見ながら、わたし自身が残酷にたのしんでいたり、わたしに恋こがれている人を目の前にしながら、わたしがもの固くことわりつづけるよりは、喜びには喜びを、愛には愛をさしあげるほうが、ずっと美しいことよ。」

「あなたの素直さはうれしいです。それだけじゃなく・・・・・」
「とおっしゃると?」
「・・・・」
しばらく沈黙をつづけたが、気の弱い大バカ者で、とうとう思いきって、
「あなたは、どうしてそんなふうにお考えになるようになったのですか?」
「それはなんでもないことよ。ほかの子どもたちがシンデレラ姫に夢中になっているころに、わたしはヴィーナスやアポロに夢中になっていましたの。そして大きくなって、結婚してから、結婚後まもなく不治の病にとりつかれてからも、顔を曇らせることなんか一度もなかったわ。夫は亡くなる日の前夜、わたしを抱いてくれましたが、ときどき、冗談めかして、もう好きな人がみつかったかね?と、いうのよ。わたし恥ずかしくて、顔を赤くしてしまいましたわ。そうしたら、ぼくには隠さなくてもいいよ。隠されると、かえっていやな気がする。君は美しい愛人を選ぶのだから、おもちゃがいるよ。・・・・」

「そういってたわ。って?」
「ギリシャの女神のようにだっち」
「どの女神?」
「ヴィーナスだっちさ」
と、反問して、彼女は微笑んだ。
「もちろん、毛皮を着てだっち」
彼女はまた微笑した。
次回