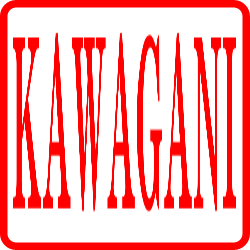初回
DQX毛皮を着たヴィーナス
前回
『毛皮を着たヴィーナス』分担
<腰かけ>

「今どこだっち?」
「彼女は白い手でわたしのあごをおさえて・・・・・」

「しかしだっち、ボクが無条件でいうなりになっている間だけのことだっちさ」
「それはあまりお利口さんの言葉じゃないよ、ゼフェリン」

「しかし、あなたには、気持ちがのみこめない。あんまり無条件に身をまかせてしまうと、きっと傲慢に・・・・」
「いいだっち。傲慢にも、専横にもなってだっち。ボクはだっち、ボクだけのものになって、それだけでいいだっち。永久にわたしのものにだっち!」

「そんなふうだと、きっと最後にはよくない結果に。」
「最後になんかなるもんかだっち。キミはどうなのだっちさ?」

わたしは興奮のあまり乱暴に叫んだ。
「ボクたちは死ななければ別れない。すべてがボクのものになれば、ボクは奴隷になってつかえます。どんなことをされても、ボクはがまんします。ボクを追い出しさえしなければ!」
「落ちついてちょうだい」

「わたし、ほんとうにあなたが好き、でもそんなふうな振舞いは、わたしに打ち勝つ方法ではないわ」

「あなたを失わないためなら、ボクはどんなことでもします。失うかもしれないと思うと、ボクはたえきれない」

「立ってちょうだい」

「不思議な人だっちね。どんな代価を払っても、所有したいだっちね」
「そうですとも!」
「でもだっち、どれだけの値打ちがあるだっち?もしもだっち、だれかほかの人のものになったとしたら?だっち?」
わたしは鋭いおどろきの衝動が体内をつっ走るのを感じて、思わずうち眺めた。
「やっぱり、おどろくだっちね」

「ボクは、ボクの愛にこたえてくれる女性が、かりにもほかの男に身を捧げてボクを忘れるとしたら、そう思うだけでボクは恐怖で身震いします。そういう女性に気の狂うまで恋していたら、ボクは虚勢を張って彼女に背をむけるでしょうか、それとも自分の手で頭へ弾丸を打ち込むでしょうか?もしもどうしてもボクの愛の幸福を十分に楽しむことが許されないなら、愛の苦しみと悩みを一滴もあまさず味わいたいと思います。」

「愛する女性から虐待され、裏切られたいです。残酷にやっつけてもらいたい。これだって、ボクにはやっぱり贅沢のひとつです」
「それ、正気でおっしゃっていますの?」
「ボクは全精神をこめてあなたを愛しているのです。ボクが生きていくには、あなたの存在とあなたの人格が必要です。あなたの夫になるか、奴隷になるか、ふたつにひとつです。どちらでもいいですから、えらんでください!」
「わかったわ」

小弓のような眉をひそめて、
「まあ、もう一度腰かけてだっち、ここから読んでみるだっち」
「え!あ、はい・・・・・」

「あなたのようにわたしを愛してくださる人を完全に支配したら、おもしろいでしょうね。慰みがひとつふえるわ。わたし、えらんであげるわよ。奴隷になってちょうだい。おもちゃにしてあげるわ。わたし、えらんであげるわよ。奴隷になってちょうだい。おもちゃにしてあげるわ」

「どうぞ、どうぞ」
そして、戦慄と狂喜にふるえて叫んだ。
「結婚は共通の立場と同意によって成り立つものですが、奴隷となると違います。立場は反対になり、敵対的にさえなります。ボクの恋は、一部は憎しみ、一部は恐れになります。あなたがハンマーなら、ボクはカナシキになります。ボクは恋する女性を崇拝したいのです。」

「でもゼフェリン。そんなにどうして虐待できますか?」
「できないことはないだっち。虐待されればされるほど、崇拝するだっち」
「ほかの男性がいやがることが、魅力があるとでも?」
「そうですだっち」
「・・・・・・・」

「でも、あなたの情熱だって、それほど不思議なものではないと思うわ。美しい毛皮はだれからも愛されるし、性欲と残酷とがどんなに深い関係にあるかも、みんな知ってるわ」

わたしと彼女は、甘美な夏の夜、彼女の小さいバルコニーに腰をかけていた。緑の木の葉の天井のうえに、もう一つ無数の星をまき散らした円天井の大空があった。

恋猫が相手を呼ぶ低い鳴き声が聞こえてきた。
「腕はまだだから、おしりに注射しますね」

わたしは神々しい彼女の足もとの足台に腰掛けて、幼児の思い出をはなした。
次回
『毛皮を着たヴィーナス』伯母