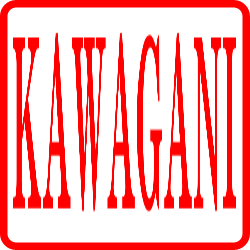初回
DQX毛皮を着たヴィーナス
前回
『毛皮を着たヴィーナス』腰かけ
<伯母>

「そんな幼いころから、そういう不思議な傾向がありましたの?」

「そうです。ボクは乳母の健康な乳房を軽蔑してたので、山羊の乳で育てられました。幼い頃から女性の前では神秘的に内気で、はにかみ屋で、しかも女性にたいして非常な関心をもっていたのです。」

「そしてひそかに父の書斎にしのび込んで、石膏のヴィーナスを眺めて秘密の喜びを味わいました。その前にひざまずいてお祈りをしました。彼女の冷たい足に熱烈に接吻しました。」

「抵抗しがたい思慕の情にかられて、彼女の美しいからだを抱きしめて、冷たい唇に接吻しました。そしてはげしい戦慄におそわれて逃げだしました。」

「十四歳のころでした。母は、若くして魅惑的な花の蕾のような少女を寝室付きの女中として召し使っていました。」

「ある日、ボクが自分の部屋でタキトゥスの文章を読んでいると、その少女が掃除にやってきました。」

「そしてとつぜん、イカ箒(ほうき)をもったまま、」

「ボクのからだのうえに身をかがめて、新鮮で熟した愛らしい唇のうえに押しつけました。」

「ボクは不思議な懐かしさにからだをうちふるわせましたが、部屋から飛び出してしまいました・・・・・」

「ホホホ!」
と彼女は大声で笑いだして、

「ほんとに、あなたみたいな人っていないわね。でも、お話をつづけてちょうだい」

「やはり、そのころのことですーーーー」
とわたしは話をつづけたーーーー

「遠縁にあたる伯母のゾボル伯爵夫人が、両親のところへたずねてきました。ボクは大嫌いでしたから、」

「この伯母にたいしてできるかぎり乱暴をはたらきました。」

「ある日、両親が州の郡へ出かけた留守に、伯母は毛皮のチョッキに身をかためて、あの、寝室付きの猫娘をつれて、ボクの部屋を襲いました。」

「そして有無をいわせずボクをつかまえると、暴れるボクをおさえつけて、ヒモで手足を縛ってから、」

「伯母は、悪意に満ちて笑顔で袖をまくりあげて、強くて丈夫なムチでボクをしたたかに打ちはじめました。ボクはとうとう悲鳴をあげて、涙を流して、熟した慈悲を請いました。」

「すると伯母はわたしを解きはなしてくれましたので、わたしはその場にひざまずいて謝罪し、伯母の手に接吻しなければなりませんでした。」

「これで、ボクがどんなに超官能のおろか者であるかが、あなたにもよくおわかりになったでしょう。ボクの感覚は、美しい女性のムチのもとで、はじめて女性の意味をさとりました。毛皮のジャケットを着た淑母が、ボクには激怒した女王のように思われました。」

「ボクが大学に進んでからのことでした。ゾボル伯母の家をたずねていきました。伯母は心をこめて親しげにボクを迎え、歓待のキッスをしてくれました。そのため、ボクの理性はたちまち混乱してしまいました。伯母はたぶん四十歳ぐらいでしたが、世界中でもっとも若さをたもっていて、今でも非常に魅惑的でした。かつてわたしを喜ばしたきびしさはまったく影をひそめていましたが、残忍さがまったくないでもなかったので、ボクはますます伯母を慕うようになったのです。」

「ボクは伯母の前にひざまずいて身を投げ出し、その手に接吻しました。なんと喜ばしいことだったのでしょう!美しい格好で、繊細で、丸く肉付いていて、白くて、なんと不思議な手であったことでしょう。ボクは実際、伯母の手に恋しました。その手と遊び、黒い毛皮の中に沈めたり、出したり、光にかざしてみたり、あかず眺めました」

わたしの言葉に、ヴァンダ未亡人はふと自分の手の上に視線を落として微笑した。
次回
『毛皮を着たヴィーナス』真夜中