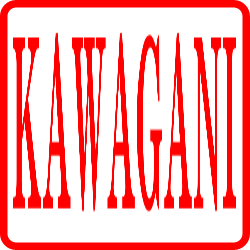初回
DQX毛皮を着たヴィーナス
前回
『毛皮を着たヴィーナス』王子
<交換>

数日後、わたしと彼女はたのしいドライブに出た。

すると途中であのロシアの王子のホッピーに出会った。

王子はわたしのそばにいるのを見ておどろき、不愉快そうな顔をしたが、稲妻のような鋭い目つきで、何度も彼女を見つめた。

しかし彼女はそしらぬふりをしていた。わたしはそれに気づいて、彼女の前にちかずいて感謝したいほどであった。彼女は彼を一個の木石のように見なして、無関心な一瞥(いちべつ)をあたえただけで、すぐにわたしのほうをむいて、やさしく微笑した。

その後、わたしが彼女にさよならをいって、部屋を出ようとすると、彼女は急に非常に不機嫌になって、
「逝ってしまっては、つまらないわね」
「わたしの苦しみを短くするのも長くするのも、やめるのもやめないのも、あなたの手のうちにあるのです」

「その強制で、わたしもやっぱり、苦しみをうけているのよ、そうは思わないこと?」
「それなら、苦しみをやめてわたしの妻になってください!」
「それはダメよ」

「どうしてですか?」
「あなたはね、わたしの夫になれる人じゃないですもの」

わたしは、やむなく部屋を出たが、彼女はわたしを呼び戻そうとはしなかった。

ねむれない一夜。
わたしは、ああも思いこうも考えたが、気持ちがきまらず、一夜を過ごしてしまった。

そして朝になってから、わたしたちの関係を解消するという宣言の手紙を書き、封蝋(ふうろう)を溶かして封印した。わたしは、ふるえる手でそれを持って、二階へあがっていくと、彼女の部屋のドアは開いていた。彼女は、髪にカールをつけるための髪でいっぱいになった頭をつき出して、
「あたし、まだ髪をゆってないのよ」
といってから、わたしの持っているものに目をとめて、

「なにを持っていらしたの?」
「手紙です」
「わたしに?」
「そうです」
「わたしに別れようというのね」
「きのう、あなたはボクのことを、あなたの夫になれない人だとおっしゃったではありませんか」
「そうよ、今でも同じよ」
「それなら、それでいいです」

わたしは全身をふるわせながら、その手紙を彼女に渡した。が、彼女は冷ややかにわたしを見つめて、
「いまのままでいいのよ。あなたが男としてわたしを満足させるかどうかは、問題ではないってことを、あなたは忘れているのね。奴隷としてなら十分にやれるわよ」

そして彼女は、いいようのないひどい軽蔑の身ぶりをして、つーんとして、

「二十四時間以内に、あなたの身の回りをきちんと片づけてちょうだい。明後日、イタリアへ旅立つから、あなたはわたしの召使いとして行くのよ」

「ヴァンダ!」

「親切さは絶対に許しませんわ。わたしがベルを鳴らさないかぎり、わたしの部屋へはいらないこと、話しかけられるまではじっとだまって待っていること、あなたの名前はゼフェリンではなくて、グレゴールよ。わかって?」
わたしは怒りにふるえたが、拒否することができなかった。それどころか、かえって不思議なたのしみと刺激を感じた。

翌日の夜更けであった。わたしは大きなストーブのそばで、夢中になって手紙や書類などを整理していた。秋は急に深くなっていた。

とつぜん、ムチの柄で窓の戸をノックする音がした。急いで窓を開けるてみると、彼女が貂の毛皮のついたジャケットを着て、カテリーナ女帝好みの貂の毛のコサック帽をかぶって立っていた。
「用意はととのいましたか、グレゴール」
「いえ、まだです、ご主人さま」

「その言葉はいいわね。これからは、いつもわたしをご主人さまと呼ぶのよ。明日の朝は九時に出発よ。それから、わたしたちが鉄道に乗ったら、あなたはわたしの奴隷よ。さあ、窓を閉めて、ドアのほうを開けてちょうだい」
彼女はわたしの部屋にはいるなり、皮肉な調子で、
「わたし、どう見えて?気に入った?」
「あなたは・・・・・」
「だれがそんな言葉づかいを許しましたか!」

彼女はムチをふるって、びゅーんとわたしを打ちすえた。
「非常にお綺麗でございます。ご主人さま」
彼女はうれしそうにほほえんで、
「ひざまずいて、ここに」

といって、わたしを椅子のそばにひかえさせた。
「わたしの手に接吻を」
わたしは彼女の冷たい手をとって、うやうやしく接吻した。
「口にも」

わたしはたちまち感激して、この残酷な美女の唇や頬や額や腕や胸に灼熱の雨をふらせた。彼女もうっとりとして、熱情的に雨をふらせた。

次回
『毛皮を着たヴィーナス』召使い