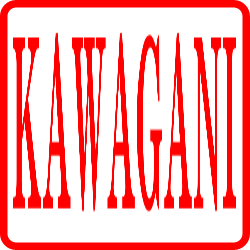初回
DQX毛皮を着たヴィーナス
前回
『毛皮を着たヴィーナス』交換
<召使い>

朝九時、わたしたちは軽馬車でカーペシアン保養地をあとにした。

州の首都について駅までくると、馬車をおりた。

彼女は毛皮をぬいで、わたしの腕にかけて、自分で切符を買いに行った。そしてもどってくると、
「これ、おまえの切符、グレゴール」
と高慢な淑女そっくりの語調でいいながら、一枚の切符をつきだした。

「へえ、三等切符!」
「だっち」
わたしは唖然とした。

「あたりまえよ。これからわたしのいうことに注意してよ。わたしが車室に落ちついて用事がなくなるまで、おまえは汽車に乗ってはいけません。どこの駅についても、すぐにわたしのところへかけてきて、わたしの命令を待つのよ。忘れてはダメよ。さあ、わたしの毛皮をちょうだい」

あいた車室を探して彼女を落ちつかせると、わたしは彼女の両脚を熊の皮で巻いてやり、湯たんぽのうえに足をのせた。

わたしは列車が駅にとまるたびに三等車からいち早く飛び出して、彼女のそばへかけ寄って命令を待った。

コーヒーといえばコーヒーを、水といえば水を、すぐさま持参した。

彼女は同じ車室の数名の男たちを近くにひきよせて、機嫌をとらせていた。

わたしは嫉妬で死ぬ思いをしながら、身を粉にして彼女のために働いた。

汽車がウィーンに着くと、彼女は贅沢なガウンを買うために途中下車した。

彼女は温泉に入り、わたしは相変わらず彼女の召使いとして、十歩の間隔をおいてうやうやしく従った。

「温泉に入ったって、ウィーンの温泉?」
「湯布院だっち、大分だっち」
「湯布ウィーン!」
「だっち」

翌日、そこを出発する前に、彼女はわたしの服を全部取りあげてホテルのボーイにくれてやり、わたしには、お仕着せだといって、彼女好みの明るい青地に黄色い縁取りの付いた服と、橙色のバンダナをくれた。この服が妙にわたしに似合ったとは!

うるわしい女魔王の彼女は、ウィーンからフィレンツェへ。

豪華な一等車でふんぞり返っている彼女にひきかえ、わたしは三等車の拷問台のような木製寝台に横たわった。からだがこわれてしまいそうだった。

夜のとばりの くまなくて
かぎりなき 星のまたたき
深きあこがれ いつしかに
夜にしみ入る やわらかく

夢のわだつみ 帆をあげて
わがこころ ひたぶるに
君が胸をば 求むなれ
やすらいの 永久のとまりと
わたしはドイツの民謡を口づさみながら、毛皮につつまれて帝王のように満足してねむる彼女の姿を想像するのだった。

フィレンツェに到着、駅前は群衆、叫喚(きょうかん)、うるさくせがむ運搬夫、辻馬車の客引き、彼女は馬車をえらんだ。

「グレゴール、これ、引き替えの切符、さあ荷物をとっておいで」
彼女は毛皮につつまれて、馬車におさまってしまった。わたしは汗水たらして重いトランクをつぎつぎに運んでいった。最後のひとつをおろしそこねて、危うく押しつぶされてるところだったが、一人の騎銃兵が手を貸してくれたので助かった。彼女は笑いながら眺めていた。わたしは額の汗をぬぐって馭者台にのった。数分ののち、立派なホテルの前に着いた。

「部屋はあって?」
「はい、ございます」
とマネージャーはいんぎんに答えた。
「一等室をふたつ。それはわたしの分よ。それから別に召使いの分をひとつ、みんなストーブ付きで」
「はい、一等室のほうはみなストーブがついておりますが、お召使いさまのほうは?」
「ストーブがなくてもねむれるから、いいわよ」

部屋の検分がすむと、彼女は、
「グレゴール、トランクを運び上げなさい。わたしは、着替えをして食堂へ行ってくるわ。おまえも用事がすんだら、なにか夕食をとりなさい」
といって、さっさと部屋におさまってしまった。

わたしは荷物を運びあげてから、ボーイのてつだいをしてストーブに火をたきつけた。

ボーイはわたしを歓待しようとして、ドイツ語でいろいろと苦労話しをしながら、食堂へ連れて行ってくれて食事の給仕をしてくれた。わたしは三十六時間ぶりで、はじめて口あけの酒を飲み、あたたかい肉をフォークで口に運んだ。

そこへ彼女が入ってきた。わたしは急いで立ちあがった。
「まア、これはどうしたわけなの。召使いが食事しているようなところへ、わたしを案内するなんて!」

彼女は怒りに燃えて、給仕をどなりつけると、さっと身をひるがえして出て行ってしまった。

わたしは食事を終わって四階にあるわたしの部屋にのぼっていった。そこにはみじめな油ランプがひとつ燃えていた。ストーブもなく、窓もない、痛風口がひとつあるだけの屋根裏の部屋であった。わたしはあきれて自嘲的に笑っていると、急にドアが開いて、給仕が芝居がかった身振りで、
「ご主人様が、すぐにくるようにとの仰せでございます」

わたしは大急ぎでかけおりて、彼女の部屋のドアをノックした。
「おはいり」
わたしはなかへはいって、ドアを閉めて、彼女の前に直立不動の姿勢をした。
彼女は心待ちよげに長椅子に腰かけていた。大燭台の黄色い灯火。大鏡の反射。暖炉の赤い焔。織物の外套をはおった彼女は冷然とした表情で、
「よくやってくれたわね。グレゴール」
「はいだっち」
わたしはうやうやしく頭を下げた。
「もっとこっちへお寄り」
「はいだっち」
「もっと、そばへ」
彼女はうつむいて、白い手で毛皮をなでまわしていたが、
「織物を着たヴィーナスが、その奴隷を接見するわ。おまえは、夢想家以上の夢想家ね。わたし、そういうのが好きよ。おまえは、むかしの帝国の時代だったら、さしずめ、恋の殉教者よ、フランス革命の時代だったら、断頭台にのぼったジロンド党のひとりというところ、でも、おまえはわたしの奴隷、わたしの・・・・・」

彼女は急に立ちあがった。織物はずり落ちた。彼女はそんなことにはかまわず、わたしの首のまわりにやわらかく両手をまきつけて、

「わたしの愛する奴隷のゼフェリン!いきな男ぶり、今夜は火の気のない部屋で、ひとり寝とは寒いでしょうね。わたしの毛皮を一枚あげましょうか、かわいいあなたに・・・・・」
彼女は、すばやく大きな毛皮を一枚取り上げて、わたしの肩にかけて、くるくるとわたしのからだをつつんでしまった。
「まあ、なんてすてき!よく似合うわ。気品が出てきたわ」
彼女はわたしのからだを愛撫して、接吻した。それがすむと、

「あなたは毛皮を着て、ひとりで喜んでいるのね。早くそれをわたしに返してちょうだい。さもないと、わたし、威厳をなくしてしまうから」
わたしは彼女に毛皮をかけてやった。

「今日は、あなたは堂々と役割を演じてくれたわね。わたし、うれしかったわ、でも、わたしのことをひどい人と思わなかったこと?ねえ、なんとか返事してよ。____これ、命令よ」
「どうしても、ボクの気持ちをいわねばならないのですか?」
「そうよ」

「それならいいますが、ボクは虐待されればされるほど、いっそう深くあなたを愛します、崇拝します」
わたしは、彼女を抱き寄せて、彼女のぬれた唇を合わせた。

「わたしがいくら残酷に振舞っても、あなたはわたしを愛してくださるのね」
彼女はほっとため息をついてから、

「さあ、お帰り!いつまでもおまえがそばにいると、退屈だわ」
といって、いきなりわたしの耳に平手打ちをくれた。
わたしは目から火が出たように感じ、耳の奥がぐわーんとした。

「その毛皮を着せてちょうだい、奴隷!」
わたしは命じられるままに手をかし、できるかぎり一生懸命になって、毛皮を着せてやった。
「なんて不器用な!」

彼女はまたもわたしの額をぴしゃりと叩いた。わたしの顔は青くなった。
「傷がついて?」
彼女は白い手で、やわらかくわたしの顔をなでまわし、

「不平をいう理由はないわね、あなたがそうしてもらいがっているんですから、さあ、もう一度、接吻して!」
わたしは、彼女のからだにしっかりと抱きついて、唇を求めた。そして重い大きな毛皮のなかで抱き合ったままころがった。

___メス熊がわたしを抱きかかえている。四肢の爪がわたしの背中の肉に突きささっている。
わたしはそんな幻想にとらわれていたが、まもなく彼女はわたしをつき放して立ちあがった。
「フィレンツェって?」
「火の国だっち」
「フィの国」
「熊本だっち」
「・・・・・・」

次回
『毛皮を着たヴィーナス』誓約同意書