
ボディソニックでリラックス&ストレスドック
私と健康心理学(5)ストレスマーカ探索の旅
●ストレスをはかる新研究
自殺者が連続7年3万人(註:2006年現在の記載。1998年以来2008年まで連続11年3万人が新しい資料)。自殺の前駆症状が鬱で、その鬱の前駆症状がストレスときている。ストレスマネジメントでなんとか鬱への移行を止められないか、そして自殺をくい止められないかと、いろんな方面から声が聞こえてくる。
健康心理学者を標榜する私は、黙ってはいられない。そこでこの春、本学に大学院人間科学研究科を創設し、ストレスマネジメントを研究する心理学領域の主任になって、臨床生理心理学実験室を作ってもらったのを機に、ストレスマーカー探しという新しい研究をスタートさせることにした。
●生理心理学
私は大学大学院を通じて、生理心理学を専攻としてきた。生理心理学は心理学の中でも、自然科学に最も近い領域である。そこで学位を得たので、医学分野の人たちとの交流も多く、共通の関心事をたくさんもっている。
しかもここ10年ほど健康心理学という応用分野に足を染めた関係上、ストレスマネジメントの生理心理学的基礎研究が大きなウェイトを占めている。中でも、自記式質問紙にハイ/イイエで答えていって、「はいあなたのストレス度は何点です」というような形式ではなく、リトマス試験紙のような検査器具を一舐めさせ、その発色具合をリーダに読み込ませたらストレス度60というような結果が出るものを開発したいとおもっている。できるだけ簡便で、かつストレスの度合いに敏感。ストレスの度合いが客観的な数値として出てくる。そんなストレス測定技法を開発したいのである。
私は生理心理学の基礎技術を発展させて、健康心理分野に貢献したいという単純な動機を以前から抱いていた。だがなかなか研究環境が整わなかった。それがこの春、実現できることになったのである。
●生理指標
これまで私の研究室では、脳波とまばたきを中心に測定できる装置をフル稼働させて、心地よさや感動体験の詳細を生理心理学的に研究してきた。この技術は、もちろんストレスの測定にも転用可能である。
脳波α波成分が増えれば、リラックス状態を現す。
私の得意とする前頭正中線部に観察される脳波Fmθ(エフエムシータ)は、集中し、没頭しているときによく現れ、ストレス状態では消失する。またストレス状態で、まばたきは多発する。
これら既存の機械に加えて、新しい生体反応記録装置を導入することになった。
まず心電図からr-r間隔を計測し、瞬時心拍率をリアルタイムで解析し、それをもとに自律神経指標を計測するシステムがある。これはテレメータを使ったワイヤレス計測なので被験者への負担は少なくて済む。被験者の胸に三箇所、使い捨ての心電図電極を装着するだけ。そのリード線は、服に装着した五百円玉大の発信器へつながっている。PCに装着した受信機でデータを受信し、心電図波形を認識するというもの。
ストレス状態が高まれば、心拍率は増加し、交感神経優位となる。
これらの機械に今春、驚愕性瞬目反射計測システムが追加導入された。
眼輪筋筋電図をワイヤレスで計測しつつ、ワイヤレスヘッドフォンを通じて100dBの強度をもつ白色バースト音を被験者に聴かせ、この刺激に対する眼輪筋反射を計測・評価するシステムである。
ストレス状態が強ければ、音刺激を繰り返し提示したときに生じる反射の慣れが、遅れるはずである。
またPPI【prepulse inhibition】という現象を測定できる。これは、驚愕誘発刺激に微弱な音刺激を百ミリ秒先行付加すると、驚愕反射が抑制される強固な現象だが、統合失調症の患者では消失し、恐怖症では亢進する。各種精神障害やストレス状態との関連を検証し、症状把握に有力な指標として確立したいところである。
●内分泌・免疫指標
よだれを3ccほどもらえれば、それを検査会社に出して唾液中分泌型免疫グロブリンA(s-IgA)の含有量が測定できる。急性ストレスによってs-IgAは増加し、慢性ストレス状況では分泌量は低下することがわかっている。
さらに残った唾液を高速液体クロマトグラフィにかけて、コルチゾール成分の含有量を計測することができる。この春、コルチゾールを分析するためのシステムを導入し、一月かけて稼働できる状態にしたところである。
さらに唾液中のαアミラーゼ活性を15秒ほどで定量化する装置も導入できた。
●動作解析
歩行中の手足の細かな動きや、閉眼片足立ち時の身体の揺れ画像を3台のカメラで撮影し、3D解析して各種の運動指標を測定評価することができる。こうした動作指標は、これまでリハビリによる運動機能回復過程を評価するのに使われてきたが、ストレス状態やうつ症状を客観的に測定する動作指標として確立できないかと期待している。
●ストレスドック
これらの装置をフル稼働させて、ストレス状態を複数の生体反応を用いて総合的に把握することができる。もちろん、これまで使ってきた自覚症状調査や主観的気分評定、状態不安尺度や各種ストレス尺度もすべて使って、ストレス状態を他覚的・多角的に把握することになる。主観的なストレス症状と、心電図や脳波などの生理反応、動作解析という行動指標、それに唾液中コルチゾールやアミラーゼ活性などの内分泌・免疫指標の動態という四つの異なる次元のデータを得ることによって、どのような画期的な成果が期待できるだろうか。今私は大きな夢を抱いているところである。
2006/5/15校了
私と健康心理学(5)ストレスマーカ探索の旅
●ストレスをはかる新研究
自殺者が連続7年3万人(註:2006年現在の記載。1998年以来2008年まで連続11年3万人が新しい資料)。自殺の前駆症状が鬱で、その鬱の前駆症状がストレスときている。ストレスマネジメントでなんとか鬱への移行を止められないか、そして自殺をくい止められないかと、いろんな方面から声が聞こえてくる。
健康心理学者を標榜する私は、黙ってはいられない。そこでこの春、本学に大学院人間科学研究科を創設し、ストレスマネジメントを研究する心理学領域の主任になって、臨床生理心理学実験室を作ってもらったのを機に、ストレスマーカー探しという新しい研究をスタートさせることにした。
●生理心理学
私は大学大学院を通じて、生理心理学を専攻としてきた。生理心理学は心理学の中でも、自然科学に最も近い領域である。そこで学位を得たので、医学分野の人たちとの交流も多く、共通の関心事をたくさんもっている。
しかもここ10年ほど健康心理学という応用分野に足を染めた関係上、ストレスマネジメントの生理心理学的基礎研究が大きなウェイトを占めている。中でも、自記式質問紙にハイ/イイエで答えていって、「はいあなたのストレス度は何点です」というような形式ではなく、リトマス試験紙のような検査器具を一舐めさせ、その発色具合をリーダに読み込ませたらストレス度60というような結果が出るものを開発したいとおもっている。できるだけ簡便で、かつストレスの度合いに敏感。ストレスの度合いが客観的な数値として出てくる。そんなストレス測定技法を開発したいのである。
私は生理心理学の基礎技術を発展させて、健康心理分野に貢献したいという単純な動機を以前から抱いていた。だがなかなか研究環境が整わなかった。それがこの春、実現できることになったのである。
●生理指標
これまで私の研究室では、脳波とまばたきを中心に測定できる装置をフル稼働させて、心地よさや感動体験の詳細を生理心理学的に研究してきた。この技術は、もちろんストレスの測定にも転用可能である。
脳波α波成分が増えれば、リラックス状態を現す。
私の得意とする前頭正中線部に観察される脳波Fmθ(エフエムシータ)は、集中し、没頭しているときによく現れ、ストレス状態では消失する。またストレス状態で、まばたきは多発する。
これら既存の機械に加えて、新しい生体反応記録装置を導入することになった。
まず心電図からr-r間隔を計測し、瞬時心拍率をリアルタイムで解析し、それをもとに自律神経指標を計測するシステムがある。これはテレメータを使ったワイヤレス計測なので被験者への負担は少なくて済む。被験者の胸に三箇所、使い捨ての心電図電極を装着するだけ。そのリード線は、服に装着した五百円玉大の発信器へつながっている。PCに装着した受信機でデータを受信し、心電図波形を認識するというもの。
ストレス状態が高まれば、心拍率は増加し、交感神経優位となる。
これらの機械に今春、驚愕性瞬目反射計測システムが追加導入された。
眼輪筋筋電図をワイヤレスで計測しつつ、ワイヤレスヘッドフォンを通じて100dBの強度をもつ白色バースト音を被験者に聴かせ、この刺激に対する眼輪筋反射を計測・評価するシステムである。
ストレス状態が強ければ、音刺激を繰り返し提示したときに生じる反射の慣れが、遅れるはずである。
またPPI【prepulse inhibition】という現象を測定できる。これは、驚愕誘発刺激に微弱な音刺激を百ミリ秒先行付加すると、驚愕反射が抑制される強固な現象だが、統合失調症の患者では消失し、恐怖症では亢進する。各種精神障害やストレス状態との関連を検証し、症状把握に有力な指標として確立したいところである。
●内分泌・免疫指標
よだれを3ccほどもらえれば、それを検査会社に出して唾液中分泌型免疫グロブリンA(s-IgA)の含有量が測定できる。急性ストレスによってs-IgAは増加し、慢性ストレス状況では分泌量は低下することがわかっている。
さらに残った唾液を高速液体クロマトグラフィにかけて、コルチゾール成分の含有量を計測することができる。この春、コルチゾールを分析するためのシステムを導入し、一月かけて稼働できる状態にしたところである。
さらに唾液中のαアミラーゼ活性を15秒ほどで定量化する装置も導入できた。
●動作解析
歩行中の手足の細かな動きや、閉眼片足立ち時の身体の揺れ画像を3台のカメラで撮影し、3D解析して各種の運動指標を測定評価することができる。こうした動作指標は、これまでリハビリによる運動機能回復過程を評価するのに使われてきたが、ストレス状態やうつ症状を客観的に測定する動作指標として確立できないかと期待している。
●ストレスドック
これらの装置をフル稼働させて、ストレス状態を複数の生体反応を用いて総合的に把握することができる。もちろん、これまで使ってきた自覚症状調査や主観的気分評定、状態不安尺度や各種ストレス尺度もすべて使って、ストレス状態を他覚的・多角的に把握することになる。主観的なストレス症状と、心電図や脳波などの生理反応、動作解析という行動指標、それに唾液中コルチゾールやアミラーゼ活性などの内分泌・免疫指標の動態という四つの異なる次元のデータを得ることによって、どのような画期的な成果が期待できるだろうか。今私は大きな夢を抱いているところである。
2006/5/15校了










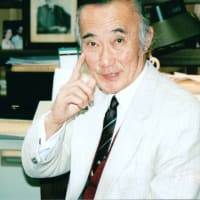

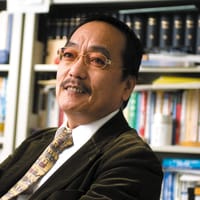







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます