
2010年5月31日開講の心理学概論、第3章学習2で使う資料です。
動機づけループのところでつかった図版が1枚目にありますね。
道具的条件づけのお話です。
ソーンダイクの問題箱の実験から話をはじめます。
試行錯誤をするうちに、問題解決をしてしまう猫の実験からソーンダイクは道具的条件づけを発見しました。
食欲(動機)が高い状況の猫を、問題箱につめこみます。
はたして猫は見事仕掛けを潜り抜けて箱の外の餌を手に入れることができるでしょうか。
立ち上がり、前足でもって、天井からつるされている紐を下に引っ張りさえすれば扉は開くという仕掛け。
いろんなことをするうちに、たまたま紐をひっぱり餌にありつける経験を何度かするうち、猫は箱に入るやすぐに立ち上がり紐をひっぱり餌にありつく。
これが試行錯誤。trial and error学習ともいわれます。
この学習は、紐をひくという行動によって、食欲を低減させたという、よい結果が正しい行動を頻発させるという「効果の法則(Law of effect)」によるといわれます。
スキナーの作った箱(スキナー箱)の中にラットも同様。
空腹ラットはスキナー箱の中でいろいろな行動(オペラント行動)をとりますが、バーを押すというただ一つの行動だけが、餌を手に入れる手段。
なん度かラットは
バー押し => 餌
の経験を経て、スキナー箱の中ではバーを押して餌をゲットするようになります。
スキナーはバー押し反応の累積曲線を分析することによって、動物のオペラント条件づけに関する様々なルールを見いだしました。
種々の強化スケジュールと累積反応パターンの特徴ある関係などは大変おもしろい。
バー押しの都度1つ餌を与えるより、何度かバーを押さないと餌を与えないようにしたほうが、反応は強くなります。
また、学習行動が形成されたあと、消去手続きにうつってもなかなか行動は減少しません。
博打うちがなかなかやめられないのと関係してそうでしょ。
スキナーは、ハトが嘴でつつく行動(ペッキング)も使って多くの実験研究をしました。
猫の紐引き行動、ラットのバー押し、ハトのペッキングは、餌(強化)を得るための道具(手段)と考えてみましょう。
道具的条件づけという言葉の意味がわかりますね。
5枚めの絵は、蛇恐怖が形成される図式です。
へびに対する恐怖(情動)の古典的条件づけが形成されたあと、恐怖の元=へびから逃れる回避行動が生まれるとするマウラーの学習二要因説の図式です。
恐怖症はphobiaとよばれます。日本人はへび嫌いが多いですね。
アメリカ人は、蜘蛛を恐れる恐怖症が多いようです。
怖がる行動は、不安障害と呼ばれる心の病の1グループです。
不安障害のほかに、うつ病などの気分障害も心の病のもう1つのグループです。
うつ病発生のメカニズムは、セリグマンが学習性絶望実験によって明らかにしました。
まず、何をやっても回避できない痛み刺激を与え続けられたイヌを用意します。
つぎに回避可能な事態に入れますが、不幸にして回避行動をとらなくなるのです。
こうして、学習性絶望(learned helplessness)という現象が現れたイヌの様子はまさにうつ病。
こうして作られた、うつの動物モデルを被献体として、鬱治療の特効薬が開発されました。
最後の資料は、人間の学習のほとんどが物真似からおこるという話。
バンドゥーラは、これを他者の模倣=他者への強化が自己への強化の代理として働くと考えました。
社会的模倣学習というのですが、人の振り見て我が振り直すという格言通りです。
以上のように学びのルールを学びましょう。
もう、先週最初に投げかけた質問に対しては正しく答えることができるようになりましたか?
最初にテストしますので楽しみに。
2010/05/31・髭
動機づけループのところでつかった図版が1枚目にありますね。
道具的条件づけのお話です。
ソーンダイクの問題箱の実験から話をはじめます。
試行錯誤をするうちに、問題解決をしてしまう猫の実験からソーンダイクは道具的条件づけを発見しました。
食欲(動機)が高い状況の猫を、問題箱につめこみます。
はたして猫は見事仕掛けを潜り抜けて箱の外の餌を手に入れることができるでしょうか。
立ち上がり、前足でもって、天井からつるされている紐を下に引っ張りさえすれば扉は開くという仕掛け。
いろんなことをするうちに、たまたま紐をひっぱり餌にありつける経験を何度かするうち、猫は箱に入るやすぐに立ち上がり紐をひっぱり餌にありつく。
これが試行錯誤。trial and error学習ともいわれます。
この学習は、紐をひくという行動によって、食欲を低減させたという、よい結果が正しい行動を頻発させるという「効果の法則(Law of effect)」によるといわれます。
スキナーの作った箱(スキナー箱)の中にラットも同様。
空腹ラットはスキナー箱の中でいろいろな行動(オペラント行動)をとりますが、バーを押すというただ一つの行動だけが、餌を手に入れる手段。
なん度かラットは
バー押し => 餌
の経験を経て、スキナー箱の中ではバーを押して餌をゲットするようになります。
スキナーはバー押し反応の累積曲線を分析することによって、動物のオペラント条件づけに関する様々なルールを見いだしました。
種々の強化スケジュールと累積反応パターンの特徴ある関係などは大変おもしろい。
バー押しの都度1つ餌を与えるより、何度かバーを押さないと餌を与えないようにしたほうが、反応は強くなります。
また、学習行動が形成されたあと、消去手続きにうつってもなかなか行動は減少しません。
博打うちがなかなかやめられないのと関係してそうでしょ。
スキナーは、ハトが嘴でつつく行動(ペッキング)も使って多くの実験研究をしました。
猫の紐引き行動、ラットのバー押し、ハトのペッキングは、餌(強化)を得るための道具(手段)と考えてみましょう。
道具的条件づけという言葉の意味がわかりますね。
5枚めの絵は、蛇恐怖が形成される図式です。
へびに対する恐怖(情動)の古典的条件づけが形成されたあと、恐怖の元=へびから逃れる回避行動が生まれるとするマウラーの学習二要因説の図式です。
恐怖症はphobiaとよばれます。日本人はへび嫌いが多いですね。
アメリカ人は、蜘蛛を恐れる恐怖症が多いようです。
怖がる行動は、不安障害と呼ばれる心の病の1グループです。
不安障害のほかに、うつ病などの気分障害も心の病のもう1つのグループです。
うつ病発生のメカニズムは、セリグマンが学習性絶望実験によって明らかにしました。
まず、何をやっても回避できない痛み刺激を与え続けられたイヌを用意します。
つぎに回避可能な事態に入れますが、不幸にして回避行動をとらなくなるのです。
こうして、学習性絶望(learned helplessness)という現象が現れたイヌの様子はまさにうつ病。
こうして作られた、うつの動物モデルを被献体として、鬱治療の特効薬が開発されました。
最後の資料は、人間の学習のほとんどが物真似からおこるという話。
バンドゥーラは、これを他者の模倣=他者への強化が自己への強化の代理として働くと考えました。
社会的模倣学習というのですが、人の振り見て我が振り直すという格言通りです。
以上のように学びのルールを学びましょう。
もう、先週最初に投げかけた質問に対しては正しく答えることができるようになりましたか?
最初にテストしますので楽しみに。
2010/05/31・髭










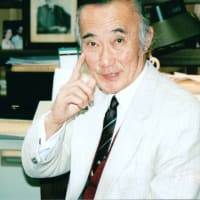

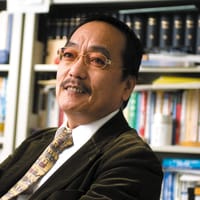







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます