







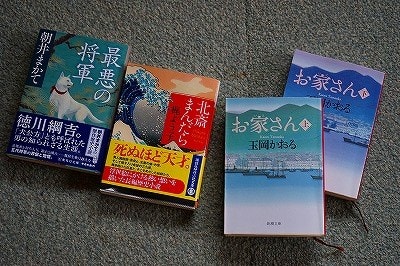
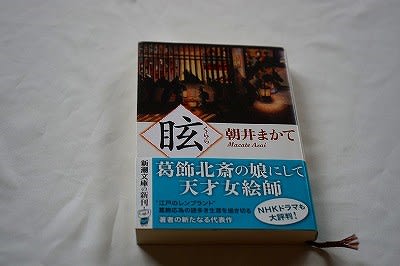
源氏物語の第30帖に「藤袴」という巻があり、夕霧は玉蔓に藤袴を差し出して
「おなじ野の露にやつるゝ藤袴あはれかけよかことばかりも」
と詠いかける。
口語訳は「あなたと同じ野原で露に濡れてしおれている藤袴です。せめて、可哀
そうだといって同情の言葉をかけてやってください」
(参照;ウイキぺディア、ほか)
優美な花姿のなフジバカマ

秋になって色あせて・・・

刈り取ることに

根の部分を残してすっきりしたプランター

昨日は、フラワーアレンジ教室恒例のクリスマス・リースの制作日。
いつものように、先生に用意していただいた素材で挑戦する。
オアシスは写真のような円形、今回はその円形に沿って生の葉や花を挿し
て埋めていく。
卓上型なので、あれこれ欲張って挿したので、これまでのクリスマス・リース
のイメージから少し外れ、空洞になるべきはずの中心も埋め尽くされた円盤
型?の賑やかな花輪に仕上がった。
まあ、いいっか、こんなリースもありかな^^
オアシスの水がなくなり、ドライリーフ(フラワー)になったら壁に吊るすことも
できるが、暫くは置き物として仏壇に供えることにしよう。
仏さんも苦笑いか・・・
!?・・・ちょっと知ったかぶり・・・!?
<リースについて>
リース(wreath)は花や葉、果物で作る装飾用の花輪で、輪はエンドレスだ
からは「永遠」という意味があり「命や幸福がいつまでも続く」という願いが
込められている。
リースは古くはローマ帝国時代のローマ人によって、祭事の際に主に
女性が身に付け、男性は冠として使用した。
威信の象徴であり、華や枝、蔓、月桂樹の葉などで作られ、結婚式な
ど特別な行事によく使われた。
ローマ皇帝がキリスト教を国教と定めたことから、ローマのリース風習が
キリスト教にも広まり、クリスマス・リースの元になったった、という説が有力。
(ウイキペディアなどから)





2017年のリース

2018年のリース

