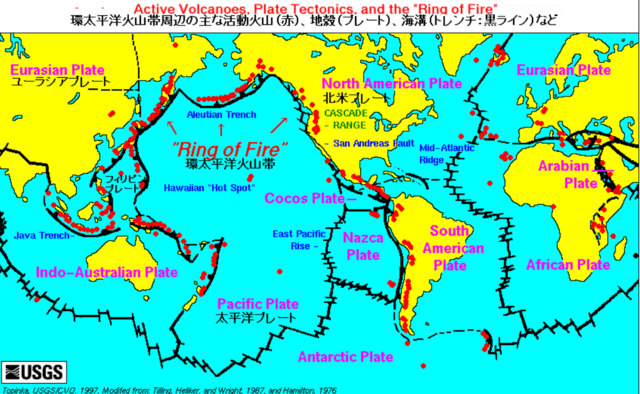<英国は世界外交リード可能なGDPや軍事力があるか>
<韓国政府の北寄りワンコリア化を防げるか>
<日本政府南大洋海路の安全保障環境維持と整合可能か>
<G7+招待国で実現か>
:::::
2020年6月11日(木)19時10分
エリック・ブラッドバーグ(米カーネギー国際平和財団欧州プログラム主任)他
:::::
ボリス・ジョンソン英首相が提唱している民主主義国10カ国の連合「D10」だ。
G7米国、英国、フランス、ドイツ、日本、イタリア、カナダに韓国、インド、オーストラリアを加えた新たな枠組みで、第5世代(5G)移動通信システムとサプライチェーンについて話し合おうというのである。
D10のアイデア自体は目新しいものではないが、パンデミックで中国頼みのサプライチェーンの脆弱性が明らかになり、米中対立がエスカレートするなか、この枠組みは注目を集めている。
中国は湖北省武漢でのCOVID-19発生時の初動対応のまずさと透明性の欠如から世界の目をそらそうと躍起になる一方で、「戦狼外交」を展開している。
戦狼は中国で大ヒットした映画のタイトルで、ランボーもどきの主人公が「中国を侮辱する者」に血の復讐をする。中国外務省はそれを地で行く「口撃」を繰り返しつつ、COVID-19「封じ込め成功」を大々的に宣伝し、アメリカとその同盟国に対し、ネット上で偽情報キャンペーンを繰り広げている。(注1)
(注1)武漢作戦は「兵は詭道なり」。「孫子」は、二千数百年前の弱肉強食の時代に生きた孫武が書いた兵法書=Sun Tzu's martial law=。「戦いとは騙し合いである。こちらの内情を外部に掴ませず、時には小さく、時には大きく見せること」
一方で、中国製のマスクや医療機器の不具合を伝える報道が相次ぎ、中国頼みの5Gインフラやサプライチェーンのあり方に警戒感が高まっている。
当初は、中国の通信機器大手、華為技術(ファーウェイ・テクノロジーズ)の5G市場参入を容認してきたイギリスやカナダ、ドイツなども規制強化に転じた。
アメリカばかりか、EUや日本も、医薬品や医療機器その他重要な製品や部品、原材料の調達における中国の比重を減らそうとサプライチェーンの分散化を進めつつある。
11月の米大統領選の結果にかかわらず、イギリス主導のD10は、EUにとっても、アメリカと付き合う上で頼りになる枠組みとなるはずだ。
EU にとって、民主主義国のグループであるD10は一種の「保険」となり、これがあれば、5Gとサプライチェーン問題でトランプ政権と建設的な協議がしやすくなる。
その証拠に、人口知能(AI)の利用について、G7で共通の倫理基準を策定するというフランスの提案をトランプはあっさり受け入れた。トランプはまた、5Gのセキュリティリスクについて、EUが評価指針を定めたことも評価している。
もしも米大統領選で民主党の指名候補ジョー・バイデン前副大統領が勝てば、EUは気候変動対策と多国間の貿易交渉についても、D10を通じて米政府に新たな作業グループの結成を呼びかけられる。
バイデンが勝った場合、D10はバイデンの外交政策の課題である安全保障、腐敗、人権に関する国際的な作業グループの立ち上げにも役立つはずだ。そうなれば、D10はかつてのG7に匹敵するか、それを上回る国際的な影響力を持つ枠組みとなる。
中国が着々と覇権拡大を進めるなか、大西洋と太平洋をまたいで民主主義の国々が結束する意義は明らかだ。一方で、ただの「おしゃべりの場」ではなく、核心的な問題に的を絞って、限定的な行動を起こすことを目指すD10が発足すれば、勝ちか負けかのゼロサム思考で一国主義的に中国に対抗しようとするアメリカに歯止めをかけることもできる。
ブレグジット後も、イギリスの出番はなくなったわけではない。かつての覇権国家イギリスは外交巧者の名に相応しく、今こそ民主主義の国々を結ぶ橋渡し役を果たすべきだ。
NATOの初代事務総長を務めたヘイスティングズ・イスメイが1949年に打ち出した有名な戦略がある。いわく
「ソ連を締め出し、アメリカを引き入れ、ドイツを抑え込む」。
それに倣えば、D10の戦略はさしずめ
「中国を締め出し、インドを引き込み、アメリカを落ち着かせろ」だろう。
From Foreign Policy Magazine
https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/06/g7d10_3.php