
概ね 20/15℃
20/15℃
播州路の旅の続きだがバスは赤穂岬のレストランから兵庫県立赤穂海浜公園内の「赤穂市立海洋科学館・塩の国」へ15分ほどで着いた。赤穂市へは3回訪れているが赤穂市立海洋科学館・塩の国へは初めての事だが塩の国は赤穂市立海洋科学館・塩の国は広大な敷地の海浜公園内にある。

まずは塩の科学館で塩についての学習である。 塩は古代から生活に欠かせないものでその製法は弥生・古墳時代は「藻塩焼き」中世は「揚げ浜式塩田」江戸時代に入ると「入浜塩田」戦後の昭和20年は「流下式塩田」昭和47年から現代は「イオン交換膜法」のみが国の法律で定められ、大量生産が出来るようになった。日本で塩が使われるようになったのは、縄文時代の終わりから弥生時代にかけてといわれており、日本は多雨多湿なので、海水は天日だけでは塩にならず、たくさんのエネルギーを使って煮詰めて塩の結晶を取り出すしかないのですが気候温暖な瀬戸内の赤穂~備前の浜辺が塩つくりの適地だとされていたようです。

学習中、復元された赤穂の塩田が気になり塩田へ行ってみたが奥能登で塩田を見たことがあるが規模が違う。 播磨国、赤穂市の海岸部一帯に作られた塩田。赤穂での製塩はすでに756年には行われ,10世紀から13世紀にかけては汲潮浜(くみしおはま),13世紀からは古式入浜による製塩が行われていたとみられ,17世紀半ばから入浜塩田へと移行したとネット調べにある。 体験学習室に戻ると皆さんは塩つくり体験の真最中で、ほゞ完成していた。

少し手に取ってみるときめ細やかで口に入れると塩辛さから甘味と変化する。 揚げたての天婦羅や刺身につけて食べると美味しく、お握りには最適だそうだ。

出来上がった塩はテーブルごとの人達に小袋分にけ入れて、お土産とし、更に塩の国kら、お土産として煮物用の「塩の国の塩」をいただき、帰路に着いたがバスは相生市の道の駅「海の駅あいおい白龍城(ペイロン城)」で買い物休憩となっている。



















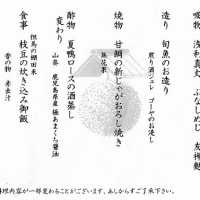
日本は設備、衛生面でもとても行き届いていて
塩は生活に活欠かせない調味料ですが、海に囲まれた昔は日本でも簡単に作れなかったようです。
忠臣蔵の
越後の上杉謙信が甲斐の武田信玄に「敵に塩を送る」で戦国時代の美談として有名です。
「塩作り体験学習」では家庭でも土鍋と海水で簡単に出来そうです。キメこまやく、舐めてみましたが甘くておい美味しいです。
赤穂の塩は日本一かと思いました。