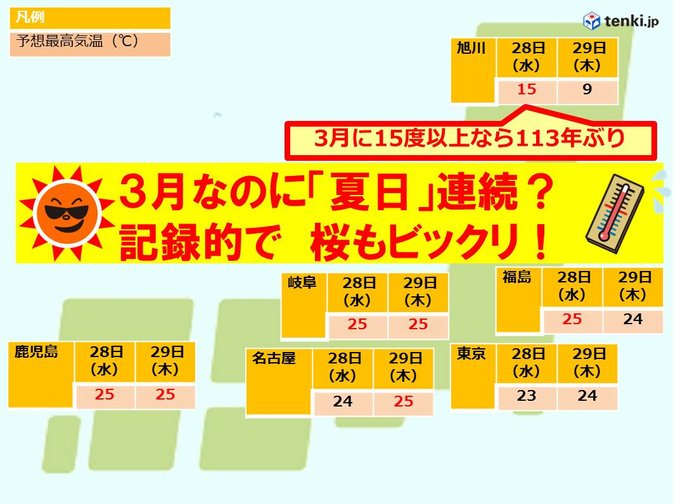日本人がサクラにエロス(性)とタナトス(死)を見る、その理由とは?七十二候「桜始開」
3月26日より、春分の次候「桜始開(さくらはじめてひらく)」となります。まさにちょうど今、日本列島をソメイヨシノ開花前線が北上中です。百花繚乱の春本番を告げる桜の開花ですが、もはや春=桜(ソメイヨシノ)、というくらいの勢いで、他の花が見向きもされない傾向は、嘆かわしいと思うと同時に、「桜」という花がなぜそれほど日本人、日本文化において特別なものになっているのか、その不思議さに毎年思いを馳せます。侘び寂びを重んじる日本文化の美意識、そして同じバラ科でも枯淡山水の趣きの梅と、ふくよかな赤子のような生命力・健康を象徴する桃を愛でた華人文化。そのどちらからも異質な一抹の妖気とあでやかな色気が特徴の桜の花は、なぜ日本で長く愛され、国の象徴にまでなったのでしょうか。
- 允恭天皇からJポップまで・日本人がサクラにたくしてきたパッション

サクラは、バラ科スモモ属サクラ亜属に分類される落葉広葉樹で、世界には約100種、日本国内には10種の自生種が分布し、自生種の交配と突然変異を基にして、数百もの園芸品種が作出されてきました。
古来、中国文化を手本としてきた日本では、奈良時代ごろまでは花見と言えば梅の花を愛でることでしたし、御所である紫宸殿には、その南庭に左近(東)の梅、右近(西)の橘が植栽されていたのが、平安期には左近の梅はサクラに置き換わり、そのまま雛人形のお飾りにも踏襲されているのはご存知の通りです。
そうした日本の伝統文化に興味のない若い世代でも、花見は大好き。サクラの花見とは、伝統的に花の下で飲み食いして浮かれるというきわめて俗なもので、その俗っぽさが戦後の消費文化の風潮とも一致した、ということももちろんあるでしょう。しかしそれだけではありません。Jポップの歌詞の中にも盛んにサクラは織り込まれ、一部で「サクラ舞い散りすぎ」と揶揄されるほどにサクラの歌詞が数多く歌われるのを見ると、現代の若い世代にとってもサクラが「何か」を感じさせるものであることは間違いないようです。
日本で最初にサクラが歌に詠まれたのは第十九代天皇・允恭(いんぎょう)天皇のこの歌であると言われています。
花細(ぐは)し 桜の愛(め)で こと愛では 早くは愛でず 我が愛づる子ら (日本書紀・巻第十三)
双方で思いあう衣通郎姫(そとおしのいらつめ)をサクラの花に例え、「桜の花の何と言う繊細な美しさだろう。どうせ愛でるのだったら、もっと早くから愛でていればよかった。私のいとしいいとしい姫よ。」と、「愛でる」を四度もリフレインし、「かわいくてたまらない」という思いがあふれ出たとんでもなく熱い歌です。現代のラブソングとほとんど同じテイストと言っていいのではないでしょうか。サクラには人を熱狂的な恋心、情念にかきたたせる魔力があるようです。
かたやサクラは死(タナトス)とも常に結びついてきました。
ねがはくは 花のもとにて 春死なむ そのきさらぎの望月のころ (西行法師 「新古今和歌集」選)
「如月の望月のころ」は、旧暦2月15日であり、太陽暦で言えば三月末。「かなうなら、桜の木の下で、満開のときに死にたいものだ。」と、西行は詠っているのです。
そして軍国主義時代には、盛んに軍歌に織り込まれ、たとえば「万朶(ばんだ)の桜か襟の色 花は隅田に嵐吹く 大和男子と生まれなば 散兵綫(さんぺいせん)の花と散れ(「歩兵の本領」)」などと歌われました。
サクラが死と結びつくのは、しばしば花の散り方がいさぎよいから、という説明がされますが、果たしてそうでしょうか。ぽとりとおちる椿の花のいさぎよい落下を「死をイメージさせ縁起が悪い」と嫌った風習と、その説明では矛盾するように思います。死のイメージがサクラと結びつくのは、もっと深い理由があり、それは後述します。
さらに、近代~現代に入って有名なのが、梶井基次郎(1901~1932)が著した短編の、有名なこの冒頭の箇所でしょう。
桜の樹の下には屍体が埋まっている!
これは信じていいことなんだよ。何故って、桜の花があんなにも見事に咲くなんて信じられないことじゃないか。
(中略)
何があんな花弁を作り、何があんな蕊(ずい)を作っているのか、俺は毛根の吸い上げる水晶のような液が、静かな行列を作って、維管束のなかを夢のようにあがっていくのが見えるかのようだ。
(梶井基次郎「桜の樹の下には」)
梶井はここで、執拗に地中に埋まった死体(タナトス)が腐敗し、木に吸い取られて導管を這い登って桜の花という生殖(エロス)に変容する、という空想をし、サクラにこめられた性愛と死のイメージをもろともに抉り出し、描出しています。
梶井の鋭敏な感性が直観したものは、実は私たち日本人が何千年にもにわたり桜に抱いてきたイメージそのものと言えます。なぜそうなるのでしょう。
なぜこれほどサクラの花は心をかき乱すように情緒をかきたて、「LOVE」に対比される言葉がなく、王朝文化の貴族以外には無縁だった西洋ロマンス的な情欲・恋情的情熱(パッション)に特別に結びついてしまうのでしょうか。
中東から欧米にかけて咲くあの花は、サクラとそっくり

アーモンドの花。桜とそっくり
サクラは世界中に自生しますが、古来サクラをこれほど特別視して思いいれてきたのは日本だけで、これは同じ文化圏に属する中国にも朝鮮半島にもありません。
ところが、サクラによく似た花を咲かせる植物で、かつ古来より中東や西欧世界で宗教的に大きな意味を持ち崇められてきた花があります。アーモンド( Prunus dulcis)です。バラ科サクラ属の落葉高木で、先端に切れ込みのある「サクラ型」の花弁、中心部が赤く染まり先端部が白っぽくなる花色、こぼれるように枝一杯に咲く様など、原産地である中東のイスラエルやレバノン、トルコ、あるいはスペインや地中海諸国に旅行した日本人が、アーモンドの花盛りに出くわして「こんなところにサクラが咲いてる」と思うほど、見た目が似ています。ご存知の通りその仁(種の中身)は食用のナッツとして有名で、漢字圏では扁桃(へんとう)、巴旦杏(はたんきょう)とも呼ばれ、咳止薬の苦扁桃油ともなります。
このアーモンドは、イスラエル(ユダヤ)人にとって特別な植物。なぜならユダヤ人をパレスチナに導き、律法(十戒)をイスラエルの民にもたらした指導者・モーゼの兄にして、イスラエルの司祭の祖であるアロンが携え、数々の奇跡で民を救った「アロンの杖(Aron's rod)」がアーモンドの木で作られていた、ともされる(諸説あり)からです。そしてこの「アロンの杖」は創世記に登場するエデンの園に生えていた二つの禁断の樹の一つ、生命の樹(セフィロトの樹 Sephirothic tree)の象徴でもありました。
さらに、旧約の神がモーセに命じて作らせたとされる七つに枝分かれした純金の聖なる燭台「メノラー」もまた、支柱にアーモンドの花の形が合計22個(ヘブライ文字は22文字あることに対応)刻まれており、これは神によってこの数のアーモンドの花とがくとを打ち出して作れと打ち出す位置も指示された意匠であり、現在もイスラエルの各家庭にはメノラーが備え付けられ、神のよりしろとして大切にされています。このメノラーもまた、生命の樹の模造であり、その形象そのものがセフィロトをあらわしています。
死と再生の象徴・十字架からサクラの花へ

生命の樹のエピソードは、キリスト教の始祖であるイエスに結びついてゆきます。
最初の人間、アダムが死ぬと、息子の一人セツは大天使からの命を受け、エデンの園に封印された生命の樹から種子を貰い受け、死んだアダムの舌に種子を載せて葬ります。その種子から三本の樹が生え、やがて一つに融合して大木となり、後にノアの箱舟の木材となった後、めぐりめぐってキリストの磔刑の十字架になった、といわれます。
このことから、磔されたイエスは、そのまま第二の生命の樹になぞらえられるのです。
イエス・キリスト伝説の原型の一つとされる、現代のトルコ地方から発し、フリギアの民に信仰されてギリシャ神話に習合された太陽神・アッティスは、処女神ナナから生まれたとされます。ナナは、両性具有の神アグディスティスの切り取られた男根が落ちた場所から生えたアーモンドの木のそばを通りかかり、その実を手に取って胸に押し当てると処女懐胎し、アッティスを生み落とします。アッティスは成人した後、大地母神キュベレーの呪いを受けて、自ら男性器を切り取って死に、3日後に復活、永遠の命を得た、という神話があります。
アッティスが復活したとする春分を迎えてもっとも近い日曜日は、陽気にどんちゃん騒ぎにふける日とされました。大地母神キュベレーの女司祭に扇動された人々は、異性装やコスプレをして踊り、太鼓を打ち鳴らし、飲んだくれたとされています。この祭りが、イースター(復活祭)の起源のひとつとも言われます。
今の私たちが、やはりイースター前後に咲くサクラの木の下で、飲んだくれてドンチャン騒ぎするのと似ていないでしょうか。
つまり、サクラの花が強く性愛と死のイメージを持つ理由とは、「生命の樹」という神話から生じた死と再生、性の宴に彩られた信仰習俗が遠い昔中東で生まれ、そのシンボルとなったアーモンドの木への信仰はイスラエルの聖典・旧約聖書に受け継がれ、やがて先史日本に流れ着き、春分の頃それとそっくりの花を咲かせるサクラの木がアーモンドに見立てられて崇拝されるようになったから、ということはないでしょうか。
山口県下関市の彦島八幡宮には、「恐れの杜」の「祟り岩」と呼ばれる不思議な遺跡が知られており、そこに紀元前2000年前後の頃に使われていたセム語系シュメール文字がツングース系の文字と混合した不思議な文字が刻まれた七つの岩石があります。解読してみたところ、「最高の大地母神が、シュメール・ウルク王朝の最高司祭となり日の神の子である日子王子が神主となり、7枝樹にかけて祈る」とあります、まさにイスラエルの七枝燭台=メノラー=生命の樹の信仰が伝わっていた証であり、アーモンド=生命の樹信仰と、サクラ信仰とが関係していることは推測できるのではないでしょうか。
サクラは情熱(パッション)をかきたてる、と先述しましたが、イエスの磔刑と言う受難のことも「パッション」と言います。ヘブライ語でアーモンドを指すシャーケード(shaqedh)という音は、日本語のサクラに転じ得る、とも想像できます。
サクラの魔性が見せたものかもしれない、時代と世界を股にかけた幻のような考察・妄想の締めに、俳聖・松尾芭蕉の句を一つ。皆さん、よいお花見をお楽しみください。
さまざまのこと思い出す桜かな (松尾芭蕉)