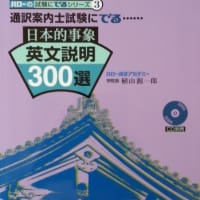2022年度<合格体験記> (33) 【16:30~17:30】(和楽器)(英語)
●英語(メルマガ読者、無料教材利用者)
①受験の動機
中学生の時の修学旅行で京都や奈良の伝統文化に触れ、感動したとともに、日本文化を海外の方に知ってもらいたいと思っていました。数年前に通訳案内士という資格があることを知り、受験を決意。今でも外国人に日本の魅力を伝えていきたいと考えておりますが、さらに日本人にも日本の魅力を再認識してもらいたいと考えています。そのためには、有資格者となって信頼ある発信がしたいと考え、受験を続けてきました。
②第1次試験対策
<英語>(免除:TOEIC Writing 190)
かつて一度だけ本試験を受験したことがありますが、各予備校で解答速報にばらつきが出たり、ネイティブでも選びきれない問題が出たりしたため(結局不合格)、自分には合わないと考え、以来TOEICでの免除に切り替えました。
TOEIC試験はほぼ毎月開催されており、受験時期をうまく調整すれば、その年度と翌年度の英語の免除に使えるため、使わない手はないと考えました。
対策としては、「はじめてのTOEIC S&Wテスト完全攻略」を試験前に使用しました。スコア120〜130を目標としている方を対象にしていますが、そこまで厚い本でないのに内容が充実しており、一冊対策すれば十分に免除スコアは狙えると思います。
<日本地理>(免除:国内旅行業務取扱管理者)
総合でも国内でも旅行業務取扱管理者資格を持っていると、日本地理の試験が免除になるため、長期戦も視野に入れて取得しました。
(以下テキストを使用しました)
・完全制覇国内旅行地理検定試験
各地方ごとの地名や温泉、祭りなど、全国の地理に関わる事項が網羅されています。前半は空欄補充、後半は4択問題とかなりボリュームがあるので、すべて解くことはできませんでしたが、旅行業務取扱管理者の試験の受験も想定されているテキストのため、勉強になりました。
・この1冊で決める!! 国内旅行業務取扱管理者テキスト&問題集
本屋に置いてあるテキストをパラパラ見て、自分に合いそうなものを選びました。各単元ごとの説明と練習問題が付いており、説明はわかりやすかったです。
・過去問(3年分)
国内旅行業務取扱管理者試験では、過去問や練習問題の数字や文章を少し変えただけの問題が多い印象で、ある程度知識を得たら、どんどん問題演習をすることが合格への近道でした。ANTAのHPから過去問が入手できるので、入手できる年度のものはダウンロードして解きました。
<日本歴史>(自己採点:83点)
まずは直近2021年度の本試験の過去問を何も勉強していない状態で解きました。自分の苦手な時代や項目などが見えてくるのと、自分の立ち位置を確認できました。
過去問の次は、山川の教科書を時代ごとに6回ずつ印を付けながら読みました。①西暦、②人物、③出来事(戦いなど)、④場所、⑤書物や文化財・建物など、⑥その他重要だと思うこと、と注目点を変えながら色の異なる蛍光ペンで印を付けていきました。読むときはあまり覚えようとしなくても、少なくとも6回は同じ文章に目を通しているので、自ずと頭に入ってきます。
山川の教科書を一周したら、「実力をつける日本史100題」という大学受験用の問題集を解いていきました。こちらは選択式ではなく記述式の問題集です。通訳案内士試験はマーク式ですが、過去問などを解いていると「何となく」で選べてしまうので、しっかり知識を定着させるために、あえて記述式のものを選びました。かなりボリュームがあり、結局近代は手が出せませんでしたが、マーク式の問題を解くよりも頭に入ったと思います。
「実力をつける日本史100題」と並行して、2014年度からの過去問を解きました。一度解いたら、すべての問題に解答とその根拠となる説明を書いて、次に解いた時はその解答を見て復習できるようにしました。最終的にどの年度も90点以上が取れるまで何度も繰り返し解きました。
(下記を利用しました)
<第1次筆記試験問題>
https://blog.goo.ne.jp/gu6970/e/18b0340041ceb26d8959b2c775736ffe
<1次合格体験記>
https://blog.goo.ne.jp/gu6970/e/03ce4dac773dd5bb9aa07527a42e0610
<最終合格体験記>
https://blog.goo.ne.jp/gu6970/e/4bb4662130eb6ebb1ae40a73c060708f
<日本歴史>の傾向と対策<資料>
http://www.hello.ac/2022.his.pdf
<日本歴史>の傾向と対策<音声ファイル>(その1)
https://youtu.be/eEcC2ypuFmc
<日本歴史>の傾向と対策<音声ファイル>(その2)
https://youtu.be/qOhdusl4XCE
<日本歴史>の傾向と対策<音声ファイル>(その3)
https://youtu.be/Qy-eMZb9ugg
<日本歴史>の傾向と対策<音声ファイル>(その4)
https://youtu.be/5r2t3ZRKD7c
<日本史の時代区分と各文化の特徴>
http://hello.ac/timeline.pdf
①受験の動機
中学生の時の修学旅行で京都や奈良の伝統文化に触れ、感動したとともに、日本文化を海外の方に知ってもらいたいと思っていました。数年前に通訳案内士という資格があることを知り、受験を決意。今でも外国人に日本の魅力を伝えていきたいと考えておりますが、さらに日本人にも日本の魅力を再認識してもらいたいと考えています。そのためには、有資格者となって信頼ある発信がしたいと考え、受験を続けてきました。
②第1次試験対策
<英語>(免除:TOEIC Writing 190)
かつて一度だけ本試験を受験したことがありますが、各予備校で解答速報にばらつきが出たり、ネイティブでも選びきれない問題が出たりしたため(結局不合格)、自分には合わないと考え、以来TOEICでの免除に切り替えました。
TOEIC試験はほぼ毎月開催されており、受験時期をうまく調整すれば、その年度と翌年度の英語の免除に使えるため、使わない手はないと考えました。
対策としては、「はじめてのTOEIC S&Wテスト完全攻略」を試験前に使用しました。スコア120〜130を目標としている方を対象にしていますが、そこまで厚い本でないのに内容が充実しており、一冊対策すれば十分に免除スコアは狙えると思います。
<日本地理>(免除:国内旅行業務取扱管理者)
総合でも国内でも旅行業務取扱管理者資格を持っていると、日本地理の試験が免除になるため、長期戦も視野に入れて取得しました。
(以下テキストを使用しました)
・完全制覇国内旅行地理検定試験
各地方ごとの地名や温泉、祭りなど、全国の地理に関わる事項が網羅されています。前半は空欄補充、後半は4択問題とかなりボリュームがあるので、すべて解くことはできませんでしたが、旅行業務取扱管理者の試験の受験も想定されているテキストのため、勉強になりました。
・この1冊で決める!! 国内旅行業務取扱管理者テキスト&問題集
本屋に置いてあるテキストをパラパラ見て、自分に合いそうなものを選びました。各単元ごとの説明と練習問題が付いており、説明はわかりやすかったです。
・過去問(3年分)
国内旅行業務取扱管理者試験では、過去問や練習問題の数字や文章を少し変えただけの問題が多い印象で、ある程度知識を得たら、どんどん問題演習をすることが合格への近道でした。ANTAのHPから過去問が入手できるので、入手できる年度のものはダウンロードして解きました。
<日本歴史>(自己採点:83点)
まずは直近2021年度の本試験の過去問を何も勉強していない状態で解きました。自分の苦手な時代や項目などが見えてくるのと、自分の立ち位置を確認できました。
過去問の次は、山川の教科書を時代ごとに6回ずつ印を付けながら読みました。①西暦、②人物、③出来事(戦いなど)、④場所、⑤書物や文化財・建物など、⑥その他重要だと思うこと、と注目点を変えながら色の異なる蛍光ペンで印を付けていきました。読むときはあまり覚えようとしなくても、少なくとも6回は同じ文章に目を通しているので、自ずと頭に入ってきます。
山川の教科書を一周したら、「実力をつける日本史100題」という大学受験用の問題集を解いていきました。こちらは選択式ではなく記述式の問題集です。通訳案内士試験はマーク式ですが、過去問などを解いていると「何となく」で選べてしまうので、しっかり知識を定着させるために、あえて記述式のものを選びました。かなりボリュームがあり、結局近代は手が出せませんでしたが、マーク式の問題を解くよりも頭に入ったと思います。
「実力をつける日本史100題」と並行して、2014年度からの過去問を解きました。一度解いたら、すべての問題に解答とその根拠となる説明を書いて、次に解いた時はその解答を見て復習できるようにしました。最終的にどの年度も90点以上が取れるまで何度も繰り返し解きました。
(下記を利用しました)
<第1次筆記試験問題>
https://blog.goo.ne.jp/gu6970/e/18b0340041ceb26d8959b2c775736ffe
<1次合格体験記>
https://blog.goo.ne.jp/gu6970/e/03ce4dac773dd5bb9aa07527a42e0610
<最終合格体験記>
https://blog.goo.ne.jp/gu6970/e/4bb4662130eb6ebb1ae40a73c060708f
<日本歴史>の傾向と対策<資料>
http://www.hello.ac/2022.his.pdf
<日本歴史>の傾向と対策<音声ファイル>(その1)
https://youtu.be/eEcC2ypuFmc
<日本歴史>の傾向と対策<音声ファイル>(その2)
https://youtu.be/qOhdusl4XCE
<日本歴史>の傾向と対策<音声ファイル>(その3)
https://youtu.be/Qy-eMZb9ugg
<日本歴史>の傾向と対策<音声ファイル>(その4)
https://youtu.be/5r2t3ZRKD7c
<日本史の時代区分と各文化の特徴>
http://hello.ac/timeline.pdf
<一般常識>(自己採点:39点)
2021年は一般常識を落としてしまったこともあり、今年は観光白書を丁寧に読むことを心掛けました。
まずは令和3年版の観光白書を、日本歴史と同じように注目点を変えながらマーカーを引いていきました。また、植山先生の傾向と対策で2021年に出題された箇所を確認しながら印を付けていきました。
その後、令和4年版の観光白書も同様に読み進めていきました。
それ以外では、過去問の日本文化のみを繰り返し解いたり、2021年度の試験を受ける際に日本文化をまとめたノートを改めて復習しました。今年は観光白書と日本文化が6:4くらいで出題されていたので、結果的にこの方法が良かったような気がします。
(下記を利用しました)
<第1次筆記試験問題>
https://blog.goo.ne.jp/gu6970/e/18b0340041ceb26d8959b2c775736ffe
<1次合格体験記>
https://blog.goo.ne.jp/gu6970/e/03ce4dac773dd5bb9aa07527a42e0610
<最終合格体験記>
https://blog.goo.ne.jp/gu6970/e/4bb4662130eb6ebb1ae40a73c060708f
<一般常識>の傾向と対策<資料>
http://www.hello.ac/2022.gen.pdf
<一般常識>の傾向と対策<音声ファイル>
https://youtu.be/_VgJAKgi78o
<令和4年版「観光白書」(完全版)
http://hello.ac/2022.hakusho.kanzen
<令和3年版「観光白書」(完全版)
http://hello.ac/2021.hakusho.kanzen
<通訳案内の実務>(自己採点:44点)
唯一出題範囲が明記されている科目なので、ハロー注解付き<観光庁研修テキスト>を徹底的に学習しました。
まずは日本歴史の教科書の読み方で、注目点を変えてマーカーを引きながら読んでいきました。次に、テキストに過去問の出題履歴を記入していきました。そうすると、同じ箇所が繰り返し出題されていることがわかり、何度も出題されている箇所は重点的に、一度も出題されていないところは確認する程度に留め、強弱をつけながら読みました。
実際の試験は、年々選択肢の文章が長くなってきているので、いかに速く正確に読めるかが大事だと感じました。試験を受けてみて、実際の試験時間よりも短く時間を設定して、過去問を解いていくのも良いと思いました。
(下記を利用しました)
<第1次筆記試験問題>
https://blog.goo.ne.jp/gu6970/e/18b0340041ceb26d8959b2c775736ffe
<第1次合格体験記>
https://blog.goo.ne.jp/gu6970/e/03ce4dac773dd5bb9aa07527a42e0610
<最終合格体験記>
https://blog.goo.ne.jp/gu6970/e/4bb4662130eb6ebb1ae40a73c060708f
<通訳案内の実務>の傾向と対策<決定版資料>
http://www.hello.ac/2022.jitumu.pdf
<通訳案内の実務>の傾向と対策<音声ファイル>
https://youtu.be/DmvJFrxey9o
ハロー注解付き<観光庁研修テキスト>
http://hello.ac/kankouchou.kenshuu.siryou.comment.pdf
③第2次試験対策
まず<2次セミナー>の資料に記載されていた、食や観光地など項目ごとのトピックをExcelにまとめました。最近の傾向を見ていると、昨年、一昨年に出題されているものがまた出題されていたので、2021年、2020年に出題されたトピックのスクリプトをすべて作成しました。
また、出題回数が多いものも同様にスクリプトを作成しました。
導入部分は「日本的事象英文説明300選」を参考にしたり、他のテキストやネットで調べながら自分の言葉にしていきました。
また、それ以外にも出そうだと思うトピックを追加しました。
●プレゼンのテーマ
①麹←これを選択しました!
②山寺
③一人カラオケ
●プレゼンの後の試験官との質疑応答
(試験官)日本語で何て言うの?
(kojiで良かったのに、ずっとrice maltと話していたので、聞かれたのだと思います。)
(私)kojiです。
(試験官) 麹は何に含まれているって言ってた?
(私) 味噌や酒です。
(試験官)醤油にも含まれている?
(私)そうだと思います。
(試験官)アメリカでは、若い人が自分で作ったりしているけど、日本でも若い人はやっている?
(私)はい、健康のために自分で作る人が増えています。
(試験官)若い人も?
(私)はい、割とポピュラーになっています。
●外国語訳の日本文
和楽器は、古来から使われてきた伝統的な日本の楽器です。和楽器には三味線、琴、尺八、和太鼓、琵琶などがあります。これらの楽器には、日本固有のものと大陸から伝わって、日本の文化の中でその形を変え、独自に進化を遂げていったものがあります。
●<条件>
和楽器に関心があります。
男女4名のグループ。
●<シチュエーション>
お客様が「前回来た時、三味線の音色が素晴らしくて、また聴きたい」と仰っています。
●試験官との質疑応答
(私)和楽器に興味があるとお聞きしてとても嬉しいです!
また聞きたいのですよね?
(試験官)そう、前に聴いて良かったからまた聞きたいんだけど。
(私)この辺で聴けるところがあるか確認しますね。いくつかのセンターでセッションやコンサートをやっているとことがあります。
(試験官)特別なホールで演奏するのですか?
(私)そういう場合もありますし、センターで開催される場合もあります。
また、旅館でも開催される場合もあります。
(試験官)旅館って何?ホテルみたいなところ?
(私)はい、日本の伝統的な宿泊施設です。
(試験官)OK。聴けるのを楽しみにしているよ。
(私)他に何かできることはありませんか?
(試験官)楽器に興味があるから、何か他に聴けるかな?
(私)もし楽器に興味があるのでしたら、和太鼓がおすすめです!とてもダイナミックで熱狂的ですよ。
(試験官)ああ、あの大きなやつ?
(私)そうです。
(試験官)聞けるところあるのかな?
(私)お祭りでよく演奏されています。
(試験官)お祭りやっているの?
(私)12月でもやっているところもあります。例えば、秩父です。
(既に先週終わっているのに、この話題を出してしまいました…。)
(試験官)そのお祭りは有名なの?どんなお祭り?
(私)山車 festival floatが特徴です。
(試験官)それって担ぐやつ?
(私)それは神輿 portable shrineですね。私が申したのは山車 festival floatです。町中を引いて歩きます。とても装飾が素晴らしいです。
(試験官)そうなんだ。あなたは行ったことある?
(私)実をいうと、行ったことはありません。テレビで見たことはあります。
(試験官)そっか、有名なんだね。
(私)はい、とても有名です。
(試験官)OK。見てみるよ。
(私)ありがとうございます。
(下記を利用しました)
2次試験問題(2013年度~2022年度)
http://www.hello.ac/2ji.mondai.2013.2022.pdf
<最終合格体験記>
https://blog.goo.ne.jp/gu6970/e/4bb4662130eb6ebb1ae40a73c060708f
<2次レポート>のまとめ
https://blog.goo.ne.jp/gu6970/e/428e10fe9085c4d498958c9973daa240
「日本的事象英文説明300選」
https://blog.goo.ne.jp/gu6970/e/1c2c0c0d82c19d1e7ad24fda018d2154
①麹←これを選択しました!
②山寺
③一人カラオケ
●プレゼンの後の試験官との質疑応答
(試験官)日本語で何て言うの?
(kojiで良かったのに、ずっとrice maltと話していたので、聞かれたのだと思います。)
(私)kojiです。
(試験官) 麹は何に含まれているって言ってた?
(私) 味噌や酒です。
(試験官)醤油にも含まれている?
(私)そうだと思います。
(試験官)アメリカでは、若い人が自分で作ったりしているけど、日本でも若い人はやっている?
(私)はい、健康のために自分で作る人が増えています。
(試験官)若い人も?
(私)はい、割とポピュラーになっています。
●外国語訳の日本文
和楽器は、古来から使われてきた伝統的な日本の楽器です。和楽器には三味線、琴、尺八、和太鼓、琵琶などがあります。これらの楽器には、日本固有のものと大陸から伝わって、日本の文化の中でその形を変え、独自に進化を遂げていったものがあります。
●<条件>
和楽器に関心があります。
男女4名のグループ。
●<シチュエーション>
お客様が「前回来た時、三味線の音色が素晴らしくて、また聴きたい」と仰っています。
●試験官との質疑応答
(私)和楽器に興味があるとお聞きしてとても嬉しいです!
また聞きたいのですよね?
(試験官)そう、前に聴いて良かったからまた聞きたいんだけど。
(私)この辺で聴けるところがあるか確認しますね。いくつかのセンターでセッションやコンサートをやっているとことがあります。
(試験官)特別なホールで演奏するのですか?
(私)そういう場合もありますし、センターで開催される場合もあります。
また、旅館でも開催される場合もあります。
(試験官)旅館って何?ホテルみたいなところ?
(私)はい、日本の伝統的な宿泊施設です。
(試験官)OK。聴けるのを楽しみにしているよ。
(私)他に何かできることはありませんか?
(試験官)楽器に興味があるから、何か他に聴けるかな?
(私)もし楽器に興味があるのでしたら、和太鼓がおすすめです!とてもダイナミックで熱狂的ですよ。
(試験官)ああ、あの大きなやつ?
(私)そうです。
(試験官)聞けるところあるのかな?
(私)お祭りでよく演奏されています。
(試験官)お祭りやっているの?
(私)12月でもやっているところもあります。例えば、秩父です。
(既に先週終わっているのに、この話題を出してしまいました…。)
(試験官)そのお祭りは有名なの?どんなお祭り?
(私)山車 festival floatが特徴です。
(試験官)それって担ぐやつ?
(私)それは神輿 portable shrineですね。私が申したのは山車 festival floatです。町中を引いて歩きます。とても装飾が素晴らしいです。
(試験官)そうなんだ。あなたは行ったことある?
(私)実をいうと、行ったことはありません。テレビで見たことはあります。
(試験官)そっか、有名なんだね。
(私)はい、とても有名です。
(試験官)OK。見てみるよ。
(私)ありがとうございます。
(下記を利用しました)
2次試験問題(2013年度~2022年度)
http://www.hello.ac/2ji.mondai.2013.2022.pdf
<最終合格体験記>
https://blog.goo.ne.jp/gu6970/e/4bb4662130eb6ebb1ae40a73c060708f
<2次レポート>のまとめ
https://blog.goo.ne.jp/gu6970/e/428e10fe9085c4d498958c9973daa240
「日本的事象英文説明300選」
https://blog.goo.ne.jp/gu6970/e/1c2c0c0d82c19d1e7ad24fda018d2154
④ハローのメルマガ、動画、教材、セミナーなどで役に立ったこと
1次、2次共に、定期的に送ってくださるメルマガに大いに助けていただきました。また、傾向をつかむのがなかなか難しいところ、植山先生にまとめていただいた資料をベースに勉強を進められたので、効率的にかつ脱線せずに準備できました。2次試験についても、トピックは無限にあるものの、これまでの出題実績をまとめていただいたおかげで、ある程度の傾向はつかめて準備できました。
「日本的事象英文説明300選」はプレゼンの導入部分として活用させていただきました。ある程度単語を知っていると通訳にも役立つので、やはり目を通しておくのは大事だと感じました。
⑤ハローに対するご意見、ご感想、ご希望
いつも無料でこれだけの資料や情報を提供くださってありがとうございます。
定期的なメルマガにも大変励まされました。
ご自身のお時間を惜しまず、受験生のためにと情報を公開していただいているおかげで、有益な情報に手が届きやすく対策できたと感じております。
また、蓄積されたレポートは本当に貴重で、勉強する上で大変助かりました。
本当にありがとうございました。
⑥今後の抱負
スポットのガイドなどを経験しながら、ガイドの幅を広げていきたいと考えております。
また、受験の動機でも申し上げた通り、外国人だけではなく、日本人の方にも日本の魅力を再認識していただけるよう、SNSなどで発信していきたいです。
インバウンドはもちろん、日本の観光を盛り上げていきたいと考えております。
⑦我、かく戦えり!
・私の<2次レポート>(60)
以上