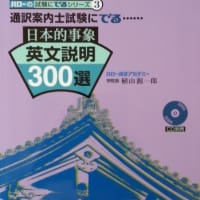2019年度<合格体験記>(55)(英語)
●英語(メルマガ読者、教材利用者)
一次免除科目無し全5科目初挑戦からの受験でしたが合格できてラッキーでした。
すでに合格していた知人からハローを教えてもらったのが2018年秋。
これから受験に向けて勉強とりかかろうとしていたタイミングでした。
一昨年の二次試験直後でしたので、メルマガを通じ二次試験再現取り組み、受験者経験談等をビビッドに拝見。
当初から二次試験までの全体イメージをしっかり持って勉強にとりくめて大いに助かりました。
セミナー等には参加しませんでしたが、メルマガのほか、一次試験では、<特訓1800題>、直前対策資料等を自分の理解度&弱点チェックに活用、二次試験では「300選」のお世話になりました。
①受験の動機
何度か海外勤務の経験、国内でも国際関係の仕事(経済、開発分野)が比較的長期でした。
また、一時期ですが国際文化交流促進に携わったこともありました。様々な国の方と接し、彼らの日本・日本人に対する関心の強さ・深さ、ハッとさせられる新鮮な視点の分析や質問に、自分の国に対する知識、理解の浅さを反省することたびたび。いつかしっかり勉強取組みたいと考えていました。
一昨年秋リタイアで時間ができたので具体的に受験を考えました。
通訳案内士は、知人・友人にすでに資格を持つ方が複数いたこと、受験中の知人もいることを知っていましたので関心を持ちました。
ほかに、「国酒」日本酒についてもかねて一度勉強したく考えていましたので、日本酒資格「SAKE DIPLOMA」も並行して受験。日本酒勉強はじめてみると覚えなければいけないことが予想以上に多く二兎追いは無謀だったかと焦りましたが、どちらも(ギリギリだったと思いますが)何とか合格できました。
日本酒試験一次(7月下旬)、二次(10月9日)それぞれ直前一ヶ月間案内士勉強はやむなく封印。案内士二次試験集中は10月10日以降でしたので、合格はうれしい驚きでした。
②第1次試験対策
まずは過去の試験問題数年分を模擬試験風に解いてどのように勉強にのぞむか考えました。
結論として、「「日本史」、「日本地理」が私にとって最難関。まぐれはありえないので、細部に亘り時間もかけてしっかり勉強必須。
「英語」一次は比較的オーソドックス(しっかり準備不可欠な二次とは異なりそう)。
「一般常識」と「通訳案内の実務」は、それぞれ、観光統計、観光庁研修テキストに的を絞って準備すればよさそう」の見通しを立てました。
受験後自己採点では、すこし軽視していた「通訳案内の実務」がギリギリ(条文文言問題ほぼ全滅、ほかにケアレスミスも)で冷や汗でした。
<英語>(78点)
他科目時間確保のため一次段階英語学習は割愛、実力で臨むことで割り切りました(一次終了後二次英語集中方針)。また、日本文化、観光関係文章からの出題、設問が多いようなので、日本地理、日本歴史の勉強が英語試験にもプラスになるはずと考えました。
<日本地理>(77点)
正直あまり得意ではなかった科目。一次準備の三割強の時間をあてました。
歴史と異なり自分にしっくりくる特定教科書を見つけられず、「平成30年版観光白書」を通覧しつつ、世界遺産、国立公園、各地域取り組み等極力原資料に当たって勉強する姿勢で臨みました。
トリップアドバイザーの「旅行なんでもランキング日本編」は今後も参考
にしたいです。
「旅に出たくなる日本地図」と都道府県別地図帳(「旅に出たくなる」は県単位の学習には不向きなので)の二冊と付箋を常時携行。合わせてタブレットフル活用(ウエブ検索。誤情報も多いウイキペディアだけで満足しない)で疑問は即時解消を心がけました。
全科目共通ですが、集中しての勉強は、長時間いてもあまり目くじら立てられない郊外型ファーストフード店に日参して行いました。ほかにも勉強しているとおぼしき人(小学生ぐらいから年配の方まで)がたくさんいましたので「私もがんばろう!」気持ちになれるメリットもありました。雑事避けられない自宅では、短時間で取組める「1800題」など。
復習(正答選択肢以外もチェック)に不可欠な採点結果と問題文コピーができるのは自宅の長所でした。ただ、今回受験の方のご報告、みなさん日本地理は非常に高得点とられていらっしゃいますね。私は、温泉等不得意あるのを認識しつつも時間切れで本番。温泉問題はやはりできませんでした。
<最重要事項のまとめ> → http://www.hello.ac/matome.geo.pdf
<直前対策セミナー>(日本地理資料)→ http://www.hello.ac/2019.7.6.pdf
<特訓1800題>を使い倒せ!→ http://blog.goo.ne.jp/gu6970/c/56e18e234050ec5f9ab991de649627c2
<日本歴史>(79点)
もともと好きだったこともありますが、五割強の時間を割いたと思います。
最初、かねて勉強したいと買っていた「新もういちど読む山川日本史」と山川「詳説日本史図録」の二冊、途中から教科書を山川「詳説日本史B」に切り替えて使いました。過去問から、「詳説」からのほぼそのまま出題あると推測しましたので。
教科書は通読四回でしょうか。旅行、テレビ番組見ながら、気になる事項は常時教科書記述もチェックしました。時間が許せばもっと読み込みたかったです。
日本歴史研究、新発見・定説の変化目白押しで、山川教科書記述もかつて高校時代にお世話になった頃とはずいぶん変わっていて新鮮でした。
いずれも常時携行。地理と歴史で合計四冊、タブレット、それから電子辞書の常時携行は「重たい」のが欠点ですが、疑問はその場で解決に有効だったと思います。
あとは、たくさん出ている歴史関係新書や令和がらみの歴代天皇、年号関係本、おもしろそうなものは時間の許す限りかたっぱしから読んで教科書理解に厚み持たせるべく努めました。
これは気分転換にもなったと思います。ちなみに、小説読書は受験期間中封印しました。
本番、問題の一部は「空回り感」ありの苦笑問題(?)でしたが、善意に解すれば案内士試験ならではの観光分野がらみ歴史問題を出題しようとの出題者試行錯誤でしょうか。「ならでは」問題、私はお手上げでした。
<最重要事項のまとめ> → http://www.hello.ac/matome.his.pdf
<直前対策セミナー>(日本歴史資料)→ http://www.hello.ac/2019.6.30.pdf
<日本史の時代区分と各文化の特徴> → http://hello.ac/timeline.pdf
<特訓1800題>を使い倒せ!→ http://blog.goo.ne.jp/gu6970/c/56e18e234050ec5f9ab991de649627c2
<一般常識>(44点)
観光統計関係に一割弱の時間を使いました。
その他は、従前からの習慣継続で、宅配新聞二誌を毎日しっかり読むことを日課としました。
外出時電車内などでも可能な限りタブレットで電子版を読みました。途中から英字新聞も購読スタート(読売が購読誌ひとつでしたのでThe Japan Newsを選択)しましたが、これは時事問題の英語訳チェック(英語二次向け地ならし)が主でした。
<最重要事項のまとめ> → http://www.hello.ac/matome.gen.pdf
<直前対策セミナー>(一般常識資料)→ http://www.hello.ac/2019.7.21.pdf→ https://blog.goo.ne.jp/gu6970/e/aa9caa987007e8ef9f390a0a88c6e667
<特訓1800題>を使い倒せ!→ http://blog.goo.ne.jp/gu6970/c/56e18e234050ec5f9ab991de649627c2
<平成31年度観光白書(要旨)→ https://www.mlit.go.jp/common/001294574.pdf
<通訳案内の実務>(33点)
配分時間は一割弱。勉強スタート直後と一次直前の二回観光庁研修テキストをそれなりに読み込んだつもりでしたが、本番後自己採点で冷や汗だったのは既述のとおり。
<最重要事項のまとめ> → http://www.hello.ac/matome.jitumu.pdf
<直前対策セミナー>(通訳案内の実務資料) → http://www.hello.ac/2019.8.5.pdf
<観光庁研修テキスト> → http://hello.ac/jitumu.122.pdf
③第2次試験対策
短期集中でしたので、「300選」と語研の「英語で説明する日本の文化」の二冊に教科書を絞りました。
(「英語で説明する日本の観光名所100選」や英語による日本の歴史説明書、「武士道」その他時間がゆるせば勉強したい本ほかにもたくさん購入しましたがおあずけにしました)
「300選」は、要領よく短く説明するパターン習得に役立ちました。
ただ、私の英語ボキャブラリーは、経済等の分野に偏りありを自覚していましたので「300」だけではまったく不足。語研で関連ボキャブラリー増加を図りました。
語研は、日本文化の諸側面、外人が関心持ちそうで私の知識・理解が不十分な事項を要領よくまとめていると思いました。「300選」四回ほどくり返したところで本番になりましたが、一回目は記載項目範囲とキーワード把握、二回目は語研と並べて(時間はかかりましたが、語研英文もすべて手を動かして一度書き写してみました)、三回目、四回目は、語研内容も頭に浮かべながら「300選」復習。
ちなみに私の今回英語学習はすべて手で繰り返し書いて。集中勉強はファーストフード店でしたので音読やCD学習には不向き。「300選」CDは聴かずに終わってしまいました。
発音は発音記号でチェックするロートルの学習法で(笑)。なお、各事項説明内容サブは、事項により、教科書にこだわらず
自分なりにしっくりする内容を自分の言葉で考えました。
「日本的事象英文説明300選」→ https://blog.goo.ne.jp/gu6970/e/1c2c0c0d82c19d1e7ad24fda018d2154
「日本的事象英文説明300選」<鉄板厳選128題> → http://www.hello.ac/teppan128.pdf
第2次口述試験対策<切腹鉄板予想問題70題> → http://www.hello.ac/teppan70.pdf
<プレゼンテーション・外国語訳>質疑応答予想問題60題→ http://www.hello.ac/yosou60dai.pdf
「通訳案内の現場で必要とされるトラブル対応方法」→ http://hello.ac/troubleshooting.pdf
本番は、いくつかハプニングがあったこともありますが、柄にもなく上がってしまいました。
⑴
入室前に、面接教室前の廊下の椅子に腰かけて入室合図を待つように指示受けたのですが、椅子に座っていると、室内から内容はわからないながら非常に流ちょうな女性の英語の声、ついで、男性の笑い声が聞こえてきたのがハプニングの一つ目。
私の前の受験生が女性の方でしたので、「そうか彼女はこんなに流ちょうに話される方なのだ!笑い声は男性試験官?!試験管を笑わせるほど和やかな雰囲気で答えられているのか。合格間違いなしだろうな。
自分はとてもあんなに流ちょうにしゃべれないな。でも、選抜試験じゃないはずだから訥々でも的確な回答できれば合格ライン達するはず。
自分のできる範囲で最善尽くすしかない」と自分に言い聞かせて落ち着こうとしている間に入室合図がかかってしまいました。
⇒あとで冷静になってみると、入室時に前の受験生とすれ違ったり見かけたりしませんでしたから、流ちょうに話されていたのはたぶん日本人女性試験官。おそらく前の受験生の評価を試験官の間ですり合わせていた声が聞こえたのだと思います。他の受験生と比較して一喜一憂は全く意味なし。自分の実力悔いなく発揮に専念すべしが教訓です。
⑵
ハプニング二つ目は、翻訳問題が終わったところで、日本人試験官から「おつかれさまでした。本日の試験はこれで終了です」説明があったこと。
驚きましたが「前半の出来が悪いと状況問題まだ進ませてもらえないこともあるのか」と思った私。試験官の勘違いにすぎなかったようで、「あ、失礼しました。まだ終了ではありませんでした」とすぐに修正されましたが一瞬肩を落とした私でした。
⑶
三つめはハプニングではないかもしれませんが、状況問題についてその場での設定変更。
寿司問題で、紙記載は「家族で寿司を希望しているが、奥様が生魚を食べることができません」とダメなのは「生」の魚でしたが、「調理した魚の寿司も種々あるから大丈夫」と話し始めたら、外人試験官から「ごめん。私の奥さんは「生」以外も魚はダメ。それでも大丈夫?」と設定修正でした。
これについては、それなりに冷静に「ハードル上がった。きっと私以前の受験生が難なく対応したので「生」だけ不可では状況問題として不十分との試験官臨機判断だろう」と考える余裕ありましたが、肝心の回答、つっかえつっかえで反省多々でした。
以下にすこし長くなりますが二次本番の模様、小生反省もふくめ参考まで記させていただきます。
○まだ上がったままスタートした説明問題選択肢は、竿灯まつり、タピオカドリンク、気象警報。いずれも私が得意でないもの。竿灯と気象警報で少し迷いましたが、気象
警報は気象庁の英語名が思い出せず、対して竿灯は口火第一文案「東北三大夏祭りの一つ」がすぐ浮かんだので竿灯を選びました。paper lanternsをつるした竹竿を体のあちこちで支えバランスとりながらと説明しましたが、話しながら「提灯は今も本当に紙製なのかな?」などと自問止まらず。支える部分、額や掌の英語(forehead, palm)も出てこず不正確自覚しながらの説明なりました。外国人試験管からの質問は二つ。
「何月に行われますか?」と「何のためのお祭りですか?」どちらも回答あやふやで、「夏祭りなので7月ないし8月だがどちらか正確には覚えていません」、「正確には覚えていませんが、確かthanksgiving関係。豊作に感謝し、祭りの参加者の多幸を祈る(結果的に遠からずの説明だったようですがその場で本人自信なし)」で終了。
⇒気象庁英語名は正確に言えなくても気象警報選択すればもうすこしいろいろ&適切に説明できたのではないかと悔い。
○翻訳問題は寿司(歴史から説き起こす方)。試験官読み上げに私のメモ追いつけず、後半はだいぶはしょった訳にならざるをえませんでした。また、前半部分に「当初は保存食として」のくだりがあったので、「熟れずし」のことだなと「fermented(発酵させて)」と言葉を補って訳したところ日本人女性試験官が少し怪訝な顔。「そうかこれは説明ではなく翻訳問題。言葉を補う説明は余計だった」と反省。試験官からの質問はありませんでした。
○状況問題。ハードル引き上げあった後ちょっと考えましたが「魚一切不可でも巻きずしどうでしょう。あなたの国では巻きずしは人気ありませんか?日本の野菜の巻きずしはおいしいですよ」と私。ここまではよかったのですが、試験官から「野菜の巻き寿司ですか。どんな野菜がお奨めですか?」
私「たとえばキュウリとか」と話した後、ほかの野菜が頭に浮かんでこず。「ほかには?」とうながされても「ええと・・・」と絶句。英語の問題ではなくあせって野菜自体が浮かびません。みかねた外人試験官から(野菜ではないが)「玉子は?」と助け舟。あわてて、「玉子食べられるなら寿司屋さんの玉子(焼き)おいしいですよ。
いずれにせよ、奥さんが魚ダメなことを私が良く説明する。客のオーダーに応えて作るのが寿司だから、奥様には食べられるものだけで用意される(はず)。
家族そろっての寿司のエンジョイ、心配なくできますよ」と急いで締めましたが、内心「きゅうりと玉子だけではいくらなんでも少なすぎ。満足には程遠いだろうな」。やり切った感なしで終了でした。
⇒終わったあとの反省尽きず。まず、寿司に関心のベジタリアン観光客はたくさんいるはず。日本食は多くの観光客にとって旅の楽しみの柱。「魚を使わない寿司」も通訳案内士にとり基本設定の一つでなければならない。
想定準備していなかった自分のふ
がいなさに呆れました。(実際、ウエブ検索すると「べジタリアン歓迎寿司屋さん」すぐ見つかりますね。)もう一つは、自分の知識と推測の範囲で対応(回答)しようとしたこと。たとえ予習できておらずでも「だろう」対応ではなく、実際に私がとるであろう対応をそのまま素直に説明するべきではなかったか。
すなわち、まず、奥様が食べられないものの範囲を正確に確認する(一口に魚と言っても互いの範囲が異なる可能性。グレイ分野もありそう。たとえば貝類は?甲殻類は?)次に、奥様食制限を前提に歓迎用意ありそうな寿司屋をウエブでチェック。
見つかればそこに、見つからなければ適宜の寿司屋に電話して、具体のもてなしを照会。結果をお客さんに説明し、お客さんがOKなら自信をもって予約。
④ハローのセミナー、メルマガ、動画、教材などで役に立ったこと。
各科目で既述のとおり。一人で勉強しましたので、メルマガ、ハロー教材が学習指針、達成度チェックに有効でした。
⑤今後の抱負
合格はしましたが、今の実力でお金をいただいたガイドはおこがましくてとてもとても。今年一年は実践の実力を少しでもつける助走期間にしたく思っています。
東京オリパラボランティア(フィールドキャストとシティキャストの双方)、東京都街中観光ボランティアに手を挙げていますのでこれらを通じた経験蓄積が一つ。コロナの収束強く期待しているところです。
東京在住ですが、東京および東京近郊の外人人気スポット・体験で私が未踏、未経験の場所・コト少なからず。二次試験で反省したベジタリアン/ビーガン、ハラール対応寿司屋、レストラン、ラーメン店も。これらの実査が二つ目。
障がいを持たれる方もたくさんいらっしゃるでしょうから、東京都発行の資料等を片手に人気スポット、主要駅等のアクセセサビリティ(バリアフリー)も確認しておきたい。防災についても然り。これらが三つ目。
そして、四つ目に外人観光客が利用しそうな英語情報サイトにもしっかり習熟しておきたい。やるべきことはたくさんあると認識しています。
また、せっかくなので旅行業務取扱管理者試験(通訳案内士と裏表の資格と認識)や英語で受験する日本酒資格(日本酒に関心の観光客もたくさんと認識)にも挑戦したいと考えています。