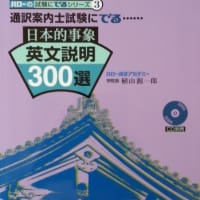2024年度<合格体験記>(5)【13:00~14:00】(キャッシュレス決済)(英語)
●植山先生
自分でも驚きだったのですが、合格していました!
植山先生が説かれるほどの真剣さで100パーセント出来たかというと自信はありませんが、自身の現在の生活の中でやれるだけはやったとは思っており、結果は付属的なものと思っていたので、試験を終えた時点で達成感を味わってはいたのですが、今回結果がついてきたことは望外の喜びでした。
振り返ると、先生が無料で提供くださっている情報や資料なしにここまで来ることは出来なかったと思います。改めてここで感謝申し上げます。
●英語(メルマガ読者、無料動画利用者、無料教材利用者、<傾向と対策シリーズ>利用者、<模擬面接特訓>受講者、
【1】受験の動機
日常で英語を使う機会がなくなって久しく、漫然と日々を過ごしていました。このままでは大好きな英語からますます遠ざかってしまうと思い、「合格」という、はっきりした結果が出る試験を受けることで、英語や好奇心のモチベーションを維持しようと、受験することを決めました。
【2】第1次試験対策
(1)<英語> 免除(英検1級)
(2)<日本地理>(76点位)
一昨年の受験で地理だけを落としました。答え合わせをしてみると、京都の箇所が全滅でしたので、昨年は京都を重点的にと心掛けて勉強しました。(が、重文等は覚えたものの、全て網羅することは叶わず、二次試験の選択肢であった「京都御所」は??で、別の選択肢を選びました。苦笑)
一昨年からの知識はありましたが、温泉や重文、山脈、世界遺産等々、日本の地理全般の知識が未だ浅かったので、地図帳ほか、子供向けものも含め分かりやすい地理に関する本を読んで、都道府県ごとに地図を描き、そこに本の情報やマラソンセミナー講義(先生が照れながら体験談とユーモアを交えてお話しされる内容が面白くて飽きませんでした。)で得られる情報を自分の地図に書き足してまとめていきました。マラソンセミナーは二巡しました。同時に項目地図帳もプリントアウトして、山や温泉、国立公園などの情報を書き込みました。
過去問も初めに一回やって、その後学習をある程度終えたあとに1回、2回と計3回ほどやりました。
(下記を利用しました)
<第1次筆記試験問題>
2024年度受験用<日本地理>の傾向と対策(資料)
<マラソンセミナー>(日本地理)(12講義24時間)
<項目別地図帳>
<都道府県別地図帳>
(3)<日本歴史>(90点)(2023年)
大学受験で日本史を選択したため、基礎知識はあったのですが、それも何十年前のことで、細かいことは忘れていました。最初に一度過去問をやって自身のレベルを確認したのち、家にある子供用歴史学習漫画を全巻読むところから始めました。2巡目にもう少し時間をかけて読んで、ノートに重要事項や年表をまとめていきました。また、江戸時代など近代の問題が毎年必ず出ているような気がしたので、江戸時代の徳川将軍名とその治政内容を暗記しました。漫画は計3回読みました。
(下記を利用しました)
<第1次筆記試験問題>
2024年度受験用<日本歴史>の傾向と対策(資料)
<最終合格体験記>(2018年~2023年)
(4)<一般常識>(2023年)(7,8割取れたと思います)
あまり覚えていないのですが、こちらに関してはハローの無料教材だけを使って、観光白書を精読&まとめ、過去問繰り返し、の学習をしました。
(下記を利用しました)
<第1次筆記試験問題>
2024年度<一般常識>の傾向と対策(資料)
令和5年(2023年)版 観光白書(完全版)
<最終合格体験記>(2018年~2023年)
(5)<通訳案内の実務>(2023年)(7,8割取れたと思います)
あまり覚えていないのですが、こちらに関してはハローの無料教材だけを使って、資料を精読&まとめ、過去問繰り返し、の学習をしました。
(下記を利用しました)
<第1次筆記試験問題>
2024年度受験用<通訳案内の実務>の傾向と対策(資料)
<最終合格体験記>(2018年~2023年)
【3】第2次試験対策
●試験官の特徴
①日本人試験官の特徴:
50代?男性。淡々とした印象でマニュアルそのままの指示を日本語だけで行っていた。
②外国人試験官の特徴:
優しそうな雰囲気の40代前半くらいのアジア系アメリカ人男性。こちらの拙い英語にもうんうんと理解を示してくれて、突っ込んだ質問はされなかった。
●試験官からの注意事項など
時計はスマホウォッチは禁止で、自身が時間を測るように、普通の腕時計はよいとされていましたが、それを身につけず、机の上に置くのは不可とのことでした。
①日本人試験官の特徴:
50代?男性。淡々とした印象でマニュアルそのままの指示を日本語だけで行っていた。
②外国人試験官の特徴:
優しそうな雰囲気の40代前半くらいのアジア系アメリカ人男性。こちらの拙い英語にもうんうんと理解を示してくれて、突っ込んだ質問はされなかった。
●試験官からの注意事項など
時計はスマホウォッチは禁止で、自身が時間を測るように、普通の腕時計はよいとされていましたが、それを身につけず、机の上に置くのは不可とのことでした。
●プレゼンのテーマ
①京都御所
②冬至
③かまくら←これを選択しました!
●プレゼンの後の試験官との質疑応答
(試験官)子供達がかまくらの中で遊ぶそうだけど、かまくらは子供達だけで作れますか?
(私)実際はちょっと難しいと思います。主に大人が作りますが、子どもが手伝ったりすることはあると思います。
(試験官)かまくらは冬ならいつでもやっていますか?
(私)よくわかりませんが(I’m not sure but….)実際は毎日と言うわけにはいかないと思います。例えば秋田など、かまくらを目的に行く際は事前にスケジュールをチェックしていく方が良いです。
<外国語訳>(確定版)
日本におけるキャッシュレス決済の普及率は、現在39%程度にとどまっています。特に、個人経営の商店や飲食店では、クレジットカードや電子決済を導入していない店舗が多く見られます。このため、外国人観光客がクレジットカードや電子マネーを利用できず、現金を持ち合わせていない場合、購入や飲食を諦めることが少なくありません。
(英語訳例)(確定版)
In Japan, the use of cashless payments is still around 39%. Many small shops and restaurants do not accept credit cards or electronic payments. Because of this, some foreign tourists may have trouble if they do not have cash. If a store does not accept credit cards or e-money, they may not be able to shop or eat there.
<シチュエーション>(確定版)
外国人旅行者が、日本の鰻屋で鰻の蒲焼を楽しみにしていました。しかし、店の入り口には「現金のみ、カード不可」との張り紙があり、クレジットカードや電子決済が利用できないことが分かりました。お客様は日本食に興味があり、特に鰻を食べることを楽しみにしていましたが、日本円の現金を持ち合わせていません。国際キャッシュカードは所持していますが、店舗では利用できません。あなたは通訳案内士としてどのように対応しますか。
<条件>(確定版)
お客様は、新婚旅行中のカップル。日本食、とくに鰻への興味が強く、是非食べたいと言っている。
●<条件><シチュエーション>に対するあなたの回答
以下のような会話をしました。
●試験官との質疑応答
(私)ウナギを楽しみにしていらっしゃるとのことですね。
(試験官)魚は嫌いなんだけど、ウナギは食べたいと思ってるんだ。
(私)そうなんですね、ウナギは確かにとても美味しい伝統的な日本の食べ物でとても人気があります。
現金の持ち合わせがないと伺いましたがそれでよろしいですか?
(試験官)はい
(私)店は現金のみと書いてありますが、今から一応中に入って店の方に確かめてみますね。visaなどのクレジットカードカードはお持ちですか?
(試験官)アメリカで使ってるvisaのクレジットカードならあります。
(私)今から聞いてみます。もし現金しかダメだということだったら、ちょうど鰻丼分のお金をお貸しするので、ホテルに戻ったら返していただけますか?
(試験官)分かりました。ありがとう。
1次試験後、毎日1時間くらい励みました。植山先生の「日本的事象英文説明300選」を何度もシャドーイング&ディクテーション後、二次セミナー資料を読んで過去問の和訳を繰り返し行いました。
先生の<模擬面接特訓>を受けた後は、京都、奈良、箱根他、今年出そうな重要語句を、いただいた資料をもとに1.5分くらいの長さにした原稿を作り、それらを何度も音読して暗記しました。
(下記を利用しました)
・<2次セミナー>のまとめ(2022年度~2024年度)https://blog.goo.ne.jp/gu6970/e/28642de0306a059277c6c574cf0a0414
・<第2次口述試験対策>のまとめ(2023年度~2024年度)https://blog.goo.ne.jp/gu6970/e/e7b55c0a4ea0e2bf34e4f49eee357667
・第2次口述試験問題のまとめ(2013年度~2023年度)
https://blog.goo.ne.jp/gu6970/e/f8580b22708c49b4a70d8d20ac3b72aa
・<外国語訳問題>の後の<質問の類型>
https://blog.goo.ne.jp/gu6970/e/c2b54d9cfb5d31644836927b6fc1332c
・<外国語訳問題>の出題分析
https://blog.goo.ne.jp/gu6970/e/1b7cce48b6f5b6c859a9b01af1f8b5b6
・<2次セミナー>のまとめ(2022年度~2024年度)https://blog.goo.ne.jp/gu6970/e/28642de0306a059277c6c574cf0a0414
・<第2次口述試験対策>のまとめ(2023年度~2024年度)https://blog.goo.ne.jp/gu6970/e/e7b55c0a4ea0e2bf34e4f49eee357667
・第2次口述試験問題のまとめ(2013年度~2023年度)
https://blog.goo.ne.jp/gu6970/e/df6562e52a65cd759c8bd492973a0193
・<プレゼン><外国語訳>質疑応答<予想問題60題>
http://www.hello.ac/yosou60dai.pdf
・「日本的事象英文説明300選」の出題実績(2006年度~2023年度)
・<プレゼン><外国語訳>質疑応答<予想問題60題>
http://www.hello.ac/yosou60dai.pdf
・「日本的事象英文説明300選」の出題実績(2006年度~2023年度)
・「日本的事象英文説明300選」の音声ファイル(mp3版)
https://blog.goo.ne.jp/gu6970/e/dc6d6c245cbc0364b16eaf04c9d60205
・ハッピー・ガイド・ナビ(Happy Guide Navi)(第2次口述試験攻略法)https://blog.goo.ne.jp/gu6970/e/dc6d6c245cbc0364b16eaf04c9d60205
https://blog.goo.ne.jp/gu6970/e/f8580b22708c49b4a70d8d20ac3b72aa
・<外国語訳問題>の後の<質問の類型>
https://blog.goo.ne.jp/gu6970/e/c2b54d9cfb5d31644836927b6fc1332c
・<外国語訳問題>の出題分析
https://blog.goo.ne.jp/gu6970/e/1b7cce48b6f5b6c859a9b01af1f8b5b6
(3)受験の感想
上記で書いたようにスムーズに会話できればよかったのですが、実際は焦りながら、簡単なワードを使って稚拙な英語レベルでしか説明できませんでした。自身の英語レベルは自覚していましたが、やはり実力以上のものは本番で出せるものではないなぁと実感しました。「実力」を付けるにはやはりもう少し時間をかけて研鑽することが必要だと思いました。
【4】メルマガ、動画、教材、セミナーなどで役に立ったこと
二次の準備を始めるにあたって、日本的事象を実際にどう説明するか、日本語でさえおぼつかないものが多かったので、植山先生の「日本的事象英文説明300選」はとても頼りになりました。
実際の試験の情報については二次セミナー資料が大変役立ちました。どれも大事な資料として役立たせていただきました。
<模擬面接特訓>については植山先生から、情報を「階層」順に説明する、と教わったことが深く印象に残りました。確かに、旅行者にとって一番知りたい情報を出さないとガイドとしての意味はないなと思わせられました。したがって、その後の勉強では情報の階層を意識して自身でカンペを作って覚えるなどを繰り返し行い、学習の方向性が定まりました。実際の試験では残念ながら用意したワードは出題されませんでしたが、それは一体なにか、という第一義の情報を意識して説明することは出来たかもしれません。
【5】ご意見、ご感想、ご希望
これでもかというほどの熱意をもって指導くださり、無料で提供くださる情報に支えられて二次試験まで到達することが出来ました。植山先生の熱意に圧倒されていました。
一番最初に書きましたが、この度合格したのも、植山先生の提供される情報を無料で使わせていただくことが出来たおかげです。貴重な情報をアップデートしながら常に発信していただき本当にありがとうございました。
今回合格となりましたが、ガイドとしての知識はもちろん、英語力に関してもまだまだ十分とは言えません。それでも受かったのは、二次面接で、口ごもったり、沈黙することなく、とにかくひとまずやりとりが出来たこと、会話を気持ちよい形で終えられたこと、「現金がないが鰻を食べたい」という無理難題型の質問にそれなりにこたえることが出来たことによるのかなと自己分析しています。
【6】今後の抱負
実際にガイド業界に入るのかどうかいまだ決めていませんが、入り口に立つまでに情報を集め、判断したいと思います。そしてせっかくの資格ですので、今後のために怠ることなく研鑽していく所存です。
【7】私の<2次レポート>
【8】<模擬面接特訓> 受講の感想(2024年11月4日)
本日は貴重なお時間をいただき、時間ギリギリまで教えていただきありがとうございました。以下感想をお送りいたします。
準備がまだ整っておらず、恐る恐る臨んだ<模擬面接特訓>でしたが、準備が整っていないからこそ、何に焦点を置いて本番までの学習を進めたらいいかが、明確になり、模擬面接を受けてとてもよかったです。
頂いたアドバイスの中で特に踏まえて練習していきたいことは、まず、ゆっくり焦らないで喋ること、2分という時間を意識してプレゼンの練習をすること、単語のアクセントもおろそかにせず、基本的な文法を押さえて話すこと、そして外国人観客にとって何を伝えるべきか、情報は「階層」に沿って話すこと、です。これらはこれまでご公開されている模擬面接体験談の中でも繰り返し言及されてはいましたが、植山先生を目の前にして直接説明いただくことでより、感覚的に理解することが出来ました。
本日の面談を経て、自分が言える情報をあれもこれも詰め込んでその場しのぎで話すのではなく、説明する語句をまず定義し、(外国人観光客にとっての)情報の優先順位を意識して説明できるようにし、また、日本を説明する上で最重要の事柄は暗記してスラスラ言えるまで練習したいと思います。あと1ヶ月頑張ります。
最後に植山先生のご熱意とホスピタリティに改めて感謝申し上げます。宿題も持ち帰って励みます。
以上