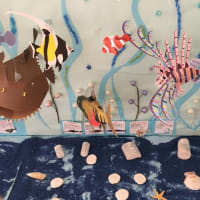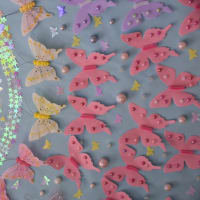インフルエンザの流行がピークにあり、それに伴って副鼻腔炎や中耳炎の患者さんも増えています。インフルエンザの熱が下がったのに、いつまで経っても鼻と咳が止まらなくて受診される患者さんが多いです。インフルエンザの診断を受けて、2日目にはもう急性中耳炎になって受診した子もいます。逆に2日前から熱と鼻水で、小児科の先生に検査をしてもらったがインフルエンザ陰性で、熱が下がらず中耳炎を心配して受診され、耳鼻科で再検査をしたら、実はインフルエンザだったという子もいました。そのような患者さんたちで、昨日は今月1番の患者数でした。
患者さんには、ウイルスで弱った粘膜で細菌が増えて炎症が起きる、と説明しています。その実際のメカニズムは、複合的なものでしょうが、先日MRさんの持ってきてくれたパンフレットに、札幌医大の氷見教授が、その一部をまとめてくれていました。
スウェーデン留学中、副鼻腔炎の研究をしているとき、共同研究者だった細菌学の教授に、まず教わったのは、細菌が感染して病気を起こすためには、標的の細胞にくっつくこと、そしてそこで増えること、毒や炎症を引き起こす物質を放出すること、宿主の免疫の攻撃から自分を守って生き延びること、という4つの要素が必要だということでした。インフルエンザやRSウイルスのような呼吸器ウイルスが、鼻、耳、咽の気道上皮の細胞に感染すると、上皮の細胞膜に血小板活性化因子(PAF)受容体というものの発現が誘導されます。これは肺炎球菌やインフルエンザ菌(名前は同じでもインフルエンザウイルスとは全く別物)といった、副鼻腔炎や中耳炎の原因菌の受容体でもあるのです。ウイルスの感染によって、細菌が上皮細胞にくっつきやすくなるのです。
そしてクラリスロマイシンという薬が、そのPAF受容体発現亢進を抑制することも書かれていました。その薬をつくっている会社のMRさんが一番強調したかったのは、そこでしょう。しかし、この薬は抗菌薬としては、肺炎球菌やインフルエンザ菌にはあまり効きませんので、急性の副鼻腔炎や中耳炎になってしまったときの治療には、別の抗菌薬が使われます。