皆様こんにちは。
本日は空き時間があったので、珍しく昼間の更新です。
さて、前回の囲碁用語について・その2では、形を示す囲碁用語は意味・目的を含んでいることがあるとお話ししました。
今回はそれを確認していきましょう。
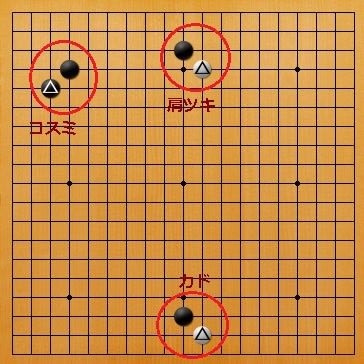
<1図>
まずはこの図をご覧ください。
左上黒△は、前回示したコスミですね。
自分の石から斜め隣に打つ手であり、これは純粋に形だけを示す手と言って良いでしょう。
ですから、黒△の代わりに2路上や2路右、2路斜め右上に打つ手も全てコスミです。
そして、右側の白△が肩ツキ(衝き)であることも前回示しましたね。
では、下辺白△はどうでしょうか?
これは肩ツキではなく、単にカド(角)と呼ばれます。
カドというのは相手の石の斜め隣に打つ手の総称です。
机の角、本の角などと同じイメージですね。
肩ツキもカドの一種なのですが、打たれる目的がある程度はっきりしているため、独自の名前が付いています。
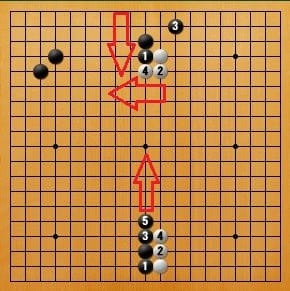
<2図>
1図の後の進行を考えてみましょう。
上辺黒1~白4は、肩ツキからの基本の進行です。
この結果ですが、元々黒石には中央方面への道があったところを、白が上から押さえ付けて妨害したことになります。
大抵の場合、肩ツキはこういうことを目的としているのです。
次に、下辺を見てみましょう。
黒5までの進行を想定してみますと、黒石の中央方面への道は止まっていませんね。
つまり、1図下辺白△には肩ツキと同じ目的は無いので、単にカドと呼ぶことになります。
ところで、また上という表現が出てきましたね。
上が碁盤の中心、端が碁盤の下であるという概念は、慣れないとピンと来ないかもしれません。
一方で上辺、下辺といった表現をすることもあり、ちょっとややこしいですね。
ですが、囲碁用語を正しく理解するためには重要な概念です。

<3図>
意味や目的によって、形の名前が変わることがある・・・。
それを示すために、問題を作ってみました。
8問とも、最後に黒△と打ったところです。
それぞれの黒△は、何と呼ばれる手でしょうか?
解答は次回です。
初段ぐらいの棋力があっても、全問正解できるとは限りません。
囲碁用語を覚えることは、棋力アップのために必須のことではありませんからね。
ただ、覚えておけば解説などを聞いていて混乱することは減るでしょう。
本日は空き時間があったので、珍しく昼間の更新です。
さて、前回の囲碁用語について・その2では、形を示す囲碁用語は意味・目的を含んでいることがあるとお話ししました。
今回はそれを確認していきましょう。
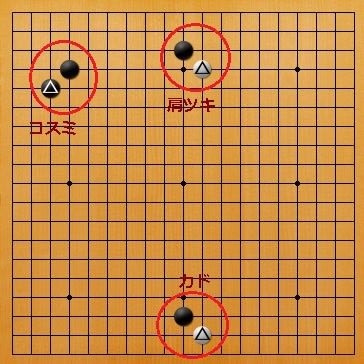
<1図>
まずはこの図をご覧ください。
左上黒△は、前回示したコスミですね。
自分の石から斜め隣に打つ手であり、これは純粋に形だけを示す手と言って良いでしょう。
ですから、黒△の代わりに2路上や2路右、2路斜め右上に打つ手も全てコスミです。
そして、右側の白△が肩ツキ(衝き)であることも前回示しましたね。
では、下辺白△はどうでしょうか?
これは肩ツキではなく、単にカド(角)と呼ばれます。
カドというのは相手の石の斜め隣に打つ手の総称です。
机の角、本の角などと同じイメージですね。
肩ツキもカドの一種なのですが、打たれる目的がある程度はっきりしているため、独自の名前が付いています。
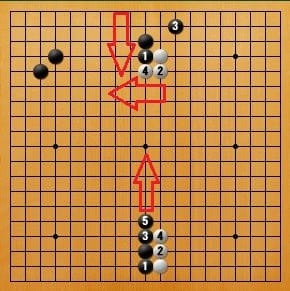
<2図>
1図の後の進行を考えてみましょう。
上辺黒1~白4は、肩ツキからの基本の進行です。
この結果ですが、元々黒石には中央方面への道があったところを、白が上から押さえ付けて妨害したことになります。
大抵の場合、肩ツキはこういうことを目的としているのです。
次に、下辺を見てみましょう。
黒5までの進行を想定してみますと、黒石の中央方面への道は止まっていませんね。
つまり、1図下辺白△には肩ツキと同じ目的は無いので、単にカドと呼ぶことになります。
ところで、また上という表現が出てきましたね。
上が碁盤の中心、端が碁盤の下であるという概念は、慣れないとピンと来ないかもしれません。
一方で上辺、下辺といった表現をすることもあり、ちょっとややこしいですね。
ですが、囲碁用語を正しく理解するためには重要な概念です。

<3図>
意味や目的によって、形の名前が変わることがある・・・。
それを示すために、問題を作ってみました。
8問とも、最後に黒△と打ったところです。
それぞれの黒△は、何と呼ばれる手でしょうか?
解答は次回です。
初段ぐらいの棋力があっても、全問正解できるとは限りません。
囲碁用語を覚えることは、棋力アップのために必須のことではありませんからね。
ただ、覚えておけば解説などを聞いていて混乱することは減るでしょう。









