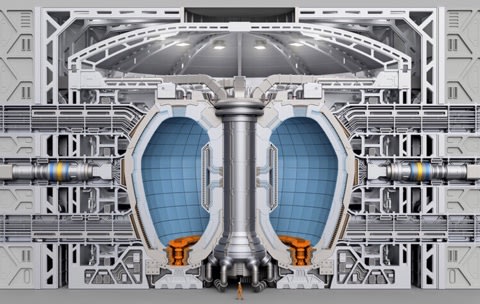大阪環状線開通60年 乗客に優しく「改造プロジェクト」
産経新聞より 210419
大阪市中心部を走るJR大阪環状線は、今月で開通60年となる。
通勤・通学や観光にも欠かせない路線として定着する一方、車両や駅舎は老朽化。
文字通り環状運転する電車に加え、和歌山や奈良方面に向かう快速電車が乗り入れることから、不慣れな利用者から困惑の声が寄せられることもあった。
明るく、分かりやすく-。JR西日本は還暦を迎えた環状線のイメージや利便性向上に向け、改良を進めている。(野々山暢)

「いろいろな行き先の電車が止まるので、どこに並べばいいか迷う」。JR西にはこのような声が寄せられてきた。
東京都内を回るJR山手線のホームにいれば、同線を一周する電車がやってくる。シンプルな山手線に対し、環状線は少し事情が異なる。
例えば、大阪駅の環状線内回り(西九条方面)ホーム。環状線は天王寺駅までの半周しかせず、加茂駅(京都府木津川市)や和歌山駅(和歌山市)、関西空港駅(大阪府田尻町)に直接向かう快速電車も止まる。乗り換えなく目的地に向かえるのは利点だが、乗り過ごすと思わぬ場所に着いてしまう可能性がある。
こうした課題を解消するため、JR西が対応を進めている。
シカ、ミカン、飛行機…。奈良や関空に向かう電車が慌ただしく発着する大阪駅では2年前、足元の乗車位置案内をアイコンで示し、目的地別にどこの列に並べばいいのか一目で分かるようにした。並ぶ場所を路線ごとに定めた色(ラインカラー)でも示していたが、今年1月からはその幅を広くした。
環状線と東西・学研都市線が十字に立体交差し、乗り換え方法の説明が難しかった京橋駅。平成29年夏から始まった同駅のリニューアル工事では、エレベーターを5基から8基に増設し、それぞれに動物のイラストを割り当てた。何を目印に駅構内を移動すればいいのか、初めて来た人にも分かりやすくした。
他路線と比べ利用者が減少傾向にあった25年、JR西は「大阪環状線改造プロジェクト」を立ち上げた。大阪駅や京橋駅におけるさまざまな改善も、プロジェクトの一環だ。
歴史を重ねる中で、駅舎や車両の老朽化も進んだ。そこで「明るい、きれい、わかりやすい」をコンセプトに、駅店舗のリニューアルやトイレの改良を進め、新型車両も導入した。
27年には全駅で発車メロディーが採用された。
大阪駅は大阪で愛された故やしきたかじんさんの代表曲「やっぱ好きやねん」、
天王寺駅は地元出身の和田アキ子さんの「あの鐘を鳴らすのはあなた」。
駅ごとのシンボルフラワーも定めた。
プロジェクトに携わるJR西の渡辺修二さん(40)は「引き続き魅力ある路線の実現を進めていきたい」と話した。
プロジェクトに携わるJR西の渡辺修二さん(40)は「引き続き魅力ある路線の実現を進めていきたい」と話した。
◇
大阪環状線 大阪、京橋、天王寺、西九条など19駅を経由する路線。全長21・7キロで踏切はない。開通は昭和36年4月25日。すでに運行していた旧城東線(大阪-天王寺)や旧西成線(大阪-西九条)などをつなげ、一つの輪とした。ただ当初の西九条駅は、地上ホームと高架ホームに分断されていたため電車が一周できず、完全な環状運転は39年3月から始まった。
💋その昔、帰宅時、ちょくちょく疲れ癒やしで内回りで帰るを、仮眠しつつ外回りでぐるっと遠回りして帰宅。更に乗り越しても元に戻るだけ。気楽、懐かしい。
心地よい振動と移り変わる車窓と思い出。