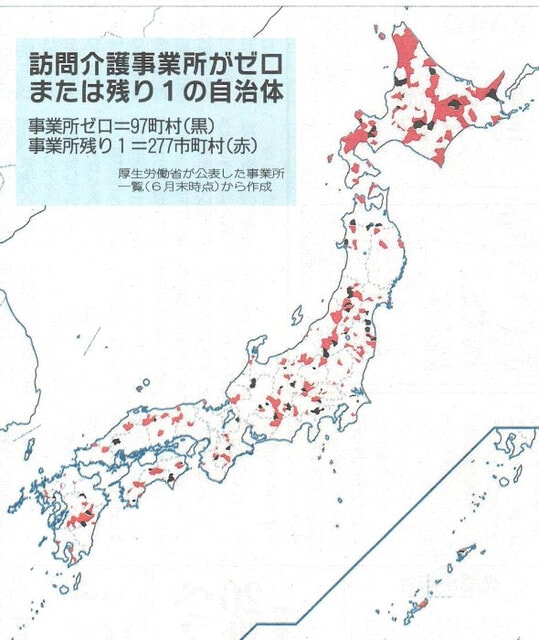お盆に入り、お墓参りに行った。
お寺での、孫もいて家族総出でお参りしている風景はほほえましい
先祖を中心に家族や親せきも集まる日本的風習でもある。
宗教的行事ではあるが、多くは宗教を意識せず「世俗化」しているのではないか。
それにしても日本の思想史のなかでは、仏教の位置づけは大きい。
お盆を前に、
史的唯物論の立場にたつ宗教学者の佐木秋夫氏の著作「仏教の源流と日本の仏教文化の形成」「鎌倉仏教の成立」の二編を久しぶりに再読した。
佐木氏は、
「古代・中世のきわだった思想家の多くが仏教僧だといっていい。現代日本においても、仏教は宗教文化の主軸をなしている」
として、社会・経済的な階級的視点から分析している。
1 仏教の基本的観念と歴史の流れ
シャカとその教え
「シャカの基本的な発想は、人生は苦である、と見定めて、その原因をみきわめ、その苦からの解脱(解放・脱却)のための、正しい道を選び進む」
「インドの伝統的な業報・輪廻の思想は、仏教においても抜きがたく根を張っていた」
「前の生での行為(業)のむくい(報)は後の生で受ける、という・だから悪をやめて善業を積む、という道徳的規制にもなるのだが、これが階級的に悪用されて、身分が低く貧しいのも前生の悪業の報い、ということにもなる」
「シャカは、快楽主義と苦行主義との両極端をしりぞけて中道を歩めと説いたというが、それは中庸とか中間的、どっちつかずという意味ではない
要するに中道とは正しい方向、路線ということを意味する」
「しかし、これが後代の「上流」意識をもつ説教師たちによって、危なっ気のない保身的な処世術とか、あるいは政治的な中間・灰色主義の正当化のために利用されてきていることは、事実である」
すこし長いが、引用させてもらった。
歴史は、宗教を権力を維持するために取り込んでいったことがよくわかる。
これが宗教団体の堕落に繋がり、階級闘争が宗教の衣をまといながら激動の時代、鎌倉時代の大変革となっていく。
念仏の法然と親鸞、禅の道元、法華の日蓮と鎌倉仏教の大先達、日本仏教の抜群の巨峰が、肩をならべている時代に突入する。
時あたかも、貴族階級から武士階級への大きな歴史の転換点にさしかかる。
まだ「社会科学」のない時代であるがゆえに、佐木氏の宗教論はおもしろい。
次回へ・・・
追記
仏教の源流のひとつに「般若心経」がある。
写経などで心が落ち着くと広く知られている。
氏の解説は次のように。
一世紀ごろから数世紀にわたり書かれた「般若経」は、般若(プラジェヤー=知恵)という題名がしめすように、哲学的に「空」の原理を詳細に説く。その簡便な要約とされる『般若心経』は日本でも広く流布しているが、その構造は次のようになっている。
観音が「悟りの彼岸に至る知恵」を深くつきつめて、すべて「皆空」とさとり、いっさいの苦厄を救おうと、シャーリプトラ(シャカの賢い弟子)に説きあかす。「色即是空、空即是色……」(色=有が「即」空であり、空がそのまま有である……)。それから、存在と認識に関する仏教の形而上学的な説を述べ、最後にダラニ(呪文)がつけてある。すなわち苦を脱するには空観が必要で、そこをとおってから現実肯定に進めば、迷いもなくなるし呪術的な霊験も得られる、としている。
どうだろうか?
これを入口にしてさらに内容を「哲学的」に深めては。
「空」を哲学的に考察しては?
私は、すぐれて弁証法的だと思う。しかし、後半部分の呪術的な、加持祈祷にはついていけないが。