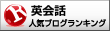<お盆>
7. 墓参りをして、死者の霊を弔う。
→墓参りは、一般的には visit a graveという。
今回のポイントは『弔う』。死者を弔うとは一体いかなることか。
こういう、いかにも日本的な表現を英語にするには、よく考える必要がある。
弔うとは、亡き人の冥福を祈ること(広辞苑より)。では冥福を祈るとは?死者であれ生者であれ望む事は『幸せ』である。よって、
・I hope they are happy after death.
・I hope the dead people are happy in the heaven.
検証のために海外のブログ等を見ても、やはり hope they are happy 等の言い方で失った者への想いが綴られている。
弔う、冥福を祈る、また成仏するなども、全く発想としては同様である。日本的な表現であっても、言葉は英語と日本語で違っても、人間の想いは変わらない。
「天下のこと万変といえども、吾がこれに応ずるゆえんは、喜怒哀楽の四者を出でず」
中国、明代の思想家、王陽明の言である。
人生とは、つまるところ、いかに喜び、いかに怒り、いかに哀しみ、いかに楽しむか。
複雑極まる人生が、即ち喜怒哀楽?面白い。
敷衍(ふえん)して考え、語学に当てはめる。様々な感情がある。それに伴い様々な表現がある。しかし、様々な感情表現を分析すると、結局のところ喜怒哀楽というカテゴリーに収まるのではないか。
安易な単純化を勧めているのではない。
単純化だけでいいとなると、どんな事でも『微妙』や『うざい』等表現するボキャブラリー貧困状態と変わらない。
そうではなく、表現に苦しむ英語学習者として、どうすれば表現力を伸ばせるかの方法論としての単純化、思考の整理である。
種々雑多な事物から、それぞれに共通する項目を抽出する理性の働き。人間、違いには敏感である。人のアラはよく目立つ。個性の時代。各企業も生き残りをかけて差別化を図る。全部『違い』である。その一方、違いの中に『同じ』要素がある。
あいつと俺は違うのだ!と個性を主張していても、病気になったら病院へ行き、診察を受け、薬をもらう。違う人間なのに、医療が可能なのは、同じ人間として、共通の体の構造になっているから。当たり前かもしれない。語学でも同じである。
違いの中に同じものを見出す。
古来、哲学者は、違いの中に共通のもの(本質)を、相対の中に絶対を、変化の中に不変(普遍)を、そして滅びる者の中に不滅なる者、即ち永遠を見出そうとした。
たかが英語、されど英語。私には、英語を学ぶことと、いにしえの哲学者が求めたものが、どうも違うようには思えない。
以上。
7. 墓参りをして、死者の霊を弔う。
→墓参りは、一般的には visit a graveという。
今回のポイントは『弔う』。死者を弔うとは一体いかなることか。
こういう、いかにも日本的な表現を英語にするには、よく考える必要がある。
弔うとは、亡き人の冥福を祈ること(広辞苑より)。では冥福を祈るとは?死者であれ生者であれ望む事は『幸せ』である。よって、
・I hope they are happy after death.
・I hope the dead people are happy in the heaven.
検証のために海外のブログ等を見ても、やはり hope they are happy 等の言い方で失った者への想いが綴られている。
弔う、冥福を祈る、また成仏するなども、全く発想としては同様である。日本的な表現であっても、言葉は英語と日本語で違っても、人間の想いは変わらない。
「天下のこと万変といえども、吾がこれに応ずるゆえんは、喜怒哀楽の四者を出でず」
中国、明代の思想家、王陽明の言である。
人生とは、つまるところ、いかに喜び、いかに怒り、いかに哀しみ、いかに楽しむか。
複雑極まる人生が、即ち喜怒哀楽?面白い。
敷衍(ふえん)して考え、語学に当てはめる。様々な感情がある。それに伴い様々な表現がある。しかし、様々な感情表現を分析すると、結局のところ喜怒哀楽というカテゴリーに収まるのではないか。
安易な単純化を勧めているのではない。
単純化だけでいいとなると、どんな事でも『微妙』や『うざい』等表現するボキャブラリー貧困状態と変わらない。
そうではなく、表現に苦しむ英語学習者として、どうすれば表現力を伸ばせるかの方法論としての単純化、思考の整理である。
種々雑多な事物から、それぞれに共通する項目を抽出する理性の働き。人間、違いには敏感である。人のアラはよく目立つ。個性の時代。各企業も生き残りをかけて差別化を図る。全部『違い』である。その一方、違いの中に『同じ』要素がある。
あいつと俺は違うのだ!と個性を主張していても、病気になったら病院へ行き、診察を受け、薬をもらう。違う人間なのに、医療が可能なのは、同じ人間として、共通の体の構造になっているから。当たり前かもしれない。語学でも同じである。
違いの中に同じものを見出す。
古来、哲学者は、違いの中に共通のもの(本質)を、相対の中に絶対を、変化の中に不変(普遍)を、そして滅びる者の中に不滅なる者、即ち永遠を見出そうとした。
たかが英語、されど英語。私には、英語を学ぶことと、いにしえの哲学者が求めたものが、どうも違うようには思えない。
以上。