25年くらい前、港北区(港北区役所)から「港北区の自然とわたくしたち」という本が出版されました。
その際、執筆者を募集しており、当時から環境問題や自然環境保全に関心を持っていた私は、それに応募することとしました。
私はそれ以来、港北区また横浜市の行政とも関わりながら、自然環境保全関連のボランティア活動を始めるようになったのです。
15年ほど前には港北グリーンプログラムという施策がありました。
その委員となる人材を募集していたため、それにも応募し参加しました。
初年度では港北区の自然をいかにして保全していくかの議論が月1回のペースで行われ、次年度は区内各地の現地で「港北 水と緑の学校」を行なうことになりました。
私は篠原池の自然観察及び砂田川の自然観察を担当しました。
このころ同時に、港北区庁舎の屋上緑化をすることも決定され、港北グリーンプログラムの一環として行なわれるとのことでした。
グリーンプログラムと同様、委員会のような形式で参加者を募り、どのような緑化にするか計画段階から議論が行われました。
私はこの時、屋上に小屋があることに着目、その屋根から雨どいを引いて、小さな池のビオトープを設置することを提案しました。
また、港北区の緑が減少しているのは、ただ緑が減少しているというだけでなく、自然の樹木や野草の種類が減少しているということ。
だから地域に昔から生育している植物を保護していくことも必要なのではないかと提案していました。
それは屋上緑化がグリーンプログラムの一環として位置づけられており、しかもグリーンプログラムの委員でもあったという立場からの提案でもありました。
グリーンプログラムの次年度の施策が終了し、屋上緑化も完成して間もなく、港北区の緑被率の現状の付いて発表する機会があり、その時の投影したものが今回の記事の内容です。

👆港北区では(もちろん横浜市全体がそうですが)年々緑(緑被率)が減少しています。

👆どうして緑の減少は問題となるのかをまとめました。

👆平成9年の港北区の緑被率は31.8%。公園と農地を合わせても4.71%。残りの27.09%は・・・?

👆港北区の緑のほとんどは民地によって確保されているのです。

👆こうした緑の推移と現状から導き出される課題は、このような内容と考えられました。
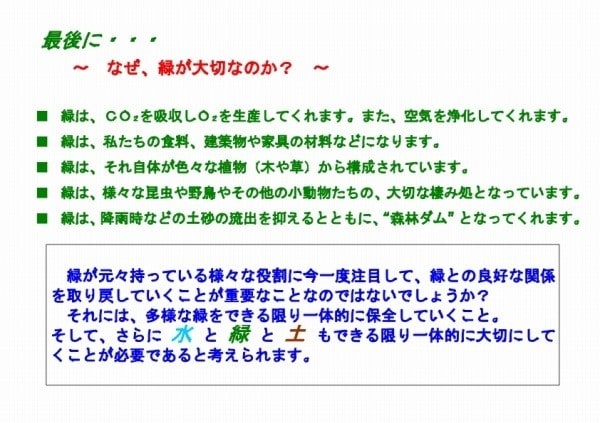
👆始めになぜ緑の減少が問題なのかをまとめたので、最後になぜ緑が大切なのかをまとめました。

👆緑つまり木々や草花たちの生物多様性の一例です。緑はこのようにいろいろな自然の木々や草花によって構成されています。
緑の減少とは、こうした野生植物が、その生育地・生育環境もろとも消失させられることを意味しているのです。
また、そこには昆虫や野鳥もいるものです。そうした生きものたちの生息場所も奪うこととなります。

👆よって、緑化に際しては園芸植物のみならず、元々その地に生育していた草花や木々の生育を回復させることも重要なのでは・・・?
ということで、屋上緑地でのビオトープを例に挙げました。
その後、8年くらい前でしょうか。
横浜市から委員として選ばれ、横浜市の自然環境保全を今後いかに進めていくかの議論に参加する機会がありました。
そこでも、ビオトープすなわち生物生息環境の保全が大きな課題となっていました。
あれから何年も経ちましたが、横浜市の自然環境保全施策は、いったいどうなってしまったのでしょう。
こうした議論というのは大事です。
真剣に考えなくてはいけない内容だと思います。
里山ガーデンの事例に見られる方法は、環境問題を改善しようと思慮深く行なわれているようには見えないのですが・・・。
その際、執筆者を募集しており、当時から環境問題や自然環境保全に関心を持っていた私は、それに応募することとしました。
私はそれ以来、港北区また横浜市の行政とも関わりながら、自然環境保全関連のボランティア活動を始めるようになったのです。
15年ほど前には港北グリーンプログラムという施策がありました。
その委員となる人材を募集していたため、それにも応募し参加しました。
初年度では港北区の自然をいかにして保全していくかの議論が月1回のペースで行われ、次年度は区内各地の現地で「港北 水と緑の学校」を行なうことになりました。
私は篠原池の自然観察及び砂田川の自然観察を担当しました。
このころ同時に、港北区庁舎の屋上緑化をすることも決定され、港北グリーンプログラムの一環として行なわれるとのことでした。
グリーンプログラムと同様、委員会のような形式で参加者を募り、どのような緑化にするか計画段階から議論が行われました。
私はこの時、屋上に小屋があることに着目、その屋根から雨どいを引いて、小さな池のビオトープを設置することを提案しました。
また、港北区の緑が減少しているのは、ただ緑が減少しているというだけでなく、自然の樹木や野草の種類が減少しているということ。
だから地域に昔から生育している植物を保護していくことも必要なのではないかと提案していました。
それは屋上緑化がグリーンプログラムの一環として位置づけられており、しかもグリーンプログラムの委員でもあったという立場からの提案でもありました。
グリーンプログラムの次年度の施策が終了し、屋上緑化も完成して間もなく、港北区の緑被率の現状の付いて発表する機会があり、その時の投影したものが今回の記事の内容です。

👆港北区では(もちろん横浜市全体がそうですが)年々緑(緑被率)が減少しています。

👆どうして緑の減少は問題となるのかをまとめました。

👆平成9年の港北区の緑被率は31.8%。公園と農地を合わせても4.71%。残りの27.09%は・・・?

👆港北区の緑のほとんどは民地によって確保されているのです。

👆こうした緑の推移と現状から導き出される課題は、このような内容と考えられました。
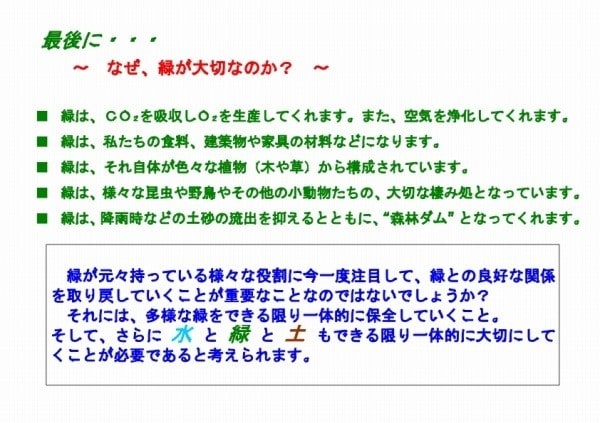
👆始めになぜ緑の減少が問題なのかをまとめたので、最後になぜ緑が大切なのかをまとめました。

👆緑つまり木々や草花たちの生物多様性の一例です。緑はこのようにいろいろな自然の木々や草花によって構成されています。
緑の減少とは、こうした野生植物が、その生育地・生育環境もろとも消失させられることを意味しているのです。
また、そこには昆虫や野鳥もいるものです。そうした生きものたちの生息場所も奪うこととなります。

👆よって、緑化に際しては園芸植物のみならず、元々その地に生育していた草花や木々の生育を回復させることも重要なのでは・・・?
ということで、屋上緑地でのビオトープを例に挙げました。
その後、8年くらい前でしょうか。
横浜市から委員として選ばれ、横浜市の自然環境保全を今後いかに進めていくかの議論に参加する機会がありました。
そこでも、ビオトープすなわち生物生息環境の保全が大きな課題となっていました。
あれから何年も経ちましたが、横浜市の自然環境保全施策は、いったいどうなってしまったのでしょう。
こうした議論というのは大事です。
真剣に考えなくてはいけない内容だと思います。
里山ガーデンの事例に見られる方法は、環境問題を改善しようと思慮深く行なわれているようには見えないのですが・・・。









