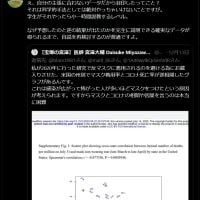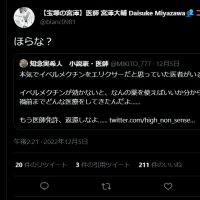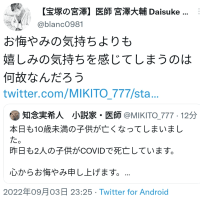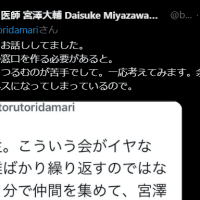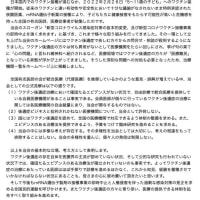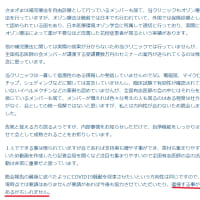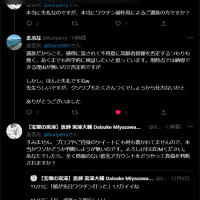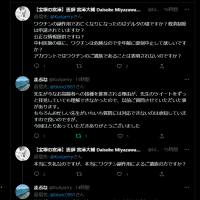2022年3月29日<ロシア侵攻、国際商品上昇に拍車>そのような状況下、ロシア・ウクライナ戦争の影響で、日本の輸入依存度が高い資源の価格が軒並み高騰、貿易収支の赤字が膨らんでいる。燃料、農林水畜産物、金属などは生活や産業に不可欠なものが多く、基軸通貨ドルで取引されるケースが多いため、ドルの上値を追いかけてでも買わざるを得ないつらい立場に追い込まれた輸入業者によるドルの買い切り注文が膨らんでいる。
<日米金利差拡大、トリガーに>ドル高・円安の背景は明快だ。
インフレの抑制に本腰を入れた米連邦準備理事会(FRB)が今月16日にゼロ金利政策を解除、今年だけでも0.25%刻みであと6回分もの追加利上げを示唆する一方、物価目標2%達成の見通しが立たない日本では、日銀が大規模緩和を継続。短期金利をマイナス0.1%に据え置くと同時に、満期10年の国債を無制限に買う「指し値オペ」を駆使して長期金利に0.25%の強力な天井制限を課す方針を崩さずにいる。短期と長期の両方で、日米金利差の拡大観測が強化され、ドル高・円安圧力が増している。

債券は、価格が上昇すればするほど利回りは低下し、逆に価格が下落すればするほど利回りは上昇します。表面利率2%、残存年限5年の場合(債券価格)(最終利回り)105円 0.952%104円 1.153%103円 1.359%100円 2.00%99円 2.222%96円 2.916%
為替の変動に関係するさまざまな要素金利差銀行預金や債券投資では、金利が高い方がより多くの収益を得ることができます。例えば、期間10年の国債が、日本とアメリカでそれぞれ年利2%で発行されていて、その後アメリカの国債の金利だけが3%に上昇したとすると、日本の投資家の中には持っている円を米ドルに替えて米国債を購入したくなる人が増えるはずです。この場合は、米ドルの需要が高まり、米ドル高・円安の中期的な要因になります。
「指値オペ」は、日銀が利回りを指定して(=指値)、国債を無制限に買い入れる措置です。通常の国債買い入れオペでは、買い入れ金額を例えば4250億円などと明示して実施しますが、指値オペは金額に制限をつけず買い入れるもので、特別かつ強力な措置と言えます。指値オペには、長期金利の上昇をブロックする効果が期待できるからです。国債と金利は「国債が売られると金利が上がり」、「国債が買われると金利が下がる」という関係にあります。国債を売買する債券市場では、アメリカが金融引き締めに転じて利上げに積極的な姿勢を打ち出した影響で、このところ日本の国債が売られる動きが強まり、長期金利が上昇傾向にあります。
一方で、日銀は長期金利の上昇を抑えたい立場です。今の金融緩和策の一環で、長期金利(=10年もの国債の利回り)を0%程度にするとしていて、具体的にはその変動幅を「±0.25%程度」にするとしています。ところが長期金利が上昇を続け、この変動幅の上限に近づいたため、指値オペを実施することを決めたのです。

2022/03/29(中略)しかし、日米の金利差が拡大すれば、当然、円安も進んでいく。黒田日銀は、円安が加速することを分かりながら、低金利を優先した格好だ。
経済評論家の斎藤満氏がこう言う。
「岸田政権と黒田日銀の間に亀裂が生じているということです。夏の参院選を控えた岸田政権は、絶対にインフレを抑えたい。そのためには、円安をストップさせる必要があります。輸入物価が高騰しますからね。なのに日銀の黒田総裁は、インフレを招くと承知しながら円安を容認している。いまだに『円安は経済にプラス』と公言しています。恐らく黒田総裁は、いまさら“低金利”と“円安”というアベノミクスをやめるわけにはいかないのでしょう。アベノミクスの失敗を認めることになりますからね」
本日は、山口市で憲法改正早期実現山口県総決起大会が開催され1100名の同志が結集しました。自民党の党是でもある憲法改正の実現に向けてこれからも全力で取り組んで参ります。 pic.twitter.com/ZtmaC8oc7f
— 安倍晋三 (@AbeShinzo) April 3, 2022
そして病気になって総理をやめ(2回目)、コロナのおかしな政策や、犠牲者多数のワクチン推進等の荒仕事はガースーや岸田さんにやらせ、現在、大切に温存されて、元気いっぱいだ。
改憲したら、また出てくるんだろうな、あべちゃん。
今度は総理大臣じゃなくて天皇だったりして?
また明治維新のときみたいに表天皇とウラ天皇の交替が起きて・・・?
まるで北朝鮮みたいな憲法だしね・・・。
しかし、このまま円安が進行したら、インフレも加速してしまう。すでに4月に値上げが予定されている物品は500品目を超えているという。黒田日銀の都合によって、さらに国民生活は圧迫される恐れがある。(省略)
あらゆる物が値上がりする中、収入は増えないのだから、即効性のある経済対策は消費税凍結しかない。
— なかつ (@tho9vY5gIpCmPbw) March 31, 2022
物価上昇するだけで苦しいのに消費税が重くのしかかるのは大変なのだ。10万円一回ポッキリ支給じゃどうにもならない。 pic.twitter.com/seka5xdTYN

Wikipedia「アベノミクス」より第1次安倍内閣における経済政策を指す言葉として命名されたが、第1次安倍内閣の政策はその後の第2次安倍内閣の政策とは基本的なスタンスが異なっており、財政支出を削減し公共投資を縮小させ、規制緩和によって成長力が高まることを狙った、小泉純一郎による「小泉構造改革」(聖域なき構造改革・いざなみ景気)路線の継承を意味するものであった。第2次安倍内閣では新たに、デフレーションを克服するためにインフレターゲットが設定され、これが達成されるまで日本銀行法改正も視野に入れた大胆な金融緩和措置を講ずるという金融政策[9][10]が発表された。「三本の矢」[編集]アベノミクス個別の政策としては、それぞれの矢として下記などが提示、あるいは指摘されている。
- 第一の矢:大胆な金融政策(デフレ対策としての量的金融緩和政策、リフレーション)
- 2%のインフレ目標[9][10][14]
- 無制限の量的緩和[10][14]
- 円高の是正[10][注 6]と、そのための円流動化
- 日本銀行法改正[10][15]
- 第二の矢:機動的な財政政策(公共事業投資、ケインズ政策)
- 大規模な公共投資(国土強靱化)[10]
- 日本銀行の買いオペレーションを通じた建設国債の買い入れ・長期保有[16]、ただし国債そのものは流動化
- 第三の矢:民間投資を喚起する成長戦略(イノベーション政策、供給サイドの経済学)
- 「健康長寿社会」から創造される成長産業[17]
- 全員参加の成長戦略[17]
- 世界に勝てる若者[17]
- 女性が輝く日本[17]
- NISA
2014年6月30日、安倍はフィナンシャル・タイムズ紙に「私の『第3の矢』は日本経済の悪魔を倒す」と題した論文を寄稿し、経済再建なしに財政健全化はあり得ないと述べ、日本経済の構造改革を断行する考えを表明している[18]。改革の例として、
- 法人税の引き下げ。2014年に2.4%引き下げ、数年で20%台に引き下げ。
- 規制の撤廃、エネルギー・農業・医療分野の外資への開放。
- 働く母親のために家事を担う外国人労働者の雇用。
を挙げた[18]。また、2014年4月の消費税増税については「影響は限定的である」と述べている
1デフレ脱却などと理由をつけて カネを刷り
2インフレに転じたと称して 消費税を増税し
3消費税増税から来るデフレ圧力にはさらにカネを刷り
こうやってお金の価値を落としながら増税を繰り返し、景気回復して税収も増えたでしょ? と情報操作するのがアベノミクスの基本戦略です。
(中略)今まで蓄えていた貯蓄をお金の価値を下げながら奪い取るのがアベノミクスです。
石破氏も指摘していたがアベノミクスは大企業と富裕層に富を集中させ、中間層と貧困層から激しく収奪する逆再分配の政治を行っている。このアベノミクスを象徴するのが大企業の役員報酬額だけ2倍増にしたことだ。 pic.twitter.com/PrSmZorIse
— 井上伸@雑誌KOKKO (@inoueshin0) September 14, 2018
はぁ?( ゚д゚)
— とんぬら先輩RX (@stere0lab) June 12, 2021
元害務大臣で赤坂自民亭メンバーのフミポン、オマエのホザくアベノミクスで実現した事って、日本政腐(株)による国民への効率的な資産収奪と、その収奪した資産を外資系経済(テロ)団体や海外投資家に回す搾取体制の確立じゃね?#新しい資本主義#新共産主義 https://t.co/H8RFNRkFi1
アベノミクスという人災。金融緩和により無理やり株価上昇させ、100兆円以上の資金を海外へ流出させた。アベノミクスは私達の金を収奪する#ヤバすぎる緊急事態条項#ケチって火炎瓶#子や孫を戦争に行かせない
— 九楽 華 🌼🌈☃️皆様お体大切にして下さい🤗 (@hhyr1426) September 4, 2018
<自民党総裁選>アベノミクス重いツケ 経済好循環生まれず https://t.co/aacfsiPLYq
恐らく黒田総裁は、いまさら“低金利”と“円安”というアベノミクスをやめるわけにはいかないのでしょう。アベノミクスの失敗を認めることになりますからね
2022/03/18
(省略)
日銀・黒田東彦総裁:「円安が経済・物価を共に押し上げ我が国経済にプラスに作用している基本的な構造は変わりはない」
黒田総裁は日本の企業が海外であげた収益を国内に送金する際に「円建ての金額は円安によって拡大しGDPもプラスになる」と述べ、円安を容認する考えを示しました。
発言を受けて円相場は一時およそ6年1カ月ぶりの水準となる1ドル=119円台まで円安が進みました。
金融政策については原油価格の高騰などで消費者物価が「4月以降2%程度の伸びとなる可能性がある」としながらも
引き締め策を取ると企業収益を悪化させ家計の負担を増やすとして「金融緩和を続ける」との考えを強調しました。
このほか物価の上昇と景気の停滞が同時に起こる「スタグフレーション」については「そういう恐れが日米欧にあるとは思っていない」と述べました。その理由として「資源価格の上昇は一時的なものでコロナ禍からの経済回復は明確だ」としました。
これはね、ロシアの制裁に見せかけた、ヨーロッパと日本の制裁なんですよ。
— 沙羅双樹 (@Maarmastansind3) April 1, 2022
だって、資源大国に喧嘩を売ったらどうなるか、ふつう考えたら分かるじゃないですか。
ヨーロッパ経済を崩壊させるシナリオに、日本が巻き込まれたわけです。
日本政府は米国の傀儡なので、筋書き通りですが。 https://t.co/FKTQNx1e4g
(省略)
私たちに突きつけられているのは、「二酸化炭素を出さずに経済や社会をどう成り立たせていくか」という命題です。(中略)価格の高騰が起きているのは、原油だけではありません。二酸化炭素の排出量が比較的少ない「LNG(液化天然ガス)」もまた、価格が跳ね上がっています。
(記事より)「ヨーロッパは、脱炭素の過程として、発電燃料を 石炭や石油よりも、温暖化ガスの排出が少ない天然ガスに切り替えているため、ロックダウン後の景気回復により、需要が供給をはるかに超える一連の"ボトルネック"が発生している。
国際レベルでのガスの価格が上昇したため、ヨーロッパは危機に瀕しているのだ。」
(中略)この中国の動きに、大きな影響を受けると見られているのが、日本です。火力発電の割合が高い日本は、これまでLNGの輸入量は世界1位でした。それが、ことし初めて中国に追い抜かれる見通しです。(中略)一方、私たちの生活に身近な対策も見えてきました。26位には「電気自動車の普及」、31位には「住宅などの断熱化」があげられています。注目すべきは、上位にランクインした「食生活に関わる対策」です。第3位は「食料廃棄の削減」。消費されない無駄な食料の生産などで世界が排出する温室効果ガスは、地球全体の年間排出量の8%に上ります。そして第4位は、「植物性食品を中心にした食生活」。つまり、あまり肉を食べないようにするという対策。実は牛や豚など家畜の飼育では、二酸化炭素だけでなく、その20倍以上も温室効果が高いメタンガスが大量に排出されています。世界全体で食肉の量を減らせば、今後30年間で二酸化炭素661億トン分もの削減につながると試算されたのです。(中略)脱炭素社会の実現に向けて、何をリセットしていくべきか、市民が月に1回ほど集まって議論を重ねてきました。(中略)9か月にわたる議論の末、まとめられたのが、149ものリセット案が盛り込まれた提言書です。実は、そこから実現したひとつが、近距離の航空路線の廃止。夜行列車を復活させる、あの取り組みにつながっていたのです。そのほかにも、排気ガスの多い車が市の中心部に入るのを禁止する提言など、社会全体で取り組むべきさまざまなリセット案が示され、国によって検討されたのです。(中略)国、企業、そして市民が挑む、脱炭素社会への「グレート・リセット」。地球温暖化を巡って、科学は次々と厳しい未来予測を突きつけています。私たちはリセットを成し遂げ、この美しい地球を未来に引き継ぐことができるのか。残された時間は、もう長くはありません。

2022年4月1日内田氏はこれまで理事として企画局・金融市場局・決済機構局を担当し、金融政策の企画、金融市場調節、中央銀行デジタル通貨(CBDC)の研究開発まで一手に担ってきた。(中略)黒田総裁の任期が2023年4月で終わるため、担当替えなどがなければ、内田氏は黒田氏の後任総裁の下でも金融政策の企画立案を担うことになる。今回、内田氏が黒田総裁をトップとする政策委の厚い信頼を得て再任されたことがうかがえる。
今ある電子マネーとは違う。「それ自体が法定通貨」れっきとした人民元だ。中国の中央銀行が発行するデジタルマネーだ。こういう中央銀行が発行するデジタル化された通貨のことを「CBDC」というそうだ。日本はこういうの検討してないの?日銀HPより「日本銀行では、現時点でCBDCを発行する計画はないが、決済システム全体の安定性と効率性を確保する観点から、今後の様々な環境変化に的確に対応できるよう、しっかり準備しておくことが重要であると考えている。」技術はすでにあるのにやらないんだ?ふーん。
2022年3月25日日銀は25日、4月から中央銀行デジタル通貨(CBDC)の実証実験フェーズ2を始めると発表した。CBDCの周辺機能について、実現可能性や課題を検証する。日銀は昨年4月にフェーズ1を開始し、CBDCの基本機能を検証してきた。フェーズ1は予定通り3月で終了する。
「国債が発行されるとき、
民間の資金が政府に吸収され、金利が急上昇することを
防ぐために、日銀は
民間保有の国債を買い取っている。その際には、通貨が新たに発行される。」それが我々の資産となっている。財政健全化はこれを回収、、、つまり、私有財産の没収につながりそうだ。(中略)これ、私有財産の没収って、あいつらのグレートリセットではないか!
2022年3月22日日本銀行の黒田東彦総裁は22日、現在の消費者物価の上昇は国際商品市況高によるコストプッシュ型であり、企業収益や家計の実質所得の減少を通じ「長期的にはむしろ景気を押し下げる方向に働く」と語った。参院予算委員会で白真勲氏(立憲民主)の質問に答えた。今年の春季労使交渉では、製造業を中心にかなり高いベースアップ(ベア、基本給の底上げ)が認められつつあるとし、「名目賃金は数年ぶりにかなり上昇する可能性がある」とした。ただ、エネルギーや食料品を中心とした消費者物価の上昇によって「実質賃金は下押しされる可能性がある」との見方を示した。
2022年4月5日日銀の内田真一理事は5日の衆院財務金融委員会で以下のように述べた。* 内田日銀理事:コストプッシュ型物価上昇で、物価が継続的に上昇するとは考えない* 内田日銀理事:為替は内外金利差の影響受けるが、投資家のリスク感覚や資源輸入のドル買いも影響* 内田日銀理事:コストプッシュ型物価上昇、日本経済を下押しする可能性
生産コストの上昇により起こるインフレのこと。具体的には、原材料や資源価格の上昇による資源インフレ、賃金の高騰による賃金インフレなどがある。いわゆる供給サイドの要因によるインフレであり、輸入物価の上昇などその原因が自国に収まらない場合は、対策が比較的難しいとされる。それに対して、好景気によりモノがよく売れることで需要が供給を超え、モノの値段が上がる需要サイドの要因によって生じるインフレはディマンドプルインフレと呼ばれる。