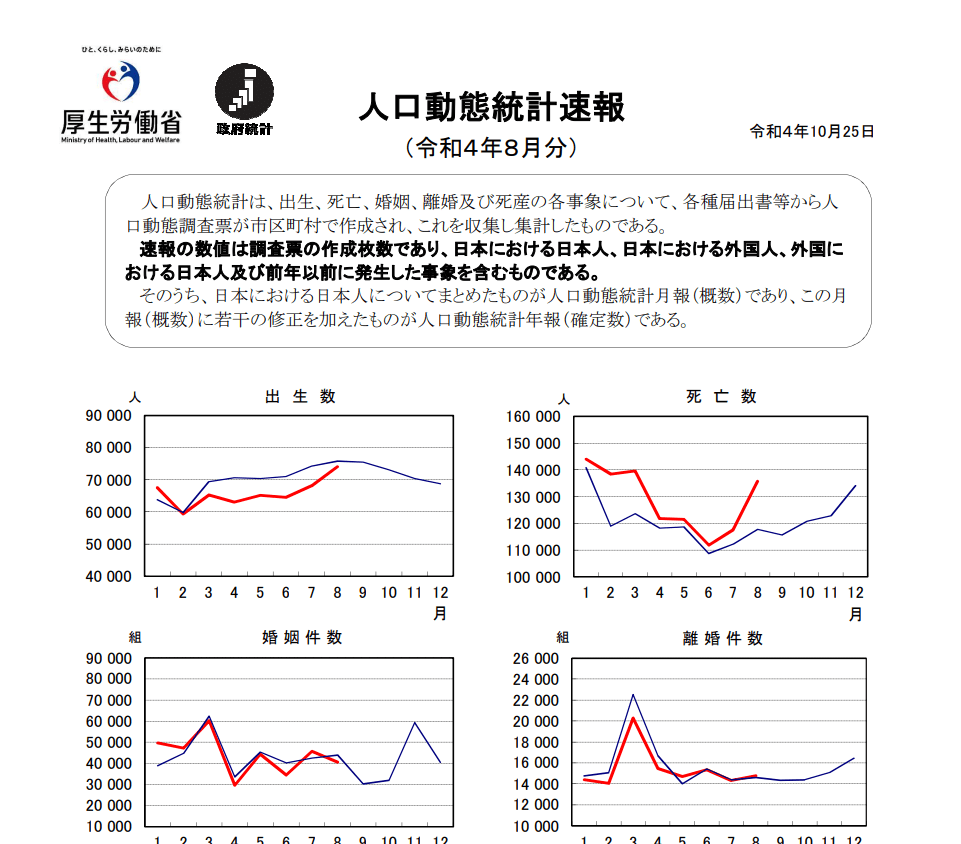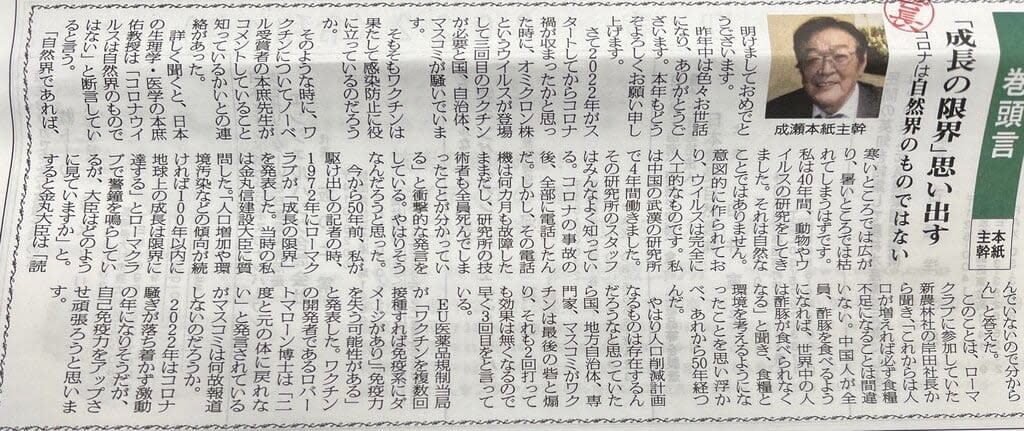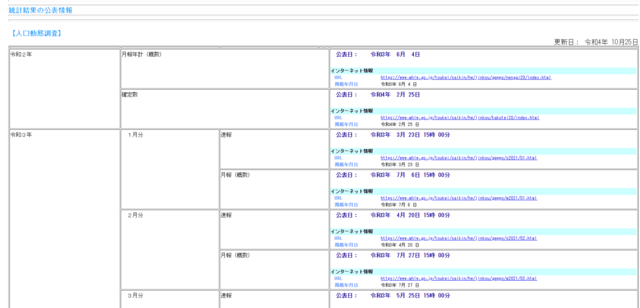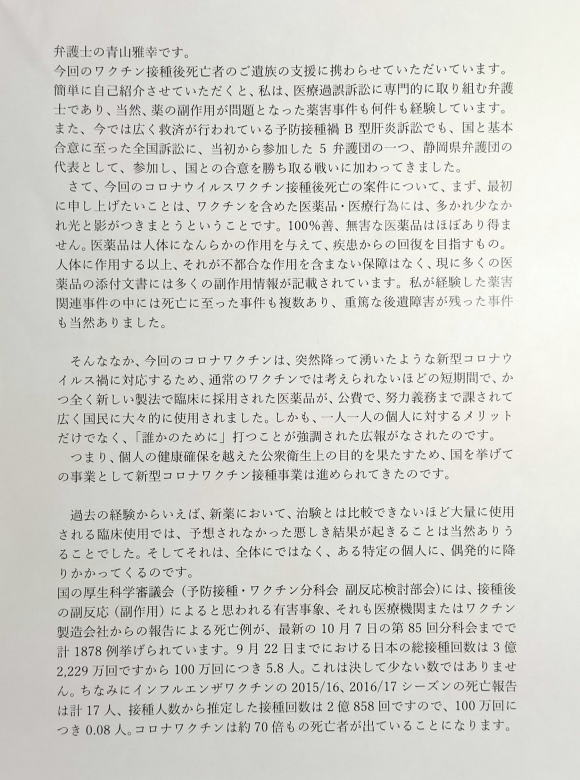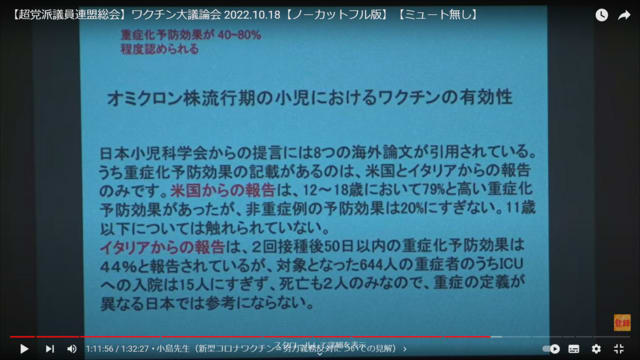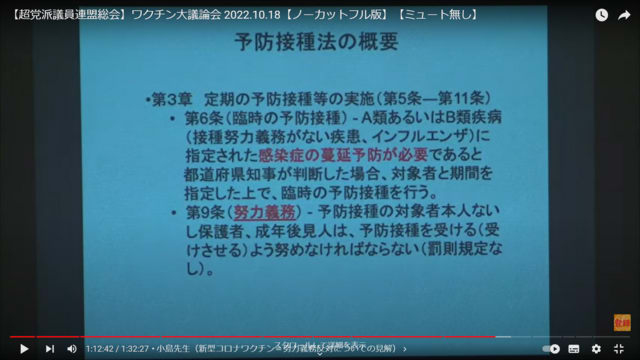2022/10/27 17:00(最終更新 10/27 20:58) 1511文字文部科学省は27日、全国の学校を対象に2021年度実施した「問題行動・不登校調査」の結果を公表した。
病気や経済的理由などとは異なる要因で30日以上登校せず「不登校」と判断された小中学生は24万4940人、小中高と特別支援学校のいじめの認知件数は61万5351件で、ともに過去最多だった。
文科省は、新型コロナウイルス禍による行動制限などで、人間関係や生活環境が変化したことが影響したとみており、「心のケアを中心とした早期の対策が必要だ」としている。文科省は毎年、国公私立全ての小中学校・高校と特別支援学校におけるいじめの認知件数を調べ、小中高については、暴力行為件数▽年間30日以上の長期欠席者や不登校の人数▽自殺者数――を集計している。不登校と判断された小中の児童生徒数は9年連続で増えた。
今回の増え幅は特に顕著で、過去最多だった前年度から24・9%増加した。
一方、高校の不登校は18・4%増の5万985人だが、過去10年でみるとほぼ横ばいで推移している。
小中の不登校の主な要因で最多なのが「無気力、不安」(49・7%)で、「生活リズムの乱れ、遊び、非行」(11・7%)、「いじめを除く友人関係をめぐる問題」(9・7%)が続いた。小中学校で1000人当たりの不登校の児童生徒数は平均25・7人となり、都道府県でばらつきもあった。
最も多かったのは高知の31・2人で、宮城の30・3人、島根の29・9人が続いた。一方、最も少ないのは福井の17・8人で、文科省の担当者は「早期対応に力を入れているかどうかなど自治体ごとの対策が反映されている可能性がある」と分析する。
福岡県 公立小中学校96%”いじめ”認知
1日前公開
クラス29人中26人が加担した「集団いじめ」 西宮市教育委が最終報告書 両親は「なぜ気付いてあげられなかったのか…」
7か月前公開
香川県で暴力行為・いじめの認知の件数など増加 小学校での暴力は過去最多に
2日前公開
小学校担任50代男教諭「スルーしよう」児童に相次ぎ“いじめ行為”滋賀・野洲市教委が謝罪|TBS NEWS DIG
4週間前公開
【集団いじめ隠ぺいか】『SNSで拡散とか対外的に開示しないように』集団いじめ報告書渡す際に市教委が発言...「最悪の対応」の数々を被害児童の両親が証言(2022年6月1日)
4か月前公開
「学校の対応は、最初から最後まですべて口頭です。紙ベースのものはいっさい作らず、残してもらえず、保護者らへの周知もしてもらえなかった。今思えば隠蔽したいから、学校から発信されなかったんだろうと思う」学校側は1か月たってもアンケート調査や学年集会などはなし。不信感を抱いて、両親は市教委のいじめ相談ダイヤルに電話をかけた。「絶対に学校には電話したことは言わないでほしい」と約束していただいて、私と息子の名前を伝えた。市教委が学校の対応を把握しているかを確認したかっただけで、問い合わせたことは学校には知らせないよう約束した。しかし、電話した方とは違う方が電話をかけてこられて、意気揚々とした感じで「学校にもちゃんと連絡を入れて、どんないじめだったか把握できました」と報告された。「こちらのミスです。あせってしまって、きちっと保護者の意向を確認せずに学校に電話してしまった」学校に漏れたことで影響は?「学校が情報をとにかく伏せるようになった。2回目の聞き取りの時は、こちらから聞かないと、聞き取りしたことすらも伏せていた。こっちのことを信用してもらえてないなと感じた」すぐに市教委に抗議したが、市教委からは「引継ぎミスだった」との説明。こどもは不眠や幻聴をうったえ、学校には通えなくなった。昨年12月、校長や担任らで構成された「いじめ調査委員会」が中間報告を提出。報告をもってきた際の録音されたやりとり市教委の担当者:お渡しするにあたって、お約束していただきたいことがいくつかありまして、内容を他人に見せたり、SNSで拡散したり、対外的に開示しないようにお願いしたい。損害賠償請求等の資料としても使わないよう、そういう目的のために調査をしているんではないということをご理解いただきたい。中間報告の段階で、「裁判では使うな」ともとれる発言。今年3月14日、最終報告書を提出。集団で執拗かつ継続的に行われた極めて重大ないじめ行為と認定された。その一方で異変に気付くことはできなかったと記されている。「日記や作文なども定期的に実施していましたが、本事案についての内容が書かれたことはなく、いずれも早期発見にはつながりませんでした。」4日後の3月18日、校長と担任が自宅を訪問。「じつは学校で、日記帳と作文帳を保管していたんです」「SOSをじつは書いていたんです」と言って担任が泣きながら・・・日記帳を担任が預かっていて、存在を忘れていた。報告書では日記になにも書いてなかったと言いきっていた。本当は日記と作文帳を隠蔽して、書いたことすらなかったことにしようと思ったのか。弁護士:中間報告書を手渡す際に「訴訟に使わなければ渡す」などと、そんな条件を勝手につけることはできない。日記の存在など、あとからわかったと主張していることは、調査漏れならまだいいんですが、ふつうそんなところを見ないというのはありえない。事実の隠蔽ととられてもしかたない。保護者から要求があれば第三者委員会を設置しなければならないが、それをしないならとんでもない法律違反になる。
市教委:中間報告を手渡す際に約束を迫ったという認識はない。仮に約束できませんとおっしゃられてもお渡ししようということで臨んでいたので。
日記帳が最終報告後にでてきたことは、見直したら出てきたということです。担任はそこにコメントを返していないということで、残念ながら読めていなかったようです。わかっていたが隠していたということではございません。知らなかった事実が後から出てきて大変申し訳ないという気持ちでいっぱいです。今回は学校主体の調査であったが、今後も第三者による調査は行わないとしている。
旭川いじめ 最終報告も再調査へ
1か月前公開
名古屋市いじめ問題 遺族が激怒 一言で救えたかもしれない命
1年前公開
内容:第三者委員会はいじめがあったと認められず、自殺は部活の疲れが原因であったと結論。議事録も見せない教育委員会に不信感を抱き、父親は外部の有識者による再調査を強く要望。自殺から2年後、再調査が始まる。再調査委員会担当者:いじめの認定でございますが、部活動の練習において、無視されたことをいじめと認定しております。こどもへの聴取は最初の聴取がとても重要。
しかし教育委員会は生徒らの聴取について、録音もせず、簡易なヒアリングしか行っていなかった。いじめにあっていたと認定。さらに当時の教育委員会や学校の調査はずさんで、遺族に寄り添う姿勢が著しく欠如していたと厳しく批判。報道陣に言われて、教育委員会は初めて謝罪。父親:娘は学校や教育委員会に殺されたというふうに感じています。いじめ対策で学校がおこなっていた生活ノートに異変が見られるのに、先生は対応しなかった。いじめを発見するアンケートツールがあって、危険領域にあったのに、なにも対応してくれなかった。市長と教育長が謝罪に訪れる。教育長:加害者とおっしゃっていただくのをぜひ勘弁していただきたい。お父さん激怒。当時市教委の職員だった男性:あの日のことは、今も鮮明に覚えている。事案が1月5日で、6日に登庁したら報告があったのが「こどもの自殺がありました。あれは家庭の問題だ」と言っていました。結論ありきだった。この案件の担当者ではなかったが、市教委の体質について、慣習のようになっている。こどもの自殺が起こるたびに、だいたい家庭の問題になる。
10代のこどもの悩みを家庭で発見するのは困難だと専門家はいう。「本人からはなかなか言わないだろうと思います。それは隠しているのではなく、成長の過程として、自分で解決したいとか、周りを気遣う気持ちが育っていくため。自分で頑張ろうとしている人に対して『大丈夫?』と聞けば『大丈夫』と返してしまう。
当時市教委の職員だった男性:カウンセラーやソーシャルワーカーを雇おうが、そこの部分が変わらないとこどもの問題はなくせない。名古屋市は再発防止のチームを立ち上げた。しかし立派な施策よりも、一声かけてくれたら救えたかもしれない命。
【NNNドキュメント】不登校の子どもたち 母が作った新たな”居場所”とは NNNセレクション
2022/06/24公開
内容:14歳のくれはさんは、小学4年生からほとんど登校していない。
母親は、我が子のために「みんなでつくる自由な学校」をコンセプトに、新たな居場所づくりに取り組んでいる。
小中学校の不登校は、全国で19万人を超え過去最多に。学校や教室に居場所を見い出せない子どもたちの声に耳を傾け、考えた。とくに原因があるわけではないけれど学校に行きたくない。学校に行かなければと、泣いても引きずってでも行かせようとしたときもあったけど、こどもとの信頼関係が崩れると思ってやめた。大丈夫よと言ってくれる先輩ママさんたちがいっぱいいて救われた。母親の手伝いや地域の人の交流でいろんなことを学んでいる。新しい双子の新入生が来た。幼稚園から登園拒否で、いろんな学校を見させたんだけど、この学校がいいと言った。自治体もフリースクールなど、生徒それぞれに合わせた学び方を目指している。広島の教育長:教室であってもどこであっても、最終的にその子が自信を持って、いろいろなコミュニティに出入りしながら愉快な人生を歩んでいく。これが究極の目的なので、多様な環境を用意していくことが大切かなと思っている。くれはさんは今、ミュージカルに夢中になっている。学校ってなんだろう?
いじめ、不登校共に過去最多。
— ゲーニャ (@AiKaye1) October 27, 2022
「行事制限・黙食が続き人間関係を築くのが難しくなってる」と文科省。
分かってるなら何故このまま放置する?フリースクールの子供達の表情が明るいのは救い。でも国の援助は無い。 pic.twitter.com/ExclHEuQQ4
子どもたちの急増に対応するため、このスクールは2度にわたって移転を繰り返しました。
保護者からの利用料だけでは人件費や移転にともなう経費などを賄うことはできませんが、フリースクールの運営自体を補助する国の制度はないため、クラウドファンディングで資金を募るなどしてやりくりしています。不登校対応【1】オンライン授業不登校の小中学生への支援が追いつかない中、オンライン授業を活用することで、不登校から学校に通う生徒が増えたという地域もあります。(中略)市内にある甲田中学校では不登校の家庭向けの配信のほか、学校に通い始めた生徒向けの別室を設け、現在は10人ほどがここでオンライン授業を受けています。
ここに通う女子生徒は別室でオンライン授業を受けながら、少しずつ教室にも行けるようになったということです。
(女子生徒)
「教室では悪口を言われているようなイメージがあって入ることのハードルが高くなっていた。別室があることで周りの目を気にしなくてよくなり、学校に行くことへのハードルも下がった」不登校対応【2】メタバース登校メタバース=仮想空間での学習支援を活用する取り組みを始めている地域もあります。埼玉県戸田市が活用するのは東京の認定NPO法人が1年前に始めたサービスで、「メタバース登校」とも呼ばれています。子どもたちは自分の分身、アバターを使ってメタバースの世界を自由に移動でき、特定の教室に入ることで、他の子どもや講師と学習できます。2年前から不登校で、サービスを利用している小学5年生は「オンラインなので気軽におしゃべりできる。実際に友達と会って、鬼ごっことかオンラインではできないこともしてみたい」と話し、現実の世界での交流にも興味を持ち始めている様子でした。(中略)今回の文部科学省の調査では、不登校の小中学生24万人余りのうち、3分の1以上にあたる8万8000人余りが学校やフリースクールなどの支援を受けていないということが分かっています。文部科学省の担当者は、不登校の増加に相談や指導の受け入れ先の対応が追いついていないと見て、体制の拡充を検討しています。