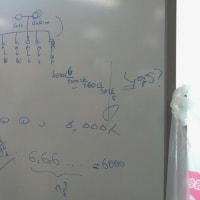1986年のチャレンジャー号の事故http://www.youtube.com/watch?v=7O87x_V6KVsは工学部の技術倫理の授業で取り上げられることの多い実例だそうである。チャレンジャーでググっていたら東京大学大学院工学系研究科原子力専攻教授 班目春樹(まだらめはるき) という人のサイトに行き着いた。
http://www.nuclear.jp/~madarame/lec1/challenger.html
打ち上げ時の気温が低いとブースターのOリングのシール効果が低下するという技術者からのデータと打ち上げ中止の警告を無視し、データについて自らの分析結果を述べ、データは打ち上げを中止するほどの決定的なものではないと主張したNASAの幹部がおったそうな。事故調査委員会の記者会見がTV中継された場で、ファインマン氏はコップに入った氷水の中に件のOリングを入れ、取り出したOリングを押しつぶし弾力性がなくなっているのを示した。それは小学生でも理解できるとてもシンプルな卓上実験だったのだが、ビューロクラートは事実を無視することを仕事にしているらしい。いや、脳内の事実に忠実というべきか。もともと、存在しない誇りを守るため、小学生が理解できるシンプルな事実を理解できなくなるのだ。大組織内で、書類の間違いだったら別に人は死なない。でもさ、ロケットなんですけど。
昼休みにipodのpodcastでNOVAを聴いていたら、2003年のコロンビア号の事故の話をしていた。事故の原因は打ち上げ時に、外部燃料タンクから剥がれ落ちた断熱材の破片が衝突したことで開いた穴に大気圏再突入時、高温の空気が流れ込んだことで、左翼から破壊が始まり空中分解した。聴いているうちに流星のように機体がいくつかの光の筋になって流れていったTV画面を思い出した。ラジオでは事故を予見していたNASAの技術者たちの中の一人がインタビューに答えていた。断熱材の破片が左翼に衝突したことは、打ち上げ翌日に映像をチェックした際に確認していて、重篤な結果につながると考えた彼は軍の映像データをリクエストするべきと上司にメールを送るが反応は返ってこなかった。さらなる上層部にメールを作成するも、指揮命令系統(chain of command)から外れる行動ができず、そのメールは送信されることがなかったというのが要約である。 http://www.pbs.org/wgbh/nova/columbia/ THE INSIDER WHO KNEW
NASA engineer Rodney Rocha, whose warnings and calls for action went unheeded, speaks out about the disaster.
人は間違う生き物なのである。そこのところを認めて、頭を使って対策を立てる。物をちゃんとありのまま見て分析する。想定されるあらゆる可能性を否定しない。そういう頭の使い方は科学者でなくとも、できるはずと信じたい。
JSTの失敗知識データベース 失敗百選というサイトに双方の事故の詳しい解説が載っていた。他にもいろいろ失敗があって、とんでもなく初歩的な失敗だったが、からくも乗組員の命に別状はなかったアポロ13号とか中々ためになるサイトである。
http://shippai.jst.go.jp/fkd/Detail?fn=2&id=CA0000639 チャレンジャー号
http://shippai.jst.go.jp/fkd/Detail?fn=0&id=CB0011019 コロンビア号
しばらく、このサイトで遊べそう。すごいぞJST!
http://www.nuclear.jp/~madarame/lec1/challenger.html
打ち上げ時の気温が低いとブースターのOリングのシール効果が低下するという技術者からのデータと打ち上げ中止の警告を無視し、データについて自らの分析結果を述べ、データは打ち上げを中止するほどの決定的なものではないと主張したNASAの幹部がおったそうな。事故調査委員会の記者会見がTV中継された場で、ファインマン氏はコップに入った氷水の中に件のOリングを入れ、取り出したOリングを押しつぶし弾力性がなくなっているのを示した。それは小学生でも理解できるとてもシンプルな卓上実験だったのだが、ビューロクラートは事実を無視することを仕事にしているらしい。いや、脳内の事実に忠実というべきか。もともと、存在しない誇りを守るため、小学生が理解できるシンプルな事実を理解できなくなるのだ。大組織内で、書類の間違いだったら別に人は死なない。でもさ、ロケットなんですけど。
昼休みにipodのpodcastでNOVAを聴いていたら、2003年のコロンビア号の事故の話をしていた。事故の原因は打ち上げ時に、外部燃料タンクから剥がれ落ちた断熱材の破片が衝突したことで開いた穴に大気圏再突入時、高温の空気が流れ込んだことで、左翼から破壊が始まり空中分解した。聴いているうちに流星のように機体がいくつかの光の筋になって流れていったTV画面を思い出した。ラジオでは事故を予見していたNASAの技術者たちの中の一人がインタビューに答えていた。断熱材の破片が左翼に衝突したことは、打ち上げ翌日に映像をチェックした際に確認していて、重篤な結果につながると考えた彼は軍の映像データをリクエストするべきと上司にメールを送るが反応は返ってこなかった。さらなる上層部にメールを作成するも、指揮命令系統(chain of command)から外れる行動ができず、そのメールは送信されることがなかったというのが要約である。 http://www.pbs.org/wgbh/nova/columbia/ THE INSIDER WHO KNEW
NASA engineer Rodney Rocha, whose warnings and calls for action went unheeded, speaks out about the disaster.
人は間違う生き物なのである。そこのところを認めて、頭を使って対策を立てる。物をちゃんとありのまま見て分析する。想定されるあらゆる可能性を否定しない。そういう頭の使い方は科学者でなくとも、できるはずと信じたい。
JSTの失敗知識データベース 失敗百選というサイトに双方の事故の詳しい解説が載っていた。他にもいろいろ失敗があって、とんでもなく初歩的な失敗だったが、からくも乗組員の命に別状はなかったアポロ13号とか中々ためになるサイトである。
http://shippai.jst.go.jp/fkd/Detail?fn=2&id=CA0000639 チャレンジャー号
http://shippai.jst.go.jp/fkd/Detail?fn=0&id=CB0011019 コロンビア号
しばらく、このサイトで遊べそう。すごいぞJST!