仕事が終わったのが午後10時・・・
帰ってからいろいろ作るのが面倒。
ということで夕食は冷凍の枝豆。

そして生協の宅配で届いていたローストビーフ。

昨日の反省で、今夜はこの二品だけ。
仕事が終わったのが午後10時・・・
帰ってからいろいろ作るのが面倒。
ということで夕食は冷凍の枝豆。

そして生協の宅配で届いていたローストビーフ。

昨日の反省で、今夜はこの二品だけ。
二年ぶりの文楽の口上。
二年前は二代吉田玉男襲名、今回は六代豊竹呂太夫襲名。
開演は午前11時だけれども、10時半に劇場に到着するように出発。
今日もいい天気。
平城宮跡の朱雀門。

劇場前の桜はもう葉桜。



ちらし

ちらしの画像は松王丸。
かしらは「文七」。この百日鬘、頭に飾られた力紙(熨斗紙)は美化された力の象徴。
そして衣装は雪持ち松に鷹の刺繍、黒天鵞絨(ビロード)の長羽織。
ちなみにプログラムの表紙がこの衣装。「黒天鵞絨雪持松鷹繍平袖大寸着付」。


今回の芝居絵。

あ、もう八月の公演が決まったんだ。
第三部はいかにも納涼公演らしいですね。「夏祭浪花鑑」。

ポスターはできていたものの、ちらしはまだこんな感じ。

襲名のご祝儀を貼り付けた展示。

今日早めに来たのはこの本公演に先立って披露される三番叟を観る為です。
二人遣いのようですね。
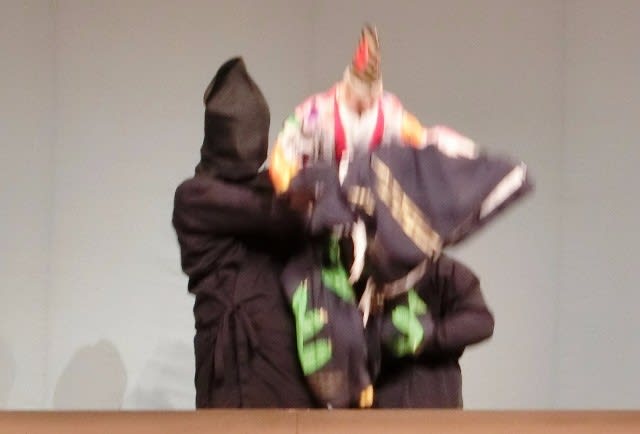
劇場内。

そうそう、第二部の曾根崎心中の道行きの義太夫が書かれた額。

今回の目玉は、一つは襲名の口上。
歌舞伎の襲名口上に比べるとつつましいものですが。
今回司会を兼ねて咲大夫さんが挨拶。
そして三味線からは鶴澤清治さん。
真面目だと思っていると、先代の呂太夫さん「は」美男子だった。を強調して笑いを誘っていました。
人形遣いからは桐竹勘十郎さん。まじめな挨拶でした。
あとは、襲名披露興行の「菅原伝授手習鑑」。
最近涙腺緩みっぱなしのやじは、桜丸切腹の段、寺子屋の段を涙流さずに観ることができません。
芝居が終わって、何処にも寄らず帰ることにします。
今日は近鉄日本橋から奈良行きの電車に乗車です。
向こうに明るく見えているのが駅。本当にすぐそばの駅です。

電車の窓からの生駒山の大阪側。


右下に見えているのが阪神高速東大阪線。
二股にわかれた間からは大阪市営地下鉄の中央線が昇ってきます。

遠くにあべのハルカス。

大和西大寺駅を過ぎてから若草山。

次にある文楽公演は「文楽若手会」。
今回の第一部とほぼ同じ演目。
「菅原伝授手習鑑」で「車曳の段」が入ってますが。

文楽鑑賞教室の新しいちらしができていました。
配役も決まったようです。


「菅原伝授手習鑑」の文楽のDVDボックスを持っていますが、
「桜丸切腹の段」はvol.3に、「寺子屋の段」はvol.4に収録されています。
いずれも平成元年に国立文楽劇場での通し上演の録画映像です。


今回の公演、平成元年の公演での配役を見てみます。
多くの文楽関係者がお亡くなりになっていますね。
| 今回平成27年 | DVD平成元年 | ||
| 桜丸切腹の段 | 親白太夫 | 吉田玉也 | 吉田玉男(初代・故) |
| 女房八重 | 吉田蓑二郎 | 桐竹一暢(故) | |
| 女房千代 | 桐竹勘十郎 | 吉田文昇(故) | |
| 女房春 | 吉田一輔 | 桐竹紋壽(故) | |
| 松王丸 | 吉田玉男(二代) | 吉田文吾(故) | |
| 梅王丸 | 吉田幸助 | 吉田玉幸(故) | |
| 桜丸 | 吉田蓑助 | 吉田蓑助 | |
| 義太夫 | 竹本文字久太夫 | 竹本越路太夫(故) | |
| 三味線 | 鶴澤藤蔵 | 鶴澤清治 | |
| 寺子屋の段 | 女房戸波 | 桐竹勘壽 | 吉田蓑助 |
| 女房千代 | 吉田蓑助 | 吉田文昇(故) | |
| 竹部源蔵 | 吉田和生 | 吉田文雀(故) | |
| 松王丸 | 吉田玉男(二代) | 吉田文吾(故) | |
| 義太夫前 | 竹本呂太夫(六代) | 竹本織大夫(故) | |
| 義太夫切 | 竹本咲大夫 | ||
| 三味線前 | 鶴澤清介 | 鶴澤燕三(五代・故) | |
| 三味線切 | 鶴澤燕三(六代) |
今夜の夕食何しよう?
いろいろ考えつつスーパーへ。
途中にコデマリが咲いていました。


線路際の土筆、穂がすっかり開いています。

八重桜が満開!


薊の蕾。

佐保川、水がきれいです。桜の花びらが少し流れてきます。
ソメイヨシノはもう完全に終わり。


白い花水木。


菜の花も盛りを過ぎた感じですね。

いつもの橋の上から。
もう咲いているのは八重桜と菜の花くらい。

芝辻四丁目緑地の八重桜が満開。





雪柳もほぼ散っています。

買い物を終えて部屋に戻ると、多肉植物の朧月に蕾。もうすぐ咲きそうです。

美しい夕焼け。そして飛行機雲。


スーパーで半額になっていた、朝堀り国産筍の水煮が半額になっているのを買って、今年二度目の筍ご飯。
今日は忘れずに写真を撮りました。

おかずはベイクドポテト。

炭水化物摂りすぎ・・・

東洋陶磁美術館を出て元来た道を北浜駅まで。
そこから堺筋線で日本橋駅まで。
歩いて5分ほどで国立文楽劇場です。
地下鉄の構内や通路に文楽の紹介の掲示。

紙屋治兵衛が遊女紀国屋小春とが深夜に茶屋大和屋を抜け出し、網島の大長寺で心中するわけですが、その道行の場面です。
頃は十月十五夜の 月にも見えぬ身の上は 心の闇のしるしかや
今置く霜は明日消ゆる はかなき譬えのそれよりも 先へ消えゆく閨の内
いとしかはいと締めて寝し 移り香も なんとながれの蜆川
このあと「名残の端尽し」でいろいろな橋を渡り、網島の大長寺までたどり着きます。
ちなみにこの大長寺の跡地には現在藤田美術館が建っています。

「双蝶々曲輪日記」の大宝寺町米屋の段。
「双蝶々~」といえば、歌舞伎では角力場、引窓が有名ですが、
文楽では時々通しが出ますね。(といっても不完全ですが)

これは「義経千本桜」の「道行初音旅」の静御前ですね。
四月公演の宣伝ポスター。


文楽鑑賞教室の宣伝ポスター。

左の階段を歩いて50mほどで国立文楽劇場です。

駅を上がって逆に少し歩くと、谷崎潤一郎の「蓼喰ふ蟲」の一部がきざまれた石碑。


とある店にもポスター。これは東京の国立劇場での公演ですね。

劇場前には「豊竹呂太夫」の幟が並んでいます。
そう、英太夫が六代目豊竹呂太夫を襲名し、第一部はその襲名披露公演なのです。
劇場前の桜、まだ残っていますね。

劇場前の柱にも演目のポスター。

上の写真でも見えていますが、劇場に足を進めると芝居絵。

1階の展示室では企画展示「豊竹呂太夫-代々の魅力-」展。


1階の売店でプログラムを購入し、2階へ上がる途中に吊看板。


二階には豊竹呂太夫襲名披露のご祝儀の展示。
写真のシャッターを切ろうとしたら突然横からスマホがにゅっと。
傍若無人。

そしていつものスタンプ。

今日の演目は
祖父は山へ柴刈りに 祖母は川へ洗濯に 「楠昔話」
「曾根崎心中」
女の人形には足が無いのですが、
「楠昔話」の祖母小仙、そして「曾根崎心中」の天満屋お初も、途中で足が出てきます。
小仙の方は「碪拍子の段」で洗濯をするために洗濯物を踏んでいるところで、
お初の方は「天満屋の段」で床下に隠れている徳兵衛が自分と一緒に心中する気があるかどうかを確かめるところで。
芝居が終わったのが午後8時半頃。


なんばWALKを通って近鉄大阪難波駅までブラブラ歩いてゆきます。

大阪に通っていたとき、帰りにここでよく皿うどん食べたな~。

ここでも服買った。
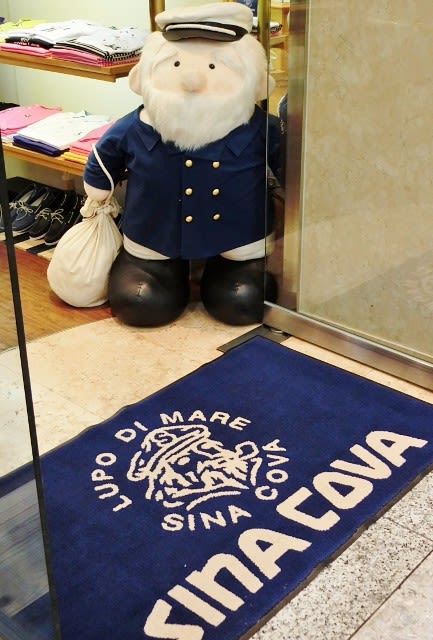
くじらパーク

近鉄大阪難波駅に到着。

ここにも文楽の大きなポスター。高さ2mはありますよ。

なぜかやってきた電車は行き先表示は「回送」なのですが、アナウンスでこれに乗れということ。

次回の文楽公演は6月。「文楽入門」。
例年は学生たちの貸し切りで、席があれば予約できるということでしたが、
「社会人のための文楽入門」「BUNRAKU for beginners」としてそれぞれ2日、1日公演があります。


夏休み文楽公演の演目はまだ発表されていませんでした。
地下鉄谷町線で天王寺まで。
地下から地上へ出ると目の前に大きな立体看板の群れ。

そして後ろを振り返るとあべのハルカス。

目の前が天王寺公園。
以前はここに足を踏み入れるには入場料金がかかったのに、今は無料です。
園内には桜がたくさん。
もう満開は過ぎて散り始めていますが、まだまだ花見はできます。

向こうに見えるのは世界の「大温泉スパワールド」。新世界ですね。

桜と大阪市立大学医学部附属病院。

ピラミッド型の建造物は、植物園の温室。







トキワマンサク。

あべのハルカスと桜。

天王寺動物園のゲート。
以前はここにこんな立派なゲートはなかったですね。

後ろを振り返るとJR天王寺駅。


大阪市立美術館へ向かう階段を上り切ったところから通天閣と桜。

キリシマツツジが咲き始めていますね。




桜の写真を撮ろうとすると、蜂が飛んできました。

散り始めた桜と通天閣を美術館の前から。
