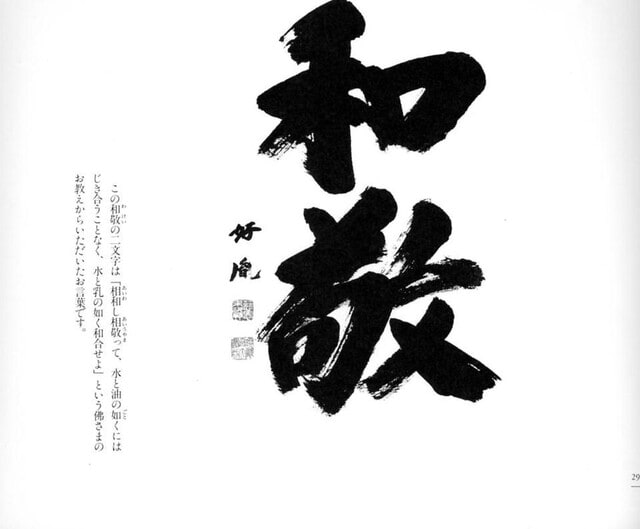盆・・・7月 33回忌までのホトケが帰ってくる
正月・・1月 33回忌を過ぎたカミが帰ってくる
お盆は仏教の盂蘭盆会(うらぼんえ)とはあまり関係のない日本の行事です。
七夕はもともとお盆の一環で篠は先祖が目印とする依り代と考えられました。
正月の依り代は門松です。
浄土真宗では極楽往生しているわけですから、帰ってくるのはおかしいですが、
そういうことをおかまいなしにお盆の行事をやってきた門徒の地方もあります。
(石見地方は浄土真宗が盛んでもあり、地域の祖霊をまつる大元信仰も盛んなので神事を重要視してきました。)

正月・・1月 33回忌を過ぎたカミが帰ってくる
お盆は仏教の盂蘭盆会(うらぼんえ)とはあまり関係のない日本の行事です。
七夕はもともとお盆の一環で篠は先祖が目印とする依り代と考えられました。
正月の依り代は門松です。
浄土真宗では極楽往生しているわけですから、帰ってくるのはおかしいですが、
そういうことをおかまいなしにお盆の行事をやってきた門徒の地方もあります。
(石見地方は浄土真宗が盛んでもあり、地域の祖霊をまつる大元信仰も盛んなので神事を重要視してきました。)