【検体取り違え事故】9/21の各紙が熊本大学病院で、肺生検を受けた50代女性と80代男性の病理検体が入れ違ったため、がんでない女性の肺の1葉が切除されるという事故が起こったのを報じた。
その後の続報がないので、一番詳しそうな「西日本新聞」の記事を再掲する。
http://www.nishinippon.co.jp/nnp/kumamoto/article/40987
この事故には、以下の3つの複合的要因がからんでいると思います。
1)ブロックを薄切した際、切片を貼り付けるスライドグラスを間違えた。
(内視鏡により採取された組織片は、細長いろ紙に付着させ、小さなホルマリン瓶に入れてトレーに載せ、病理検査室に提出される。複数の患者の内視鏡検査を続けて行うと、内視鏡室でビンのラベルを間違えて、検体違いが生じることもあるが、今回はこれではない。
受け付けた検体は、台帳に登録し病理検査番号をあたえられた後、専用のプラスティック製の網カゴに入れたまま、脱水・パラフィン包埋という過程をへて、標本ブロックにされる。ブロックには検体番号がついている。
このパラフィン製のブロックをミクロトームという薄切機をもちいて、薄い切片にする。この切片をあらかじめ検体番号を印字したスライドガラスに載せ、シワを伸ばす。
その後、脱パラフィンと染色操作を行う。
薄切の段階で、切ったブロックの番号と切片を載せるスライドガラスの番号を間違うと、検体の前後の入れ違いが生じる。
今回のミスは、この段階で生じたごく初歩的なミスだ。)
2)検体を取り違えたことを、病理技師も診断した病理医も気づかないで病理組織診断書を発行した。
(普通、内視鏡生検の場合、1箇所だけから検体を採取することはなく、検査申込書に内視鏡所見のスケッチと検体採取部位、及び採取個数を記載する。
これが書いてあれば、二人の患者の採取検体数が異なる場合、申込書記載の数と標本に含まれている組織片数が一致しないので、染色標本ができた段階で、取り違えに気づく。技師が見逃しても、顕微鏡を見た病理医がサンプル数の合わないことに気づく。
この両方をスルーしているので、おそらく熊本大病院の場合、生検申込書の書式に不備があったと思われる。もしそうなら、これも初歩的なミスだ。
病理医は臨床医から独立して診断を行わなければならない。そのためには、「申込書」記載の主治医による記載を読むことなく、まず虚心に標本の所見を読まなくてはいけない。標本を診れば、その検体の持ち主が、50代か80代かの区別はつくし、バー小体を認めれば女であることもわかる。バー小体は組織切片では見にくいが、その気になれば見つけられる。そして仮の病理診断を形成した後、申込書をよく読み、臨床所見と病理診断が一致している場合には仮診断を本診断としてよい。これには性と年齢の一致も含まれる。ある種のがんは若い人にしか起こらないし、女にはほとんど起きないがんもある。
臨床診断と病理診断が食い違う場合が、本当の病理医の出番で、気づかれていない病気の発見や検体の取り違えなどの発見に通じる。つまり病理は一種のディテクティブなのである。Cf. B.ルーチェ「推理する医学」, 西村書店, 1985)
3)50代女性患者と80代男性患者の担当医も、臨床的所見と病理診断書に記載されている病理所見が合わないことに気づかないまま、間違った患者の肺手術をおこなった。
(生検に際して病変部だけでなく、正常部を採取するのが基本である。なぜなら肺全体の状態を病理検査できないので、代表的な一部を採取して、その老化度やびまん性病変の有無をチェックするために、生検がある。統計学におけるサンプル調査と同じである。病変部だけでなく、正常部も検体として採取されていたら、当然それらの所見は病理検査報告書(病理診断書)のなかに記載され、それを読んだ担当医は疑問をいだき、病理部に連絡するのが当然である。
もし病理医が50歳の肺と80歳の肺の所見の違いが顕微鏡下に読み取れないのなら、それは病理医失格である。
術前に病理と話し合いが行われていれば、今は電子カルテの時代だから、肺の画像所見と合わせることで、病理における検体の食い違いが明らかになったはずだと思われる。
要するにチーム医療として、ひとりの患者を治療するという初歩的な体制が整っていなかったのだと思われる。)
2008年に病理医の長年の夢だった「病理標榜科」が実現し、「医療における病理の役割」が評価されるようになってきたのに、こんな初歩的なミスが発生したことは残念でならない。間違えた技師の責任にするのではなく、より安全でミスの起こらないようなシステムの構築を、若い病理医の方々に切に切望する。
その後の続報がないので、一番詳しそうな「西日本新聞」の記事を再掲する。
http://www.nishinippon.co.jp/nnp/kumamoto/article/40987
この事故には、以下の3つの複合的要因がからんでいると思います。
1)ブロックを薄切した際、切片を貼り付けるスライドグラスを間違えた。
(内視鏡により採取された組織片は、細長いろ紙に付着させ、小さなホルマリン瓶に入れてトレーに載せ、病理検査室に提出される。複数の患者の内視鏡検査を続けて行うと、内視鏡室でビンのラベルを間違えて、検体違いが生じることもあるが、今回はこれではない。
受け付けた検体は、台帳に登録し病理検査番号をあたえられた後、専用のプラスティック製の網カゴに入れたまま、脱水・パラフィン包埋という過程をへて、標本ブロックにされる。ブロックには検体番号がついている。
このパラフィン製のブロックをミクロトームという薄切機をもちいて、薄い切片にする。この切片をあらかじめ検体番号を印字したスライドガラスに載せ、シワを伸ばす。
その後、脱パラフィンと染色操作を行う。
薄切の段階で、切ったブロックの番号と切片を載せるスライドガラスの番号を間違うと、検体の前後の入れ違いが生じる。
今回のミスは、この段階で生じたごく初歩的なミスだ。)
2)検体を取り違えたことを、病理技師も診断した病理医も気づかないで病理組織診断書を発行した。
(普通、内視鏡生検の場合、1箇所だけから検体を採取することはなく、検査申込書に内視鏡所見のスケッチと検体採取部位、及び採取個数を記載する。
これが書いてあれば、二人の患者の採取検体数が異なる場合、申込書記載の数と標本に含まれている組織片数が一致しないので、染色標本ができた段階で、取り違えに気づく。技師が見逃しても、顕微鏡を見た病理医がサンプル数の合わないことに気づく。
この両方をスルーしているので、おそらく熊本大病院の場合、生検申込書の書式に不備があったと思われる。もしそうなら、これも初歩的なミスだ。
病理医は臨床医から独立して診断を行わなければならない。そのためには、「申込書」記載の主治医による記載を読むことなく、まず虚心に標本の所見を読まなくてはいけない。標本を診れば、その検体の持ち主が、50代か80代かの区別はつくし、バー小体を認めれば女であることもわかる。バー小体は組織切片では見にくいが、その気になれば見つけられる。そして仮の病理診断を形成した後、申込書をよく読み、臨床所見と病理診断が一致している場合には仮診断を本診断としてよい。これには性と年齢の一致も含まれる。ある種のがんは若い人にしか起こらないし、女にはほとんど起きないがんもある。
臨床診断と病理診断が食い違う場合が、本当の病理医の出番で、気づかれていない病気の発見や検体の取り違えなどの発見に通じる。つまり病理は一種のディテクティブなのである。Cf. B.ルーチェ「推理する医学」, 西村書店, 1985)
3)50代女性患者と80代男性患者の担当医も、臨床的所見と病理診断書に記載されている病理所見が合わないことに気づかないまま、間違った患者の肺手術をおこなった。
(生検に際して病変部だけでなく、正常部を採取するのが基本である。なぜなら肺全体の状態を病理検査できないので、代表的な一部を採取して、その老化度やびまん性病変の有無をチェックするために、生検がある。統計学におけるサンプル調査と同じである。病変部だけでなく、正常部も検体として採取されていたら、当然それらの所見は病理検査報告書(病理診断書)のなかに記載され、それを読んだ担当医は疑問をいだき、病理部に連絡するのが当然である。
もし病理医が50歳の肺と80歳の肺の所見の違いが顕微鏡下に読み取れないのなら、それは病理医失格である。
術前に病理と話し合いが行われていれば、今は電子カルテの時代だから、肺の画像所見と合わせることで、病理における検体の食い違いが明らかになったはずだと思われる。
要するにチーム医療として、ひとりの患者を治療するという初歩的な体制が整っていなかったのだと思われる。)
2008年に病理医の長年の夢だった「病理標榜科」が実現し、「医療における病理の役割」が評価されるようになってきたのに、こんな初歩的なミスが発生したことは残念でならない。間違えた技師の責任にするのではなく、より安全でミスの起こらないようなシステムの構築を、若い病理医の方々に切に切望する。












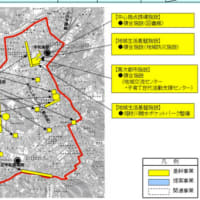
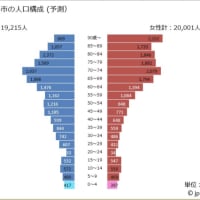



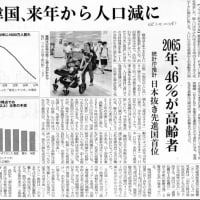










※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます