【読書日記から22】
R.ホフスタッター『アメリカの反知性主義』(みすず書房, 2003, ¥5,616)が在庫切れでなかなか手に入らない。古書価格は8000〜1.2万円にまで上昇している。一体、出版社は何をしているのであろうか?ハードカバーでなく、ペーパーバック版を量産して、定価3000円位で売れば、大いにもうかるだろうに…。
10年ほど前、川喜田愛郎『近代医学の史的基盤(上・下)』(岩波書店, 1977)が品切れで、そろいの古書価格が5万円以上に高騰したことがあった。間もなく岩波が再版し、そろいを1万5400円で売り出したので買い求めたことがあった。
ホフスタッターの訳者田村哲夫という人は、他にどんな仕事をしたのであろう。最近「反主知主義」という言葉がよく出てくるが、田村の意見を聞いたことがない。
この著書の比較的中立的な内容紹介は、
1)巽孝之・編『反知性の帝国:アメリカ・文学・精神史』(南雲堂, 2008/4)
に含まれている、志村正雄「知性・反知性・神秘主義:マッカーシーイズムからIDまで」において行われている。
マッカーシズムは1950年代に荒れ狂った「赤狩り」で、真ん中より左よりの知識人狩りであり、IDは「インテリジェント・デザイン」つまり、進化現象における「適応」の巧みさに「神の摂理」を見ようという、キリスト教原理主義の運動だ。
全部で7人の分担執筆だが、誰一人としてR.Hネービア『マッカーシズム』(岩波文庫,1984)、ポール・ジョンソン『インテレクチュアルズ』(講談社学術文庫, 2003)を引用していないのに驚いた。
ジョンソンの本の訳者別宮貞徳は、インテレクチュアルズとは「知識人」のことだという。彼がこの本で描いたのはルソー、マルクス、イプセン、トルストイ、ヘミングウェイ、ラッセル、サルトルの肖像である。ジョンソンの本の末尾はこうなっている。
「この悲劇的な世紀(20世紀)の主な教訓の一つは —知識人に気をゆるすなー である。
知識人を集団としてとらえれば、その属するサークルの中では、ウルトラ体制順応者であることが多い。このために知識人は、集団として危険な存在となる。」
ユダヤ人であるジョンソンは『ユダヤ人の歴史(上・下)』(徳間書店, 1999)も書いている。
彼の知識人への不信と警戒への呼びかけは、「反知性主義(アンチ・インテレクチャリズム)」とは異なると思う。
2)森本あんり『反知性主義:アメリカが生んだ<熱病>の正体』(新潮選書, 2015/2)
は、基本的には「アメリカ・キリスト教史」で、あまり面白くない。索引がなく、目次小項目に頁が表記されておらず、使いにくい本だ。
1890年代のフランスで「ドレフュース事件」に際して誕生した「知識人(インテレクチュアル)」という言葉から、ホフスタッターが「反知性主義(アンチ・インテレクチュアリズム)」という造語を行い、アメリカ社会思想を歴史的にまとめた。
(C. シャルル『<知識人>の誕生 1880- 1900』, 藤原書店, 2006/6)
しかし森本は、「反知性主義」を「知性と権力の固定的な結びつきに対する反感」と定義しており、「他の国で知識人が果たしてきた役割を、アメリカでは反主知主義が果たしてきた」とまでいうと、少し首を傾げざるをえない。
オリジナルなホフスタッターの本を入手して、原語の意味を正確に把握する必要がある。
3)内田樹・編『日本の反知性主義』(晶文社, 2015/3)
内田を中心に、白井聡、小田嶋隆、鷲田精一など11人による論文が掲載されているが、「知性主義」、「反知性主義」ともに定義があいまいだ。
「まえがき」で内田は、主題名はホフスタッターから借りたと述べ、他方で「現代日本の反知性主義は(アメリカの)それとはかなり異質」と述べている。「為政者からメディアまで、ビジネスから大学まで、社会の根幹部分に反知性主義・反教養主義が深く食い入っている」とも書いている。
これでは反知性主義=反教養主義であり、ポール・ジョンソンや森本のいう「反知性主義」とは全然といえるほど、異なる。
白井聡は同じくホフスタッターを引用し、「反知性主義とは<知的な生き方およびそれを代表するとされる人びとに対する憤りと疑惑>であり、<そのような生き方の価値をつねに極小化しようとする傾向>と定義される」としている。
さらに「知的な事柄に単に無関心なのではなく、知性の本質的な意味での働きに対して侮蔑敵で攻撃的な態度を取ることに、反知性主義の核心は見いだされる」と書いている。
小田嶋は「反知性主義って、オレのことか?」と書いているし、赤坂真理は「実は、<反知性>という言葉が私にはわかりません」と書いている。
つまり執筆者が用語の概念の定義や共通理解もないまま、好き勝手を書いているということだ。
4)白井聡『永続敗戦論:戦後日本の核心』(太田出版、2013/3)
著者の職業が「文化学園大助教」となっている。内田樹編『日本の反知性主義』(2015/3, 上記)では「京都精華大専任教員」とある。「専任教員」という肩書は見たことがないが、まあそれは置いておこう。帯に「内田樹、孫崎享、水野和夫」の推薦が載っている。
著者は1977年、東京都生まれ。早稲田大政経学部政治学科を卒業し、一橋大大学院に進み博士号(社会学)を取得している。
著者はいくつかの客観的事実や統計数値を提示して、それに基づいて論理を組み立てるのが巧といえない。「永続敗戦論」の中核となるメッセージは「8・15は日本の敗戦により、戦争が終わった日である。それなのにこの日を<終戦記念日>と欺瞞的に呼び続けてきた。そこに戦後民主主義のいっさいの欺瞞の根底がある」というものだ。
論証でも実証でもない。
著者の主張は、実証的に証明できないだけでなく、「左」とも「右」ともとれる、両義性ある内容だ。
太田出版だから、こういう本が出ても不思議でないが、著者が2015/5には「反主知主義」を糾弾する本の共著者になっているから、不思議だ。こういう「コウモリ的」というか、「ヌエ的」な言説の横行に、日本の知性の確実な劣化傾向を感じる。
5)藤井聡『<凡庸>という悪魔:21世紀の全体主義』(晶文社, 2015/4)
1968年奈良県生まれ、京大工学部卒(土木工学科)、京大工学研究科教授とある。
この本自体はハンナ・アーレントの『全体主義の起源』と彼女がアイヒマン裁判を取材した『悪の凡庸性』を下敷きにしており、内容的に独創的なところはひとつもない。その意味では「知の劣化」を再認識させてくれる。
唯一の政治的新味は「大阪都構想が全体主義に通じる」と批判しているところであろうか…。
6)原田伊織『明治維新という過ち(改訂増補版)』(毎日ワンズ, 2015/1)
毎日だけに度々大きな広告が載り、「そういえば最近、毎日新聞社の本を見かけないな」と、つい毎日新聞の本かと思ってしまった。
広告の文章に「週刊文春」書評から立花隆の文を利用しており、副題に「日本を滅ぼした吉田松陰と長州テロリスト」とあり、「松陰が征韓論を唱えた」という韓国の言い分と同じだな、と思った。「作家・原田伊織」とあり、出て間がないのに「改訂増補版」とあるのも不思議なのでアマゾンに注文した。
届いて読んだ後、5/19の毎日に<勝俣範之『「抗がん剤は効かない」の罪』,毎日新聞出版>という近藤誠批判本の広告が載っていたので、「なんだまだあるのか…」と思った。毎日も昨今はこういう本を売るのか…。
<<余談=5/19毎日「記者の目」欄で、山田麻未という前生活報道部(現東京社会部)記者が、「氾濫するがん情報、科学的裏付け見極めを」という上記勝俣範之本の「よいしょ記事」を書いているのを見つけて、唖然としてしまった。記事が美事に一面の新聞広告とシンクロナイズしている。
もともと「記者の目」欄は、社論と関係なく第一線の記者の意見表明の場であったはずだ。
私は2006年11月に表面化した「病気腎(修復腎)」移植を扱ったNFドキュメント『第三の移植』にこう書いている。(未刊行)
<中には現場と本社が意見衝突する新聞もあった。『毎日』の「記者の目」欄がそうだ。この欄は社説に反する記者の意見でも発表できるのが特徴とされている。
12月1日の同欄に松山支局の津久井達記者は「病気腎移植の万波誠医師 治療への献身 飾らぬ性格 無頓着、無用の誤解招く」と題する手記を寄せ、
「この問題が発覚するきっかけになった臓器売買事件から約2ヶ月間、近くで取材をしてきて、常に患者を第一に考える万波医師の人柄に親近感を覚えたのも事実だ。病気腎移植を〈地方医師の暴走〉と片づけてはいけないと思う」と東京本社・科学環境部(医療担当)の報道姿勢を、暗に批判する意見を表明した。
すると12月5日の同欄に、同科学環境部大場あい記者が「病気腎移植の万波 誠医師 必要手順 踏むべきだった 〈練達の頼れる人〉ゆえ」と題する反論を載せた。
津久井記者のいう人柄論はよく分かるが、患者への説明不足は「パターナリズム」であり、インフォームド・コンセントを取っていないのも認められない、という論旨である。
『産経』松山支局長の立花慶三記者も12月4日、「一線から」というコラム欄に、「病腎移植 前向きな論議を」と題する論説を発表し、毎日の津久井記者と類似の意見を述べ、
「東京女子医大など全国8病院でも病腎移植が行われ、日本移植学会誌で発表されていた。病腎移植が今回、なぜ異端視されるのか」と問いかけている。
この立花記者の記事が立派なのは、自論を補強するために、匿名の権威者を一人も用いていないことだ。先程の津久井論説には、2ヶ所これがあり、大場論説には3ヶ所ある。
特に後者では「万波移植を手厳しく批判する移植医」が匿名にされ、その批判のみが紹介されている。これでは読者は検証の方法がないし、大場記者が「移植医の万波医師に対する悪口」を鵜呑みにして信じ込んでいるだけ、と受け取られても仕方がない。>
で、時代は変わる。まだあどけない表情が残る山田麻未記者が、往年の「記者の目」のスピリットを忘れ、自社出版本のよいしょ記事をこの欄に書くのも仕方ないのかも知れないが、真実を知れば確実に読者は減るだろう。>>
で、この本にはさぞかし実証的な証拠を挙げて、吉田松陰が征韓論や大陸進出を提唱したこと、幕末の長州人がテロリストであったこと、明治維新後の政府が長州閥の独占するところであったことが、統計数値などを示して、仔細に述べられているものと思ったが、まったく違った。
68冊の参考文献を巻末に掲げているが、90%が司馬遼太郎の紀行文や他の著者による二次資料で、幕末明治の同時代一次資料は、『ベルツの日記』、『会津戦争のすべて』(会津史談会)、永倉新八『新撰組顛末記』、イサベラ・バード『日本奥地紀行』しかない。
しかも『日本奥地紀行』は金坂清則による「完訳本全4冊」ではなく、旧い高梨健吉訳による「抄訳1冊本」(東洋文庫)を用いている。
この人は相楽総三の「赤報隊」について述べながら、長谷川伸の労作『相楽総三とその同志(上・下)』(中公文庫)に触れていないし、参考文献にもあがっていない。
永倉新八『新撰組顛末記』(新人物文庫)にふれて、
(「池田屋事件」の)経緯については諸説があるが、もっとも信憑性が高いとされるのが、討ち入った一人で大正四年まで生きた長倉新八の書き残した『浪士文久報国記事』である。大正四年というと、私の父の生年である…」といういささか意味不明な文を書いている。
長倉の『浪士文久報国記事』など書名として聞いたこともない。
長倉が残したはずの記事の引用が全くなく、いきなり『新撰組顛末記』から、小樽新聞連載の「維新史に残る活劇、池田屋襲撃の顛末」という文章が2頁にわたり続く。
それが終わった後(全文から4頁目)に、
「永倉新八は大正四年まで生きたが、大正四年といえば私の父の生年である。」
という文章がまた出てくる。
長倉回想録のこの会の終わりには、「このとき会津、桑名の両藩から人数をくりだして池田屋を遠巻きにしたようすに、二十余名の同志(長州浪人のこと)はここに窮鼠かえって猫を噛むの形で、猛然と太刀をふりかざして向かってきた」とある。
これは依頼していた会津、桑名の援軍が出動して池田屋を包囲して長州浪士に逃げ場がなくなったということであろう。
ところが伊藤伊織は、「(池田屋事件の時)会津藩、桑名藩に(新撰組が)応援を頼んだかどうか疑わしい。『浪士文久報国記事』は、この切り込みに関しては会津藩のことには全く触れていない」と書いている。(それほど重要な文献なら、巻末参考資料として示すべきだし、該当する本文を引用すべきであろう。)
文庫版の『新撰組顛末記』には、『新撰組永倉新八外伝』(新人物往来社)の著者で、永倉新八の曾孫にあたる杉村悦郎が「解説」を書き、元記事が1913(大正2)年3月から6月まで、小樽新聞に70回にわたり掲載されたことを述べている。長倉の遺稿「同志連名記」も付録で収録されており、そこに永倉新八が新撰組時代のことを書いた「遺稿」はある人に貸与したところ、そのまま行方不明となった、と書いている。
従って、長倉手記は他にもあった可能性があるが、遺稿にも曾孫による「解説」にも文書名は書かれていない。
さて著者のいう『浪士文久報国記事』なる長倉手記は実在するのであろうか?それとも、わずか5頁先に自分の父の生年について、同じ文を二度も書くような「ウッカリン過剰症」のため、書名を混同したのであろうか?
著者はさかんに「倫理、倫理観」を強調しているが、オットー・ワイニンガーが『性と性格』で述べたように、「論理と倫理は結局同じものである。一切の倫理は論理の諸原理に従ってはじめて可能になる」。
論理矛盾を平気でおかし、弱い記憶力の人は、倫理的になれないのである。
というわけで、これは中身のない本でありましたな。
こういう本の推薦文を書く「立花隆」とは何者だろう?
R.ホフスタッター『アメリカの反知性主義』(みすず書房, 2003, ¥5,616)が在庫切れでなかなか手に入らない。古書価格は8000〜1.2万円にまで上昇している。一体、出版社は何をしているのであろうか?ハードカバーでなく、ペーパーバック版を量産して、定価3000円位で売れば、大いにもうかるだろうに…。
10年ほど前、川喜田愛郎『近代医学の史的基盤(上・下)』(岩波書店, 1977)が品切れで、そろいの古書価格が5万円以上に高騰したことがあった。間もなく岩波が再版し、そろいを1万5400円で売り出したので買い求めたことがあった。
ホフスタッターの訳者田村哲夫という人は、他にどんな仕事をしたのであろう。最近「反主知主義」という言葉がよく出てくるが、田村の意見を聞いたことがない。
この著書の比較的中立的な内容紹介は、
1)巽孝之・編『反知性の帝国:アメリカ・文学・精神史』(南雲堂, 2008/4)
に含まれている、志村正雄「知性・反知性・神秘主義:マッカーシーイズムからIDまで」において行われている。
マッカーシズムは1950年代に荒れ狂った「赤狩り」で、真ん中より左よりの知識人狩りであり、IDは「インテリジェント・デザイン」つまり、進化現象における「適応」の巧みさに「神の摂理」を見ようという、キリスト教原理主義の運動だ。
全部で7人の分担執筆だが、誰一人としてR.Hネービア『マッカーシズム』(岩波文庫,1984)、ポール・ジョンソン『インテレクチュアルズ』(講談社学術文庫, 2003)を引用していないのに驚いた。
ジョンソンの本の訳者別宮貞徳は、インテレクチュアルズとは「知識人」のことだという。彼がこの本で描いたのはルソー、マルクス、イプセン、トルストイ、ヘミングウェイ、ラッセル、サルトルの肖像である。ジョンソンの本の末尾はこうなっている。
「この悲劇的な世紀(20世紀)の主な教訓の一つは —知識人に気をゆるすなー である。
知識人を集団としてとらえれば、その属するサークルの中では、ウルトラ体制順応者であることが多い。このために知識人は、集団として危険な存在となる。」
ユダヤ人であるジョンソンは『ユダヤ人の歴史(上・下)』(徳間書店, 1999)も書いている。
彼の知識人への不信と警戒への呼びかけは、「反知性主義(アンチ・インテレクチャリズム)」とは異なると思う。
2)森本あんり『反知性主義:アメリカが生んだ<熱病>の正体』(新潮選書, 2015/2)
は、基本的には「アメリカ・キリスト教史」で、あまり面白くない。索引がなく、目次小項目に頁が表記されておらず、使いにくい本だ。
1890年代のフランスで「ドレフュース事件」に際して誕生した「知識人(インテレクチュアル)」という言葉から、ホフスタッターが「反知性主義(アンチ・インテレクチュアリズム)」という造語を行い、アメリカ社会思想を歴史的にまとめた。
(C. シャルル『<知識人>の誕生 1880- 1900』, 藤原書店, 2006/6)
しかし森本は、「反知性主義」を「知性と権力の固定的な結びつきに対する反感」と定義しており、「他の国で知識人が果たしてきた役割を、アメリカでは反主知主義が果たしてきた」とまでいうと、少し首を傾げざるをえない。
オリジナルなホフスタッターの本を入手して、原語の意味を正確に把握する必要がある。
3)内田樹・編『日本の反知性主義』(晶文社, 2015/3)
内田を中心に、白井聡、小田嶋隆、鷲田精一など11人による論文が掲載されているが、「知性主義」、「反知性主義」ともに定義があいまいだ。
「まえがき」で内田は、主題名はホフスタッターから借りたと述べ、他方で「現代日本の反知性主義は(アメリカの)それとはかなり異質」と述べている。「為政者からメディアまで、ビジネスから大学まで、社会の根幹部分に反知性主義・反教養主義が深く食い入っている」とも書いている。
これでは反知性主義=反教養主義であり、ポール・ジョンソンや森本のいう「反知性主義」とは全然といえるほど、異なる。
白井聡は同じくホフスタッターを引用し、「反知性主義とは<知的な生き方およびそれを代表するとされる人びとに対する憤りと疑惑>であり、<そのような生き方の価値をつねに極小化しようとする傾向>と定義される」としている。
さらに「知的な事柄に単に無関心なのではなく、知性の本質的な意味での働きに対して侮蔑敵で攻撃的な態度を取ることに、反知性主義の核心は見いだされる」と書いている。
小田嶋は「反知性主義って、オレのことか?」と書いているし、赤坂真理は「実は、<反知性>という言葉が私にはわかりません」と書いている。
つまり執筆者が用語の概念の定義や共通理解もないまま、好き勝手を書いているということだ。
4)白井聡『永続敗戦論:戦後日本の核心』(太田出版、2013/3)
著者の職業が「文化学園大助教」となっている。内田樹編『日本の反知性主義』(2015/3, 上記)では「京都精華大専任教員」とある。「専任教員」という肩書は見たことがないが、まあそれは置いておこう。帯に「内田樹、孫崎享、水野和夫」の推薦が載っている。
著者は1977年、東京都生まれ。早稲田大政経学部政治学科を卒業し、一橋大大学院に進み博士号(社会学)を取得している。
著者はいくつかの客観的事実や統計数値を提示して、それに基づいて論理を組み立てるのが巧といえない。「永続敗戦論」の中核となるメッセージは「8・15は日本の敗戦により、戦争が終わった日である。それなのにこの日を<終戦記念日>と欺瞞的に呼び続けてきた。そこに戦後民主主義のいっさいの欺瞞の根底がある」というものだ。
論証でも実証でもない。
著者の主張は、実証的に証明できないだけでなく、「左」とも「右」ともとれる、両義性ある内容だ。
太田出版だから、こういう本が出ても不思議でないが、著者が2015/5には「反主知主義」を糾弾する本の共著者になっているから、不思議だ。こういう「コウモリ的」というか、「ヌエ的」な言説の横行に、日本の知性の確実な劣化傾向を感じる。
5)藤井聡『<凡庸>という悪魔:21世紀の全体主義』(晶文社, 2015/4)
1968年奈良県生まれ、京大工学部卒(土木工学科)、京大工学研究科教授とある。
この本自体はハンナ・アーレントの『全体主義の起源』と彼女がアイヒマン裁判を取材した『悪の凡庸性』を下敷きにしており、内容的に独創的なところはひとつもない。その意味では「知の劣化」を再認識させてくれる。
唯一の政治的新味は「大阪都構想が全体主義に通じる」と批判しているところであろうか…。
6)原田伊織『明治維新という過ち(改訂増補版)』(毎日ワンズ, 2015/1)
毎日だけに度々大きな広告が載り、「そういえば最近、毎日新聞社の本を見かけないな」と、つい毎日新聞の本かと思ってしまった。
広告の文章に「週刊文春」書評から立花隆の文を利用しており、副題に「日本を滅ぼした吉田松陰と長州テロリスト」とあり、「松陰が征韓論を唱えた」という韓国の言い分と同じだな、と思った。「作家・原田伊織」とあり、出て間がないのに「改訂増補版」とあるのも不思議なのでアマゾンに注文した。
届いて読んだ後、5/19の毎日に<勝俣範之『「抗がん剤は効かない」の罪』,毎日新聞出版>という近藤誠批判本の広告が載っていたので、「なんだまだあるのか…」と思った。毎日も昨今はこういう本を売るのか…。
<<余談=5/19毎日「記者の目」欄で、山田麻未という前生活報道部(現東京社会部)記者が、「氾濫するがん情報、科学的裏付け見極めを」という上記勝俣範之本の「よいしょ記事」を書いているのを見つけて、唖然としてしまった。記事が美事に一面の新聞広告とシンクロナイズしている。
もともと「記者の目」欄は、社論と関係なく第一線の記者の意見表明の場であったはずだ。
私は2006年11月に表面化した「病気腎(修復腎)」移植を扱ったNFドキュメント『第三の移植』にこう書いている。(未刊行)
<中には現場と本社が意見衝突する新聞もあった。『毎日』の「記者の目」欄がそうだ。この欄は社説に反する記者の意見でも発表できるのが特徴とされている。
12月1日の同欄に松山支局の津久井達記者は「病気腎移植の万波誠医師 治療への献身 飾らぬ性格 無頓着、無用の誤解招く」と題する手記を寄せ、
「この問題が発覚するきっかけになった臓器売買事件から約2ヶ月間、近くで取材をしてきて、常に患者を第一に考える万波医師の人柄に親近感を覚えたのも事実だ。病気腎移植を〈地方医師の暴走〉と片づけてはいけないと思う」と東京本社・科学環境部(医療担当)の報道姿勢を、暗に批判する意見を表明した。
すると12月5日の同欄に、同科学環境部大場あい記者が「病気腎移植の万波 誠医師 必要手順 踏むべきだった 〈練達の頼れる人〉ゆえ」と題する反論を載せた。
津久井記者のいう人柄論はよく分かるが、患者への説明不足は「パターナリズム」であり、インフォームド・コンセントを取っていないのも認められない、という論旨である。
『産経』松山支局長の立花慶三記者も12月4日、「一線から」というコラム欄に、「病腎移植 前向きな論議を」と題する論説を発表し、毎日の津久井記者と類似の意見を述べ、
「東京女子医大など全国8病院でも病腎移植が行われ、日本移植学会誌で発表されていた。病腎移植が今回、なぜ異端視されるのか」と問いかけている。
この立花記者の記事が立派なのは、自論を補強するために、匿名の権威者を一人も用いていないことだ。先程の津久井論説には、2ヶ所これがあり、大場論説には3ヶ所ある。
特に後者では「万波移植を手厳しく批判する移植医」が匿名にされ、その批判のみが紹介されている。これでは読者は検証の方法がないし、大場記者が「移植医の万波医師に対する悪口」を鵜呑みにして信じ込んでいるだけ、と受け取られても仕方がない。>
で、時代は変わる。まだあどけない表情が残る山田麻未記者が、往年の「記者の目」のスピリットを忘れ、自社出版本のよいしょ記事をこの欄に書くのも仕方ないのかも知れないが、真実を知れば確実に読者は減るだろう。>>
で、この本にはさぞかし実証的な証拠を挙げて、吉田松陰が征韓論や大陸進出を提唱したこと、幕末の長州人がテロリストであったこと、明治維新後の政府が長州閥の独占するところであったことが、統計数値などを示して、仔細に述べられているものと思ったが、まったく違った。
68冊の参考文献を巻末に掲げているが、90%が司馬遼太郎の紀行文や他の著者による二次資料で、幕末明治の同時代一次資料は、『ベルツの日記』、『会津戦争のすべて』(会津史談会)、永倉新八『新撰組顛末記』、イサベラ・バード『日本奥地紀行』しかない。
しかも『日本奥地紀行』は金坂清則による「完訳本全4冊」ではなく、旧い高梨健吉訳による「抄訳1冊本」(東洋文庫)を用いている。
この人は相楽総三の「赤報隊」について述べながら、長谷川伸の労作『相楽総三とその同志(上・下)』(中公文庫)に触れていないし、参考文献にもあがっていない。
永倉新八『新撰組顛末記』(新人物文庫)にふれて、
(「池田屋事件」の)経緯については諸説があるが、もっとも信憑性が高いとされるのが、討ち入った一人で大正四年まで生きた長倉新八の書き残した『浪士文久報国記事』である。大正四年というと、私の父の生年である…」といういささか意味不明な文を書いている。
長倉の『浪士文久報国記事』など書名として聞いたこともない。
長倉が残したはずの記事の引用が全くなく、いきなり『新撰組顛末記』から、小樽新聞連載の「維新史に残る活劇、池田屋襲撃の顛末」という文章が2頁にわたり続く。
それが終わった後(全文から4頁目)に、
「永倉新八は大正四年まで生きたが、大正四年といえば私の父の生年である。」
という文章がまた出てくる。
長倉回想録のこの会の終わりには、「このとき会津、桑名の両藩から人数をくりだして池田屋を遠巻きにしたようすに、二十余名の同志(長州浪人のこと)はここに窮鼠かえって猫を噛むの形で、猛然と太刀をふりかざして向かってきた」とある。
これは依頼していた会津、桑名の援軍が出動して池田屋を包囲して長州浪士に逃げ場がなくなったということであろう。
ところが伊藤伊織は、「(池田屋事件の時)会津藩、桑名藩に(新撰組が)応援を頼んだかどうか疑わしい。『浪士文久報国記事』は、この切り込みに関しては会津藩のことには全く触れていない」と書いている。(それほど重要な文献なら、巻末参考資料として示すべきだし、該当する本文を引用すべきであろう。)
文庫版の『新撰組顛末記』には、『新撰組永倉新八外伝』(新人物往来社)の著者で、永倉新八の曾孫にあたる杉村悦郎が「解説」を書き、元記事が1913(大正2)年3月から6月まで、小樽新聞に70回にわたり掲載されたことを述べている。長倉の遺稿「同志連名記」も付録で収録されており、そこに永倉新八が新撰組時代のことを書いた「遺稿」はある人に貸与したところ、そのまま行方不明となった、と書いている。
従って、長倉手記は他にもあった可能性があるが、遺稿にも曾孫による「解説」にも文書名は書かれていない。
さて著者のいう『浪士文久報国記事』なる長倉手記は実在するのであろうか?それとも、わずか5頁先に自分の父の生年について、同じ文を二度も書くような「ウッカリン過剰症」のため、書名を混同したのであろうか?
著者はさかんに「倫理、倫理観」を強調しているが、オットー・ワイニンガーが『性と性格』で述べたように、「論理と倫理は結局同じものである。一切の倫理は論理の諸原理に従ってはじめて可能になる」。
論理矛盾を平気でおかし、弱い記憶力の人は、倫理的になれないのである。
というわけで、これは中身のない本でありましたな。
こういう本の推薦文を書く「立花隆」とは何者だろう?












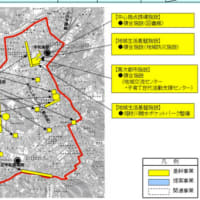
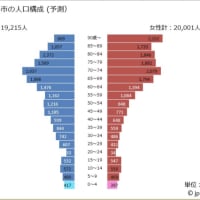



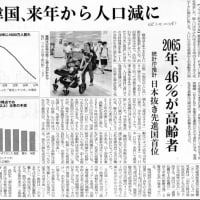










※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます