【アナグラム】昼食後、ソファーの上に寝転んで「日本唱歌集」(岩波文庫)をぼんやり見ていたら、「夏は来ぬ」(佐々木信綱作詞、小山作之助作曲)があった。「夏はもう終わったな」と思いながら5番まである歌詞を読んでゆくと、5番は1~4番からキーワードを抜いて作った一種の「索引詩」だとわかった。5番の歌詞:
「五月闇(さつきやみ)、蛍とびかい、くいな鳴き、
卯の花さきて、早苗植え渡す、夏は来ぬ」
1番は「卯の花が匂う垣根に ホトトギスが来て鳴き始めた、夏が来た」という意味。
2番は「五月雨がそそぐ山田に早乙女が、玉苗を植える、夏が来た。の意。
3番は「橘が香るのきばの窓に、蛍が飛び交い、蛍雪の功を積めと励ます、夏が来た」の意。
4番は「あうちの花が散る河辺の宿からクイナの鳴き声がする、夏が来た」の意。
1歌が6句よりなり、5番は1~4番から5句を採用し、各番の締め句である「夏は来ぬ」を、全体の締めくくりの句として採用している。この句は同時に唱歌のタイトルになっている。
佐々木信綱は歌人で、岩波文庫「新古今和歌集」の校訂もやっている。手元の岩波文庫「新古今和歌集」は大型本で「教科書版」とあり、10年近く前に神田の古書店で買ったものだ。「昭和11年印刷」とある。今でいう「ワイド版」で、当時は学生の教科書用に使われたらしい。活字が大きくて読みやすい。ただし歌の索引も、人名索引もない。
パピルスの巻物や和本の時代には、本にページ番号も目次もなく、読む人はどこに何が書いてあったかを記憶しておかなければならず、脳に大変な負担がかかったろうと思う。芥川龍之介は記憶の天才で、「その事は本棚の上から何段目の右から何冊目の本の、何ページに書いてある」というふうに即座に言えたという。
頭を酷使しすぎて、おかしくなって自殺した。友人だった広津和郎に「あの時代:芥川(龍之介)と宇野(浩二)」という回想記がある。
その芥川は久米正雄宛の遺書に「或阿呆の一生」原稿を託し「発表するとしてもインデキスをつけずにもらいたい」と述べている。このIndexは「索引」でなく「目次」の意味である。文庫本で20余頁の分量で1冊の本にすらならない。索引はおろか目次さえ無理で、通読するしかない。
日本の文学者にIndexには冒頭に付ける「目次」と巻末に付ける「索引」という二つの意味があることを正確に理解していた人は、少なくともこの頃にはいなかった。
話をもどすと、信綱の「夏は来ぬ」では5番は1~4番を圧縮して、キーワードを選び、その配列を変更して作詞している。
出現順に見ると、「卯の花、五月雨、苗植え、蛍とびかい、くいな鳴く」である。
これを「五月闇、蛍とびかい、くいな鳴く、卯の花咲き、苗植え」に順番を変え、「夏は来ぬ」という統一句で締めることにし、語調を整えると完成した5番になる。
5番は既出の情景の入れ替え(アナグラム=綴り変え)で成り立っており、新しい情景は盛り込まれていない。つまり全体の「要約」である。
これは要するに、昔の医学論文みたいに、序文があり、ついで材料と方法の記述があり、結果が述べられ、ついで考察に移り、最後に「要約」が来るのと同じだ。今は忙しい時代だから、「要約」が冒頭に来る。ここしか読んでもらえない論文も多い。
前からこの「夏は来ぬ」は歌詞も曲も優れたよい歌だと思っていたが、その秘密は「夏は来ぬ」というリフレインのほかに、5番が語句の上でも意味の上でも、1~4番の圧縮リフレインになっていることにあるとわかった。さらにこの「夏は来ぬ」をタイトルに持ってきている。
信綱作詞の唱歌には他に「すずめ」、「水師営の会見」があるが、こういうリフレインと圧縮という技法を用いていない。
「すずめ」は「すずめ雀、」という歌い出しをタイトルにしたもの。「水師営」は1番の末尾に「ところはいずこ、水師営」と9番まである歌の1箇所に出てくるだけだ。
やはり「夏は来ぬ」は作歌構造論から見ても、他のふたつの歌にくらべ、格段にすぐれているようだ。
「五月闇(さつきやみ)、蛍とびかい、くいな鳴き、
卯の花さきて、早苗植え渡す、夏は来ぬ」
1番は「卯の花が匂う垣根に ホトトギスが来て鳴き始めた、夏が来た」という意味。
2番は「五月雨がそそぐ山田に早乙女が、玉苗を植える、夏が来た。の意。
3番は「橘が香るのきばの窓に、蛍が飛び交い、蛍雪の功を積めと励ます、夏が来た」の意。
4番は「あうちの花が散る河辺の宿からクイナの鳴き声がする、夏が来た」の意。
1歌が6句よりなり、5番は1~4番から5句を採用し、各番の締め句である「夏は来ぬ」を、全体の締めくくりの句として採用している。この句は同時に唱歌のタイトルになっている。
佐々木信綱は歌人で、岩波文庫「新古今和歌集」の校訂もやっている。手元の岩波文庫「新古今和歌集」は大型本で「教科書版」とあり、10年近く前に神田の古書店で買ったものだ。「昭和11年印刷」とある。今でいう「ワイド版」で、当時は学生の教科書用に使われたらしい。活字が大きくて読みやすい。ただし歌の索引も、人名索引もない。
パピルスの巻物や和本の時代には、本にページ番号も目次もなく、読む人はどこに何が書いてあったかを記憶しておかなければならず、脳に大変な負担がかかったろうと思う。芥川龍之介は記憶の天才で、「その事は本棚の上から何段目の右から何冊目の本の、何ページに書いてある」というふうに即座に言えたという。
頭を酷使しすぎて、おかしくなって自殺した。友人だった広津和郎に「あの時代:芥川(龍之介)と宇野(浩二)」という回想記がある。
その芥川は久米正雄宛の遺書に「或阿呆の一生」原稿を託し「発表するとしてもインデキスをつけずにもらいたい」と述べている。このIndexは「索引」でなく「目次」の意味である。文庫本で20余頁の分量で1冊の本にすらならない。索引はおろか目次さえ無理で、通読するしかない。
日本の文学者にIndexには冒頭に付ける「目次」と巻末に付ける「索引」という二つの意味があることを正確に理解していた人は、少なくともこの頃にはいなかった。
話をもどすと、信綱の「夏は来ぬ」では5番は1~4番を圧縮して、キーワードを選び、その配列を変更して作詞している。
出現順に見ると、「卯の花、五月雨、苗植え、蛍とびかい、くいな鳴く」である。
これを「五月闇、蛍とびかい、くいな鳴く、卯の花咲き、苗植え」に順番を変え、「夏は来ぬ」という統一句で締めることにし、語調を整えると完成した5番になる。
5番は既出の情景の入れ替え(アナグラム=綴り変え)で成り立っており、新しい情景は盛り込まれていない。つまり全体の「要約」である。
これは要するに、昔の医学論文みたいに、序文があり、ついで材料と方法の記述があり、結果が述べられ、ついで考察に移り、最後に「要約」が来るのと同じだ。今は忙しい時代だから、「要約」が冒頭に来る。ここしか読んでもらえない論文も多い。
前からこの「夏は来ぬ」は歌詞も曲も優れたよい歌だと思っていたが、その秘密は「夏は来ぬ」というリフレインのほかに、5番が語句の上でも意味の上でも、1~4番の圧縮リフレインになっていることにあるとわかった。さらにこの「夏は来ぬ」をタイトルに持ってきている。
信綱作詞の唱歌には他に「すずめ」、「水師営の会見」があるが、こういうリフレインと圧縮という技法を用いていない。
「すずめ」は「すずめ雀、」という歌い出しをタイトルにしたもの。「水師営」は1番の末尾に「ところはいずこ、水師営」と9番まである歌の1箇所に出てくるだけだ。
やはり「夏は来ぬ」は作歌構造論から見ても、他のふたつの歌にくらべ、格段にすぐれているようだ。












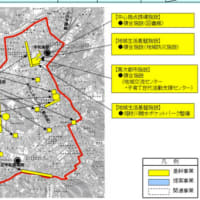
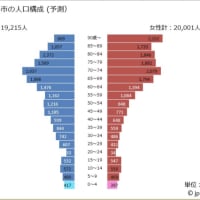



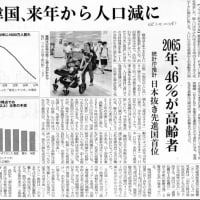










※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます