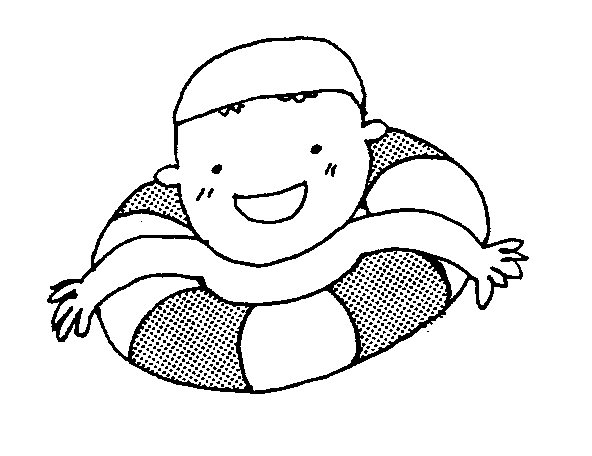足立では6月1日から段階的解除
 緊急事態宣言解除後のイベントの再開について、屋内施設・屋外施設の利用再開の考え方について
緊急事態宣言解除後のイベントの再開について、屋内施設・屋外施設の利用再開の考え方について
 足立区新型コロナウイルス感染症拡大防止ガイドライン に記述している対策を講じる。
足立区新型コロナウイルス感染症拡大防止ガイドライン に記述している対策を講じる。
 感染症拡大防止ガイドライン
感染症拡大防止ガイドライン
各イベント主催者及び施設管理者は本基準を参考とし、当該イベント・施設の状況に応
じて追加策を講じること。
なお、本ガイドラインは東京都『事業所向け東京都感染拡大防止ガイドライン~「新し
い日常」の定着に向けて~』【令和2年5月22日】を基本として作成した。
1 施設利用人数の制限等
施設の再開に際しては、次のことに留意すること。なお人数については、感染拡大状
況により変更される。
(1)屋内施設
ア 利用者同士が一定の距離を保つこと
イ 施設が定める定員がある場合は、入場者はその定員の1/2まで
ウ 当面の間、最大50人までとする
(2)屋外施設
ア 利用者同士が一定の距離を保つこと
イ 当面の間、最大50人までとする
(3)施設利用者の名簿管理
ア 施設管理者は施設入場時に名簿を必ず準備し、施設利用者に記入を求めること
イ 利用団体代表者は利用者名簿を作成し、1カ月程度保管すること
2 利用者向け対策
(1)入場時等における対策
・ 施設入口に「発熱のある方、体調不良の方は入場をご遠慮ください」という趣旨
の張り紙を掲出する【足立区独自】
・ 入場者の列は間隔(できるだけ2m)を空ける。このための職員による行列の整
理、立ち位置の目印を付すなど、入場整理を行うことで混雑を避ける
・ 入場者にマスク着用の徹底などの周知を図る
※マスク着用の張り紙を掲出する
※マスクを所持していない場合は配布する【足立区独自】
・ 発熱が疑われる利用者に対しては、非接触式体温計を用いて体温を測定し、発熱
が認められる場合は入場を制限する
・ 入場口や施設内各所に消毒備品等を設置し、入場者の手洗いや手指消毒の徹底を
図る
※施設入場時に手指消毒の実施を促す張り紙を掲出すること【足立区独自】
・ 施設の規模に応じて入場者数や滞在時間の制限を設ける(とりわけ屋内施設につ
いては、3密(密閉、密集、密接)にならないよう入場者数の制限に十分留意す
る)
(2)施設内における対策
・ 適宜換気を行う【足立区独自】
・ 可能な場合は窓、出入り口等を常時または適宜解放する【足立区独自】
・ 施設内における座席や利用場所の配置を工夫するなど、人と人との間隔(できる
だけ2m)を確保する
・ 利用者に対し、手洗い・消毒の慣行に加え、大声の会話を慎むよう適宜アナウン
スする
・ 複数の人が使用する場所(トイレなど)、手や口が触れるようなもの(商品やコ
ップ類など)をこまめに消毒・洗浄する
・ 利用者や来場者等に対する紙やチラシ類、販促品などの物の配布は手渡しで行う
ことは中止し、机等に設置するなど、据え置き方式で行う
・ 喫煙スペースがある場合は、3密(密閉、密集、密接)にならないよう利用者数
の制限を設け、利用者に対して周知徹底を図る
3 従業員向け対策
(1)職員の体調管理
・ 職員が使用する制服や衣服は、こまめに洗濯する
・ 職員に対し、出勤前の検温や新型コロナウイルス感染症を疑われる症状の有無を
確認させ、毎日の報告を徹底する
・ 体調不良の場合は、休養を促し、勤務中に体調不良となった場合には、直ちに帰
宅させ自宅待機とする
(2)営業中における対策
・ 職員にこまめに石鹸で手洗いを行うよう指導する
・ 職員が、こまめに手洗いができない状況である場合は、適宜手指消毒を行うよう
指導する
・ 手指消毒は市販のアルコール消毒液を原則とする【足立区独自】
※市販のアルコール消毒液の入手が困難な場合は、危機管理部が備蓄している高
濃度アルコールを供出する【足立区独自】
・ 職員に勤務中のマスク着用を促す
・ 職員間で、できるだけ2mの距離を保てるように配慮する
・ 適宜換気を行う【足立区独自】
・ 可能な場合は窓、出入り口等を常時または適宜解放する【足立区独自】
(3)更衣室・休憩時等における対策
・ 更衣室・休憩室の規模に相応しい人数以上の入室を制限し、休憩する際も対面で
の食事や会話をしないよう徹底する
・ 特に、屋内の休憩スペースについては、座席間のスペースを十分にとり、できる
限り常時換気を行う
・ 職員同士が共有する物品や、手が頻繁に触れる場所をなるべく減らし、共有を避
けることが難しい物品等(テーブル、椅子等)は、定期的に消毒する
・ 職員は、更衣室・休憩室に入退室する前後の手洗い・消毒を徹底する
4 施設環境整備
(1)レジ・窓口等における対策
・ レジや窓口など人と人の対面が想定される場所に、アクリル板や透明ビニールカ
ーテンなどを設置し遮蔽する
・ レジ前など利用者の列が想定される場合には、立ち位置の目印を付すなど行列の
整理を行うことで混雑を防ぐ
・ チケットレス、キャッシュレスなど、非接触によるやり取りが可能な手法をでき
る限り導入し接触機会を回避する
(2)トイレにおける対策
・ 適時、手袋・マスク着用の上、定期的に拭き上げ消毒を行う
・ ハンドドライヤー利用や共用タオルの使用は中止し、できる限り、ペーパータオ
ルを設置する
・ 個室ではない便器(男性用小便器など)の利用に当たっては、一つおきに使用す
るよう、利用者に対して周知を図る
(3)ごみの廃棄における対策
・ 鼻水、唾液などが付いたマスク等のごみは、ビニール袋に入れて紐を縛るなど密
閉した上で捨てるよう表示する
・ ごみを回収する従業員は、収集の際に手袋・マスクを着用するとともに、手袋・
マスクを脱いだ後は、必ず石けんと流水で手を洗ったうえで、手指消毒を徹底す
る
5 消毒・清掃について
・ 不特定多数の人が触れる場所・器具等(ドアノブ、タッチパネル、ベンチ、エレ
ベーターのボタン等)は、次亜塩素酸ナトリウム水溶液による消毒を原則とする
・ 消毒液を雑巾、ペーパータオル等に含ませ拭き取る【足立区独自】
・ 使用した雑巾は再利用、ペーパータオルは通常のゴミと同様に廃棄する【足立区
独自】
・ 消毒は次の機会に実施する【足立区独自】
ア 共用スペースは施設開館前、閉館後のほか、日に数回実施する
イ 会議室等貸出スペースについては、貸出終了ごと、利用者の入替ごとに実施
6 各業種に共通する感染拡大防止の主な取組例
主な取組みは、東京都『事業者向け東京都感染拡大防止ガイドライン~「新しい日常」
の定着に向けて~』【令和2年5月22日】を参照のこと。
 学校開放事業について
学校開放事業について 当面の間、再開を見合わせる。
当面の間、再開を見合わせる。
 6月1日(月曜日)以降の区立小中学校の対応について
6月1日(月曜日)以降の区立小中学校の対応について
一部を除き、5月15日付け新型コロナウイルス対策本部決定の再掲。一部変更箇所は太字で表示。
1 学校再開後の対応
(1)登校方法等
6月1日(月曜日)に学校再開後3週間(6月1日(月曜日)から6月19日(金曜日)まで)、児童・生徒3分の1ずつの分散登校期間とする。
クラスを3分割する、学年で登校日を分けるなど、1日に登校する児童・生徒数が全体の3分の1程度になるよう校長裁量で工夫する。
また、給食(昼食)の提供方法については項番8のとおり。
(2)プール指導等
今年度のプール指導は行わない。
東京都児童・生徒体力・運動能力、生活習慣等調査も実施しない。
(3)休業期間の短縮
ア 夏休み
7月21日(火曜日)から8月31日(月曜日)まで(42日間)で予定している夏季休業期間を8月8日(土曜日)から8月23日(日曜日)まで(16日間)に短縮する。
イ 冬休み
12月26日(土曜日)から1月7日(木曜日)まで(13日間)で予定している冬季休業期間を12月26日(土曜日)から1月5日(火曜日)まで(11日間)に短縮する。
ウ その他
都民の日(足立区民の日)、開校記念日は、授業日として設定する。
エ 学校行事
・小中学校の連合行事は開催しない。
・当面は夏休み前の学校行事を中止し、授業時数を確保する。
・修学旅行(中学校)は実施の方向で検討する。
・自然教室(小・中学校)は教育委員会が校長会と協議して別途判断する。
・全校児童・生徒や保護者、来賓が一堂に集まる学校行事(学芸会、音楽会、合唱コンクール、運動会など)については開催の可否を校長会と調整中。
・今年度の卒業式については感染拡大防止に配慮する形での実施を検討する。
2 その他
国の東京都に対する緊急事態宣言が延長された場合や東京都から臨時休業延長の要請があった場合は、さらに臨時休業を延長する。
8 学校再開に伴う給食(昼食)の提供について
1 分散登校時
(1)6月4日(木曜日)から6月19日(金曜日)まで簡易昼食(※)を提供する。
ただし、アレルギー対応をしている児童生徒には、献立に関わらず(該当食材の有無に関わらず)、簡易昼食を提供しない(弁当持参)。
(※)2品(例:どんぶり、汁物)と牛乳
(2)費用は公費負担とする。
1食単価:小学校:200円、中学校:220円
【アレルギーがある児童生徒への対応】
1食単価×登校日数の費用を支給する。
2 6月22日(月曜日)以降について(予定)
(1)分散登校が解除される6月22日(月曜日)以降、8月末まで夏季休業期間(8月8日から8月23日)を除き、簡易昼食を提供する。
(2)アレルギー対応を行う。費用は保護者負担とする(小学校:200円、中学校:220円)。
【文科省通知】
学校給食(昼食提供)の工夫として、配膳の過程での感染防止のため可能な限り品数の少ない献立で提供する。
※給食調理室の環境も考慮し、調理従事者の負担軽減(調理時間の短縮等)を図る。
(3)通常の給食提供は、9月から実施予定。
9 緊急事態宣言解除を想定した幼稚園・保育施設等の対応について
5月21日(木曜日)に発表された国の緊急事態宣言の内容変更及び、東京都の対応を受け、対応方針を検討する。
1 幼稚園及び保育施設等の再開に向けた準備について
(1)区内幼稚園の再開について
6月1日の再開に向けて準備をするように幼稚園に通知する。
(2)区内保育施設等の再開について
6月1日の再開に向けて準備をするように保育施設等に通知する。
(3)6月1日(月曜日)より保育園を再開するにあたり、感染防止策等について具体的な確認内容を記載したチェックリストを送付するなど十分な注意喚起を行う。
2 緊急特別保育の利用状況について
保育園(子ども家庭部)
申込者は平時の12.5%(5月7日時点)
10 緊急事態宣言解除を想定した学童保育室の対応について
1 学童保育室等の再開に向けた準備について
(1)学童保育室の再開について
6月1日の再開に向けて準備するように各学童保育室等に通知する。
(2)ランドセルで児童館の再開について
6月1日の再開に向けて準備するよう各児童館等に通知する。
(3)6月1日から再開するにあたり、学校の分散登校期間中は学童保育室及びランドセルで児童館ともに1日保育を実施する。また、登下校における、児童の安全確保等について事前に各学校と連携を図るよう通知する。
2 緊急特別保育の実施状況について
登録数は平時の17.2%(5月20日現在)
11 緊急事態宣言解除後の区民事務所の取扱いについて
マイナンバーカード関連事務など応援従事をしていた業務が一定程度円滑に遂行されるようになり、区民事務所職員の応援態勢を解除することが可能となったため、6月1日(月曜日)から全区民事務所を通常開庁体制とする。
 その他細かい内容が区のホームページに掲載されています。
その他細かい内容が区のホームページに掲載されています。
ご質問、ご意見などお気軽にお寄せください。











 <figcaption id="caption-attachment-47058" class="wp-caption-text">記者会見する(左から)大山、田辺、谷川各氏=20日、都庁(「しんぶん赤旗」</figcaption>
田辺・谷川の両氏は検査の実施が極めて低い状況の危険性を指摘。
<figcaption id="caption-attachment-47058" class="wp-caption-text">記者会見する(左から)大山、田辺、谷川各氏=20日、都庁(「しんぶん赤旗」</figcaption>
田辺・谷川の両氏は検査の実施が極めて低い状況の危険性を指摘。

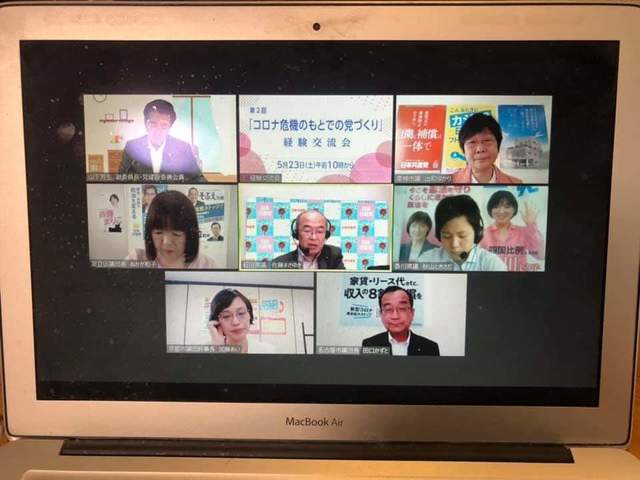
 ある小学校の休校中の保護者通知(一部)
ある小学校の休校中の保護者通知(一部)