
六本木の国立新美術館で開催されている「日展100年展」に行ってきた。最近ますますセレブなトリックスターと化している黒川紀章設計の美術館の建物は、写真で見るより小ぶりに見えるが、バブル時代を髣髴させる壮大な無駄施設という印象だ。美術館というよりイベント施設、体育館の佇まいだが、内部から見ると、平面の連なりが曲面を形成するということが実感できる建物ではある。それと、1階のカフェは生ビールが飲めるのはうれしいが、700円、サンドイッチも650円とちょっとお高い。田舎モン丸出しで言わせてもらえば、国立の施設ならもっと安くしろよ、といいたい。
展示は、文展、帝展を経て日展に至る日本の美術の100年が概観できるという点では楽しめるものだった。とりわけ明治期の画家たちが驚くべきスピードで西洋絵画を吸収しながら独自性を発揮したこと、洋画の影響受けながら100年で変化してきた日本画の変貌ぶりが堪能できておもしろい。鏑木清方「三遊亭円朝像」のオーラ、無を描く日本画の空間表現はあらためてすごいと思う。瓦だけを描いた福田平八郎「雨」、電信柱と空に凶暴な夏を感じる山崎覚太郎「漆器 空 小屏風」など、はじめて見る作品だが、日本画の多様性に触れることができた。
ちなみに、和田三造の代表作「南風」は、四人の漁師を描いたといわれるが、画面右側に麦藁帽を被り弱弱しく座っている人物は、ある画家らしい。その方の孫から聞いた話として知人が教えてくれた。確かに、他の三人に比べると佇まいが違うのだった。
展示は、文展、帝展を経て日展に至る日本の美術の100年が概観できるという点では楽しめるものだった。とりわけ明治期の画家たちが驚くべきスピードで西洋絵画を吸収しながら独自性を発揮したこと、洋画の影響受けながら100年で変化してきた日本画の変貌ぶりが堪能できておもしろい。鏑木清方「三遊亭円朝像」のオーラ、無を描く日本画の空間表現はあらためてすごいと思う。瓦だけを描いた福田平八郎「雨」、電信柱と空に凶暴な夏を感じる山崎覚太郎「漆器 空 小屏風」など、はじめて見る作品だが、日本画の多様性に触れることができた。
ちなみに、和田三造の代表作「南風」は、四人の漁師を描いたといわれるが、画面右側に麦藁帽を被り弱弱しく座っている人物は、ある画家らしい。その方の孫から聞いた話として知人が教えてくれた。確かに、他の三人に比べると佇まいが違うのだった。













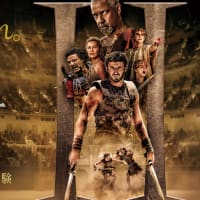













※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます