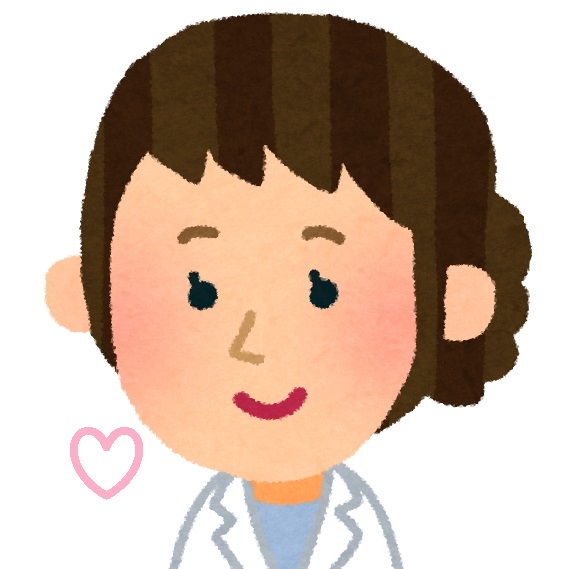現代の私達はなんとなくイメージで「伝統的に日本人は沢山野菜を食べていたが、食の欧米化で野菜を食べなくなった。」と思う傾向があります。雑誌等でそのようなエッセイを見かけることがあります。
しかし、民俗学などの本を調べると、それは思い込みのようです。
例えば、秋田市太平八田(はった)という所では「村の鎮守様は野菜嫌い」という古くからの言い伝えがあり、昭和30年代ごろまでほとんど野菜を食べなかったそうです。
そこまで極端な例ではないにしろ、日本の伝統的食事では穀類が多い割に野菜が少なく、野菜を食べる場合は大根を偏愛し、他の野菜(特に緑黄色野菜)は少量しか食べない傾向がありました。
明治の初頭、1871年に日本に来た元米国農務長官のホーレス・ケプロン氏は、日本の野菜の種類やその摂食量の少なさに驚き、日本政府に米国の野菜・果物の種と苗、そして家畜や農機具を献上して、日本の農畜産業の振興に力を尽くしました。政府はもちろん明治天皇とその家族にも大変喜ばれ、外国人で初の勲二等旭日章を贈与されました。ケプロンの記録によると、当時の日本人は野菜というと大根ばかり食べていたと記されています。
「いや、伝統野菜には沢山の種類があるではないですか?」と疑問に思った方もいるかもしれませんね。実は、非常に限られた種類の野菜の中で、大きさとか色とかのバリエーション(これを専門用語で品種と言います。)が豊富にあったということなのです。例えば大根だと全国ではおそらく100や200を超える品種があっただろうと思いますが、しかし、どれを食べても大根は大根。栄養的にはほとんど変わりが無かったと考えられます。紫の大根でしたらポリフェノールも摂取できるかもしれませんが、日本人は白くて大きい大根を好む傾向が強かったので、そうした大根はめったに食べられませんでした。
江戸時代に食べられていた野菜の種類は、大根、なす、カブ、漬け菜、ゴボウ、里芋、白瓜、ネギ等が主体でした。キュウリ、ニンジン、スイカなどは品種があまり多く生じなかったといわれます。そのほかは山から山菜を採取したり、ミョウガ等を食べていましたが、長期保存可能なゼンマイなどの一部を除けば、山菜等はほんの1~2週間の旬の間だけ食べていたとみられるため、一年を通じての健康の維持には余り役立ったとは言えません。
しかも、ほうれん草については「大和本草」中で貝原益軒氏が「多食してはいけない。身体に毒である。」と唱えていました。キュウリは、江戸中期までは苦みが強くて「下品(げぼん:価値が最低のこと)」とされて(旬の前の「はしり」の時には江戸っ子は珍しがって買いましたが、それ以外の時期は)嫌われており、特に武家では切り口が葵の御紋に似ているからと禁じられました。このように、大根以外の野菜は少量食べられていたのです。キャベツやアスパラガス、セロリは江戸時代までには日本に伝来していましたが、ほとんど食用にされませんでした。
白菜、タマネギ、トマト、ブロッコリー、オクラ、ピーマンなどの今日良く食べられる野菜は、明治以降に日本に伝わったものです。今では白菜は和食に欠かせないものとなりましたが・・・・。現在私達が食べているカボチャ、ニンジン、レタスの品種も、ほとんどが明治以降に外国からもたらされた品種です。
明治時代以降、次第に野菜を食べることが健康によいと知られはじめ、栄養学の関係者は野菜を勧めたのですが、明治以降から第二次世界大戦までの時代も、あまり野菜は食べられませんでした。そうなった理由ははっきりしませんが、おそらくは「穀食主義」の流行の影響もあったのではないかと推測します。
「穀食主義」について説明します。明治40年に石塚左玄氏を中心として発足した「食養会」(前々回のこのブログでも登場した団体です。)は「玄米には人体に必要なほとんどの栄養が詰まっている。」として肉は要らないどころが、野菜さえもごく少量食べるだけで十分だと唱えました。これが現在の玄米食運動の起源なのですが、現在の玄米食運動では野菜も推奨されますが、当時は野菜さえ少なくて良いと唱えたので「穀食主義」と呼ばれていたのです。
食養会は昭和に入ると人気になり、日本各地の知識人に「玄米さえ食べれば野菜は少量で十分」という説が広まりました。例えば昭和6年(1931年)に宮沢賢治が「雨ニモ負ケズ」という詩の中で「一日ニ玄米四合ト味噌ト少シノ野菜ヲタベ」と書いた様に、野菜は少しでいいのだという考えは知識人の間で人気になったようです。
1931~35年の1人1日あたり野菜摂取量は220.7gです。当時の統計の取り方は現代とは異なりますので単純比較は難しいのですが、農水省の食料需給表によると、戦後の高度経済成長を経て日本人の食事のアメリカナイズが進んだ昭和43年には、野菜の1人1日当たり供給純食料(野菜からヘタや皮など食べられない部分を除いた量。)が340.4gです。昭和初期にいかに野菜の摂取量が少なかったかが分かります。
昭和初期、石塚氏の説に影響を受けた医師、二木謙三博士も、石塚氏の説と似たような説を唱えて評判となりました。昭和17年には東条英機首相の夫人が二木先生の大ファンとなり、これを通じて首相や閣僚もすっかり玄米食ファンになり、とうとう閣議で「国民は玄米食をしなければならない。」と決定されました。そして「玄米さえ食べればおかずはほとんど不要、お弁当も玄米と梅干しだけの『日の丸弁当』で良い。」という説が国民に広められました。このように、日本では野菜にとって長く不遇な時代が続いたのです。
ただし、大根はお米と一緒に炊くとお米が増えたように見えるため、お米が余り手に入らない貧しい家庭では、大根を刻んでお米に混ぜて炊く「大根飯」を沢山食べていたようです。また、大根に限らず様々な野菜を混ぜて炊く場合もあり、これは「糧飯(かてめし)」と呼ばれていましたが、糧飯の多くも野菜は大根主体だったようです。他の野菜はやっぱり少量食べられていました。キュウリは明治以降中国から入った品種の影響で苦みが減り、比較的食べられるようになりましたが、緑黄色野菜は相変わらずあまりたべられなかったそうです。
日本人がいろいろな種類の野菜を沢山食べる様になったのは第二次世界大戦後の事で、米国文化の影響や、マスコミや栄養士が野菜をたべようと宣伝し、普及員(農家向けに栽培技術や生活面を指導をした県の職員)が野菜生産を振興しようと農家に勧めた影響だと言われます。特に緑黄色野菜の大切さは各方面が強調しました。つまり、食の欧米化のおかげで日本人は他種類の野菜を食べる様に変化したのです。
参考文献:「ホーレス・ケプロン将軍」メリット・スター著 北海道出版企画センター
「食生活の中の野菜」施山紀男著 養賢堂
しかし、民俗学などの本を調べると、それは思い込みのようです。
例えば、秋田市太平八田(はった)という所では「村の鎮守様は野菜嫌い」という古くからの言い伝えがあり、昭和30年代ごろまでほとんど野菜を食べなかったそうです。
そこまで極端な例ではないにしろ、日本の伝統的食事では穀類が多い割に野菜が少なく、野菜を食べる場合は大根を偏愛し、他の野菜(特に緑黄色野菜)は少量しか食べない傾向がありました。
明治の初頭、1871年に日本に来た元米国農務長官のホーレス・ケプロン氏は、日本の野菜の種類やその摂食量の少なさに驚き、日本政府に米国の野菜・果物の種と苗、そして家畜や農機具を献上して、日本の農畜産業の振興に力を尽くしました。政府はもちろん明治天皇とその家族にも大変喜ばれ、外国人で初の勲二等旭日章を贈与されました。ケプロンの記録によると、当時の日本人は野菜というと大根ばかり食べていたと記されています。
「いや、伝統野菜には沢山の種類があるではないですか?」と疑問に思った方もいるかもしれませんね。実は、非常に限られた種類の野菜の中で、大きさとか色とかのバリエーション(これを専門用語で品種と言います。)が豊富にあったということなのです。例えば大根だと全国ではおそらく100や200を超える品種があっただろうと思いますが、しかし、どれを食べても大根は大根。栄養的にはほとんど変わりが無かったと考えられます。紫の大根でしたらポリフェノールも摂取できるかもしれませんが、日本人は白くて大きい大根を好む傾向が強かったので、そうした大根はめったに食べられませんでした。
江戸時代に食べられていた野菜の種類は、大根、なす、カブ、漬け菜、ゴボウ、里芋、白瓜、ネギ等が主体でした。キュウリ、ニンジン、スイカなどは品種があまり多く生じなかったといわれます。そのほかは山から山菜を採取したり、ミョウガ等を食べていましたが、長期保存可能なゼンマイなどの一部を除けば、山菜等はほんの1~2週間の旬の間だけ食べていたとみられるため、一年を通じての健康の維持には余り役立ったとは言えません。
しかも、ほうれん草については「大和本草」中で貝原益軒氏が「多食してはいけない。身体に毒である。」と唱えていました。キュウリは、江戸中期までは苦みが強くて「下品(げぼん:価値が最低のこと)」とされて(旬の前の「はしり」の時には江戸っ子は珍しがって買いましたが、それ以外の時期は)嫌われており、特に武家では切り口が葵の御紋に似ているからと禁じられました。このように、大根以外の野菜は少量食べられていたのです。キャベツやアスパラガス、セロリは江戸時代までには日本に伝来していましたが、ほとんど食用にされませんでした。
白菜、タマネギ、トマト、ブロッコリー、オクラ、ピーマンなどの今日良く食べられる野菜は、明治以降に日本に伝わったものです。今では白菜は和食に欠かせないものとなりましたが・・・・。現在私達が食べているカボチャ、ニンジン、レタスの品種も、ほとんどが明治以降に外国からもたらされた品種です。
明治時代以降、次第に野菜を食べることが健康によいと知られはじめ、栄養学の関係者は野菜を勧めたのですが、明治以降から第二次世界大戦までの時代も、あまり野菜は食べられませんでした。そうなった理由ははっきりしませんが、おそらくは「穀食主義」の流行の影響もあったのではないかと推測します。
「穀食主義」について説明します。明治40年に石塚左玄氏を中心として発足した「食養会」(前々回のこのブログでも登場した団体です。)は「玄米には人体に必要なほとんどの栄養が詰まっている。」として肉は要らないどころが、野菜さえもごく少量食べるだけで十分だと唱えました。これが現在の玄米食運動の起源なのですが、現在の玄米食運動では野菜も推奨されますが、当時は野菜さえ少なくて良いと唱えたので「穀食主義」と呼ばれていたのです。
食養会は昭和に入ると人気になり、日本各地の知識人に「玄米さえ食べれば野菜は少量で十分」という説が広まりました。例えば昭和6年(1931年)に宮沢賢治が「雨ニモ負ケズ」という詩の中で「一日ニ玄米四合ト味噌ト少シノ野菜ヲタベ」と書いた様に、野菜は少しでいいのだという考えは知識人の間で人気になったようです。
1931~35年の1人1日あたり野菜摂取量は220.7gです。当時の統計の取り方は現代とは異なりますので単純比較は難しいのですが、農水省の食料需給表によると、戦後の高度経済成長を経て日本人の食事のアメリカナイズが進んだ昭和43年には、野菜の1人1日当たり供給純食料(野菜からヘタや皮など食べられない部分を除いた量。)が340.4gです。昭和初期にいかに野菜の摂取量が少なかったかが分かります。
昭和初期、石塚氏の説に影響を受けた医師、二木謙三博士も、石塚氏の説と似たような説を唱えて評判となりました。昭和17年には東条英機首相の夫人が二木先生の大ファンとなり、これを通じて首相や閣僚もすっかり玄米食ファンになり、とうとう閣議で「国民は玄米食をしなければならない。」と決定されました。そして「玄米さえ食べればおかずはほとんど不要、お弁当も玄米と梅干しだけの『日の丸弁当』で良い。」という説が国民に広められました。このように、日本では野菜にとって長く不遇な時代が続いたのです。
ただし、大根はお米と一緒に炊くとお米が増えたように見えるため、お米が余り手に入らない貧しい家庭では、大根を刻んでお米に混ぜて炊く「大根飯」を沢山食べていたようです。また、大根に限らず様々な野菜を混ぜて炊く場合もあり、これは「糧飯(かてめし)」と呼ばれていましたが、糧飯の多くも野菜は大根主体だったようです。他の野菜はやっぱり少量食べられていました。キュウリは明治以降中国から入った品種の影響で苦みが減り、比較的食べられるようになりましたが、緑黄色野菜は相変わらずあまりたべられなかったそうです。
日本人がいろいろな種類の野菜を沢山食べる様になったのは第二次世界大戦後の事で、米国文化の影響や、マスコミや栄養士が野菜をたべようと宣伝し、普及員(農家向けに栽培技術や生活面を指導をした県の職員)が野菜生産を振興しようと農家に勧めた影響だと言われます。特に緑黄色野菜の大切さは各方面が強調しました。つまり、食の欧米化のおかげで日本人は他種類の野菜を食べる様に変化したのです。
参考文献:「ホーレス・ケプロン将軍」メリット・スター著 北海道出版企画センター
「食生活の中の野菜」施山紀男著 養賢堂