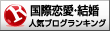http://freeimagescollection.com
(愛する)人を亡くすという押しつぶされるような重圧感と、例えようのない損失感は、残された者を暗闇の奈落へ落とす。ただただその暗闇の底でひっそりと潜み、隠れていたい。本当に明日が来るのだろうか。光がさすのだろうか?

https://onlybigbang.files.wordpress.com/2011/05/so-sad.jp
学校に上がる前の弟と私は、ある日庭に、亀がいるのを発見した。 横浜市内の家だったが、やや山間と言える場所で、夜は街灯の柱に、よくヤモリが貼り付いていた。 亀を見つけて、興奮気味に二人は、母親を呼び、母親は、じゃあ、これから野毛山動物園に預けてきましょうか、と言った。 幼い私達でも、亀はうちの庭にいるよりも、動物園で飼われたほうが幸せだろうと思ったので、その日のうちに亀を小さな入れ物にいれて、母と弟と手をつないで野毛山へ行くバスに乗った。動物園の人は、快く亀を引き受けてくれて、私達は、その亀が池に放たれるのを見てから、帰途についた。
小学校低学年の頃は、地蜘蛛取りに夢中になった弟と私。 我家だけではなく、他所のお宅へにもお邪魔した。 縁側の下を覗くと、大抵その蜘蛛は巣を作っていた。 それを採取しても、結局は原っぱに行って、放したのだが、そんなことを、弟とするのが楽しかった。 少し経つと、弟は父親から、昆虫採集セットを貰い、私も捕虫網を母に買って貰って、その夏、弟と私はファーブルの「弟子」となった。ある日は、二人共長靴を履いて、青々とした田んぼ道から水田を覗き、ちょろちょろと泳ぐオタマジャクシを持ってきた瓶に掬って、意気揚々として家に帰った。
「それ、もうすぐ皆カエルになるのよ? そんな大勢のカエル、どうするの? みんな、おうちに帰りたいと、泣くわよ。かわいそうだなあ。」と言った長姉の最後の一言で、弟と私は、翌朝早々、水田にオタマジャクシを「帰宅」させたのだった。その帰り道、水田の一部が水を抜き取られ、赤みがかった底土が、ひっくり返されていたのを見た。そこが、新しい住宅地になるらしいと、父母が話していたっけ。
宅地造成作業は、早急に進まず、1年ほどは赤い土が台状に盛り上げられているだけで、勿論そこは弟と私の「秘密基地」となったのは言うまでもない。ただの赤い盛り土に過ぎなかったのに、そこで弟と私は、宇宙からやってくる敵や、ジャングルを流れる河のワニと戦ったり、恐るべき空想力で遊んだのである。私はお転婆ではなかったが、弟といると、今で言えば、インデイアナ・ジョーンズにも、ハンス・ソロにもなれたのだった。
それが、いつの間にか弟は弟の、そして私は私の道を離れ離れで進み始め、二人で一緒に何かをすることは、もうなかった。それが成長というものらしかった。弟は数学に夢中になり、私は、あのWinnie The Pooh(クマのプーさん)のように、頭はStuffed with Fluff(ふわふわの雲のようなものが詰められている頭)の人になった。
やがて私は結婚し、五回母となり、もう一組半の手があれば、と願う毎日になり、弟は、数学教師となった途端、結婚を考えていた女性が不意に病死してしまった。たくさんの生徒を東大にまで進ませた教師は、孤高の道を行くかのように生き、自然の中に安らぎを求め、そして行き場のない猫を可愛がった。
そして初雪の早朝、弟は静かに逝った。発病から短期間ではあったが、姉一家に手厚く看病され、看取られて。その一週間前私は病床にある弟に、心のうちを綴った手紙を出した。弟がそれをじっくりと読み、例のニヒルな笑みを浮かべて、綺麗にたたんで、封筒に戻して、それを枕の下に入れたのよ、と姉は言った。姉は棺の中にその手紙を入れてくれた。その手紙の最後に私は、書いた:私から逃れようとしてもそう簡単には逃げられないの。今は信じないでしょうが、私は貴方に再会すると決めているの。その時、本当だったねえ、と言うわよね、貴方は。
弟の遺品を整理していたら、黒船のマシュー・ペリー提督の本をいくつか見つけた。比較的新しく購入していたので、思わず私は、「やっぱり。」と微笑まずにはいられなかった。その頃私は、系図調査関係で、ペリー提督の家系について、調べていたからである。同じ頃、同じことに興味を持っていたのは、昔と全く変わっていない。弟、私は貴方にまた会う時を心から楽しみにしているわよ。
今日12月12日のクリスマス・カレンダーは、「悲しんでいる人たちは幸いである。(彼らは慰められるであろう。)」(マタイ伝5:4)である。深い悲しみのうちにある方には、話したいことを話したいならば、いつでもお聞ききします、とメモをつけて食事を持って行く。泣くだけ泣いて、気の済むまで泣いて、疲れたら私の肩に頭を置けます、とも。弟が逝った時、夫も子供達も、私が話したい時だけ、話を聞いてくれた。泣きたい時には、夫が胸を貸してくれた。そこで私は千の慰めを得た。