
先日、進学校でもなんでもないごく普通の公立高校から国立大学へ飛躍的に進学した人の話を聞きました。その人も歴史は苦手科目だったのに受験の前には日本史も世界史も、もう勉強しなくても大丈夫、どんな問題が出てもたいていわかる、というレベルまで達してしまったのだそうです。
苦手科目を得意科目にするのは並大抵の努力ではなかったと思います。文字通り死に物狂いで勉強されたようです。そして、その人が言ったことは
とにかく書く!!
それに尽きるそうです。今の検定テキストって歴史が1ページにきれいにまとめて書かれているでしょう。あれ、とても便利なんですが、考えようによっては自分なりにまとめたほうが、より身につくのかなとも思えます。
せっかくあるのだから有効利用したほうがいいので、あのページをノートに書き写すだけでもやらないよりはいいかと思います。付け加えるのなら自分なりに色分けして表にしてトイレに貼ってもいいでしょう。
歴史以外の勉強にも通じることですが、
試験範囲外にも目を向ける
ことも大切だと思います。
1.視覚的に覚える
どんな偉い人でもその顔がわかると割と親近感が沸くものです。図書館で文献を漁るのもいいし、もっと手短にインターネットを駆使して顔写真を入手してみましょう。
2.ほかの歴史と絡めてみる
例えば日本史が得意なら関が原が1600年、このころのアロマ史ではジェラードやパーキンソンなどのハーバリストが活躍した時代。
イブン・シーナ(980ー1037)の時代は日本では900年『竹取物語』、935年『土佐日記』、1001年『枕草子』、1011年『源氏物語』など王朝文学が栄えていた優雅で平和な時代だった・・・なんて。
ただ、アロマの歴史って割とすかすかなので他の歴史と絡めるにも絡めずらい。
3.時代背景を知る
上とも関連するが、この時代のこの国はどんなだったとあらじめ調べる。アロマ史はとびとびなのでこれも骨が折れる作業かもしれない。ただ無駄にはならないし、世界の大きな流れの中にアロマがどんなふうに絡んできたのかを調べればわかりやすいでしょう。
4.ドラマで覚える
大河ドラマで放送された人物は印象に残るので、その人の活躍した時代の歴史に詳しくなったりするものです。そこで関連する人物の人生をストーリーじたてで覚えるとはいりやすいんじゃないかな。といってもアロマ史に登場する人物ってヒポクラテスのように物凄く昔の人物かガットフォセみたいに比較的最近の人物なので、歴史的に取り上げられずらいんですよね。
以上のことを踏まえておすすめなのがウィキペディア。ウィキリークスじゃないですよ。ヒポクラテスからイブン・シーナ辺りの偉人は割りと詳しく書いてあります。どの程度正確かはわからないけど一応肖像画も載ってます。
逆に17世紀のハーバリストから後は英語版のほうに詳しく載ってます。英語があまり得意じゃない人は地道に検索してください。
面白いなと思うのは、イブン・シーナ=蒸留法、ガレノス=コールド・クリームといったキーワードはアロマの世界では結構重要なことなんですが、ウィキペディア読んでみるとガレノスについては解剖などの記述はあってもコールドクリームっていうキーワードも見当たらない。イブン・シーナの蒸留法も然り。
ついでにプリニウスの『博物誌』は植物、動物、鉱物などの自然についての記述だけでなく、地理とか歴史とか科学などにも及んだ、どちらかというと百科事典的なものだったようです。しかも動物の中にペガサス、ユニコーン、バジリスク、フィニックス、人魚、半獣神などが真面目に載っていたみたいです。
もうひとつ序でに面白かったのが暴君ネロ。アロマ史では薔薇が好きだったこととプリニウスを雇っていたことぐらいしか出てきませんが、この人の経歴調べてみるといろんな逸話が出てきて飽きない。暴君であったけど画期的に社会のシステムを作り直したり(これは側近の業績かもしれませんが)、新しいものはどんどん取り入れたり、風流人でもあり自ら竪琴を鳴らしながら歌を歌ったり、当時さげすまれていたパフォーマンスを栄えさせた人物でもあった。また、変な趣味もあって、自ら女装したり美少年を側女にしたとも。読んでいて織田信長を思い出してしまいました。
冒頭に出てきた歴史が苦手だったけど得意になってしまった方が言うには、
勉強ってそれぞれ独立したものじゃなくて実は繋がっているんだ。ひとつの科目を勉強していくうちに別の科目で習ったことが関連して出てくる。すると、ああそうなんだと納得する。それでそういった勉強が必要なんだとわかる。
なんとなくわかります。勉強というか生きていくための知恵はいろんな学問の中に織り込まれていて、別のアプローチで辿りついた知識が出会ってそこで知恵として身に付く・・・・う~~ん。上手く表現できない。


↑ポチっとよろしく↑お願いします。
※トラックバックを送られる方は、コメント欄にひとことお書きください。コメントのないもの、記事の内容と関連のないものは削除させていただきます。
苦手科目を得意科目にするのは並大抵の努力ではなかったと思います。文字通り死に物狂いで勉強されたようです。そして、その人が言ったことは
とにかく書く!!
それに尽きるそうです。今の検定テキストって歴史が1ページにきれいにまとめて書かれているでしょう。あれ、とても便利なんですが、考えようによっては自分なりにまとめたほうが、より身につくのかなとも思えます。
せっかくあるのだから有効利用したほうがいいので、あのページをノートに書き写すだけでもやらないよりはいいかと思います。付け加えるのなら自分なりに色分けして表にしてトイレに貼ってもいいでしょう。
歴史以外の勉強にも通じることですが、
試験範囲外にも目を向ける
ことも大切だと思います。
1.視覚的に覚える
どんな偉い人でもその顔がわかると割と親近感が沸くものです。図書館で文献を漁るのもいいし、もっと手短にインターネットを駆使して顔写真を入手してみましょう。
2.ほかの歴史と絡めてみる
例えば日本史が得意なら関が原が1600年、このころのアロマ史ではジェラードやパーキンソンなどのハーバリストが活躍した時代。
イブン・シーナ(980ー1037)の時代は日本では900年『竹取物語』、935年『土佐日記』、1001年『枕草子』、1011年『源氏物語』など王朝文学が栄えていた優雅で平和な時代だった・・・なんて。
ただ、アロマの歴史って割とすかすかなので他の歴史と絡めるにも絡めずらい。
3.時代背景を知る
上とも関連するが、この時代のこの国はどんなだったとあらじめ調べる。アロマ史はとびとびなのでこれも骨が折れる作業かもしれない。ただ無駄にはならないし、世界の大きな流れの中にアロマがどんなふうに絡んできたのかを調べればわかりやすいでしょう。
4.ドラマで覚える
大河ドラマで放送された人物は印象に残るので、その人の活躍した時代の歴史に詳しくなったりするものです。そこで関連する人物の人生をストーリーじたてで覚えるとはいりやすいんじゃないかな。といってもアロマ史に登場する人物ってヒポクラテスのように物凄く昔の人物かガットフォセみたいに比較的最近の人物なので、歴史的に取り上げられずらいんですよね。
以上のことを踏まえておすすめなのがウィキペディア。ウィキリークスじゃないですよ。ヒポクラテスからイブン・シーナ辺りの偉人は割りと詳しく書いてあります。どの程度正確かはわからないけど一応肖像画も載ってます。
逆に17世紀のハーバリストから後は英語版のほうに詳しく載ってます。英語があまり得意じゃない人は地道に検索してください。
面白いなと思うのは、イブン・シーナ=蒸留法、ガレノス=コールド・クリームといったキーワードはアロマの世界では結構重要なことなんですが、ウィキペディア読んでみるとガレノスについては解剖などの記述はあってもコールドクリームっていうキーワードも見当たらない。イブン・シーナの蒸留法も然り。
ついでにプリニウスの『博物誌』は植物、動物、鉱物などの自然についての記述だけでなく、地理とか歴史とか科学などにも及んだ、どちらかというと百科事典的なものだったようです。しかも動物の中にペガサス、ユニコーン、バジリスク、フィニックス、人魚、半獣神などが真面目に載っていたみたいです。
もうひとつ序でに面白かったのが暴君ネロ。アロマ史では薔薇が好きだったこととプリニウスを雇っていたことぐらいしか出てきませんが、この人の経歴調べてみるといろんな逸話が出てきて飽きない。暴君であったけど画期的に社会のシステムを作り直したり(これは側近の業績かもしれませんが)、新しいものはどんどん取り入れたり、風流人でもあり自ら竪琴を鳴らしながら歌を歌ったり、当時さげすまれていたパフォーマンスを栄えさせた人物でもあった。また、変な趣味もあって、自ら女装したり美少年を側女にしたとも。読んでいて織田信長を思い出してしまいました。
冒頭に出てきた歴史が苦手だったけど得意になってしまった方が言うには、
勉強ってそれぞれ独立したものじゃなくて実は繋がっているんだ。ひとつの科目を勉強していくうちに別の科目で習ったことが関連して出てくる。すると、ああそうなんだと納得する。それでそういった勉強が必要なんだとわかる。
なんとなくわかります。勉強というか生きていくための知恵はいろんな学問の中に織り込まれていて、別のアプローチで辿りついた知識が出会ってそこで知恵として身に付く・・・・う~~ん。上手く表現できない。


↑ポチっとよろしく↑お願いします。
※トラックバックを送られる方は、コメント欄にひとことお書きください。コメントのないもの、記事の内容と関連のないものは削除させていただきます。










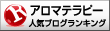
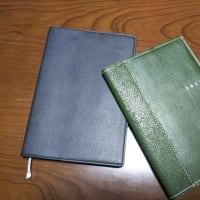















私も国家試験勉強をしている時にこれを実感しました。
アンダーラインを引くだけで満足している人ほど勉強の仕方がわからないなんていってた気がします。
書かなきゃ覚えられないし、それも独自に絵を描いたりすることでさらに覚えやすかったです。
学校に入る前に歯科助手で経験を積んで、点レベルの理解だったのが、学校に入って勉強することで点と点が線で繋がる感じがとても楽しく、勉強が嫌になることはあまりなかったように思います。
私は恵まれていたんですね☆
そうなんですよね。私も上手くいえないけど、たいせつなことって繋がっている。古代ギリシャやローマの偉人は哲学者であって数学者であって医者であって芸術家であった・・・ように。
私も書かないと覚えられないほうですが、書くことっていわゆる「咀嚼」だと思うんですね。どんなに栄養のあるものでも飲み込んでしまうと上手く消化できなくて栄養にもなりずらい。咀嚼することで消化されやすく吸収されやすくなるんでしょうね。