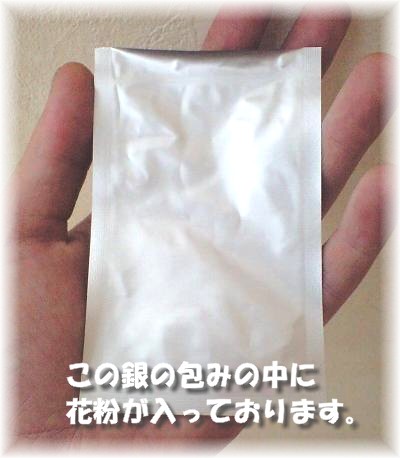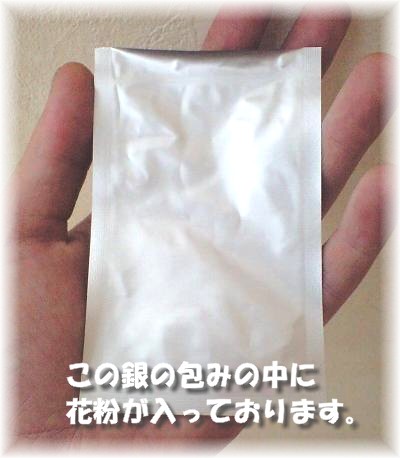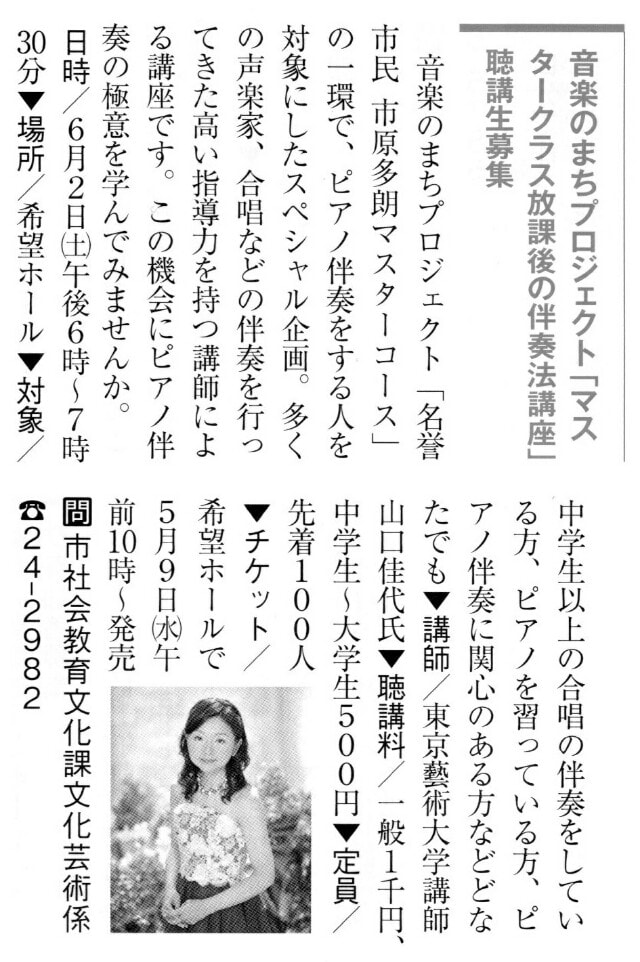音楽のまちプロジェクト 市原多朗マスターコースが酒田市民会館希望ホールで開かれ,関連でピアノ伴奏として来酒された芸大講師の山口佳代さんによる「伴奏法講座」があったため聴講してきた。
本体のマスターコースは部門ではあるが,合唱指揮者の立場では伴奏法の方が参考になるであろうと聴いたもの。
前半は芸大の講義で聞けそうな,本来の伴奏とは?という高度な話。
日本では,ソロの歌や楽器にピアノ,という組み合わせでは,殆どの場合に「ピアノ伴奏」と言われてしまうが欧米では単に「ピアノ」とされ,位置づけも添え物でなくてセッションしている場合が多い。
オペラなどでも,レチタチーヴォと伴奏の役割がはっきりしている場合が多い,等々。
実演では①合唱のピアノ伴奏のみ,②独唱+ピアノ,③女声二部合唱+ピアノという3パターンを指導された。
①は,指揮者も合唱もいない中「歌や指揮があるとすれば」と仮定したイメージトレーニングとなった。
曲に変化のつく直前にいきなり不協和音になる理由がある⇒合唱を誘引するようにはっきり弾かねばならない。
同じ歌を歌っていくのに,なぜピアノだけ奏法を変えているのか⇒日本語からドイツ語に変わり子音が変化するからであろう。
②では,歌い手は呼吸するがピアノは呼吸しないため,音が詰まる傾向にあるのでタイミングを合わせる。
どこで音を落ち着かせるか決めて演奏する(フレージングのような話)
右手の和音の1音が歌とかぶり邪魔する場合は,その音のみを弱くする。
伸ばす音のあとに,ペダルを踏みつつ次の不協和音を出す場合,高等テクだけど,ソフトペダルを使うことも必要だ(ここは初めて知った)
③でやっと合唱の出番になるが,未知というか不知の女声"コーラス"で,ピアノ側だけが指導されるのはどうかと思った。
ので,ピアノ側の注意事項は際立った面を1点だけ..(普通のことですが)
伴奏から始まる場合や間奏などは,もっと自分を主張するようにし,合唱の入りの部分を合わせる。
そして場面変化のある時は,必要に応じ合唱をリードする。
(③は総じてベーシックな話)
以上は指摘の一例で,かつ,全てケース・バイ・ケースと理解したけれど,私が気付いた点ともかなり重複していたし,その理論も十分に理解できるものだった。
普段はなかなか言えていないことだが,ピアニストの方と共通理解していかないとだめだな,と思わされた。
今回の行事本体であるソリストのレッスンよりは,こっちの方が自分には合っていたな,とも思った。