実践編が「動」ならば、こちらは「静」。
糸をほどいて、ふたたび縒っていくようにして、思考と感情をみつめなおし、
心と身体をつないでいきます。
座禅のように「無になる」というよりも、身体が発している信号を素直に受け取って、
呼吸をしながら、対話のチャンネルを作るような感じです。
それでは今日の「観察」の記録から。
両方の瞼を閉じてしばらくしていると、
目の回りの筋肉の緊張がほぐれてくる。
とくに左の眉のあたりの緊張が強かったせいか、
そこがほぐれていくにしたがって、両方の瞼を力を抜いて、左右均等に
柔らかく閉じることができた。
それに加えて、眉間の緊張がほどけた。
呼吸をしてしばらくリラックスしていると両肩が落ちてきた。
喉の下から鎖骨の付け根にかけての詰まりが流れると、気分が良くなった。
さらに左右の坐骨がしっかりと床を捉えるのが感じられた。
15分ほど、気持ちの良い時間を過ごすことができました。
日によってほぐれる部分、開いてくる部分が違うのがおもしろいです。
今回は喉の下、ここは幼少期に気管支喘息をやったところなので
個人的には詰まりやすい部分。

第5チャクラ。
色は水色。自己表現に関する部分だそうですね。
この部分が緩むと肩がスッと落ちて、身体のなかを安心感が拡がります。
困ったことや悩みなども、その時の身体に聴いてみれば、何かしらの応答が
返ってくるのが不思議なところです。
<姿勢>
仰向け、胡坐など、楽な姿勢であればどんな姿勢でも構いません。
<呼吸>
胸式呼吸、腹式呼吸、なんでも構いません。
最初から深い呼吸をしようとせず、ありのままの今の呼吸をみつめることから
はじめましょう。
<意識の方向>
身体の内部にどこか違和感があれば、そこに集中します。
見つめていると、ときどき身体の方から「ここだよ…」と信号を発してくれる
ことがあります。そういうときはそちらに意識をむけてあげましょう。
その部分に軽く触れたり、揺さぶったり、意識を向けやすいように姿勢を変えても
構いません。
<もしも…>
あたまのなかにネガティブな考え、
たとえば「こないだあの人なんであんなこと言ったんだろう」とか、
「この先が不安だ、、」などの感情が起きてきたら、それをそのまま認めて
あげましょう。自分がこういう思考や感情を持っているんだ、ということを
認識して、決してそれを否定しようとせず、大事に包んであげてください。
糸をほどいて、ふたたび縒っていくようにして、思考と感情をみつめなおし、
心と身体をつないでいきます。
座禅のように「無になる」というよりも、身体が発している信号を素直に受け取って、
呼吸をしながら、対話のチャンネルを作るような感じです。
それでは今日の「観察」の記録から。
両方の瞼を閉じてしばらくしていると、
目の回りの筋肉の緊張がほぐれてくる。
とくに左の眉のあたりの緊張が強かったせいか、
そこがほぐれていくにしたがって、両方の瞼を力を抜いて、左右均等に
柔らかく閉じることができた。
それに加えて、眉間の緊張がほどけた。
呼吸をしてしばらくリラックスしていると両肩が落ちてきた。
喉の下から鎖骨の付け根にかけての詰まりが流れると、気分が良くなった。
さらに左右の坐骨がしっかりと床を捉えるのが感じられた。
15分ほど、気持ちの良い時間を過ごすことができました。
日によってほぐれる部分、開いてくる部分が違うのがおもしろいです。
今回は喉の下、ここは幼少期に気管支喘息をやったところなので
個人的には詰まりやすい部分。

第5チャクラ。
色は水色。自己表現に関する部分だそうですね。
この部分が緩むと肩がスッと落ちて、身体のなかを安心感が拡がります。
困ったことや悩みなども、その時の身体に聴いてみれば、何かしらの応答が
返ってくるのが不思議なところです。
<姿勢>
仰向け、胡坐など、楽な姿勢であればどんな姿勢でも構いません。
<呼吸>
胸式呼吸、腹式呼吸、なんでも構いません。
最初から深い呼吸をしようとせず、ありのままの今の呼吸をみつめることから
はじめましょう。
<意識の方向>
身体の内部にどこか違和感があれば、そこに集中します。
見つめていると、ときどき身体の方から「ここだよ…」と信号を発してくれる
ことがあります。そういうときはそちらに意識をむけてあげましょう。
その部分に軽く触れたり、揺さぶったり、意識を向けやすいように姿勢を変えても
構いません。
<もしも…>
あたまのなかにネガティブな考え、
たとえば「こないだあの人なんであんなこと言ったんだろう」とか、
「この先が不安だ、、」などの感情が起きてきたら、それをそのまま認めて
あげましょう。自分がこういう思考や感情を持っているんだ、ということを
認識して、決してそれを否定しようとせず、大事に包んであげてください。














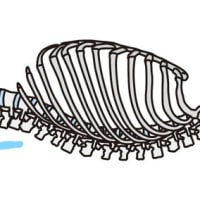

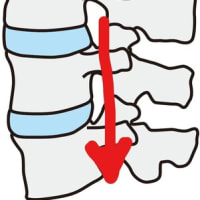
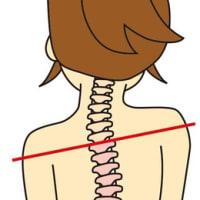
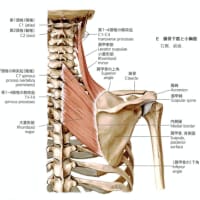

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます