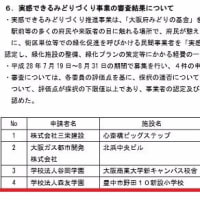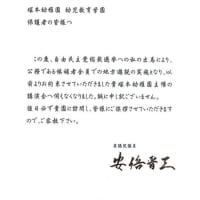27日、厚労省が2040年までの人口の見通しを明らかにした。それによると7割の市町村で20%超の減の見通しだという。殆どの今朝の新聞の一面トップの記事である。しかしながらこれは今わかった分けではなく、投稿者も別に人口問題の研究者ではありませんが以前にも触れましたが、全く因果関係が明らかなわけで、それに何の対処もしない特に自民党政権の政策にその原因が有るとしか言いようが無いでありましょう。
まずデータ的にはっきりしているのは30代男性で年収300万円未満になると婚姻率が格段に下がる(内閣府、結婚家族形成についての意識調査)2010年でそれは26.5%→9.3%である。http://www2.ttcn.ne.jp/honkawa/2451.html
また雇用形態で言えば30-34才男性の婚姻率は
正社員:59.6% 、非典型雇用30.2%(内閣府[子ども・子育て白書]2011年版)であり、非正社員の婚姻率は圧倒的に低い。
また
子育てにかかる負担として大きいと思われる事は何か?と言う問いに
①学校教育費(大学、短大、専門学校)が68.9%
②学習塾など学校以外の教育費47.2%
③保育所、幼稚園、認定子ども園にかかる費用34.8%
④学校教育費(小学校、中学校、高校)31.5%
⑤学習塾以外の習い事の費用17.0%
となっており教育に関する費用が大きいことを伺わせる。内閣府[子ども・子育てビジョンに係わる点検、評価のための指標調査 報告書](2012年3月 資料全労連春闘白書p89)
またそれを裏付ける調査としてはOECD諸国の中で”一般政府支出中に占める公財政教育支出”は加盟国中、最下位である。(同白書p88)
これを見れば何故、人口が急減に向かっているかは全く一目瞭然である。90年代半ば以降急上昇してる非正規の拡大(現在も”雇用流動化”等言ってそれを拡大するつもりである)
本音では最低賃金制度の廃止等唱える某維新等も同罪である。
更に”景気対策”と称して公共事業に毎年20兆円も使おうとしているその見通しの無さ加減、公支出は究極的にはその国の産業構造に影響を与えるわけであり、このままの方向で行けば日本は悪い意味で”土建国家”に向いているとしか言いようが無い。教育や福祉は”無駄金”、”消費的”と一部では捉えられているが、それは当然その分野の雇用を増やし”産業”になるわけであり、上記需要に適うものであり、公教育分野への公的支出の増はその分家庭の支出が削減され、他の分野の個人消費へと資金が向かい全体としての個人消費の拡大になる。その辺の理解がないと2040年には上記報告書のとおりになるでありましょう。