猫の本を5冊、続けて読んだ。(正確にはタイトルに「猫」のつく本。)
昔猫を飼っていて、飼わなくなってから6年くらい経つ。今はもっぱら野良猫を観察したり、たまに近所の飼い猫に首筋をなでさせてもらったりするだけ。と言っても、この辺りの野良猫社会も移り変わりが激しいし、飼い猫も外に出て来なくなった。最近は閑散としている。野良猫が多ければ良いかと言えば、そうではないけれど、私の住んでるアパートの周りはコの字型の行き止まりになっていて、小さな駐車場もあり、野良猫が迷いこむのには中々向いた造りになっている。
やっぱり猫には親近感が湧くし、挨拶くらいならわりと上手に出来ると思う。いなくなった猫や、なくなった猫が、たまに夢に出てきたりする。どの猫にもすごく感謝しているし、とても尊敬している。
一冊目は、
『私の猫たち許してほしい』、佐野洋子著、ちくま文庫1990年発行。
もともとリブロポートから、1982年に発行されたらしい。言わずと知れた『100万回生きたねこ』の作者で、あちらは1977年発行なので、こちらが少し後になる。と言ってもこちらはエッセイ。そしてタイトルに猫がつくけれど、猫の話はほんのわずか、主に佐野さんの来し方、少女時代のこと、学生時代のこと、が書いてある。タイトルの「私の猫たち許してほしい」は、猫に見られ、猫を見てきた佐野さんの、愛憎やら憧憬やら距離感やら、言葉にできない様々な気持ちが詰まってるんだと思う。なんて知ったようなことを書いている自分がはずかしい。私も出来れば「私の猫たち許してほしい」と言いたい。
『猫にかまけて』、町田康著、講談社2004年発行。
猫好きで知られる町田康さんの、エッセイ。こちらはどっぷりと猫。ご自宅と仕事場にいる猫たちの様子が中心なので、猫と人間の共同生活が微に入り細を穿って描写されていて、とてもたのしい。町田さんはよく猫と会話されている。でもよく見ると、初対面の猫とは会話しない。気心が知れれば、会話する。
猫にも色んな猫がいて、それぞれ全く違うんだなあと思う。じゃあ共通点は、何なのか。全く別の性格であっても、生物学的特徴以外のところで、「猫」に共通する何かがあるはずだ。やっぱり共通点はあるんです。それは多分人間にも、幾分かは共通している。(と思いたい。)
『猫だましい』、河合隼雄著、新潮社2000年発行。
12の物語をとりあげて、そこに描かれた猫と人間の「たましい」の関係について考察したエッセイ。
「 たましいは広大無辺である。それがどんなものかわかるはずもない。従って、何かにその一部の顕現を見ることによって、人間は「生きる」という行為の支えを得ようとする。しかし、他人とほんとうに生きようとする限り、それを超える努力をしなくてはならない。(略)
猫は、どういうわけか、人間にとってたましいの顕現となりやすい。猫を愛する人は、猫を通じて、その背後に存在するたましいにときに想いを致すといいのだろう。」(最後のページより)
猫には、何かを投影しやすい。嬉しくもあるし、怖かったりもする。「一部の顕現」とか、「ときに」という言葉は河合先生の配慮だろうか。
『猫語の教科書』、ポール・ギャリコ著、灰島かり訳、スザンヌ・サース写真、ちくま文庫1998年発行。
以前実家の母の蔵書(?)から見つかった、70年代から80年代初頭の「暮らしの手帖」のことを思い出した。すごく似てる気がする。恐縮する。猫の婦人が語る、若い猫への指南書で、結構辛辣であった。作者によるたのしい「編集者のまえがき」が付いていて、そこには、「…さらに読みすすむと、これを書いた猫は自分がメスであることをうちあけているが、こんなことはわざわざいわれなくとも、すぐわかる。というのも、この本のあちこちには実に意地悪きわまりない文章があって、こんなものはメスでなくては書けない。」と、あった。意地悪ではなくて、できれば社交的と言ってほしいのだけど。
『猫のあしあと』、町田康著、講談社2007年発行。
上段の、『猫にかまけて』の続き。ヘッケがなくなってから後の話。
家の猫のほかにも、仕事場にはボランティア団体から預かった猫が何匹かいる。このままどこまで猫は増えるんだろう。ちょっと心配になるけれど、横に流れる水のように、猫と著者の時間はゆらゆらと、ざあざあと、ある時は心地よく、ある時は音を立てて流れて行く。実際にはとても大変なこととお察しするけど、著者はそういう風に書いている。
著者は何回も言う。猫の命は預かりもので、いつか死んでしまうのなら、今日を出来るだけ楽しく過ごしてほしい、天に返さなくてはならないものなら、大切にしなくてはならない、人間の命も預かりものなのかもしれない、そう思えば、今を力の限り一生懸命生きよう、仕事を一生懸命しよう、気力も体力も知力も預かりもので、いつか利子をつけて返すのだ、
やっぱり最後には泣いてしまった。起き上がって夜中の布団から出てみたけれど、行くところがない。猫もいない。
昔猫を飼っていて、飼わなくなってから6年くらい経つ。今はもっぱら野良猫を観察したり、たまに近所の飼い猫に首筋をなでさせてもらったりするだけ。と言っても、この辺りの野良猫社会も移り変わりが激しいし、飼い猫も外に出て来なくなった。最近は閑散としている。野良猫が多ければ良いかと言えば、そうではないけれど、私の住んでるアパートの周りはコの字型の行き止まりになっていて、小さな駐車場もあり、野良猫が迷いこむのには中々向いた造りになっている。
やっぱり猫には親近感が湧くし、挨拶くらいならわりと上手に出来ると思う。いなくなった猫や、なくなった猫が、たまに夢に出てきたりする。どの猫にもすごく感謝しているし、とても尊敬している。
一冊目は、
『私の猫たち許してほしい』、佐野洋子著、ちくま文庫1990年発行。
もともとリブロポートから、1982年に発行されたらしい。言わずと知れた『100万回生きたねこ』の作者で、あちらは1977年発行なので、こちらが少し後になる。と言ってもこちらはエッセイ。そしてタイトルに猫がつくけれど、猫の話はほんのわずか、主に佐野さんの来し方、少女時代のこと、学生時代のこと、が書いてある。タイトルの「私の猫たち許してほしい」は、猫に見られ、猫を見てきた佐野さんの、愛憎やら憧憬やら距離感やら、言葉にできない様々な気持ちが詰まってるんだと思う。なんて知ったようなことを書いている自分がはずかしい。私も出来れば「私の猫たち許してほしい」と言いたい。
『猫にかまけて』、町田康著、講談社2004年発行。
猫好きで知られる町田康さんの、エッセイ。こちらはどっぷりと猫。ご自宅と仕事場にいる猫たちの様子が中心なので、猫と人間の共同生活が微に入り細を穿って描写されていて、とてもたのしい。町田さんはよく猫と会話されている。でもよく見ると、初対面の猫とは会話しない。気心が知れれば、会話する。
猫にも色んな猫がいて、それぞれ全く違うんだなあと思う。じゃあ共通点は、何なのか。全く別の性格であっても、生物学的特徴以外のところで、「猫」に共通する何かがあるはずだ。やっぱり共通点はあるんです。それは多分人間にも、幾分かは共通している。(と思いたい。)
『猫だましい』、河合隼雄著、新潮社2000年発行。
12の物語をとりあげて、そこに描かれた猫と人間の「たましい」の関係について考察したエッセイ。
「 たましいは広大無辺である。それがどんなものかわかるはずもない。従って、何かにその一部の顕現を見ることによって、人間は「生きる」という行為の支えを得ようとする。しかし、他人とほんとうに生きようとする限り、それを超える努力をしなくてはならない。(略)
猫は、どういうわけか、人間にとってたましいの顕現となりやすい。猫を愛する人は、猫を通じて、その背後に存在するたましいにときに想いを致すといいのだろう。」(最後のページより)
猫には、何かを投影しやすい。嬉しくもあるし、怖かったりもする。「一部の顕現」とか、「ときに」という言葉は河合先生の配慮だろうか。
『猫語の教科書』、ポール・ギャリコ著、灰島かり訳、スザンヌ・サース写真、ちくま文庫1998年発行。
以前実家の母の蔵書(?)から見つかった、70年代から80年代初頭の「暮らしの手帖」のことを思い出した。すごく似てる気がする。恐縮する。猫の婦人が語る、若い猫への指南書で、結構辛辣であった。作者によるたのしい「編集者のまえがき」が付いていて、そこには、「…さらに読みすすむと、これを書いた猫は自分がメスであることをうちあけているが、こんなことはわざわざいわれなくとも、すぐわかる。というのも、この本のあちこちには実に意地悪きわまりない文章があって、こんなものはメスでなくては書けない。」と、あった。意地悪ではなくて、できれば社交的と言ってほしいのだけど。
『猫のあしあと』、町田康著、講談社2007年発行。
上段の、『猫にかまけて』の続き。ヘッケがなくなってから後の話。
家の猫のほかにも、仕事場にはボランティア団体から預かった猫が何匹かいる。このままどこまで猫は増えるんだろう。ちょっと心配になるけれど、横に流れる水のように、猫と著者の時間はゆらゆらと、ざあざあと、ある時は心地よく、ある時は音を立てて流れて行く。実際にはとても大変なこととお察しするけど、著者はそういう風に書いている。
著者は何回も言う。猫の命は預かりもので、いつか死んでしまうのなら、今日を出来るだけ楽しく過ごしてほしい、天に返さなくてはならないものなら、大切にしなくてはならない、人間の命も預かりものなのかもしれない、そう思えば、今を力の限り一生懸命生きよう、仕事を一生懸命しよう、気力も体力も知力も預かりもので、いつか利子をつけて返すのだ、
やっぱり最後には泣いてしまった。起き上がって夜中の布団から出てみたけれど、行くところがない。猫もいない。















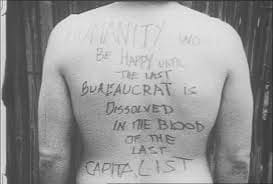


![荒野の七人 (特別編) [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51UW30dl56L._SL160_.jpg)


![八月の鯨 [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51O38s202vL._SL160_.jpg)