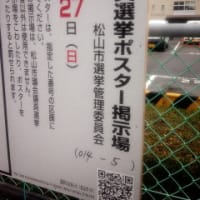日本という国は、表面的にはきれいごとを言っていても現実的には「失敗を許さない文化」に満ち満ちているのかもしれない。
特にビジネス社会においては、失敗者は信用されず、人知れず消えていくしかない運命のような気がする。
欧米では、ベンチャー企業のトップがそのような失敗者だとしたら、かえって評価される場合がある。
事業に失敗するというのは本当に悲惨である。
そこから這い上がってきたのだから二度と同じ過ちは繰り返さないだろうということである。
そういう意味では懐が深い。
学生の時に、伯父の事業の失敗で債権者側になったことがある。
ただ、その伯父が一時行方不明になったため大学生の私が、後始末と債権者会議を主導する経験をした。
なぜか、債権者席ではなく、事業経営者側としてである。
会議は5~6時間に及んだ。
ただの一言も弁明できない。
人生の中でさまざまな厳しい会議に出席したが、あれほど辛い会議はなかった。
失敗するには、さまざまな原因がある。
一つであることは珍しい。
不運が重なり合っているケースが多い。
最近知り合ったベンチャーの社長さんは、その時のトラウマで今も自信を持てずにいる。
人間的には欠点もあっただろう。
しかし、今はその時の自分を責めても、人のせいにはしていない。
そして、何とか、残りの人生を、世のため、人のためになる仕事をしたいと起業したというのである。
しかし、世間(特に金融機関)は許さない。
今も、倒産した時の従業員の顔が浮かんできて、朝起きると涙が頬を伝わっているときがあるという。
その人の不運のきっかけになったのが、阪神淡路大震災。
基幹店が被災し、大きな損害を被り、あてにしていた問屋も震災のあおりで倒産、身動きが取れなくなったというのである。
「国などの救済措置を受けなかったのですか」と問うと、
「どれも条件に合わなかったのです」と肌身離さず持ち歩いている出さずじまいに終わった「り災証明書」を見せてくれた。
行政の立場にいる人間として、他に方法がなかったのだろうかと悔やむ。
金融機関の人たちは、「お気の毒ですが...」とは言ってくれましたが、言うだけで終わりました。
その社長さんは続けて言う。
「倒産にも条理と不条理があると思うんです。条理の部分で倒産したならば致し方ないと思います。
でも、不条理なことで倒産に追いやられたら悔しくて仕方がない。諦めきれない。
でも、社会は落第者としかみないのです。」
悔しさがにじみ出る。
行方不明になっていた伯父が出てきたとき、抜け殻のようになっていた。
そんな伯父を責める気にはならなかった。
ただ、どんな人でも 「Re Dream(夢よ、もういちど)」があってもいいんじゃないかと思うのです。