
新訳「嵐が丘」で、有名な訳者のエッセイだ。
「嵐が丘」を昔学校の図書館で借りて翻訳で読んだとき、何がなんだか分からないが、その情熱と荒野と
いうイメージが心に残ったのだった。ヒースクリフ、古い屋敷、主と使用人、、、。
新訳も読んでみたい、、、でも長編だったなあ。
ということで、こちらのエッセイを借りたのだった。
「嵐が丘」の新訳を引き受けたとき、著者は37歳。「こどもを生むことをあきらめることになるのか
・・・。」という覚悟での翻訳作業だったらしい。
そして、、、。現在、一児の母として、お子さんの言葉の成長のことにもふれて、このエッセイが
書かれた。
興味深かったのは、以下の二点。
まず一点は、かいつまんでいうと、つわりの時期など、母と子は対立関係にある。その時期を乗り越え、
生まれてきたあと成長の過程で子は母を心の中で、一度殺さないと大人になれない。書いていて怖いが、
事実なのだろうと思えた。こうして書いてあるものを読むことで、楽になる人も多かろうと思う。
もう一点は、子どもが言葉を自分のものにしていくとき脳内ではニューロン同士のつながりの部分に
鞘をかぶせるようなことが起こっているという宗教家の玄侑宗久氏の書いたものをひいてあるところ。
もともと子供は直感の回路を持っていて言葉を習得することは、その回路を失うことでもある、というと
ころを読んで、こういう見方を失ってはいけないなと思った。言葉を早く習得させれば、いいってもの
でもないのだ。
もちろん、こどもが自ら、学んでいく場合はいい。
この本の中に出てくる、お子さんと著者の言葉のやり取りは、ほほえましくて豊かだなあと
思った。










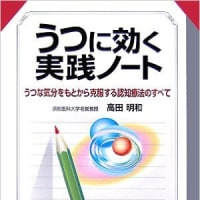


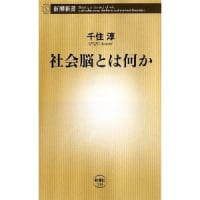
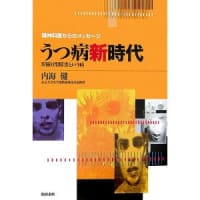
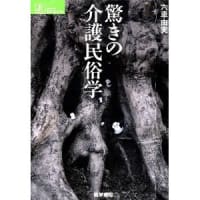

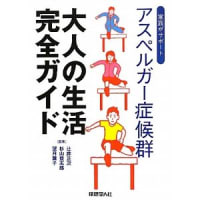


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます