
思いつきで恐縮ですが、携帯カメラに納まっていたのでアップさせて
いただきます。5月26日、冤罪「布川事件守る会」の総会&解散パーティー
の時の写真ですね。この方は、劇団青年劇場の重鎮でベテラン役者さんの
後藤陽吉氏ですね。「真珠の首飾り」公演でホイットニー将軍役を演じ
存在感の大きさを感じさせて下さったような記憶があります。
この日も、支援者の一人として挨拶をされていました。
話しは変わりますが、5月25日夜、青年劇場公演「臨界幻想」観劇のとき、
ベテラン女優の上甲まち子さんに勧められ『植民地・朝鮮の子どもたちと
生きた教師・上甲米太郎』(大月書店発行)という書籍を買いました。
最近、読んだ数少ない本の中で、たいへん感銘を受けました。戦前日本が
植民地支配をしていた朝鮮で「普通学校の教員になり、朝鮮語を学び、
朝鮮語で授業をし、生徒たちと朝鮮語で話し、生徒と朝鮮人に対等な
人間として接していた。現在の時点でいえば当然のことであったが
植民地としての日本人のなかでは、きわめて異例のことであった。」
と高麗博物館館長の樋口雄一氏は書いています。
この書籍の巻頭では上甲まち子さんが「父を語る」ということで生い立ち、
教員時代、治安維持法違反による検挙、出所、北海道の炭鉱、九州の炭鉱、
戦後、レッドパージ、紙芝居屋、失対事業・全日自労での活動、うたごえ
運動。そして60歳の還暦のときには、荒木栄さん(うたごえ全盛期の作曲家)
が「わが母のうた」(森田ヤエ子作詞)を作曲してくれたそうです。
その後、上京し、晩年、あの「金嬉老事件」事件で被告側の証言にたち
日本人による朝鮮での差別がどのようなものであったか明らかにしようと
されたそうです。
今の時代にあって、人間いかに生きるべきかを教えてくれる一冊のような
気がします。
女優・上甲まち子さんは「真珠の首飾り」では、主役ベアテ・シロタ役で
語り手として出演されていました。ちなみに、文京担当の湯本弘美さんも
タイピスト役で出ていましたね。
この作品も、戦争放棄をうたった日本国憲法がどのようにして作られたか
を知る上でのすばらしい作品でした。
いただきます。5月26日、冤罪「布川事件守る会」の総会&解散パーティー
の時の写真ですね。この方は、劇団青年劇場の重鎮でベテラン役者さんの
後藤陽吉氏ですね。「真珠の首飾り」公演でホイットニー将軍役を演じ
存在感の大きさを感じさせて下さったような記憶があります。
この日も、支援者の一人として挨拶をされていました。
話しは変わりますが、5月25日夜、青年劇場公演「臨界幻想」観劇のとき、
ベテラン女優の上甲まち子さんに勧められ『植民地・朝鮮の子どもたちと
生きた教師・上甲米太郎』(大月書店発行)という書籍を買いました。
最近、読んだ数少ない本の中で、たいへん感銘を受けました。戦前日本が
植民地支配をしていた朝鮮で「普通学校の教員になり、朝鮮語を学び、
朝鮮語で授業をし、生徒たちと朝鮮語で話し、生徒と朝鮮人に対等な
人間として接していた。現在の時点でいえば当然のことであったが
植民地としての日本人のなかでは、きわめて異例のことであった。」
と高麗博物館館長の樋口雄一氏は書いています。
この書籍の巻頭では上甲まち子さんが「父を語る」ということで生い立ち、
教員時代、治安維持法違反による検挙、出所、北海道の炭鉱、九州の炭鉱、
戦後、レッドパージ、紙芝居屋、失対事業・全日自労での活動、うたごえ
運動。そして60歳の還暦のときには、荒木栄さん(うたごえ全盛期の作曲家)
が「わが母のうた」(森田ヤエ子作詞)を作曲してくれたそうです。
その後、上京し、晩年、あの「金嬉老事件」事件で被告側の証言にたち
日本人による朝鮮での差別がどのようなものであったか明らかにしようと
されたそうです。
今の時代にあって、人間いかに生きるべきかを教えてくれる一冊のような
気がします。
女優・上甲まち子さんは「真珠の首飾り」では、主役ベアテ・シロタ役で
語り手として出演されていました。ちなみに、文京担当の湯本弘美さんも
タイピスト役で出ていましたね。
この作品も、戦争放棄をうたった日本国憲法がどのようにして作られたか
を知る上でのすばらしい作品でした。














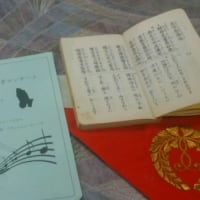





土深く 芽生える朝に~
あ~あ~ わが母こそ太 陽~
たたかいを 育~て~る太 陽~ ♪
2.雑草(アラグサ)のたくましさ
踏まれても伸び広がって
<繰り返し>
3.雑草(アラグサ)の花のすがしさ
いちはやく迎える春を
<繰り返し>
4.雑草(アラグサ)は私たち
闘いに深く根ざして
<繰り返し>
この歌は1962年、荒木栄さんが大牟田自労うたごえ行動隊責任者の還暦を祝って贈られたものだそうです。
この責任者が上甲米太郎さんだったんですね。
今もって、すばらしい歌ですね。