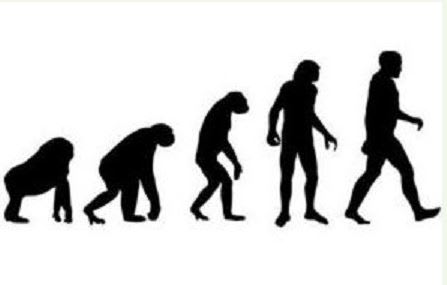「うそつき」という語感について、日本人と西洋人の語感はずいぶん違うらしい。若い日本人のカップルがデートしているとする。男性がなにか冗談を言ったとき、女性は笑いながら、「んもぅっ、哲のうそつき!」とか言って、男の上腕をたたく。こんな情景はいかにもありそうである。しかし、この男がもしアメリカ人だったら、「うそつき」と言われた瞬間顔が少しこわばるかもしれない。女性は「もうっ、ジョーったらジョークばっかり」とでも言った方がいいだろう。西洋人に対して「うそつき」と言うのはかなりの罵り言葉である。
「うそをついてはいけない」というのは洋の東西を問わない普遍的な戒律である。不妄語戒はキリスト教の十戒にも仏教の五戒にもちゃんと含まれている。しかしその受け止め方はずいぶん違うように見受けられる。どう考えてみても西洋の方が厳格である印象が強い。やはりそれは、一神教の戒律は神から与えられた絶対的なものであるのに対し、仏教における戒律は人間の定めたものであるという事情があるのだろう。(お釈迦様も人間である。)日本では昔から「嘘も方便」と言う言葉がある。ちなみに「方便」も仏教用語として輸入された言葉である。キリスト教において戒律に背くことは絶対悪であるが、仏教においては一切皆空である、そもそも究極的な善悪というものはもともとない。すべては縁起の中で相依的に生じるものにすぎないとされる。だから、仏教においては状況次第で嘘をつくことが善行となる場合もあるのである。
カントが著した「うそ論文」というものがある。正式には『人間愛から嘘をつくという,誤って権利だと思われるものについて』という題の論文である。内容は、どんな場合でも嘘をつくこと自体はよくないということを論じている。たとえば、悪者に命を狙われている友人を自分の家にかくまったとする。そこへ悪者が訪ねてきて、その友人が来ていないかと問われた時にでも嘘を言うのはよくないことだ、とカントは主張する。カントは決して悪者に友人を差し出せと言っているわけではない。この場合、当然友人を守ることが最優先であることは間違いないが、それでも嘘をつくことは良くないことだというのである。できれば友人を救うことと嘘をつかないとを両立させることが望ましいのだが、それが不可能な場合もありうる。この場合は結局嘘をつくことになるだろう。その場合でも、嘘をつくこと自体はあくまで悪なのである。どんなときにも「嘘をつく勿れ」という道徳律に対する敬意を忘れてはならないというのである。
大抵の日本人ならカントの考えは余りにも硬直しているように感じるに違いない。このような場合にはむしろ積極的に嘘をつくべきであるとする人が多いのではないかと思う。しかし、カントは善悪を仏教におけるように相対的なものであるとは考えない。数学の定理は手順さえ間違わなければ誰もが同じように到達できる。それと同様に、カントは人間が理性的であればだれもが普遍的な道徳律に到達できると考えたのである。つまり、それは人間が恣意的に決めたのではない。数学の定理のように厳然と実在する道徳であり、だから我々はそれを恣意的に解釈することはできない。絶対的なものであるから、無条件にそれに敬意を払わねばならないというのである。
カントは道徳の源泉をいわば神から理性に移したのであるが、私にはこれが名目上のものに思える。無条件に従わせるという絶対性はなにか超越的なものを措定(結局それを言葉にすれば「神」ということになるだろう)しないと導入できないことのように思えるからである。やはりカントも一神教の世界に育った人のように思える。