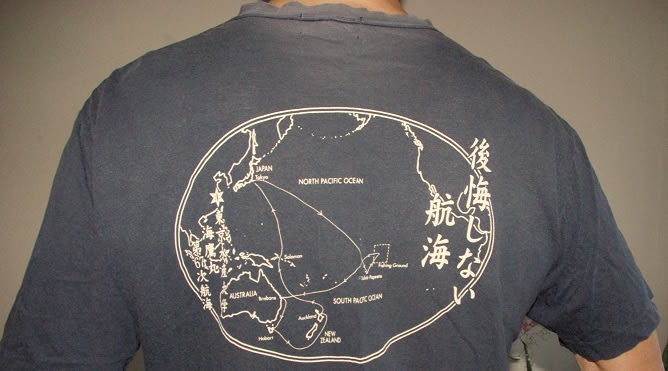あるSNSにおいて、次のような質問を提示した人がいる。
「意識とは自分が作っているのではなく他人がいることによって作り出されるものなのでしょうか?」
質問された方の真意は分かりづらいが、このような問いが出てくるという事情は理解できる。意識がなんであるか、それはあまりにも自明のことと思われていながら実はとても難しいからである。そして、この人は「他人がいることによって作り出されるものなのでしょうか?」と述べているが、少なくとも他人がいなければ概念として成立しないということは間違いないことだと思う。
上述したことについて訝しく思う人は少なくないと思う。「今、御坊哲の書いた記事をディスプレイで見ながら考えている、それは自分の意識の中で起こっている。自明のことではないのか?」と思うのは当然である。私たちはそのような思考に慣れきっているからである。しかし問題は「意識」という言葉が具体的には何を指しているのかということである。
いま私は、自宅から遠くの山を見ている。手前にはベランダがあり、そこにはマリーゴールドの花が咲いている。どこかの家でカレーライスをつくっているらしく、あけ放たれた窓からはカレーの匂いが漂ってくる。実は私は昨日6回目コロナワクチンを接種したばかりで、少し気分がすぐれない。左肩が少し痛いし、体も頭もだるく、心臓の鼓動も感じる。これらはみな私の意識の中で起こっていることであるが、しかし、私が感じるもの考えるものをすべて数え上げていっても、その中に私の意識そのものは見当たらないのである。そこで気がつくのは、どうやらそれらもろもろのことが展開される場所のようなものを「意識」と呼んでいるのではないかということである。
しかしここには一つ問題がある。それは言葉というものは比較があってはじめて成立するものだからである。意識という言葉が成立するためには、意識と意識以外のものを分別できなければならない。あらゆるものが意識の中にあるのであれば、意識の外に出ることは不可能なので、意識を認識することはできないはずである。しかし、「意識」という言葉が現に成立しているからには、我々は確かに比較しているはずなのである。どのような比較かと言うと、それは「私の意識」と「他者の意識」を比較しているのである。もちろん他者の意識を直接確認して比較しているわけではない。言語によるコミュニケーションを通じて、他者も自分と同じような景色を見たり感じたり、同じように考えたりしていると推論することによって、自分の意識と他者の意識を共に見下ろす客観的視点を確保するのである。しかし、この客観的視点というものはあくまで架空の視点である。
自分も他者も同じようにものを見たり感じたりすることの出来る同等の人間であるという世界観(客観的世界観)に立てば、「意識」という概念は成立する。むしろそれがなければ心理学などという学問も成立しない。客観的世界があるという前提が無ければ自然科学をはじめとするほとんどの学問は成立しないのである。しかし、その事が哲学にとっては悩ましい問題となる。哲学は前提を設けないで考えることをする学問であるからである。
自分の意識と他者の意識を比較すると言っても、他者の意識を観察することは出来ない。だからその「比較」はある意味虚構でしかない。したがって、客観的世界を俯瞰する客観的視点というものも実際には存在しない。客観的世界というのは推論によるある種の虚構だとも言えるのである。客観的には意識があることは自明であっても、ここに哲学的には巨大な問題が存在する。実存的な視点から見れば、意識は存在しないとしてもなんの矛盾もない。ちなみに哲学者の永井均は「なぜ意識は存在しないのか」という本を書いている。ウィトゲンシュタインは「比類なき私」という言葉を使うが、これも「私の意識」というものが比較対象がないというところからきているのである。
実は、このことは実存的問題を追求する禅仏教においても大問題で、己自究明を徹底したその究極には「無」に行き着くのである。

鎌倉明月院「悟りの窓」