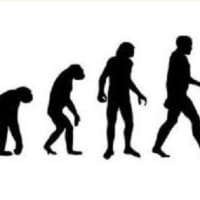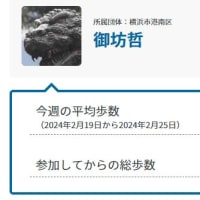NHK Eテレの「100分 de 名著」という番組でサルトルが取り上げられている。私の学生時代はサルトルが全盛の頃でやたら「実存主義」という言葉を耳にしたような気がする。しかし、実際のところ私の周りにはサルトルを読んだという人は見かけなかったし、私自身もそれほど関心を持ったことはなかった。
実存とは現実存在の省略であると言われている。「現にそこにあるもの」という意味だ。19世紀になって、近代文明が個人を「現にそこにあるもの」として目覚めさせたのだ。それ以来、人々は「現にそこにあることの偶然性」という不安にかられるようになる。
一般に一神教の世界ではすべては神の差配であるので、人々は神のシナリオによる必然性の中に生きている。ところが、文明の進歩が徐々に聖書的世界観を侵食してくると、その必然の世界が揺らぎだす。ニーチェの「神は死んだ。」という言葉はそのような文脈の中でとらえると理解しやすい。
もともと神のいなかった仏教世界ではどうだっただろう。実は、釈尊はサルトルに先立つこと2千年も前にこの問題に取り組んでいた。
仏教では「無常」という。無常とは単に変化するというだけのことではない。この世に確かなもの保障されたものは一つもないという冷厳な事実が無常という概念である。サルトルのいうところの偶然性と同じ意味である。人が「現にそこにある」というリアルさを意識するとき、無常のすさまじさに気付かずにはいられないのである。
無常といえば、平家物語の冒頭の「祇園精舎の鐘の声‥」がよく引き合いに出されるが、これは本来の無常観を捻じ曲げている。「盛者必衰の理をあらわす 」という文言があるが、無常の中には予定調和的な法則はないのである。この世界には差配するものなどいない、偶然性は人の感情など斟酌しないで世界を変化させていくのである。感傷的な無常観はあくまで文学上のものでしかない。
ニーチェは永劫回帰というアイデアの中で、「世界が何度めぐり来ても、いまここにある瞬間がかくあることを望む」ということを述べている、過酷な世界が何度でも繰り返されても受け止めてみせるという勇壮な覚悟のほどを表明したのだ。彼に本当にそれほどの覚悟があったのかどうか不明だが、好むと好まざるとも我々はこの世界を受け入れざるを得ないのである。
無常の世界では当然悲しいことつらいことに出会うこともある。そのことは避けがたくすべて受け入れるしかない。悲しいときは悲しいようにつらい時はつらいように生きるしかない。そして、釈尊は「執着するな」というのである。それを「あるがまま受け入れる」というふうに言う。その覚悟ができた時、無常の中に「妙」が見いだせるというのである。それが仏教的実存主義である。