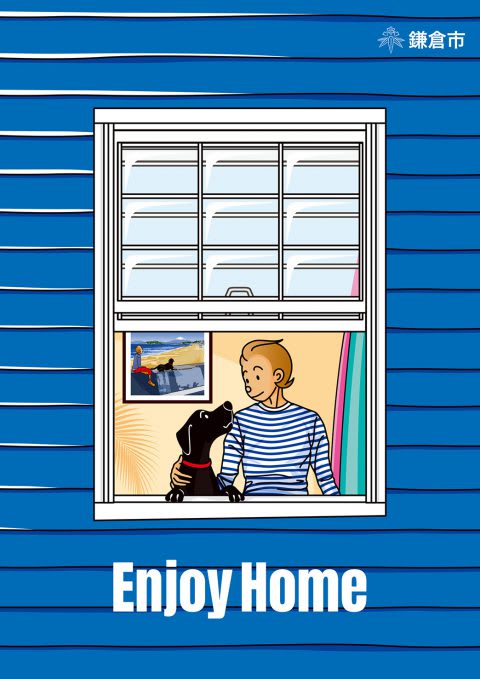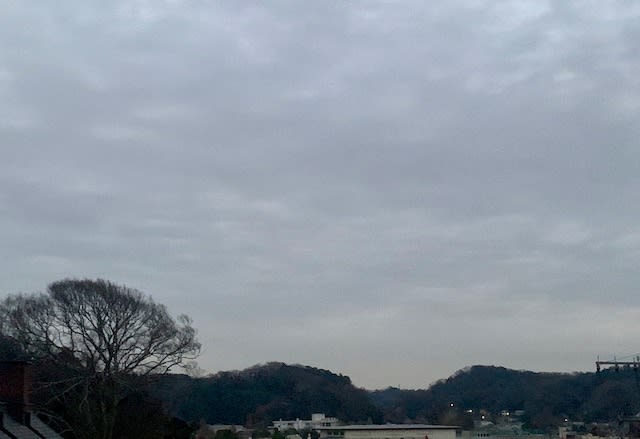朝からの大雨が昼前にはすっかりやみ、青空が広がりいいお墓参り日和となった。多くのお墓にお花が供えてあって華やかだった。
さて、12月30日は恒例の今年のボツ記事特集。まあ、エントリーの供養のようなもの。古い順にタイトルと書きかけの文章。
『』内がタイトル、続く文章が記事(もちろん書きかけ)。・・・以下は一言コメント。
『こんな考えの人っているんだ』・・・鎌倉であった、傍若無人なおっさんのことを書いたのだが、もし知っている人だったりしたら嫌な目に合わせられるかもしれないと妻が心配するので一旦公開したけどボツに。ほんと、あの時は嫌だったな。コメントまでいただいたiminaineさん、すみません。
『備えあれば憂いなし』
「ああ、今日はちょっと仕事に余裕ができたな」なんて幸運な日があったら、ぼんやりしていないで、自己研鑽に励む。
私のように一人でやっていると、そんな日は気が緩んでしまいがちだが、そんな日こそ気を引き締めて、勉強する。勉強の種は山ほどある。
・・・まだ、2月のエントリー。のんびりしていた。
『反省すべきか、結果オーライか』
先週末、新宿で飲んだ。大恩ある先輩に誘われ、とっておいてくれた店が新宿三丁目の居酒屋の、それも奥の方の席。
新宿の飲み屋街に行くなんて数年ぶりだったし、新型コロナウイルス感染症のせいで人ではないと思っていたらあに計らんや、すごい人出。末広亭の前には並んでいる人がいて、入った店も結構混んでいる。隣の席にはコロナウイルスなんて全然へっちゃらという風態の20代の若いサラリーマンが口角泡を飛ばしながら大声で話し、タバコをガンガン吸っている。これはまずいなと思ったがどうしようもない。
その先輩もマスクを外して店に入ってきた私を見て、「あれ?マスクしないの?僕はまったく気にしてないから」って、たしかにあなたは私からみたらむちゃくちゃ強運の人です。なんて思いながら、数時間楽しい時間を過ごした。そして、十日ほど経ってなんの症状もでなかったのでこの記事を出している。
もし、私が高熱でも出しているようだったらそれは新宿の裏町の飲み屋がクラスター形成をしたというわけだけど、そうならなくてよかった。
・・・3月23日に書いている。少しずつ緊迫してきた頃。
『心の中でお別れを』
先日、今の私を育ててくれた先輩の先生が亡くなられた。コロナのせいではない。
10年ほど前に体調を崩し、それ以来の療養生活ののちのことだった。
・・・今でもしょっちゅう思い出す。
『ストレスがブログの原動力?』
家でじっとしていると、ブログを書く気がなかなか起きてこない。
ストレスを感じているときの不平不満がブログを書く原動力になるのだろうか。
・・・5月1日。緊急事態宣言中。ある意味コロナ鬱の始まりとも言える?
『この先、政治家とは必要なのか』
今では読まなくなったが、さいとうたかおのゴルゴ13に、実は東西の緊張はそれぞれのスパイが作り出していた、というような話(『色あせた紋章』)があった。新型コロナウイルス感染症による人類の危機を目の当たりにして、政治家という人たちの役割というのを改めてかんがえるうちに、その話を思い出した。
人間にとって必要なのは命であって、その次は平和だ。命は健全な肉体と平和で豊かな世の中によって紡ぎ出されるものであるが、健康は医療従事者が担っている。豊かな世の中というのは、生産者消費者の間で行われる経済活動が基盤となって
・・・5月28日の書きかけ。もう、政治家不要感が出始めていたみたい。
『緑、あれこれ』
冬青(ソヨゴ)の木をシンボルツリーにしている家は多い。我が家のソヨゴも12年目、しっかり根付いて2階の屋根と同じくらいの高さとなってきた。そのソヨゴに花がつき始めた。小さな花で新芽のようにもみえてしまう。
以下はシリーズだったが続かず。
『言語を手放しつつある日本人(1)はじめに』
日本という国の凄いところは開国に際して猛烈な量の外国語を日本語に翻訳してしまったということだと思う。そうしたことで西洋からの文化的浸潤を食い止めることができた。独自の言語を持ち、それを使う文化があるからこそ外国人からも興味を持たれる。とても誇らしいことだ。
その、日本の文化が失われてしまうのではないかと、最近各方面で言われている。もう、日本語に直すという努力をせず、なんでもそのまま使っている。
それももともとの発音で正しく使っているのならばいいが元の意味もわからずに略語を使っているのを見聞きすると絶望感に包まれる。
『言語を手放しつつある日本人(2)カタカナ言葉の氾濫』
数年前から言われていることだが、使われても意味がよくわからない言葉が増えている。サステイナブルとか・・・とか、
こういう言葉を使うことが悪いというわけではないけれど、使っている当の本人もこの人本当にわかっているのかな?と思う様なことがある。
『言語を手放しつつある日本人(3)医学の世界での状況』
病理学、という言葉に相当する表現があるかというのを、ある発展途上国の病理の先生に尋ねたら、そういうものはないと言われた。そもそもそういう概念が無いということだった。
日本でも病理学という概念はなかっただろうが、言い得て妙の字を当てることでpathologyを表現することに成功した。
『言語を手放しつつある日本人(4)病理の世界での状況』
病理の世界でも、外国語がよくわからない入り込み方が始まっている。がんゲノム医療が開始され、病理医はそのただ中に立たされる様になった。
『言語を手放しつつある日本人(5)日本語を手放すことは哲学を手放すこと』
開国の時、日本人が外国語を徹底的に日本語化したことで、日本人は固有の文化、考え方、哲学をまもった。
・・・グローバル化の中で日本人はどうやって日本語を守っていかなくてはならないか。改めて考えてみたい。
『価値観の転換・・・”新しい生活様式のもたらす新しい時代”(3)』
金の価格が高騰しているそうだ。30年前に金持ちの友人に金を買うことをすすめられたことがあったが、あの頃はまだ千円台だった。その7倍となると、100万円分購入していたら、今頃700万円。もうすこし頑張ったら1000万円にもなるだろう。残念ながらその頃金を買う余裕などなかった。その話は別として、確かに金はあればあるだけ資産として有用なものだろうが、金それ自体は何もしない。ただ眩く光るばかりの金属だ。
金に囲まれたミダス王は決して幸せになることはなかった。
電子マネー化が進むことによって、貨幣の価値というものを裏付けるものは一体何になっていくのだろうか。中国が強力に推し進めているからには、世界中で元が使われるようになり、基軸通貨をとってかわるかもしれない。やがて世界は元という単一の電子マネーによって統一されてしまうのかもしれない。
・・・これ、なんでやめたのだろう。(1)(2)がマスク関連話で、これが別の話題だったからか。
『私の哲学』
哲学者になりたかった。
以前はそのことを自己紹介にも書いていたが、みっともないのである時からそれはやめた。ただ、哲学者であることと哲学することは同じではない。哲学は哲学者のものではなく、アマチュアであっても哲学しながら生きることはできる。
・・・このこと、いつまでこだわるだろう。それがいやでボツにしたか。
『私にそんな資格はない』
日曜にクチナシの鉢植えの手入れをしてたら、大きな蜂が飛んできてびっくりした。だが、蜂にしては羽音があまりせず、よくみるとどうも蜂ではないようだ。
土いじりをしていると、いろいろな昆虫にお目にかかるが、そのほとんどの名前は知らない。テントウムシやカミキリムシはわかるがそれぞれの正式な名前は知らない。
そんな虫たちは、葉っぱをかじって、ひどいときには丸裸にしてしまうほどで、駆除の対象となる。蚊やダンゴムシ、ムカデも害虫呼ばわりして駆除する。だが、それぞれの昆虫を見ると、それはよくできていて、美しい。
そんな昆虫を、たたき殺したり、薬を撒いたりして駆除しているがそんなこと、私はやってもいいのだろうか。
・・・全ての生き物に生きる権利が。
『過去の栄光に満足するな!』
過去の栄光にすがって生きるようになるのは、認知症の第1歩という話をどこかで聞いた。
iPS細胞でノーベル医学生理学賞を受賞した山中伸弥先生は、日本最高の科学者として、この国の科学技術の発展を牽引している。iPS研究はその後、他の未分化細胞の開発に伴って一頭地を抜くほどのものではなくなりつつあるが、その発想自体が色褪せることはない。
『ソクラテスの弁明は単なる事実か謙遜か』
先日読んだ小説に、”文字で表すことはできるけど、実際には存在しないもの”が主題として提示されていた。
私は知らないことを知っている
私だってそんなこと百も承知で毎日ヒイヒイ言いながら病理診断の仕事をしている。
・・・話が大きくなりそうで撤退。
『仕事が遅いと相手に無礼に』
締め切りまじかの仕事をなんとか仕上げて、メールに添付して送る。
その時のメールを読むと、つくづく無愛想な文面だと思う。礼を欠くようなものではないが、首を長くして待っていた相手に用件と簡単なお詫びだけというのもどうだかと思うが、こっちも切羽詰まっているのでとにかく送ってしまえとやってこうなる。
一応、先方が依頼してきたことだからなんとなくこっちのほうが仕事をしてあげた、というような感じになるのだが、引き受けた時点ではそうでも、ちょっと遅れたという状況ではこっちのほうに非がある。
・・・今となってはなんの話か。
『私の混乱』
今、私がしなくてはいけないことはなにか?
病理医としての医学の研鑽か、より良い世界を手に入れるために自分にできることを考え、そのための勉強か。
過去の偉人も、現代の他の巨匠にしてもそのためのアドバイスは示唆してくれるが、その答えは与えてくれない。
・・・どうしたことか。
『自分が死ぬときのこと』
叔母のお兄様という方が亡くなった。叔母といっても母の弟の連れ合いなので、私と血のつながりはなく、遠い親戚だ。82歳で、がんだったものの、つい数日前まで仕事していたのに、急に容態が悪くなり、そのまま帰らぬ人となったそうだ。
私はどんなふうに死ぬのだろうかと考える。
『中高年男性VSその他 という』
駅のホームに若者の集まりがいた。夏休み中なら当たり前の光景だ
この先の私が降りる駅よりずっと先の観光地に向かうのだろう。みんなお行儀よくマスクをつけているが、帰ってくるときまでにどのぐらいがつけているかはわからない。ちなみに鎌倉駅に帰り着いた時、海から帰ってくる若者の中でマスクをつけている人は少ない。まあ、鎌倉の場合マスクをつけていない不良を気取っている大人も多勢いるので、比較は難しいか。それはさておき、彼ら若者は活動的で、未熟で多くのことを知らない。
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)さえなければ彼らはずっと自由に、たくさんの人と関わり言葉を交わすことができただろうに、それができない。それどころか彼らは感染の媒体として大人からは目の敵にされている。重症化のリスクの高い年寄りなどいないところで彼らはのびのびしたいだろうし、彼らにとってはちょっとした風邪程度でこれほどの不自由な生活を強いられているのは我慢できないことに違いない。私が彼らの立場だったならそんな世界を恨むことだろう。
中世で大流行して多くの人の命を奪ったペストは老若男女分け隔てなく襲って中世ヨーロッパを席巻した。だが、COVID-19の標的は中高年男性だ。私にしても、かつての喫煙者で、血圧も高い。感染したら死なないまでも、随分苦労するだろうと思う。結局のところ、私たちの世代以上の持病持ちの男性を守るために他のグループの人たちに犠牲を強いているとも言える。中高年男性>中高年女性>若年男女の3グループに分けた場合、3分の2が割を食っていることになる。
前々から言っていることだがーーーよその国のことは別としてーーーこの国は若者を食い物にして生きている。とんでもない若者もいるにはいるが、そういう輩は目立ちたいから目立つような行動をするので、目立って目につくだけだ。多くの若者は冒頭に挙げたような、未熟で不用意な行動を取ってしまうことのあるおとなしい者がほとんどだと思う。
・・・8月17日のエントリー、もう完成していたのに。
『隷属的服従 という概念』
先日書いた”自発的隷従論”に基づいたエントリー『自発的隷従が今日の私の改造マスク』で、当初私が勘違いして編み出した”隷属的服従”という考え方、案外今の世の中に起こっていることではないかと思って、考えてみることにした。
・・・もっと考えてもよかったのに。
『おこもり生活によるルサンチマンからの解放』
家にいる時間が長くなると、考え方も狭くなってしまう可能性はあるが、かといってこれまでーコロナ前ーのように他人と関わり過ぎてストレスを感じることも少なくなった。
私自身、やるべき仕事は明確になったし、どこそこの誰が教授になったなどということが気にならなくなった。多くの人との関係性がネットを通じて等間隔となったからかもしれない。
もちろんコロナをものともせず、人と人との距離をつめてマウントしてこようとする人がいなくなるわけではないものの、新しい生活様式が提示されたことでそれらの人のプレッシャーは断末魔の叫びのようにも聞こえる。
インターネットの普及した今の社会に降ってきた新型コロナウイルスcovid19はルサンチマンの構造?を大きく転換させていくのかもしれない。
・・・ルサンチマンとは、弱者が強者に対して「憤り、怨恨、憎悪、非難」の感情を持つこと。
『新型コロナと無縁の人っている?』
全世界を大混乱に陥れている今回の新型コロナウイルス感染症、これから無縁の人、というのはいるのだろうか。
全ての存在は関係を持っている統一体だから、皆んな関係しているなんて当たり前だなどというのはナンセンスだ。それよりはもう少しはっきりした、実体としての新型コロナとの直接の関わりという意味で、無縁の人はいるか、おそらくいないだろう。
これってすごいことだ。
いくらキリスト教の宣教師が世界中で布教をしたって、世界中の人に関係を持たせることはできなかったがコロナは違う。南米の先住民の間にもコロナが持ち込まれたため、大変なことになっているというニュースがあったほどだ。 ・・・新型コロナは全ての人に襲いかかる。
『ギムザ染色を乾かすときに使うドライヤー』
この前、病理医がたくさんいる病院の病理診断科の部屋で、剖検から戻ってきた若い病理の先生に、少し年長(とはいっても若い)の病理の先生(これも若い)にむかって、
「髪の毛もう乾かしたんですか?早いですね、もしかしてギムザ染色を乾かすときに使うドライヤーを使ったとか。」と冗談を言っているのが聞こえてきて思わず笑ってしまった。
その先生の言い方も面白かったのだが、なんというかそういうなんてことない家庭用のドライヤーをギムザ染色のための乾燥固定標本作成に使っていて、でも、それが命にかかわる診断に結びついているというのが”いかにも病理”という感じがして、面白かった。
なぜって、高価な医療機器を駆使して診断とか治療をする臨床と違って、病理ってホルマリンとかHE染色とか安上がりなものばかり使っていて、本当にコストパフォーマンスがいいと考えると、なんとなくいい気分になった。
・・・内輪話でイマイチと考えたか。書き始めは面白いと思ったのだが。
『顔が覚えられなくなってきた』
この前、女性医師の顔がよくわからないと書いたが、男も40歳前後だとわからないということが判明した。
あの服のせいだと思うが、それにしても区別がつかない。
・・・年のせい。
『私がやってていいのかな』
この前、急ぎの診断をするために、夏休みを一日早く切り上げて出勤したのは臨床的には大いに役立ったみたいで、感謝の言葉をいただいた。私としては病理医として当たり前のことをしたまでで、たまたま息子の結婚式がそう遠くないところで行われ、そのままその地にとどまっていただけだったのでそんなことができただけなので、あまり言われると、患者さんのために夜を日に継いで仕事をしている臨床医に申し訳なくなってしまう。もちろん、彼らは数人の医師団であって私は病院に一人しかいないという違いはあるが。
曲がりなりにも病理医として仕事をさせてもらっているが、それはこのような専門的な医療を行う病院であるからなんとかなっているような気がする。ある意味つぶしがきかない参入者の少ない領域なので、30年近くやっていたら自然と専門家面してやっていることが出来る。これが、ありふれた癌の診断でもをやっていたら、そう目立つこともない。
医者になるには、医学部に入らなくてはならず、昔から狭き門といわれている。したがって、優秀な人材はたくさんいて、天井知らずだ。筑駒開成灘の卒業生はもうそれだけで優秀だし、二番手高校の卒業生でも難関医学部出身者もとても優秀だ。そんな中で私が同じ医者を名乗っていいのだろうかと疑問に思うことがある。決して学歴とか偏差値のことを言っているのではない。当然のことながら、優秀なだけで人間的に使えない医者も少なくないが、それはせいぜい3割ぐらいだろう。1学年100人中の30人が使い物にならなければ、それはさすがに目立つが、製品の歩留まりなんてそれでも十分だ。優秀な人の残り7割ぐらいは普通のコミュニケーションがとれるし、その半分ぐらいはコミュニケーション能力も高いので、どうやっても追いつくことは難しくなる。
もう60が見えてきたところで、こんなことを言っているのもおかしいが、天賦の才とはそんなもの、だれもが同じように与えられるものではない。
・・・若年人口が減ると医学部のハードルも低くなる。
『変に偏差値の高いところを目指したばっかりに』
私はなぜ哲学を勉強する道に進むことが出来なかったのか。今でもそのことを考える。その理由の一つが大学入試だったとしたら、それはバカバカしいことだろうか。
文系の科目は得意だったが、東大の文学部に余裕で入れるような成績ではなかった。そこで、文理どちらに進むかを決めるとき、私は父の勧めに従って”転んだ”わけだが、親に勧められるまま医学部にすすむため、理系にすすみ、そこそこの私立医大にもぐりこみ、何とか病理医となり、現在に至る。ただ、あの時、東大もしくは京大に固執することなく、どこの大学でもいいから哲学を勉強したいと考えるほどの切迫感はもっていなかった。
・・・夢を実現するには、現実的になるべきだったかも。
『学問する意欲』
先日、専門領域仲間の病理医からのメールに、親の介護と専門分野の診断業務だけで毎日が過ぎてしまい、研究はほとんどやっていません、というようなことが書いてあった。
私なんぞ一人病理医で、コロナ禍で切磋琢磨する相手もおらず勉強しに出かける意欲も機会もなく全くダメダメで過ごしている。
最後に勤め上げようと転職してきた病院にももうすぐ1年、
・・・意欲がないのはコロナのせいか。
『病気とはいつから病気なのか』
ぎっくり腰の痛みは治ることなくまだまだ続いている。こうしょっちゅう痛めてしまうということは、痛めやすい状態になっているということであり、その部分の神経が傷害されているということだろう。そういう意味では私の腰痛は慢性化しているといえるだろう。
病気とはどのような状態を指すのだろう。カンギレムという人は病気はその状態を指していうとしたが、果たしてそうだろうか。たしかに新型のような感染症は感染した時点で病気の状態が始まるからわかりやすい。だががんはどうか。発癌のメカニズムはいまだ不明な点が多いが、多段階発癌という考え方に従えば、癌は一発で癌なるわけではない。
・・・これも難しい話題、もう少し考えないと。
『ガラスの天井』
男女雇用機会均等法により女性の社会進出は一定の結果を見ることができたように思う。少なくとも医者の世界では男女比は半々に近づきつつある。通勤途中にすれ違うのも男女比は6:4といった感じだ。今後はガラスの天井をどう打破していくか、男女間の競争が公平になされるようにするのはまだまだ難しいだろうから、クオーター制など男女の固有枠を設けての登用を考えなくてはならないだろう。男性にしても女性にしても働きたい人は働く、子育てをしたい人は子育てと、そんな社会が実現してくれるといいのだが、まだそれには時間がかかりそうだ。
・・・女性の地位向上は喫緊の問題。
『社会規範のハードルの高さの低下』
いろいろな考え方があることが明らかになってきて、自分と同じような考え方をしている人が他にもいるということを知り、そのことで自分を正当化することが昔よりも容易になってきている。社会規範のハードルが、いい意味でさがってきているわけだが、屁理屈、自己正当化にもつながってしまうわけで、考え方は難しい。
・・・お手本となる大人のいない社会。
『休日って、』
朝の空模様にはがっかりしたが、昼前からやっと晴れた。
『妻の弁当』
今の職場に移ってから1年以上経つ。食堂の昼食のシステムがよくわからず、食べたいと思っているのにありつけないとか、孤食よりも技師さん達と一緒に食べてコミュニケーションをとったらいいのではと、妻に弁当を作ってくれるように頼んだ。
それからかれこれ1年がたつ。毎朝私だけのために作ってくれている。
『人間だけがわがままで』
夜、ヴェランダに出てみると静か。
自分の存在を感じる。
昼間、あたりをウロチョロしているリスも雀もいない。
ふと思う、彼らはこんな家も何もなく野山で暮らしている。ほんの小さな巣とけもの道さえあれば十分だ。人間だけが自分の体の何倍ものスペースを使って生きている。
・・・もっと謙虚に生きよう。
『”老いては子に従え”って、いつの間にやら自分が老いてた』
何でも知っているような気でいたが、実はもうそんなこと全くなくなっていた。最近、病理診断を取り巻く環境も急速に変化していて、ただ、標本を診て形態像から診断していたらいいという時代ではなくなった。
・・・年のことが多い。
『ご本人はどうだったのかわからないが』
新型コロナウイルスに感染し、2日に退院した歌舞伎俳優・片岡孝太郎(52)が3日、ブログを更新。医療従事者への感謝を記した。 孝太郎は11月22日未明に微熱があり、PCR検査を受けたところ、陽性が確認された。2日のブログでは「当時軽度との診断でしたが入院を希望しそのまま減圧隔離病棟へ入らせて頂きました」と説明していた。約1週間は発熱を繰り返し、平熱状態を72時間経過したため、2日午前に退院できたという。 3日夜に更新したブログでは、「減圧隔離病棟の四人部屋」に入院していたこと、シャワー以外は部屋から基本的に1歩も出ることができなかったこと、部屋に入る度に看護師さんが防護服を着脱していたことを伝えた。 「正直四人部屋で窓も開けられず皆んな咳込み 夜になると皆体温が上昇し自然と咳も出ますし 朝まで咳込み続ける患者さんも」いたという。 さらに「隣の患者さん」が「あんな飲み会でうつるくらいならヤバイよ」「俺死にかけたけどレムデシビルで助かったよな アレいくら?」と話していたことを明かし、「正直腹わたが煮えくりかえりました」と告白。「看護師さん医師の方が命懸けで働いてくれているのにコイツは…、と」いう思いだったという。 世話になった看護師さんが、食堂で「うつるからこないで」と差別を受けていること、クルーズ船の感染者から対応をしている看護師さんがいたこと、などを伝え、「一番お世話になった身で恐縮ですが是非皆さん一緒に医医療現場の方に感謝しこの日本を守って頂けたらと改めて考えさせられる今日この頃です」とつづった。 なお孝太郎は後日、この投稿を削除している。(※一部加筆しました)。 ・・・真相がよくわからないので。
『政治家が先導する新型コロナ感染拡大』
・・・タイトルだけ
ボツ記事、39もあったか。世に出すことはできなかったけど、この先のブログ作成の糧にはなるでしょう。
あと1日
 お願いします
お願いします