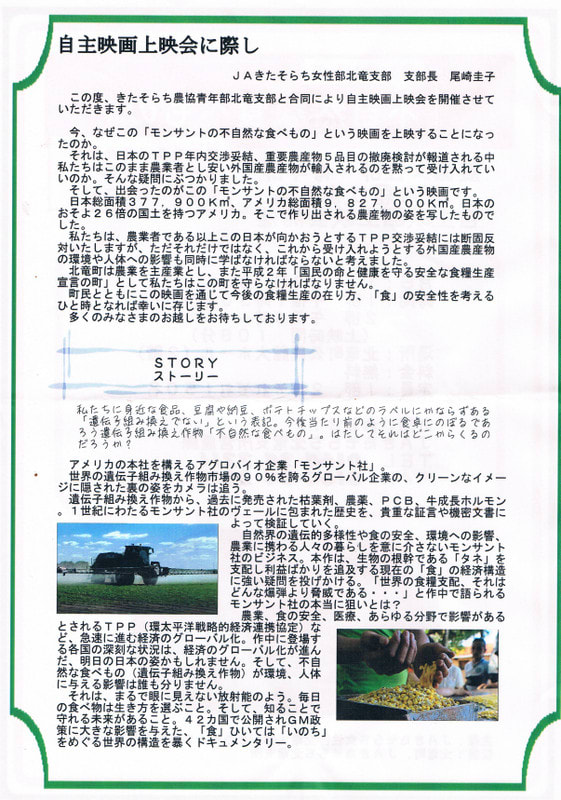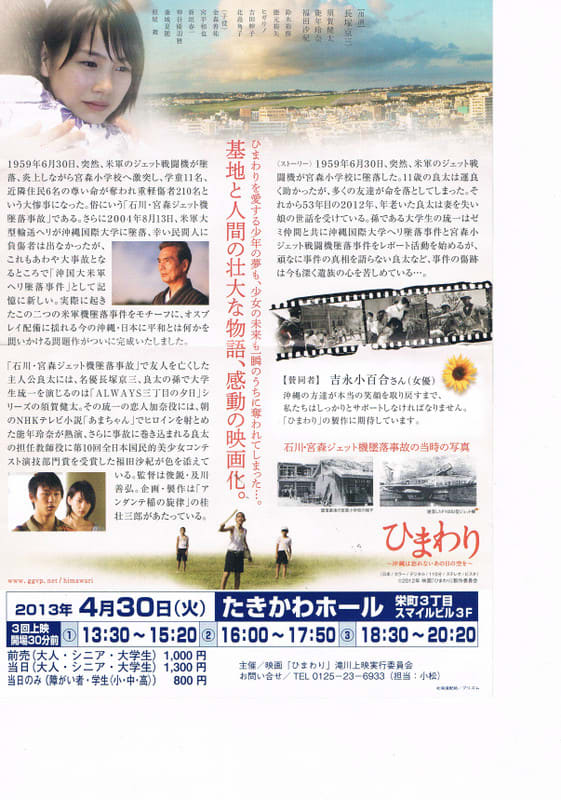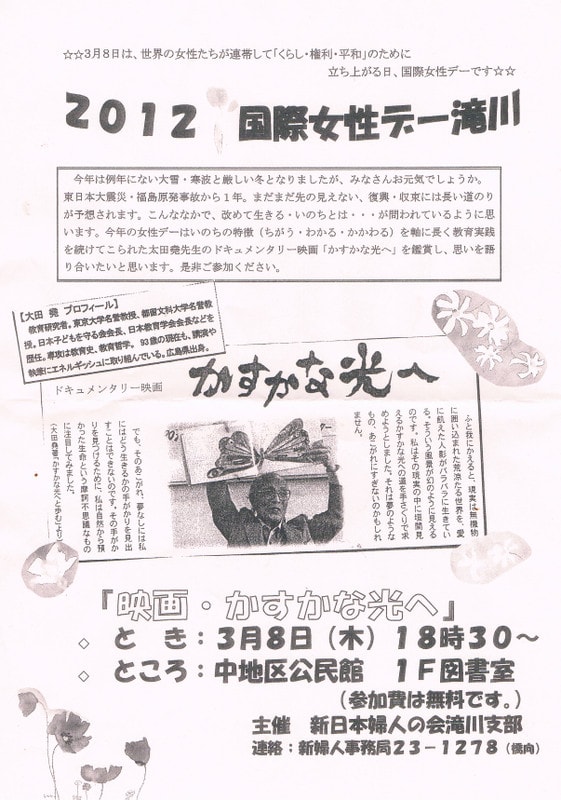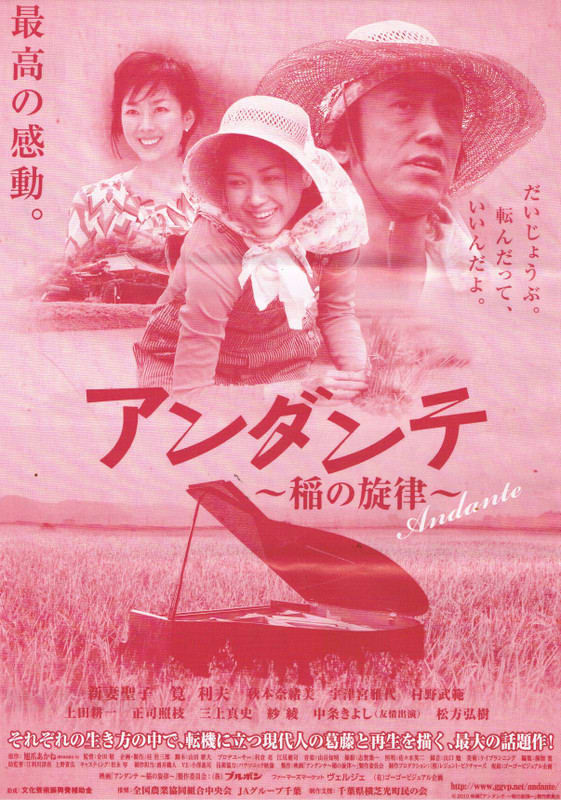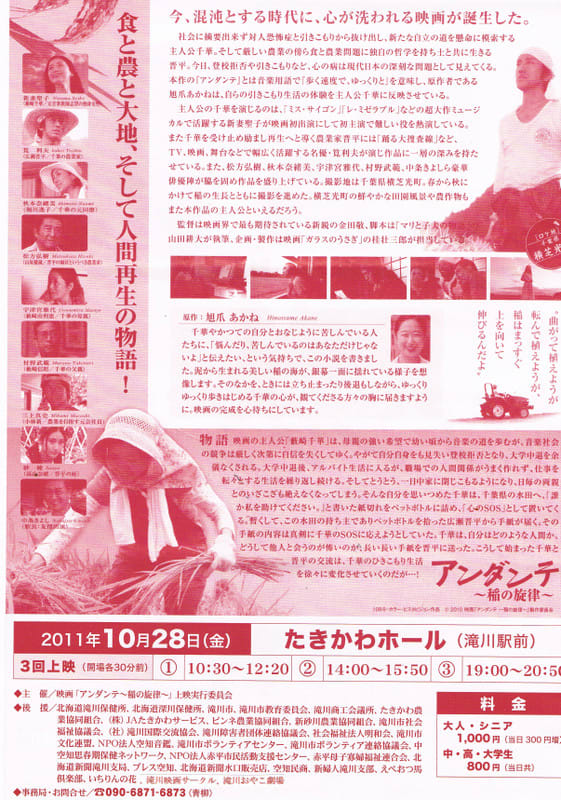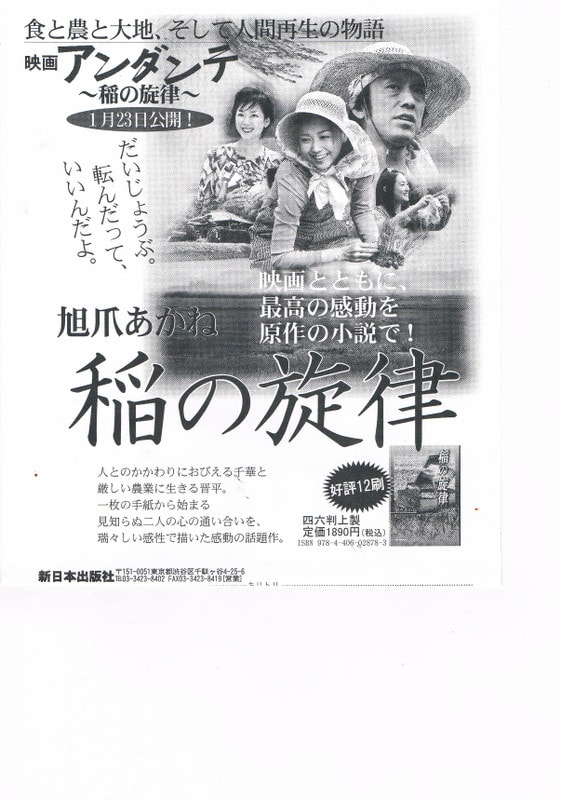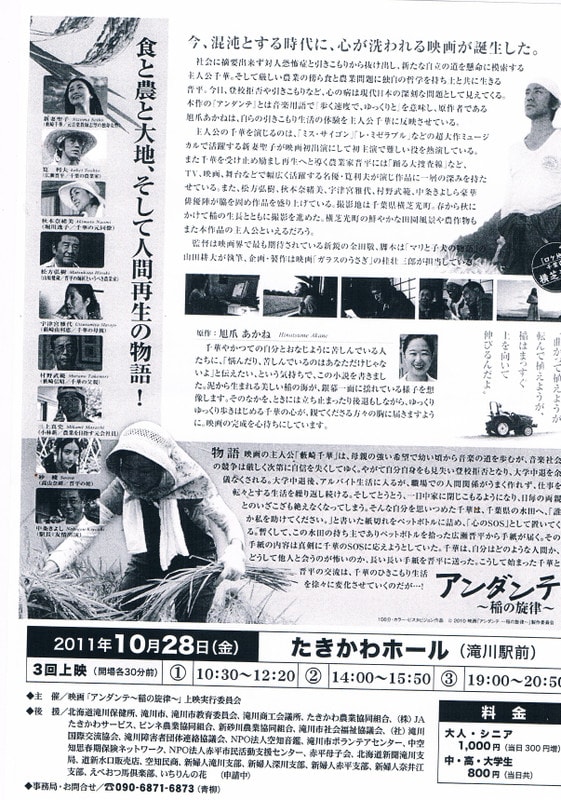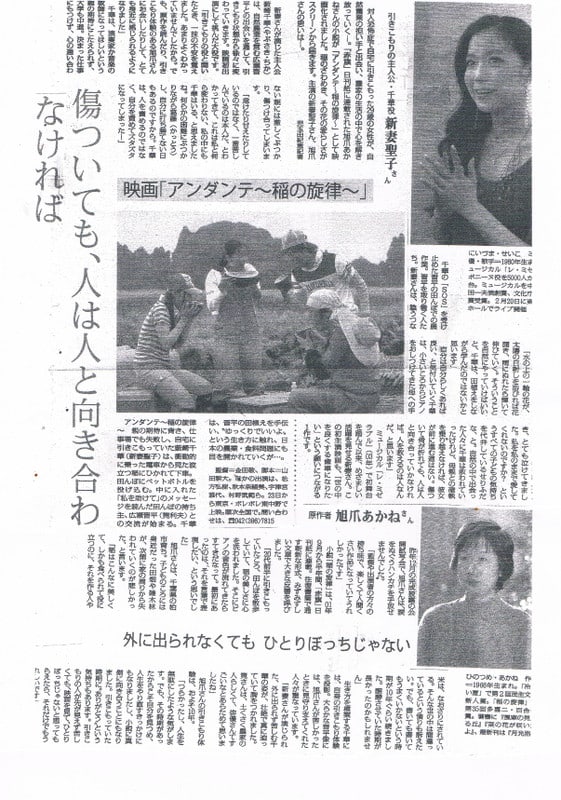ハフポストBLOG 2018年04月12日
子ども食堂はなぜ広がったのか?
背景を描く映画「こどもしょくどう」、「火垂るの墓」の日向寺太郎監督が製作
1人でご飯を食べたりしている地域の子どもたちのために始まった取り組みが、なぜ今の日本でここまで広がったのか
いまや全国で2200カ所を超える子ども食堂。家でおなかをすかせていたり、1人でご飯を食べたりしている地域の子どもたちのために始まった取り組みが、なぜ今の日本でここまで広がったのか――その背景を描く映画「こどもしょくどう」が2018年冬の公開に向けて、クラウドファンディングに取り組んでいる。「火垂るの墓」などの作品で知られ、本作の監督を務める日向寺太郎さん(52)に話を聞いた。
映画「こどもしょくどう」は、ある子ども食堂ができるまでの物語だ。小学生のユウトは、食堂を営む両親、妹の4人で暮らしている。幼なじみのタカシは、親がほとんど家におらず、典型的なネグレクト(育児放棄)の家庭。ユウトの両親はそんなタカシのことを心配し、タカシを食堂に招き夕食を振舞っていた。ある日、ユウトとタカシは、河原で父親と車上生活をしている姉妹に出会う。数日後、姉妹の父親が2人を置いたまま失踪。住まいにしていた車も壊され、行き場を失ってしまう...。
「実際の子ども食堂はすばらしいと思っています。だけど、劇映画としてはいい人ばかりだと人間の幅が狭くなってしまって、おもしろくない。ある種の教育映画的なものにはしたくなかったんですよね。結果、子ども食堂ができるまでを子どもたち目線で描く映画になりました。取り立てて悪人が出てくるわけではないんですけど、親に捨てられた姉妹が出てくる。その親にも事情はあるんだと思いますが、子どもや観客にとっては『なんて親だ』と思うんじゃないかと」
プロデューサーから話を持ちかけられたのは2015年ごろ。既に子ども食堂がメディアに採り上げられ始めていた。日向寺さんたちは、子ども食堂の名付け親とされる人が始めた食堂にも足を運び、構想を練った。原作はなく、オリジナルの話だ。
「提案を受けたとき、初めはドキュメンタリーの企画かと思いました。ドキュメンタリーだった場合、実際の子どもたちの内面に入るのは難しいというか、不可能かもしれない。でも、劇映画だと言われて、『これは面白くできるなあ』と思いました。劇映画となると、発想を自由にして子ども食堂を描ける。もともと子ども食堂のシステムはバラバラです。週1回のところがあれば、隔週のところもある。料金も300円だったり、無料だったり、やっている場所もお店だったり、教会だったりする。でも新しいところを作るとき、みんな子ども食堂という名前をつけている。これが別の名前だったら、やっていることは同じでも広がりは全然違ったと思いますね」
「今の社会は血縁、地縁といったいろんな共同体が崩れ、関係性が薄れていっている。そういう中で子ども食堂がやろうとしていることは血縁じゃないですよね。地縁ではあるかもしれないけれど、それだけではない新たな関係を作っている。そのきっかけ、萌芽みたいなものをこの映画では描きたい。他人の子どもを育てる、共同保育ができるというのは、人間を人間たらしめている大事な要素の一つだと思うんです。人が人と出会うこと、人が人を思うことによって、人は変わりうるということを一番描きたいと考えました」
2017年秋に撮影を終え、現在はクラウドファンディングで映画につける音楽を作るための費用を募っている。制作を依頼する「Castle In The Air」は、日向寺さんが監督をした「火垂るの墓」で映画音楽を手掛けた音楽ユニットだ。
「なぜか私は子どもの映画のときにギターがイメージされるんですよ。ピアノも楽器としては好きなんですが、今回の場合はピアノの音じゃ強いなあと思ったんです。映画から音楽を思い浮かべたり、音楽から映画を思い浮かべたりすることがあるでしょう? 例えば、『禁じられた遊び』『ゴッドファーザー』『戦場のメリークリスマス』...今回の映画も、そういう音楽がほしいなあと思っているんです」
「子ども食堂を一過性のブームで終わらせることなく、子ども食堂が広がっている根本的な問題を考え続けてもらいたいという思いを込めて、この映画の企画を始めました。子どもたちには、今の社会に責任はない。その社会で子どもが追い詰められている。それを作ったのは大人ですから、次世代にどういう社会を残せるか、大人が考えなくちゃいけないことだと思う。今回のクラウドファンディングも含め、いろんな形で、この映画のことを知ってほしい。映画に参加していただいて、よりこの作品に興味を持ってもらいたい。子ども食堂という名前であちこちに広がっていったように、クラウドファンディングに参加した方が、それぞれの思いでこの作品を広げてくださればいいなあと思います」
映画は2018年冬の公開を目指している。出演は藤本哉汰、鈴木梨央、吉岡秀隆、常盤貴子ら。
雪解けが進まない。昨夜から今朝にかけても氷点下。週間天気予報を見ると最低気温が氷点下以下になる日はなくなった。⛄マークも明日☂マークと並んで出ているが、それ以降は今のところなくなった。融雪が進むのは15℃以上が必要だ。