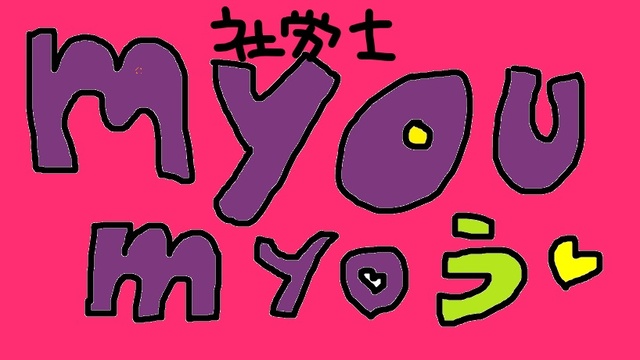職務上請求書を使って初めて戸籍謄本と住民票を取りました。
役所の窓口ってその市町村の民度が的確に出ていると思いました。
親切で丁寧な人や、ぞんざいな人、偉そうな見下した態度の人、投げやりな人など職員は様々ですが、その人個人としてではなく、どうしてもその市町村の顔として見てしまいます。
私が戸籍謄本を取ったのは市役所ではなく市民センターでしたが、若い方と年配の方2人いてどちらも行政職としての自覚のあるしっかりとした仕事をされる人でした。
私はおもわず「○○(自分の住む町)だったら、こんなことまで教えてくれないです!」と言ってしまいました。いやいやみんな教えてくれますよ、とおっしゃられましたが、そんなことないです!!
私は戸籍のことをまったくなんにも知らず、筆頭者をそもそも間違えて書いて、「直系の人しか取れません」と言われ、慌てて「じゃあ、直系の夫を請求人にして…ああっ!でも生年月日わからないーーーー」と大騒ぎをしていたのですが、そもそも筆頭者を間違えているのだから筆頭者を変えればいいわけで、係りの人の誘導でなんとか無事取ることができました。
結婚したら親の戸籍から出るとかいうすごーく当たり前のことをよくわかってなかったです。自分の戸籍を見たことあるのに、なんぞげ~に見てるんですね。
親子3代が同じ戸籍に入るということは現在の戸籍ではないそうです。子どもが生まれたら戸籍から出るのだそうです。例えば、未婚の母が子どもを産んだら、お母さんは親の戸籍から出て子どもと二人だけの戸籍になるそうです。知りませんでしたーーーー。
係りの方は本当によくできた方でした。
住民票コード通知書についても、ここでできればあなたの町でもできるはずだし、ここでダメならどこでもダメでしょう、と言って自分の担当じゃないのに、調べてくれました。
住民票コード通知書は、職務上請求書では出してもらうことができす、規程の用紙に委任のサイン・ハンコをもらった上で請求し、その場ではもらえず本人に郵送となるということでした。
とっても勉強になりました。
私も社労士の名を貶めたり品位を汚したりしないようにがんばらなきゃ…
役所の窓口ってその市町村の民度が的確に出ていると思いました。
親切で丁寧な人や、ぞんざいな人、偉そうな見下した態度の人、投げやりな人など職員は様々ですが、その人個人としてではなく、どうしてもその市町村の顔として見てしまいます。
私が戸籍謄本を取ったのは市役所ではなく市民センターでしたが、若い方と年配の方2人いてどちらも行政職としての自覚のあるしっかりとした仕事をされる人でした。
私はおもわず「○○(自分の住む町)だったら、こんなことまで教えてくれないです!」と言ってしまいました。いやいやみんな教えてくれますよ、とおっしゃられましたが、そんなことないです!!
私は戸籍のことをまったくなんにも知らず、筆頭者をそもそも間違えて書いて、「直系の人しか取れません」と言われ、慌てて「じゃあ、直系の夫を請求人にして…ああっ!でも生年月日わからないーーーー」と大騒ぎをしていたのですが、そもそも筆頭者を間違えているのだから筆頭者を変えればいいわけで、係りの人の誘導でなんとか無事取ることができました。
結婚したら親の戸籍から出るとかいうすごーく当たり前のことをよくわかってなかったです。自分の戸籍を見たことあるのに、なんぞげ~に見てるんですね。
親子3代が同じ戸籍に入るということは現在の戸籍ではないそうです。子どもが生まれたら戸籍から出るのだそうです。例えば、未婚の母が子どもを産んだら、お母さんは親の戸籍から出て子どもと二人だけの戸籍になるそうです。知りませんでしたーーーー。
係りの方は本当によくできた方でした。
住民票コード通知書についても、ここでできればあなたの町でもできるはずだし、ここでダメならどこでもダメでしょう、と言って自分の担当じゃないのに、調べてくれました。
住民票コード通知書は、職務上請求書では出してもらうことができす、規程の用紙に委任のサイン・ハンコをもらった上で請求し、その場ではもらえず本人に郵送となるということでした。
とっても勉強になりました。
私も社労士の名を貶めたり品位を汚したりしないようにがんばらなきゃ…