江戸時代に入り、和蝋燭が少しづつ出回ることになりますが、庶民には高嶺の花でした。文献によると、江戸初期の和蝋燭の価格は、10匁(37.5グラム)の蝋燭が24文で、当時の大工さんの一日分の賃金と同じだったようです。
当地柳川藩でも元禄16年(1703)には、「櫨運上の制」を定め、藩の財政を潤すため、木蝋の製造が促進されることになり、田畑や道筋などに櫨の木が植えられます。
亨保2年(1717)、瀬高町の談議所で武田蝋屋が創業を始め、藩の奨励もあり、蝋屋と呼ばれる板場(製蝋所)をもつ木蝋製造業者ができてゆきます。
農家も櫨の実を高価で引き取られ、また正月前の現金収入になるため、櫨の木を増やしてゆきます。
秋の紅葉の時期には、田畑や道筋、川や土手などの櫨の木は赤く染まり、木蝋は柳川藩の主要産物に成長し、幕末、明治へ、木蝋の需要は、維新前の薩摩藩からの特需も相俟って、生産も拡大し、蝋屋も増え続けます。
柳川藩は、「筑後蝋」として、瀬高町下庄談議所から矢部川を通じ舟により、大阪や長崎に領外輸出を始めます。
大阪市場では、福岡県産の木蝋が8割を占め、日本一の生産高を誇り、木蝋は、石炭とともに、藩財政を支えていきます。
因みに荒木製蝋所が1850年に創業を始めます。
そして、明治維新を迎えます。(1868)
江戸後期から明治にかけて、蝋燭といえば、櫨蝋が中心となり、その座を不動のもとします。
明治5年、東京浅草の商人で元合津藩士内藤愼之という者が、ドイツより、西洋蝋燭の製法を学び、製造しはじめます。
☆ 「木蝋の里みやま」キャンドルナイトが18日夜、保健医療経営大学にて行われました。
「和ろうそく」のゆらゆらとゆらぐ温かい灯りのなか、元青年海外協力隊の古賀智美さんが中央アジアのキルギスの楽器で演奏、そしてブリヂストン2kバントの演奏を楽しみながら、スローな夜を過ごしました。
☆ キャンドルナイトの様子は、千寿の楽しい歴史 http://kusennjyu.exblg.jp/
で詳しくみれます。













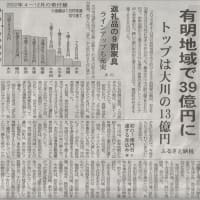






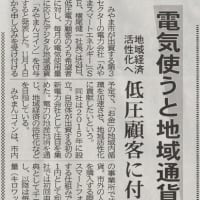

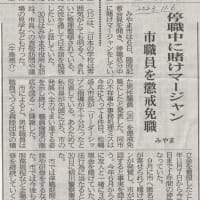
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます